高松市で高松高校・附属中学校受験専門の学習塾なら
佐藤進学塾
〒760-0079 香川県高松市松縄町1060-15
琴電 林道駅から徒歩15分
入塾をご希望、ご検討の方は
『お問合せフォーム』を送信願います。
受付時間 | 火・水・木 14:00~16:00 月・金 16:00~18:00 |
|---|
2026.2.19

『実力を発揮する』
テスト前に、いつも伝えることが三点ある。
まず、一点目
「問題が配られたら、すべての問題に目を通すこと」。
問題の構成や難易度を確認してから試験に取り掛かる。必ず、時間配分がうまくいく。
次に、二点目
「見たことない問題や難しい問題には手を出さないこと」。
焦ったりパニックになったりすると、冷静さを失う。平常心で取り組むことで普段通り問題を解く事が出来る。
最後に、三点目
「問題文を指でなぞりながら読んでから問題を解くこと」。
テストの時は、問題文を読む速度が速くなる。音読する速さで丁寧に黙読すると、正答率は上がる。
この三点を守ることで、実力を確実に発揮出来る。練習の時と同じ状態で取り組むと良いのである。
『テスト本番≒テスト練習』
の状態にする。
これが、なかなか難しい。
しかし、結果が出る子は守っている。運動の試合も、音楽の発表会も同じだ。「このテストは簡単だ」と思ったならば、満点を狙う。「今回は難しい」と思ったならば、9割を狙う。
解けない問題は、あとで復習すれば良い。テストが終わってから、生徒たち一人ひとりに声を掛ける。「良くがんばったね。解けなかった問題は復習しよう。分からない問題があることが分かり良かったね」点数のことにはあまり触れない。本人が、一番よく分かっているのだから。
2026.2.18

『卒業生の思い出』
中三で成績が伸び悩んだ子がいた。
中間、期末テストは90点以上取得出来る。しかし、診断テスト第三回以降が下降傾向に陥った。
勉強をさぼっているわけではない。
部活を引退してから、本気で勉強していた。小さな塾だから、そういう熱気はダイレクトに伝わって来る。その子が思う様な結果が出ない時、自分のノートを持って相談に来た。
「どこに問題点がありますか」
と訊かれた。
私はノートを丁寧に見ていった。
1.間違った問題について時間を掛けて丁寧に直している
2.教科書、辞書を調べて間違った原因を細かく確認している
3.三回以上、反復練習して学習内容を完全に定着させている
完璧な勉強が出来ている。
「素晴らしい勉強が出来ているよ。自信を持ってこれからも続けるといいよ」
と私は伝えた。
「ありがとうございます。この勉強を最後まで続けます」
ニコリと笑い、こたえた。
残念ながら第五回も、総合一も思う様な結果は出なかったが、入試に向けて最後まで諦めることなく私が伝える正しい勉強方法を信じて続けた。そして、高松高校合格という栄冠を手にした。今、毎日が充実していて勉強も部活も学校行事も、とても楽しいと言う。
「先生、ぜひ、塾の子たちに伝えて下さい。最後まで諦めることなく勉強を続けて下さい。諦めなければ、必ず合格を手にする事が出来る」と。
中三後半、この子はスランプに苦しんだ。これが半年以上続き、そのまま入試へ突入した。本人は本当に苦しかったことであろうと思う。入試当日、スランプから抜け出た。そうとしか、考えられない。
正しい努力を続ける事で、この様な奇跡に見えることも起こる。ただ、奇跡ではなく、奇跡を起こす位に努力したのだ。この子が、「すごいな」と思ったことがある。苦しい時も、笑顔を忘れなかったことだ。しんどい時も、まわりの子に優しく接していた。私が伝えることを真摯に受け止め、誠実に実行した。
そういう姿は、誰かがどこかで見ている様である。
2026.2.17

『笑顔の効果』
1.ポジティブになる
2.自律神経が安定する
3.みんなが明るくなる
科学的にも、証明されている。笑顔になると、脳内でエンドルフィンやセロトニン、ドーパミンが分泌される。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制される。
さて、中学生は学年末テスト直前、中三生は入試一カ月前だ。
この時期、緊張感が高まる。適度の緊張は試験に対してプラスとなる。しかし、極度の緊張はマイナスだ。心も体もガチガチになるからだ。
生徒たちみんなが良い緊張感を維持するために、私自身が気を付けていることがある。
1.肯定的な言葉を掛ける。
2.笑顔でみんなに接する。
3.私がゆっくり行動する。
生徒に嫌なことを言わない。
私がバタバタ忙しそうにしない。
「こんにちは」
と笑顔で挨拶する。
「こんにちは」
と笑顔で返してくれる。
良い結果が必ず出る。緊張で顔が強張る子もいる。笑顔が出なくなる子もいる。よくないサインである。いつも言うことだが、笑顔は意識する必要がある。うっかりすると、笑顔が消えて暗い顔になる。
朝起きて、
鏡に向かって「ニコリ」。
夜寝る前に、
鏡に向かって「ニコリ」。
自分の笑顔を確認しよう!
笑顔だと素晴らしい結果が出る。
2026.2.16

『診断テスト結果』
診断テスト結果が出揃った。
高松高校を目指す生徒は五科210点を超えていれば、ひと安心である。220点を超えた子は実力十分である。230点を超えた子は本質が理解出来ている。
「テストは終わってからが始まり」
間違った問題は、丁寧に復習してほしい。
1.教科書で出題元を調べる
2.学校ワークで類似問題を探す
3.解法の過程を書いて解き直す
それらを、二、三回繰り返して定着させる。この流れを大切にする子は、中三で診断テストの結果が安定する。
220点を超える子は塾の平常授業の復習を完璧に行っている。230点を超える子は難しい単元について、参考書を丁寧に調べて学習している。塾テキストで類似問題を徹底的に演習、日々三時間、集中して学習している。密度の高い学習を行っているのである。
中一の子は初めての診断テスト、結果を基に一人ひとりと話し合った。各科目40点(8割)以上取れていれば、良く理解出来ている。45点(9割)以上取れていれば、深い理解が得られていると言える。学年末テストに向けて良い点は続けて、問題点は改善する方法を具体的に伝えた。
今回、良い結果を手にした子はやるべきことを早めに行っている。教科書、学校ワークは、普段の復習で理解している。テスト前には完全定着させる。何より、睡眠時間を大切に確保している。日々二三時間、限られた時間で最大限効率良い学習を行っている。
2026.2.15

『正しい努力』
「正しい努力は結果に結びつく」
私はそう考える。
「努力は結果に結びつかない」
と言う人もいる。
これも一理ある。闇雲に努力しても空回りするだけだからだ。それでも、私は努力はした方が良いと思う。空回りしていも、少しずつ、学習の本質に近付いていくからだ。
「努力しているのに結果が…」
この様に思った時は、まだ、やるべきことがある。
「まず、学習時間が十分か」
日々一時間程度頑張っても結果は出ない。まず、二、三時間、集中してやることだ。
中学生を例にとる。
「数学1時間、英語1時間、そして、国語、理科、社会で1時間」
この位、すぐに家庭学習の時間は経つ。
「次に、深く理解出来ているか」
教科書、辞書を丁寧に調べているか。心底、納得出来ていることが重要だ。
「そして、解法、解答を覚えるまで反復しているか」
問題を音読して、解法を書き写す。そして、解答を完全に覚える。目、手、口、耳、五感を活用して学習する必要がある。テストの時は、考えなくても手が答を勝手に書く位にしておく。
結果が出ない子は、原則的学習の中に必ず問題がある。
1.『音読』をしていない。
2.『書写』が不十分である。
3.『反復』の練習が少ない。
いずれかだ。
これらを強化すると変わる。
上手くいかない時もある。心理面も大きく影響するからだ。これを改善するのが一番難しい。その部分は私が声掛けしていく。アドバイスを素直に聞き入れて実行に移すといい。時間が掛かっても結果は出る。諦めることなく、正しい努力を続ける子が、素晴らしい結果を必ず手にする。
2026.2.14

『体軸』
スポーツの世界で最近話題になることが多いのが体軸についての内容である。定義は難しく、体幹のことを体軸と言ったり、野球やゴルフにおけるそれぞれの体軸があったりする。
体軸とは体の中心を貫く軸のことで、体のバランスを保つために重要な役割を果たす。具体的には頭から腰、足まで真っ直ぐに伸びるラインである。体幹はそれに筋肉を含む。
体軸がしっかりしていると、体の動きがスムーズになり姿勢が正しく保たれ、体全体のパフォーマンスが向上する。体全体には、脳のはたらきのことも含んでいる。
さて、体軸がしっかりしている子は間違いなく勉強が出来る。その為、佐藤進学塾では姿勢について少し厳しく指導する。
「テキストを机に真っ直ぐ置いて、お腹と背中にこぶし一つ分の空間をあけて、両ひじは机から離して、背筋をスッと伸ばす」。
これだけのことである。
これを意識して維持することで体幹、体軸は鍛えられて姿勢は美しくなっていく。要は、気持ちである。素直に姿勢を正す子はやがて美しい姿勢と成る。美しい姿勢と学力には正の相関関係がある。また、美しい姿勢とメンタルにも正の相関関係がある。素直な心の子が美しい姿勢となり、飛躍的に学力が伸びる。
2026.2.13

『数学の徹底指導』
佐藤進学塾では、算数及び数学の理論、概念についてわかりやすく指導、解法を丁寧に解説している。生徒一人ひとりが解法の過程において筋道立てて考えることを大切にしている。
未知の問題を解決する能力を磨き上げて、高校で理系に進んで活躍出来る様にする。将来、医学部医学科をはじめ理系の学部に進学する子たちの論理的思考能力を高める為である。
また、公立高校入試は数学が難しいからでもある。難しいとは言っても、本来の難易度の高さとは異なる。出題意図が非常に解り難い問題が多い。
解説を読んで復習すると、生徒は「何だ、それだけのことか」と感じる問題ばかりだ。しかし、入試当日、制限時間内で解くことは出来ない。入試の数学で50点満点は取得不可能だ。
まず、40点台に乗せる事が必須だ。上手く仕上げると、45点を超える。最後まで諦めることなく復習を続けていくと良い。所詮、入試問題は合否判定に使われる判断材料であり本質的な数学の内容とは異なる。拠って、点数や答えに拘るのではなく、問題の解法の過程を最後まで大切に学習してほしいと思う。
2026.2.12
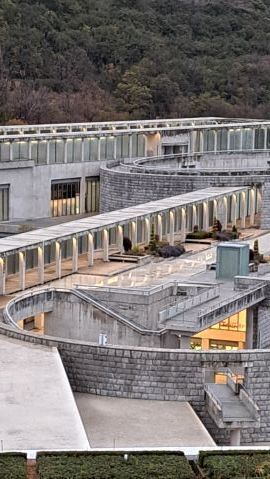
『学年末テスト対策』
佐藤進学塾の中学部では、二月、第一週より学年末テスト対策を実施している。原則的学習、即ち『音読』『書写』『反復』を推奨、生徒たちは一生懸命に行っている。
「魚を与えるのではなく釣り方を教えよ」
老子の格言「授人以魚 不如授人以漁」に由来する言葉である。佐藤進学塾では、試験に出る問題を教えるのではなく、試験に対する具体的な勉強方法を教える。
1教科書の音読・書写
2.学校ワーク類の反復
3.対策プリントの復習
テストは原則、教科書から出題される。『教科書を調べること』が大切である。あたりまえのことである。隅々まで勉強して、読んで、書いて、調べて、完全理解後に反復して習得する。
素直にやった子は上位成績だ!
ところが、全国模試、診断テスト、入試では他にやるべきことがある。試験範囲が大変広いからであり、試験内容も難しいからだ。それらの対応策はカリキュラムに組み込んでいる。平常授業の中で大切なことを時間を掛けて丁寧に伝えていく。
佐藤進学塾ではテスト対策を全学年において行うが、平常授業が最も大切と考えている。そこで、学習の本質を真剣に伝えている。小学部の授業は勉強の型を身に付ける時期の為、少し厳しい。しかし、それを乗り越えて中学生に成ると、学習内容を具体的に指示するだけでテスト対策は集中して学習する。
テスト前、私は静かに見守るだけである。何かあれば、そっと声を掛ける。一人ひとりに的確なアドバイスをする。今も、凄い集中力で塾生全員がテスト勉強を行っている。その位、佐藤進学塾の塾生が本気で頑張っているということだ。
2026.2.11

『卒業生の思い出』
中一の時、授業中によく寝る生徒がいた。数学、英語、国語の授業は直ぐ寝るが、理科、社会の授業の時はシャキッと起きている。いくら注意しても、それは変わらなかった。
理科、社会は、私が問題の答えを言う前に正解をすべて言う。理科と社会は好きで好きで仕方ない感じであった。
「アメリカの五大湖は」
「スペリオル、ミシガン、ヒューロン、エリー、オンタリオ」
高校地理レベルの答を即答した。
中一の時、内申点は悲惨だった。しかし、中二になっても数英国の授業中、目覚めることはなかった。
十二月頃、私は言った。
「本気でやらんと高高は無理やで」
生徒はすぐに答えた。
「本気でやります」
無理だろうと思っていたが、その子は勉強し始めた。副教科は姉に教えてもらい勉強した。数学と英語は塾の親友から丁寧に教えてもらっていた。親友とは読書という共通の趣味があり、自転車での行き帰りに同じ世界観で話を楽しんでいた。周りの人と環境に恵まれた運の強い子だった。
中一の時に全く勉強しなかった子が、中二後半から勉強を本気で始めた。そして、高松高校へ合格した。これは奇跡ではない。中一まで全く勉強はしていなかったが、小学校の頃から毎月三十冊位の本を読んでいた。読書が勉強の代わりを担っていたのである。読書には目に見えない凄い力がある。
2026.2.10

『卒業生の思い出』
小四の時のことである。
「必ず、復習しようね」
と私が言うと、必ず、復習を丁寧にしてきた。
ニコニコしながら、
「お願いします」
と言って、毎週ノートを出していた。
私が言っていない不思議なことをしていた。テキストに『答』を書く欄がある。そこに授業中、答えを書き込んでいる。
その答えの欄の大きさに合わせて『白い紙』を切って、丁寧に張り付けている。復習の時、答が見えない様に工夫していた。そして、答が合うまでノートに繰り返し丁寧に復習していた。
「小四の子が、一人で!」
以前、お母様に訊いたことがある。
塾長「なぜ、あそこまでするのでしょうか」
母親「紙を切ったり貼ったりするのが、小さい時から好きなんですよ」
塾長「あっ、そうなんですか」
母親「私からはその様な事をしましょうとは、言っていませんよ」
塾長「それは、図形の感性を養うことに役立っていますね」
母親「私も、そういったことは関係していると思います」
問題を解くことで図形の感覚を養うと同時に、小さな紙を切り貼りすることで図形のセンスを磨いていたのだ。かなり、時間は掛かったと思う。中三受験生の時は、塾の発展テキストの発展問題に毎日、挑戦していた。高校に入ってから伸び続けていく子の一つの型である。
高校生になってからの会話だ。
塾長「将来は何を目指しているの」
生徒「医師になることです」
塾長「大学はどこを目標にしているの」
生徒「大阪大学の医学部です」
塾長「何か、理由があるの」
生徒「医学の研究が最先端だからです」
塾長「そこまで考えているんだ」
生徒「あと、金融系の資産運用にも興味があるんです」
塾長「それはまた別の世界だね」
生徒「やりたいことはたくさんあるんです」
この子は、いつも友人のことを気に掛けてくれる子だった。塾内の子たちを温かくまとめてくれた。この子が大成することは間違いない。佐藤進学塾には成功への道を突き進んでいる子が多くいる。成功したければ、その事例を参考にすればいい。成功への道を突き進んでいく子には共通することが多くある。
2026.2.9

『如月』
小3、小4、小5は、既習事項の総復習演習及び算数・国語の発展問題演習を行っている。テキストの隅々まで仕上げよう。
小6は、中学校の数学・英語予習講座を行っている。しっかり復習することで中学校進学後に大きなアドバンテージとなる。
中1、中2は学年末テスト対策に入った。診断テスト対策から気持ちを切り替える必要がある。二週間で全教科を仕上げる。
中3受験生は、入試対策の中盤に入る。繰り返し復習して完璧に仕上げるとよい。もう、出題パターンは分かって来ている。
佐藤進学塾の生徒諸君、やるべきことをしっかり行おう!
2026.2.8

『附属中学校合格体験記』
今年も、附属高松中学校へ佐藤進学塾の受験者全員が無事合格した。以前、ブログにて伝えた通りだ。
内部連絡進学と外部受験、いずれも門戸は広くなった。かつては競争率が高かった。謎の抽選も行われていた。
「抽選の起点番号は何番です」
「えーっ」
ということが毎年行われていた。
少子化が進んで、合格しやすくなったことはありがたいことであるが、入学後のことを考えると少し気掛かりである。
さて、その子たちに、合格体験記を書いてもらった。原稿用紙に書いてくれた文章をキーボードで打ち込んでいく。
「こんな気持ちだったんだ」
「この子、すごい進歩だ」
「私の言葉が響いてたんだ」
一人ひとりの顔を思い浮かべつつ、言葉を確認しながら打ち込んでいく。
「厳しく言いすぎた」
と思い出すことがある。
「何度も伝えて良かった」
と思うことがある。
「真意が伝わっていた」
とうれしくなることもある。
公立中学校進学の子を含めて、全員が中学部に継続通塾する。高松高校合格という新たな目標に向かって努力する新中学一年生を全力で応援する。現中三と同じく、驚くくらいに努力をしている子が多くいる。
※『附属中合格体験記2026』更新
ぜひ、ご一読ください。
勉強のヒントがたくさんあります。
2026.2.7

『努力』
「もし、報われない努力があるならば、それはまだ努力と呼ぶことは出来ない」と元野球選手の王貞治さんは言った。
昭和の時代、誰もが憧れた野球選手の一人だ。
「努力は報われる」
それは事実である。
しかし、報われない努力もある。診断テスト、後半は点が伸びない。毎回、問題の傾向が変わるからだ。また、点が伸びても順位は変わらない。まわりの皆も、頑張っているからだ
ところが、入試では努力が報われる。出題傾向が変わらないからだ。努力した分だけ、点数は確実に伸びる。拠って、合格を手にする為に正しい努力をすれば良い。
高松高校を目指す子の場合、英語、理科、社会は40~50点取得出来る。数学、国語は40点前後取得可能である。五科で210点取得出来れば合格出来る。もちろん、内申点は200㌽を超えているのが前提だ。
ただ、その努力は半端なものではない。数学と国語は難しい。社会は近年難しくなってきた。理科は難しい問題の年がある。それでも、入試では努力が報われる。最後まで諦める事無く取り組むと良い。
2026.2.6

『佐藤進学塾』
県外受験を考えるなら大手進学塾、学校の勉強を見て貰うなら補習塾がいいと思う。佐藤進学塾は少人数制集団指導の進学塾である。高松高校を第一志望とする子の為に受験指導を行う。
高松高校進学後、国立大学、理系進学を希望する子の集団だ。将来、医師として活躍したい、研究機関で研究者として働きたい、スタートアップを起業したいなど夢が大きい子が多い。
現時点では本が好きなだけでも、数学が好きなだけでもいい。人の気持ちを思い遣る素直な子であればいい。
理系分野に進みたい子の為に学力とメンタルを鍛え上げる塾である。少人数制で誠心誠意指導を行う中、一人ひとりと話して長所を伸ばす。お子様の良い部分にスポットライトをあてる。きらりと光る部分を見つけ、徹底的に伸ばす指導を行う。
高松市松縄町の閑静な住宅街の中に、広告も看板もなく、真剣に指導を行う格式高い少数精鋭の進学塾が存在する。ご縁があって、大切なお子様のお役に立つことが出来ると幸いである。
2026.2.5

『主導権』
入塾面談は80分掛けて行う。
「出来ることは出来る。出来ないことは出来ない」
はっきりと伝える。
「何でも出来ますよ」
など、決して言う事はない。
適性検査を終えて現時点での学力を伝えて、三者が話し合った内容に対して納得した時点で入塾手続きにはいる。
「新年度、毎週水曜日です」
「宜しくお願いします」
スムーズに話が進むと気持ちがいい。佐藤進学塾は学年によって曜日と時間が決まっている。季節講習会、テスト対策においてもそれは同じだ。
だから、生徒はルールを守る。
曜日も時間も自由だと、生徒は気楽である。しかし、自由ゆえに学習面も生活面もルーズになる。勉強は軌道に乗るまでが大変だ。拠って、私が主導権を握り、生徒たちのメンタルと学力を引き上げていく。
「こうするべきです」
明確に伝えると親は安心する。
「次はこうしなさい」
具体的に言うと子は行動する。
そういった関係性を築くには、ある程度のルールと決まりが必要である。佐藤進学塾では安心して主導権を塾長へ渡すといい。生徒たちは学習へ向かうルーティンが身に付いて、能動的に学習する様に成る。
2月より『入塾受付』を再開しています。
〈新小3、新小4は各二名、新中2、新中3は各一名で定員に達します〉
2026.2.4
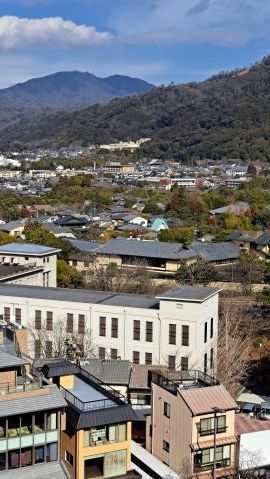
『テスト対策』
「テスト対策はして頂けますか」
入塾面談で聞かれることがある。
附属小学校の六年生は一年間に三回の『学力テスト』がある。中学生は『中間・期末・学年末・診断テスト』がある。中一、中二は一年間に六回、中三は十一回もある。
特に、中学生はそれらの結果を基に内申点が決まる。拠って、各々のテストに対して、三週間に亘りテスト対策を実施する。
進学塾としてハイレベルな平常授業に力を入れて指導しているので、普段から真剣に学習、徹底的に復習している。拠って、テストに出る内容は、ほぼ完全に理解出来ている。
従って、テスト対策の時に具体的な学習方法を指示するだけで生徒一人ひとりが集中して試験勉強を行う。結果も素晴らしいものが出る。その結果が、佐藤進学塾のすべてを物語っている。
2026.2.3

『復習について』
平常授業の指導に力を入れている。テスト対策、入試対策もきめ細やかに実施している。誠心誠意、学習指導を全力で行っている。静謐な学習空間で生徒たちは生き生きと学習している。
『進学塾』として徹底した予習及び準備を行い、最高の指導を一人ひとりに誠心誠意行っている。実際、生徒の成績は抜群であり、合格実績は申し分ない。
しかし、佐藤進学塾に入塾したからといって、それだけで成績が上がり、高松高校へ合格するわけではない。成績抜群、高松高校合格を手に入れる子は、家庭で必ず復習を行っている。
「復習は、家でやるべき」
と私は考えている。家、塾、学校、それぞれ役割がある。塾に依存し過ぎてはいけない。各々のバランスが大切なのである。
家で勉強出来ない子は、塾でも出来ない。家で勉強出来る子が、塾で集中して学習出来る。考えて見れば、当たり前のことである。出来る子はバスの中でも電車の中でも勉強出来る。家で二、三時間集中して家庭学習を行うと良い。あとは興味ある事に時間を使えばよい。好きなだけ本を読むなど、素敵である。
佐藤進学塾の小学部は午後七時前、中学部は午後九時過ぎに必ず終わる。
「早く帰って、早く寝なさい」といつも生徒たちに言っている。
2026.2.2

『二月「生徒募集」』
「入塾をお願いします」
入塾を希望するお問合せフォームが多い。一人ひとり、順番に回答しているので少しばかりお待ち頂く事も多い。
誠心誠意、一人ひとりに指導する進学塾ということが浸透してきた感がある。高松高校受験専科以来の実績が高松高校合格者は100名を超えて大きな安心感となっている。
佐藤進学塾の方針
「大切な生徒の為に『静謐な学習環境』を維持する」
この方針を守る為に大切なことはすべて行う。最低でも、一年間受講しないと授業内容の本質は伝わらない。カリキュラムは一年単位で組んでいる。
三年間受講して、本質が概ね理解出来る。五年間受講して、本質が深く理解出来る。七年間受講して、本質が心底理解出来る。時間を掛けて入塾三者面談を行い、塾理念、方針をご理解戴く事の出来る保護者様とお子様にご通塾戴いている。佐藤進学塾では、授業指導が一時的なパフォーマンスに走ることはない。
一人ひとりの学力を伸ばす為に最高水準の内容を指導している。奇を衒うことはない。ひたすら、地道に指導を続ける。演習と講義をバランスよく行う日があれば、復習方法の指導にすべてを使う日もある。
入塾を希望する保護者様とお子様には、『1時間20分』入塾面談の時間を確保する。一般的に入塾面談は10分程度で「あとは体験学習で」と親は帰される。「10分×8=80分=1時間20分」拠って、八倍の時間を保護者様及びお子様との話に使うことになる。
これだけの時間があれば、保護者様が知りたい情報はすべて聞く事が出来る。ひとりのお子様の為だけに設ける。そして、じっくり三者で話し合う。適性検査の結果を基に現状の問題点を明確に伝えて、今後の具体的な学習方法を伝える。一人ひとりと真剣に向き合う。私の方針であり、信念である。
「佐藤進学塾は、信頼出来る」
と思った時点で入塾を決定戴く。
「少し、気になる点があるなあ」
と思った場合は再度お考え戴く。
二、三日後、
「先生、子どもをお願いします」
「誠心誠意、指導にあたります」
と言う場面が、殆どである。
※『各学年の残席数』更新しました。
2026.2.1

『質問について』
「塾では、質問出来ますか」
と言う『質問』を入塾面談でよく受ける。
質問したければ、質問すればいい。聞きたいことがあるならば、いくらでも聞けばいい。
しかし、「質問してきなさい」と親が強く言ってはいけない。子どもは、委縮する。そのことばかりが気になって、他のことがまったく手につかなくなる。
「質問、疑問、ドラえもんある」
と、私は生徒によく訊く。
こう言うと、少し笑いが起こり、生徒たちは気軽に聞くことが出来る。色々な質問が出る。それに、一つ一つ丁寧に答える。生徒たちは心から納得すると明るい笑顔になる。
残念な質問にはこう答える。
「それは教科書に載ってるから、自分で調べてね」
2026.1.31

『運』
イギリスのハートフォードシャー大学、心理学者リチャード・ワイズマンは運の良い人と悪い人を対象に調査を行った。
「人生に異なる成果をもたらすのは」
「偶然か、必然か、本質的な違いか」を検証した。結果、運は単なる偶然ではなく、その人の選択による部分が大きいことが判明した。
千人以上を調査したところ、ワイズマンは、運のいい人の性質を発見した。新しい経験を積極的に受け入れ、外向的で些細なことは気にしないと示された。
「なるほど」
佐藤進学塾の子たちは私の話をいつも興味津々で聴いている。外向的な子が多く、小さなことはあまり気にしない。
※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。
次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。
〈新小3、新小4は各二名、新小5、新中2、新中3は各一名募集します〉
2026.1.30

『笑顔と肯定的な言葉』
同じ学力の子が入塾する。
入塾後、差がつく時がある。
一方の子は良い結果を出す。
笑顔で肯定的な言葉を発する。
「先生ありがとうございます。良い結果が出ました」
一方の子は良い結果が出ない。
暗い表情で否定的な言葉を発する。
「先生、暗記が苦手です。成績が伸びません」
前者は、三点が共通している。
1.私が言うことを
素直にすぐに実行する
2.失敗の原因を
考え抜いて改善していく
3.いつも笑顔で
肯定的な言葉を発する
一、二点目は学習面、生活面に関すること、三点目は精神面(メンタル)に関することである。当たり前の事を当たり前に実行している子が抜群に出来る様に成る。意外だが、三点目が一番重要だ。精神面が安定しないと、学習面、生活面に気が回らないからだ。
私自身、肯定的な言葉を発する様に意識している。生徒たちも自然と肯定的な言葉を発するように成る。佐藤進学塾の子たちは、みんな笑顔になっていく。自分自身が変わって初めて、周りの環境が良い方向へ変わっていく。周りを変えることはとても難しい。しかし、自分を変えることは直ぐ出来る。
『実行、改善、笑顔と肯定的な言葉』
これらを大切にして過ごすと結果は必ず出る。
※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。
次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。
2026.1.29

『スマホ脳』
スティーブ・ジョブズは、自分の子にiPhoneを与えなかった。ビル・ゲイツは、自分の子に14歳までスマホを与えな かった。世界の賢者は、我が子にスマホを使わせないのが常識と言う。
成績が伸びない子を見ていて思うことがある。
「この子、『スマホ』に振り回されているな」と。
直感的に感じるのだが、理由はある。以前より、目が合わなくなった、会話が成り立ち難くなった、友人関係が希薄になった、音読がいつまで経っても上達しない等々数多ある。
人対人の関係を避けるようになるのだ。
(スマホ内の世界ではその関係は続いている)
昔の様に、服装が悪くなった、態度が悪くなった、帰宅が遅い日が増えた、等々とは全く異なる現象で、敏感な大人でないと非常に気がつきにくい。
昔は、ゲーム、マンガ、テレビが勉強最大の敵であった。今は、スマホが勉強の敵である。しかし、意外にも親がそれに気づいていない。子が「スマホで何をしているか」を知らないからである。また、それが学力低下の大きな要因であることに気付いていない場合も多い。
スマホに脳が支配されると思春期にかかる小中学生の子たちは24時間、スマホに振り回される事になる。自己肯定感は大きく下がり、集中力も恐ろしい位に下がる。百害あって一利なしである。
『スマホ脳』
アンデシュ・ハンセン著
を読めば、よく分かる。
先日、高松高校の生徒たちと話をした。勉強、部活、…、学校生活全てが楽しいという。途中、スマホが話題に上がった。スマホを手にしたのは高校生になってから、中学生活は支障がなかったと言う。スマホは部活と家の連絡に使っているという。SNSに夢中な子もいるが、一部の生徒に限られるそうだ。
「なるほどな」と思った。
最近、ICT教育 先進国のスウェーデンではタブレット、パソコンなどの電子機器から紙と鉛筆での学習に回帰している。タブレットでは成績が伸びないことが立証されたからである。佐藤進学塾でも結果を出す子はスマホ(電子機器)に振り回されていない。親が良い意味でしっかりと管理しておられる。
※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。
次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。
2026.1.28

『傾聴』
『聴』の漢字が意味すること。
言葉に「耳」を傾け、表情に「目」で注意を払い、感情即ち「心」を配り、話に共感する。
目、耳、心を使って相手の話に耳を傾けると、相手もこちらを理解してくれる様に成る。
友人間で傾聴を大切にすると、その関係性は大変良好な状態が長く続く。
教える側の先生が傾聴を大切にすると、生徒は先生の話を良く聴く様に成る。
育てる側の親が傾聴を大切にすると、お子様が親の話すことを良く聴く様に成る。何より親子間の関係がとても良好に成る。
時々、「うちの子、私の話を聞かないんですよ」と大きな声で言われる方がおられる。その様な方と話して感じる事だが、私の話を殆ど聞いておらず、自分の言いたいことだけを只管大きな声で言われている。その子が人の話を聞かないのは当然のことと言えるように感じる。
2026.1.27

『整理整頓』
整理整頓は大切である。
整理整頓が出来る子は、頭の中も整理整頓出来ている。
だから、とても賢い。
整理整頓した状態は、その子の心の状態も表している。
心の中も整理整頓されているので、心がすっきりして美しい。
整理整頓を習慣化すると、心が輝きはじめる。
心が輝くと周りのみんなが引き寄せられる様に集まって来る。そして、みんなから大切にされる。物事が上手くいかない時は、周りの誰かが必ず手を差し伸べてくれる。
しかし、整理整頓が苦手なのに勉強が良く出来て、人気のある子もいる。
不思議だが、事実である。
2026.1.26

『笑顔』
笑顔は大切である。
親が子に笑顔で接すると、笑顔の素敵な子に成る。
その子は多くの友達に素敵な笑顔で接する。
周りの友達もみんな笑顔に成っていく。
常に笑顔の友達に囲まれる様に成る。
やがて、笑顔が最高の素敵な子に成り、周りのみんなが応援してくれる様に成る。結果、どんな困難な場面にも立ち向かい、乗り越えていく凄い力を身に付けることが出来る様に成る。
2026.1.25

『入塾三者面談』
一月の入塾面談が終了した。
「新小5、新中2、新中3」
定員まであと『一名』となった。
「新小3、新小4」
定員まであと『二名』となった。
「新小6、新中1」
定員に達して、予約待ちとなった。
入塾面談、次回は二月、第一週の月曜日から受付を再開する。
佐藤進学塾では一人の生徒さんに『1時間20分』の面談時間を設けている。誠心誠意、話をする事を大切にしているからだ。
適性検査を実施する。
現時点の『漢字力、語彙力、文法力、物語文・説明文の読解力』について保護者様とお子様に詳しく話をする。その後、「今後、何をするべきか」を具体的に伝える。
一人ひとりを大切にしているから、時間を掛けて指導方針を詳しく説明、お子様がやるべきことを丁寧に伝える。その後、保護者様が心の底から納得頂いてから入塾を決めて戴いている。拠って、塾生はやる気が満ち溢れている。とても小さな進学塾だが、活気がある。何より、皆、楽しそうに勉強している。
塾の平常授業、小学生は「午後7時」、中学生は「午後9時15分」に終了する。子たちは早めに帰宅して、次の日の準備をして早く寝る。聡明な子は集中して学習する。睡眠をしっかり取り、健康管理が出来る。そして、勉強以外の様々な趣味や読書、家族や友人との時間も積極的に愉しんでいる。
長時間学習には否定的な考えで学習生産性の高さを大切に考えている。
塾長、副塾長は密度の高い授業を行う。生徒たちは凄い集中力で真剣に学習を行う。そして、一人ひとりが最高の結果を出す。令和の時代、『時間』を最大限大切にしなければならない。タイパと言う言葉は好きではないが、結果を出す為に全ての時間を掛ける事は出来ず常に時間対効果を考える必要がある。
お子様一人ひとりにとって、適正な時間、集中して学習を行い最大の結果を出す塾で在り続ける。最高の指導を一人ひとりに行う。静謐な学習空間と最高の指導体制を守り抜く。ご賛同頂ける方に、是非、お越し頂きたいと思う。定員に達した時点で募集は締め切り、授業指導へ専念する。
※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。
次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。
2026.1.24

『診断対策』
中学生の診断テスト対策が終了した。テスト実施日は二月中旬である。まだ、三週間もある。しかし、佐藤進学塾では対策を終えて完成させた。
一月『診断テスト』範囲を仕上げる。
二月『学年末テスト』対策を行う。
三月『新学年予習』講座を実施する。
これで、上位成績取得が可能と成る。皆、この体制に頑張ってついて来ている。診断テストは範囲が広い為、テストの直前に頑張っても間に合わない。計画的に学習する必要がある。
「計画を立てる必要はない」
生徒にいつも言っている。
計画は塾長である私が立てる。
これで、計画的に学習出来る。
勿論「音読、書写、反復」を中心に原則的学習を行う必要がある。家庭で二三時間復習する必要もある。
さて、目標は『238点』だ。
「何人、達成できるか」
今から、楽しみである。
「今、やるべきことは」
生徒たちに訊いてみた。
「教科書を隅々まで勉強して、深く理解することです」「間違った問題を完全に分かるまで復習することです」「学校のワークを繰り返し、勉強することです」「塾テキストを復習して応用力を伸ばすことです」「最後まで高い集中力を維持して学習することです」
皆、よくわかっている。
必ず、良い結果が出る。
2026.1.23

『看板犬』
佐藤進学塾には、塾を宣伝する看板の類は一つもない。教室は松縄町の閑静な住宅街に佇む。街の雰囲気に看板の類は馴染まない。松縄町は風致地区ではないが、景観を守る。
さて、看板はないが且つて看板犬がいた。こちらは閑静な住宅街にぴったりだ。雑種のかわいい子犬であった。動物好きの子にはとても人気があった。
子たちが来ると、
「こんにちワン」
子たちが帰る時は、
「気をつけて帰れワン」
と元気に挨拶していた。
授業終了後は塾長と一緒に塾の周りをワンワンパトロールに出掛けた。そして、生徒の帰路を見守った。入塾面談の時に、心の美しい親子がやって来ると、なぜか、すやすや静かに眠っていた。
二十歳で天寿を全うした時は、たくさんのお花とお供えを頂いた。心のこもった作文を書いてくれた子もいた。みんな、第一志望校へ合格した。心優しい子を応援する不思議な力がある様だ。
今日は命日、今年も、塾の庭を元気に走り回っている。とても、楽しそうに!動物の好きな心優しい子には、きっと、その姿が見える事だろう。二十年間と言う長い間、生徒を見守ってくれた看板犬だ。今も、天国から心優しい子たちを見守ってくれている。
2026.1.22

『全国模試の結果』
全国模試の結果が返って来た。生徒一人ひとりの結果にゆっくりと目を通す。総合偏差値70を超えた子が六人いる。
良く頑張った!
先日、難関の西大和高校合格を手にした子がいる。小四の時に入塾して以来ずっと頑張っている。矢張り、今回も五科、三科共に総合偏差値70を超えていた。
驚くべきは小六である。全員が偏差値を大きく伸ばしている。総合偏差値70を超えた子が三人いて、多くの子が65を超えた。附属高松中受験者も内部、外部受験ともに全員が合格した。
小五の子で私が言う原則的学習を三年間守り、復習ノートをていねいに続けた子がいる。誰よりも授業を一生懸命聞いて、問題演習は深く考え抜いていた。その子も初めて70を超えた。
佐藤進学塾では奇跡の様な事は起こらない。私が伝える原則的学習を素直に地道に続けてきた子が結果を出す。テキスト、ノートを真っ直ぐ机において、姿勢を正して勉強する素直な子が結果を出す。
「何で、偏差値70を超えたか分かる」
一人の生徒にと訊いてみた。
「わかりません」
としばらく考えてからこたえた。
その子は私が言った通りに学習している。しかし、その努力を当たり前の事だと思っている。諦める事無く正しい努力を続ける事で必ず、偏差値は「65」に到達する。それが三回位続くとその後安定する。自信がついて、学習面においての好循環が始まる。生活全般も、驚く位に充実し始める。
佐藤進学塾では聡明な子たちに向けて、今考えられる最も効率良い学習方法を伝えている。実際に、最短時間の学習で最高の結果を出している。根性論で長時間の学習を強要することはしない。ぜひ、家族で「模試成績表」に目を通して、話をしてほしい。そして、親子で一緒に間違った問題を直して頂きたい。
2026.1.21

『入試演習』
中三受験生の入試演習を行っている。中三生は入試に向けて、最後の仕上げを行っている。入試演習も三週目に入った。初めは緊張していた。診断テストと入試問題の違いに驚くからだ。
「問題形式が違う」
と驚く子が多い。
「入試問題は難しい」
と冷静さを失う子も多い。
三週目は少しリラックスしている。塾生一人ひとりが家で復習して各自、私が指導した通りに対策を立てて来ているからだ。問題を客観的に見て、冷静に取り組んでいる。
一週目、二週目は張り詰めた空気感であった。三週目はいつもの穏やかな空気感へと戻った。入試問題に対する詳しい解説と対策を聞いて、冷静さを徐々に取りもどしていく。
復習を重ねることに拠り入試問題に対して、平常心で取り組む事が出来る状態に成る。香川県立高校入試日まではあと二カ月ある。60日間、1440時間、それだけの時間があれば隅々まで学習することにより、一人ひとりが納得いくまで十分に仕上げる事が出来る。
「もう二か月ではない、まだ二カ月もある」
2026.1.20

『附属高松中学校合格』
佐藤進学塾の受験者全員が、今年も合格した。ご理解、ご協力頂いた保護者様には感謝の気持ちでいっぱいである。
「おめでとう」と声を掛ける。
「ありがとうございました」とこたえてくれる。
「どうだった」と訊く。
「算数が難しかった」と、皆が口を揃えて言う。
佐藤進学塾では、集中力を高める方法を具体的に伝えている。最大限に効率を追求した密度の高い学習指導を行っている。
実力ある指導者が最高の授業指導を行う。理数系は塾長、文系は副塾長、専任教員が担当する。ヤル気あるお子様が受講することに拠り、限られた時間で最高の成果を出す。
2026.1.19

『小正月』
「一月十八日、日曜日」
氏神様である松縄熊野神社のどんど焼きが行われた。
どんど焼きとは、注連縄、お守りなどを神社に持ち寄りお焚き上げする地域行事のことである。お習字を焼いてお焚き上げをして、字の上達を祈念する神社もある。
どんど焼きには、正月飾を目印に来て下さった年神様を燃やした炎と共に見送る意味もある。縁起物を燃やして、五穀豊穣、家内安全、無病息災を願う。
昔から炎は穢れを清めて、生命を生み出すと考えられてきた。神聖な炎で縁起物をお焚き上げするどんど焼きには縁起の良い言い伝えが残っている。
松縄熊野神社で朝の十時頃からどんど焼きの神事は始まった。神主さんが祝詞を読み上げたあとに松縄町、神社総代の方が点火、炎は天に向かって大きく燃え上がっていった。
2026.1.18

『一週間』
この時期、土曜日の午前中は授業準備をして、午後からは中三入試演習を行う。その後、入塾面談を実施している。月曜日から土曜日までカリキュラムがびっしりである。
一週間が「あっ」という間に過ぎていく。
中学生は全学年、テスト対策を行っている。いつも以上に、皆真剣である。集中すると、時間が経つのがはやい。中学生は「診断テスト対策」、中三受験生は「入試対策」である。
高得点を取る子は徹底的に復習している。
間違った問題を丁寧に解き直す。教科書、辞書、参考書を隅々まで調べる。繰り返し、解き直して理解後完全に定着させる。
「あっ、わかった」
最初の小さい感動は大切である。
ところが、テストは出来ない。
教科書、辞書、参考書、塾テキストを使って徹底的に復習する。
「あーっ、わかった」
と心の底から感動する。
ここまでやると、テストが出来る。
同じ「わかった」でも意味が異なる。前者の「わかった」は表面的なもの、すなわち、分かったつもりということだ。後者の「わかった」は本質が理解出来ている。拠って、テストで実際に解くことが出来る。
結果が出る子は、正しい努力を必ず行っている。その正しい努力の仕方は塾長である私が生徒に教える。勉強の仕方、ノートの作り方など具体的に伝える。後は、それを素直に実行へ移せばいいだけである。
2026.1.17

『阪神淡路大震災』
6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災は、発生から31年が経った。各地で早朝から追悼行事が営まれ、地震発生時刻の午前5時46分に参列者が目を閉じ、犠牲者に黙とうを捧げた。
三宮の東遊園地では、灯籠に火が点り「つむぐ」の文字が浮かび上がった。震災体験者が減り、知らない世代が増えている。次代に記憶を繋ごうと子どもと一緒の家族も多かった。
京都で進学塾勤務時、神戸にはよく行った。以前、タクシーに乗った時の運転手さんの話が忘れられない。
「あの日の朝、五時半に同業者と車で待ち合わせしてたんや。そしたら、突然、青白い光がピカッと横に走ったんや。その直後に、地面から突き上げられる様な衝撃が伝わって来たんや。車もぼくも、ひっくり返ってな、大変やったわ。急いで、会社に走って帰ったら、ビルがつぶれてもうてたわ。その時、ぼくは印刷会社の社長やってんで。もう無茶苦茶になってもうて、どうもできひんかったわ、ほんまに大変やったわ」。
2026.1.16

『一に復習、二に復習、…』
中学生は冬期講習より診断テストの対策授業を実施している。隅々まで徹底的に、復習を行ってほしい。
1.演習した問題の復習
①間違い直し
②教科書調べ
③学校ワーク類題演習
2.塾テキストの復習
3.辞書・参考書の活用
小六は数学と英語の中学予習を来週から行う。塾のテキストを出来るまで復習すること。
1.声を出して問題文を読む
2.ひたすら手を動かして書く
3.繰り返し問題を解き直す
大きなアドバンテージとなる。
中三、受験生は入試演習を実施している。入試問題と解法・解答を覚えるまで復習してほしい。授業中に伝えた得点を取得すれば必ず合格出来る。
家庭での復習が習慣化すると、勉強は少し楽しくなってくる。「勉強がほんの少し楽しい」と感じた時、良い結果が出る。大変な時期を乗り越えて、「勉強が、本当に楽しい」と感じた時、栄冠を手にする。
2026.1.15

『附属中入試』
今週、土曜日は附属中学校の入試である。いつもと変わらず、丁寧に授業指導を行う。入試直前だからこそ、授業指導を粛々と行う。算数は割合の発展問題を仕上げる。
特別なことは、何もしない。
受験の注意点、その後の中学予習講座について全員へ伝える。附属中であっても公立中であっても区別も差別もしない。高松高校合格に向けて全力で取り組む子を応援することを話す。
みんな、最大限に集中して考えている。そして、今日も静かに平常授業を終える。
受験する子に声を掛ける。
「平常心を大切に、いつも通りに取り組むこと」
「ありがとうございます。がんばります」
と言って、元気に帰って行った。
しかし、入試が勝負ではない。
勝負は来週の『中学予習講座』から始まる。
さて、ひと足先に合格を手にした中学部の子がいる。
三年前に附属中を受験して合格した公立小出身の子だ。
小四の時に佐藤進学塾へ入塾、一生懸命に学んでいる。
『西大和高校合格』
大したものである。
幸先の良いスタートだ!
2026.1.14

『丁寧な字』
年明け、復習ノートを出している子が多くいる。期末テストの復習ノート、診断テストの復習ノート、そして、冬期講習会の復習ノートなどを受け付ける。
「先生、お願いします」
授業後、一冊ずつ丁寧に見ていく。
完璧に出来ている子。
もう一息で完成の子。
少し残念な内容の子。
内容について、隅々まで見た後は、メッセージを書いて、一人ひとりに言葉を掛けて返していく。
「絶対、出来る様になるよ」
「勉強が楽しくなってくるよ」
「もう少し調べて書きこもうね」
少し、残念な内容の子は義務的にやって出している子である。残念だが、作業のように行っている。もしかしたら、親に「やりなさい」と言われたのかもしれない。学習が作業化すると、成果は出ない。
「その差はどこに表れるか」
「生徒さんの『字』である」
大きく、濃く、丁寧に書かれた字、心を込めて書かれた字。これらが出来る子たちに共通した字である。上手、下手はあまり関係ない。途中の計算も、考え方も詳しく書いている。理解しようとする気持ち、その子の心が伝わって来る。能動的に行い、自分自身の頭でとことん考えている。
素晴らしい限りである。
かつてこの様に言った子がいた。
「佐藤進学塾で実際に結果を出している人の復習ノートを見て衝撃を受けました。この様に勉強するから結果が出る。私の勉強のあまさに気付かされました。間違った原因を調べて理解している。学校ワーク、塾テキスト、辞書、参考書を徹底的に調べ、似た問題を探して解き直しをしている。私もこれから、できることからやっていこうと思います」
2026.1.13

『聞き間違い!?』
二年前の話である。
ふと、思い出す時がある。
「友だちのお父さんが 『さだまさき』のファンなんです」
「えっ、『すだまさき』かな」
「あっ、『すだまさし』です」
「えっ、『さだまさし』かな」
「あっ、そうです」
「『お前を嫁に、もらう前に…♪』と歌う人のことやね」
「友達の家に行ったら、それが流れてるんです」
「えーっ、『すだまさき』と違うか」
「友達の父が『さだまさし』のファンでいつも流れてるんです」
「今時、珍しいな」
「友達が『恥ずかしいからやめて』と言うのにやめないそうです」
「益々、珍しいな」
しばらく、話は続く。
六年前、生徒の家での会話を思いだした。
「お母さん『すだまさき』すごくいいよ」
「あー、『すだまさし』いいね」
「『すだまさき』、大阪出身だって」
「『さだまさし』さん、歌も演技も上手いね」
「あれ、お母さん、『さだまさし』って言わんかった」
「言ってないよ、『すだまさし』って言ったよ」
「えっ!」
「???」
さだまさしさんの話をしているのに、『すだまさし』、『さだまさき』と言ってしまう。
菅田将暉さんのことを話しているが、『さだまさし』、『すだまさし』と言ってしまう。
とても笑える、楽しい話だ。
なぜか、時々、思い出す。
2026.1.12

『一気呵成』
一気呵成とは、一息に文章を完成すること。また、物事を中断せずに一息に仕上げることと言う意味がある。
佐藤進学塾では原則として、新年度に生徒が入塾する。塾年間カリキュラムに則って計画的に授業を進めるので、生徒たちは学習及び復習が心に余裕を持って出来る。
ところが、少数であるが年度途中で入塾する子もいる。その子たちは塾テキストは単元の途中から学んでいくことになる。
その子達には塾テキストを家で自分の力で仕上げる様に言う。分からない時は「解説書を見て考えて良い」と伝えている。
これが出来る子は成績上位者となる。自分でやるわけだから、大変だが、能動的に考える力がつくからだ。
以前、小六で入塾した子がいた。友人に負けたくないので、小五算数テキストを春休みに完成させて提出した。中学校では塾の友人と定期テスト、診断テストで総合一位を競い合った。友人は大阪大学へ、本人は千葉大学へ進学して頑張っている。二人とも第一志望の国立大学である。
その子の妹は小四で入塾した。兄の頑張る姿を見て「私も、やる」と言って、小三算数テキストを春休みにすべて完成させて提出した。中学では運動部のキャプテンとして、勉強と両立して頑張った。その子は今、高松高校で岡山大学を目指して頑張っている。
学期の途中で入塾しても頑張る子が佐藤進学塾には存在する。佐藤進学塾が採用するテキストは教科書に準拠していないので難しい。それを自分の力で仕上げるとは大したものである。逆に、その位の気概がないとうちの塾にはついてくることは出来ないともいえる。
しかし、出来ることならば新年度に入塾するといろいろな意味で安心である。
2026.1.11

『レスポンス』
レスポンスとは反応、応答、返事のことである。
中一、中二は診断テスト対策を行っている。当該学年の学習内容は年内に終わっている。冬期講習からは診断テストに向けて試験対策問題の演習及び解説を行っている。
中一は初めての診断テストである。みんな、真剣そのものだ。私の説明を一生懸命に聴いている。
「診断テストは入試に直結する。 出題範囲は広い上に難易度も高く、実力が顕著にわかる重要な試験であり、今まで以上に本気で学習へ取り組む必要がある」
私の言葉に素直に反応して頑張っている。レスポンスが良い。素晴らしいことである。この調子であれば、何人かは220点を超える。今から、とても楽しみである。
中二は、昨年、一度経験している。経験しているだけにその重要さは十分に分かっている。拠って、真剣に取り組む子ばかりである。レスポンスが良いのである。昨年度、多くの子が210点を超えた。今年度も大いに期待できる。レスポンスが良い子は凄い結果を出す。
2026.1.10

『能動と受動』
「能動」 と 「受動」 の違いは 積極性の違いであると言える。様々な物事に対して自ら働きかけようという積極性に基づいて進んで動くのが 能動である。
積極性がない為に自ら進んで動くことなく、他からの働きかけに対して反応を示すのが受動だ。入塾当初は受動であることは仕方ない。全てをまずは受動で受け入れざるを得ないからだ。
しかし、出来る子は能動に変わる。速い子は三カ月、遅い子は六か月で能動に変わる。最初の半年が勝負であると言える。
「高校生になって思うことがあります。 最後は自分です。自主的に勉強するしかありません。受け身の状態では絶対に勉強は出来る様に成りません。能動的な学習習慣を付けてくださった佐藤先生には心から感謝しています」と言った卒業生がいる。
今、岡山大学歯学部で頑張っている。
受動から能動に変わる子には共通することがある。
1⃣家のお手伝いを進んで行っている。
お手伝いの大切さを親が子に教え、その行動に対して、親が子へ大いに感謝している。
2⃣先生の話や友達の話をよく聞いている。
人の話を良く聞く子の親は、お子様の話を一切さえぎることなく聞いてあげている。
3⃣分からなくても分かるまで粘り強く考える。
結果について、親が一喜一憂せず、結果に至る過程が大切であることを親が子に伝えている。
「能動的な行動を取る子には、『親が子にしている共通すること』があるという事だ」。
2026.1.9

『伝説の卒業生2』
塾生保護者様のご紹介に拠って入塾した小六の子の話である。入塾当初はノートに文字、数字を書くスピードも、問題を解くスピードも一番遅かった。すべてが丁寧な子であった。
焦っているので、私はよく声を掛けた。
「自分のペースを大切にするといいよ」
その子は次第に自分が解くスピードを気にしなくなった。その子は誰よりも私の話を一生懸命に聴いていた。解くスピードは遅くても、正答率は誰よりも高く、理解度は一番高かった。
中二になると、他の子と書くスピードも、解くスピードも同じ位に成った。その頃からクラスのリーダー的存在となり、皆をまとめてくれた。クラスのみんなから慕われていた。
中学校ではいつも総合二位であった。出来るライバルがいて、一番は取れなかったらしい。しかし、最後の診断テストで総合一位を取った。
「とうとう、やったね」と言うと、
「ライバルが私立受験日と重なり、受けていないんです」とニコリとしながら言った。
高校では生徒会長としても活躍、多くの人から信頼されていた。高一の時、後輩の応援に塾へ駆けつけてくれた。高二、高三では年二回、手紙で近況を知らせてくれた。最後に、いつも後輩の応援メッセージを書き添えてくれていた。
現役で東京大学に合格した時は、保護者様と一緒に挨拶に来てくれた。東京大学一年生の夏休みにも塾へ来てくれた。そして「後輩塾生を応援しています」と言って、東大鉛筆をプレゼントしてくれた。生徒たちに渡すと、みんなとても喜んでくれたことを思い出す。
周りの人のことを考えて行動する子は成功する。「人に何をして貰うかではなく、人に対して何が出来るかを考えて行動する子は、長期的に全ての事が上手くいく」。この子は、昔からいつも周りの事、友人の事を気遣っていた。たぶん、学校の先生や友人に対しても同じことをしていたのだろう。
この子は、『努力の天才』であった。私が言ったことは、すべて守った。姿勢を正し、原則的学習を続けた。復習方法を伝えると、その通りにやってきた。私のアドバイスを基に最高の学習へ辿りついた。中学の時「考古学者になりたい」と言う夢があった。高校では「哲学者になる」という夢に変わった。
今、その夢に向かって邁進している。
2026.1.8

『伝説の卒業生1』
今から約二十年前、佐藤進学塾を開校してから五年目くらいの時、小三のとても利発な子が入塾した。最初のうちは少し落ち着きがなく、時々キョロキョロしていた。
「佐藤進学塾では先生の話を良く聞いて、問題を深く考える事が大切だよ。大変だけれども、二時間の授業に集中しようね」と私はその子に言った。
神妙な顔をして話を聞いていたその子は、次回から授業に集中するようになった。姿勢を正して、先生の目を見て話を聞く、問題は深く考える事を真剣に行った。
たった、一回、丁寧に伝えただけでその子は変わった。賢い子と言うのは人の話の真意を判断する力が高い。また、言われたことを直ぐ実行に移す。だから、出来るのである。
小学校の期末テストでは全科目90点以上を取得した。全国模試は直ぐに偏差値65を超えた。そして、その後、成績は安定した。中学校でも、学年一位をキープ、高松高校入学も上位成績をキープした。高三まで部活を行い、勉強と両立した。現役で第一志望の京都大学医学部医学科へ進んだ。
今年も年賀状を戴いた。
「小児科医としてがんばっています。近々、近況報告に行きます」
その子の後輩が紹介を受けて多く入塾した。後輩たちも国立大学医学部医学科へ進み医学を学んでいる。今、高松高校で医学部を目指して頑張っている進行形の子も多くいる。佐藤進学塾は小さい塾だが社会で活躍している多くの卒業生が存在する。
2026.1.7

『真に大切なこと』
入塾を希望する親子に必ず伝えることがある。
「塾に依存してはいけません。塾の授業は一言一句もらすことなく聴くことが大切です。学校の授業も大切に考えてしっかり聞く必要があります。中でも家庭学習は最も大切です。お子様の為に家庭環境を整えることに協力して戴きます。真に聡明な子と言うのは、塾でも学校でも家庭でも集中して学習します」
私は家庭学習の大切さを常日頃から伝えている。
『塾、学校で学習する部分』と『家で復習する部分』があり、車の両輪の様なもので、両方が上手くいって初めて前進する。
その復習について、具体的にやるべきことも伝えている。
1.間違った問題をノートに書き写す
2.正しい考え方、解法を詳しく書く
3.間違った原因について、教科書を調べる
4.間違った問題を、二、三回反復練習する
5.類似問題をテキストから探して解き直す
これらが出来たならば結果は出る。
生徒の復習ノートを見ると、更に改善すべき部分が見えて来る。そこは、塾長である私が生徒一人ひとりに対して具体的にアドバイスを行う。間違った方法で長時間、作業の様に学習しても結果は出ず、徒労に終わる。正しい学習方法で「出来るように成りたい」という一心でやれば実力は飛躍的に伸びる。
2026.1.6

『卒業生の応援』
昨日の月曜日、高松高校、高松西高の卒業生たちが久しぶりに佐藤進学塾へ顔を出してくれた。
「先生、滝宮天満宮へ行ってきました。中三の子たちにご祈祷を受けた鉛筆を渡してください」と言って、渡してくれた。
卒業生は、高校生活についていろいろ話してくれた。とにかく「毎日の生活が充実していてとても楽しい」とニコニコしながらたくさん話してくれた。
一人は運動部でもう一人は文化部で活動しているという。一年経って、しっかりしたお姉さんになっているが、小学校、中学校の時のことをいろいろと思い出す。
高松高校の子が最後に言った。
「高松高校では大体、上位15位内をキープしています。矢張り、学校で習ったことを家で集中して復習することが一番大切だと思います。佐藤進学塾では、小学生の時から正しい学習方法や私に合う勉強方法をきめ細やかに教えて下さいました。今でもそれがとても役に立っていて感謝の気持ちでいっぱいです」
今年受験する中三受験生たちへ滝宮天満宮の鉛筆を一人ひとり手渡すととても嬉しそうな顔をしていた。生徒たちが合格を手にするまでには、いろいろな人たちの多大な協力と盛大な応援がある。
2026.1.5

『テスト対策』
中学一年、二年生は冬期講習会より診断テスト対策を実施している。既習事項の総復習である。
理解していることと、定着していることは異なる。理解していても、問題が解けないことはよくある。問題の正しい解法が、理解後に定着していないからだ。
「では、どうしたら解ける様になるか」
1.対策問題の復習をていねいに行う
2.教科書を調べ大切なことを書き出す
3.学校ワークで類似問題を探して解く
上記を、三回繰り返せばよい。
さて、『睡眠』についての書籍を繰り返し読んでいる。
「繰り返し学習したことは、レム睡眠中に深い記憶として残る。一回だけ学習したことは不要な事として記憶から削除される。さらに深い記憶として残す為には、十分な睡眠が必要である」と書いてある。繰り返し、反復したことは、睡眠中に脳が重要な事と認識するそうだ。
私が普段言っている「音読、書写、反復を徹底して行う事が大切である」という事は矢張り重要なのだ。私が常に「集中して学習して、早く帰って寝なさい」と言っていることは理にかなっているのだ。
さて、一、二回だけの浅い学習では、記憶に残らず、結果は出ない事がはっきりした。思うような結果が出ない子は、もう一回、繰り返し学習すると良い。それでも、思うような結果が出なければ、更に、もう一回、繰り返し学習すると良い。そのうち、何回やれば結果が出るか体感できる。
最高の結果が出ている子は、それが感覚的に分かっているのである。そこまでやり切っているから、その感覚が肌感覚として身に付いている。さあ、テスト対策に集中して全力で取り組もう。終わったら、早く帰って、翌日の準備をして早く寝よう!
結果を出すには、学習時間ではなく学習密度が大切である。
2026.1.4

『冬期講習後半戦』
一月三日、受験生の冬期講習後半戦を開始する。みんな、正月はゆっくり過ごした様だ。しかし、授業が始まると直ぐに集中モードに入る。いつもと変わらない佐藤進学塾の光景である。
あっと言う間に、五時間の講習が終わる。これだけの集中力があって初めて、入試の当日も最後まで集中することが出来る。完成度は高まっている。一人ひとりが自信を持つと良い。
授業を終えると、一人の子が話し掛けて来る。
「診断テスト、230点を超えるように頑張ります」
「もう、それだけの力は付いているから大丈夫だよ」
明後日の一月五日、月曜日からは全学年の平常授業を始める。中三生はいよいよ入試対策が始まる。睡眠をしっかりとって、免疫力を高めよう。受験生、最後は体力が勝負である。
2026年度 生徒募集状況
新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。
「素直で前向きなお子様をお待ちしています」
2026.1.3

『新たなる挑戦』
冬休みはあと一週間ある。拠ってまだ挑戦できることがある。挑戦と言っても、大仰に考えることはない。自分の得意分野を伸ばすことに挑戦する。今の自分を変えることに挑戦する。
算数や数学が得意であれば、発展問題に多く挑戦すると良い。社会が得意であれば、新聞、参考書の活用に挑戦すると良い。諦めそうになっても、あと一分考えることに挑戦すると良い。
「おもしろい」「たのしい」「すごい」など、今まで見過ごしていた大切なことに気付くはずだ。
流れやリズムが変わっていく。
そういったチャンスが冬休みにはある。普段の小さな努力が、冬休みの挑戦と相まって大きな成長に繋がることもある。
「それに気づくことが出来るかどうか、思い切って挑戦するかどうかで人生はガラリと変わる」
2026.1.2

『御祈祷』
石清尾八幡宮さんへ祈祷を受けに行った。高松の護り神ゆえ、毎年末にお願いしている。一年間、無事に過ごす事が出来たことを神様に感謝する。
石清尾さんは918年、八幡大神様が亀命山山上に現れたので、国司が祠を建ててお祀りしたと伝わっている。由来は、社殿があった赤塔山が亀ノ尾山塊の山裾にあたり、石清水八幡宮の石清水と亀の尾を合わせて、石清尾になったと言われている。
古来周辺は海で、亀がたくさん這い上がって来ていたことから亀命山、亀阜など亀とつく地名が多く見られる。南北朝時代、讃岐を治めていた細川頼之公が当宮への崇敬の念篤く、戦勝祈願を行う。細川清氏を破り、河野氏征伐が成就したことより、当宮の社殿を改修し、様々な武具を奉納された。
1588年には讃岐守生駒親正公が高松城を造営した際に当宮を城の鎮護、高松の産土神と定める。江戸時代に入り、1642年高松藩主となった松平頼重公も当宮を篤く崇拝し、1666年に社殿を造営し社領と多数の宝物を寄進された。以後、藩主は代替わりごとに当宮を参拝することになる。
以来、高松の護り神として現在に至る。
さて、以前、七五三で祈祷の子と一緒になった。
「お母さん、神様、メガネかけてるね、…」
「ご祈祷中は、お話ししてはいけませんよ」
祝詞を上げる神職さんを神様と間違えたようだ。若い神職さんは、大きな黒いメガネを掛けておられた。ご祈祷を受けて一年を締めくくることが出来た。そして、新たな一年を清々しく迎えることが出来る。
2026.1.1

『慶雲昌光』
床の間に書の軸を掛ける。
「御目出度い雲に美しく光る日光のこと。 雲は吉兆を運び、光は生活に輝きをもたらす」
正月に相応しい軸である。
器や御軸を扱う店が京都御所の南東角に在る福丸太平堂さん。年に二、三回訪れて作品を鑑賞する。気に入った京焼があるとお願いして譲って戴く。
十年前位の出来事である。ある日、不思議なことが起こった。その日は、その御店に行く気は無かった。しかし、いつも通り寺町を歩く間になぜか、その店に辿り着いた。
そして、御軸の前に立っていた。
ご主人に訊いてみる。
「こちらは何方の書ですか」
「東福寺の管長の書ですよ」
「いつのものですか」
「五十年位前の書と思われます」
「何代前の管長の揮毫ですか」
「三代か四代前の管長でしょう」
「いい書ですね」
「そうですね」
「お譲り戴けますでしょうか」
「諒解しました、準備致します」
それ以来、床の間に掛けている。
さて、随分前の事になる。
二十六年前、大いに悩んでいた。
「合併後の大きな進学塾に残るか、独立して小さな進学塾を起ち上げるか」
時間がある時に良く訪れる『東福寺』へ足を運んだ。普段は広大な境内に人はほとんどいない。そこで、伽藍を見ながら考え抜いた。三時間ほど経過した頃、雲の間から美しい光が射しこんできた。
天の啓示を感じた。
「自分でやってみなさい」
その瞬間、結論が出た。
「『理想の進学塾』を創る」
不思議な御縁を感じた。偶然ではない、必然であると感じた。御軸が来てから良いことが多く起こる様に成った。良くないことが起こっても、転じて良くなる。良いことが起こると、良いことが続いて起こる。自分自身の見方や考え方が変わったのかもしれない。僧の御心を敬う気持ちの御返しかもしれない。
コロナ禍から日常生活は戻った。
人々の考え方はコロナ前と比べ大きく変わった様に感じる。しかし、教育において真に大切なことは変わらない。そこは信念をもって、真摯に授業へ取り組む。子たちの為により良い指導をする為に変えるべきことは変えていく。子たちの心を磨いていく為に大切な幹の部分は変えずに守り抜く。
新年も宜しくお願いしたい思う。
2025.12.31

『大晦日』
二学期平常授業、冬期講習の年内日程が終了した。生徒みんな集中して取り組んだ。その集中力は素晴らしいものであった。
「ゆっくり解こうね」
普段は生徒たちにこの様に声を掛ける。
しかし、テストは時間に制限がある。適正な速度で解くには、解法を的確に覚えてリズム良く解く必要がある。
冬期講習では正しい解法を習得、適正な速度で解く時間感覚を身に付けた。あとは、家の復習に掛かっている。家で復習する内容は具体的に伝えた。
冬休みを有意義に過ごしてほしい。決めた時間でやるべきことをやると良い。あとは時間を自由に使えばいい。一人ひとりが上のステージへ上がるチャンスである。
講習期間中、一生懸命に取り組んでいるのに答が出ず苦戦している子もいた。私が指導する解説を懸命に聞いている。その後「なるほど、そうやると解けるんだ」という心の声が聞こえて来る。
「わかった」
小さな声も聞こえてくる。
「がんばったね」
すかさず、声を掛ける。
数学はセンスや閃きがある子だけが出来るのではない。一生懸命に解説を聞いて、復習して習得する子が出来るのだ。前者と後者の比率約2:8だ。中学、高校と学年が進むに連れて後者が大きく伸びていく。
「先生、一年間どうもありがとうございました」
生徒達が深々と頭を下げて、お礼を言って帰って行く。
「良くがんばったね。来年も一生懸命取り組もうね」
私も頭を下げて、一人ひとりに声を掛けてから見送る。
一年間、大切な生徒さんへ向けて授業指導ができた事をありがたく思う。インフルエンザ、コロナ等々の感染症が依然変わらず猛威を振るう中、佐藤進学塾の子たちは一生懸命授業へ参加した。ご理解、ご協力頂いた保護者様、生徒さんには心より感謝申し上げる。
2025.12.30

『卒業生』
冬期講習が終わった後、三人の卒業生が訪ねて来てくれた。
神戸大学医学部医学科の子、香川大学医学部医学科の子、そして、大阪大学工学部の子である。みんな、昔の面影はあるが、しっかりしたきれいなお姉さんになっている。
三人の子たちは一斉に話し始めた。みんな、理系の大学ゆえ、日々の勉強は大変難しくとても忙しそうである。しかし、三人とも第一志望の大学なのでとても充実している様だ。
話していると、三人とも個別指導の学習塾で非常勤講師として働いていることが分かった。そのシステムや学習内容について聞くと「えーっ」と驚く内容ばかりであった。
卒業生たちは面白可笑しく話してくれた。
中学生時代、その中の一人の子は天才型であった。しかも努力を厭わない天才型だったので、学力は盤石であった。復習ノートを毎回提出、私のアドバイス通りに学習を行い学校では常に総合一位であった。
もう一人の子は秀才型であった。私が言う原則的学習を愚直に行い実力を着実に伸ばしていった。しかし、第五回診断テストで大失敗、200点を割り込んだが努力を継続、総合一回では再び220点を超えた。
更にもう一人の子も秀才型で、音読が嫌いな子であった。音読の重要性を伝え徹底的に練習させた。音読が上達すると実力は大きく上昇した。中三・二学期期末テストでは総合二位に一気に躍り出た。
楽しい思い出と共に大変な出来事も多くあった。みんな、それを乗り越えた。そして、今、輝いている。これからも困難なことがたくさんあると思うが、ピンチをチャンスと捉え乗り越えていってほしい。
2025.12.29

『御正月飾り』
十二月二十六日、注連縄を塾建物の中央へ飾り付けた。職人さん手作りのもので、心の温かみが感じられる。
お正月を迎えるにあたって、塾玄関に飾ることに拠り年神様を迎え入れる為の依り代として年神様が下りて来る目印となる。
家の内外を清め、幸福を願う飾り付けとして、古来より日本の伝統文化として受け継がれている。
注連縄が張られていたら結界を意味していて、その場所やものは日常とは異なる神聖性を帯びていることを表している。
注連縄の注連と言う言葉には占めの意味があり、神霊が特定の場所を占めていることを示している。
佐藤進学塾では伝統文化を大切に、生徒たちへ継承していく。
2025.12.28

『師走』
冬期講習期間中は朝から晩までやるべきことがたくさんある。午前中は教室の美装、プリント類の準備、各学年の指導事項の最終確認等を行う。午後からは生徒たちを迎え入れる。
「先生、よろしくお願いします」
前向きな小学生、中学生が復習ノートを次々と提出してくる。二学期期末テストの復習、あるいは全国模試の復習だ。
「先生、通知表オール5です」
中学生が通知表の評価を伝えに来る。二学期、九教科の通知表評価である。中三オール5、内申220㌽であった子もいる。
復習ノートにじっくりと目を通す。一生懸命に取り組んだ軌跡を見ていると、心が軽くなる。一人ひとりに宛てたメッセージを書いて生徒へ手渡す。
通知表を提出した子と話をする。
まず、生徒の感想を聴く。次に、良くがんばった点をしっかりと褒める。その後、改善する必要がある点を具体的に伝える。「この科目はもうひと頑張りで5になるよ」。気が付いたら十分も話している。
私の本意が伝わると、本当にうれしい。もう授業を始めなければならない時間が来ている。小さな教室の中をあちらこちらへと移動して、生徒一人ひとりの目を見て話をする。冬期講習授業は平常授業と同様にもしくはそれ以上に力を入れて指導を行う。
師走の意味、由来には諸説ある。師匠である僧侶が、お経をあげる為に東西を馳せる月という意味である『師馳す』が最も有力な説である。私にとっての師走ももうすぐ終わる。お正月は、少しゆっくり過ごすことが出来そうである。生徒たちもお正月を家族と一緒に楽しく過ごすと良い。
2025.12.27

『サンタクロース』
「サンタさん、来たかな」
「はい、来ました」
「プレゼントは、何かな」
「大好きな本です」
「良かったね」
「はい、うれしいです」
クリスマスプレゼントに本を贈られた子が多かった。私の子たちが小さい時もサンタさんがやって来た。京都のマンションに届けてくれた。その時も、素敵な本が贈られた。
『にじいろのさかな』
マーカス・フィスター著
谷川俊太郎 翻訳
「にじいろに輝くうろこをもった、世界でいちばん美しいさかな。でも、彼はひとりぼっちでさみしい。ある日彼は、かしこいタコに相談にいくことにしましたが……」
虹色の魚は美しい鱗を周りの魚たちにあげていきました。すると、海中が、きらきらしてきました。そのうち、虹色の魚は他の魚と一緒にいることが楽しくなるのでした。とうとう、きらきらのうろこが一枚になってしまいましたが虹色の魚は、幸せな気分になるのでした。絵が大変美しく、心温まる内容です。
2025.12.26

『言葉』
言葉は大切である。
まわりのみんなから明るい言葉を掛けられている子はとても、明るい子に育つ。
まわりのみんなから優しい言葉を掛けられている子はとても、心優しい子に育つ。
まわりのみんなから穏やかな言葉を掛けられている子はとても、心穏やかな子に育つ。
2026年度 生徒募集状況
新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。
「素直で前向きなお子様をお待ちしています」
2025.12.25

『用意周到』
完璧な準備をして、「質の高い指導」を行う。
冬期講習会の準備が整った。完璧な準備を行うには、心の余裕が必要だ。これは、生徒も指導者も同じである。
賢い子は心と体をうまく休ませている。リフレッシュすることが上手なのである。「少し、ゆっくり過ごしたかな」くらいでもいいのである。
さて、冬期講習会が始まる。
昼の部は中三、夕の部は小学生、夜の部は中一、中二である。中三は診断230点突破目標に対策を行う。小学生は算数と国語の総復習を行う。中一、中二は診断テスト対策演習を行う。
一昨年より、中学生は午後9時15分に終了している。これにより、塾から遠い子でも午後11時には就寝することが出来る。
集中して密度の高い学習を行い、睡眠時間はしっかりと確保する。冬休みは規則正しい生活を送ることが大切だ。新年からも、この体制を続けていく。結果は、『成績優秀者一覧』の通りしっかりと出ている。安心して、質の高い教育を受けると良い。
2025.12.24

『年間カリキュラム終了』
中学部全学年の年間カリキュラムが終了した。佐藤進学塾では、学校で一年間掛けて習う内容を十二月までにすべて指導を終える。
数学であれば、方程式の利用、関数、図形に力を入れて指導を行う。特に、一次・二次関数、図形の証明には力を入れる。
さて、中学生は冬期講習では『診断テスト対策』を実施する。二月からは、『学年末テスト対策』を実施する。そして、三月からは、『新学年の予習講座』を実施する。
先を見据えて指導を行っているから結果が出る。各学校の進度を気にする事はない。佐藤進学塾カリキュラムで進行する。
「附属中の進度に合わせているのですか」
と時々、聞かれる。
「合わせていません。佐藤進学塾のカリキュラムに則り進めています」
といつも、答える。
さて、中一の子たちには診断テストと学年末テストの話をした。診断テストは初めて受けることに成る。範囲が広いこと、定期試験とは形式が異なることを話した。中二、中三で上位成績を取得している塾生の学習姿勢と具体的な学習内容についても伝えた。
まず、一つ目は冬休み中に平常授業の塾テキストを復習して全問題を即答出来る様にしている。そして、二つ目は学校のテストで間違った問題を、教科書、ワークで復習して完全理解している。最後に三つ目は冬期講習の復習を教科書を使い隅々まで復習行うと共に塾の国語発展テキストを仕上げている。
あとは、診断テスト対策後に復習することで210点を超える。仕上がりが非常に良いと220点を超える。問題と相性が良くコンディションも良い時は230点を超える。高松高校入学後を考えるならば、220点を超える必要がある。この様な話をすると、結果を出す子は真剣な眼差しで聴いている。
2025.12.23

『全国模試』
全国模試の受検が全学年、塾生全員、無事に終了した。今回の成績表は、一月下旬に届く。それまでにやるべきことがある。
1.自己採点
2.問題の解き直し
3.弱点分野の復習
自己採点の段階で90点を超えていれば、勉強方法は正しく軌道に乗っていると言える。自信を持って学習を続けると良い。
90点を下回っている様であれば注意が必要だ。家庭学習を見直さなければならない。勿論、間違った問題は直ぐに解き直す。
「凡ミスだった」など甘いことを言ってはいけない。凡ミスと思っている問題は、本質的な理解が出来ていないことが多い。
計算ミス、漢字の間違いなどを侮ってはいけない。そのままにしておくと、同じミスを何度も繰り返す。間違った問題は教科書、辞書、参考書を徹底的に調べ、間違った原因について深く考える。丁寧に解法を書いて、筋道立てて考えていく。それを三回繰り返して初めて本質的な理解が得られる。
「一日後、三日後、七日後に行うと効果が高い」と脳科学の研究者が著書に書いていた。エビングハウスの忘却曲線を見ても分かることだ。結果が出ない子はこれらをやっていないか軽く見ている。結果が出る子はこれらを丁寧に時間を掛けて行っている。その差が日を追うごとに開いていく。
「心の底から出来る様に成りたい」という思いが、強いかどうかである。テストが終わった今、やるべきことはたくさんある。「テスト前ではなく、テストが終わった今が最も大切なのである」。
2025/12/22

『テスト結果』
附属小学生の第三回学力テストの結果が出た。良く頑張った。良いところを褒めて、学習の改善点を伝えた。
中学生の二学期末テスト結果もほぼ出揃った。五教科・九教科『総合一位』を始め、上位成績取得者が今回も多く出ている。
「よく、がんばったね」
と声を掛ける。
「ありがとうございます」
と笑顔でこたえる。
結果は『上位者一覧』として教室に掲示している。来月十五日頃にプリントした書類を生徒を通じて各家庭に配布する。
素晴らしい結果が出ている子には共通することがある。
①塾と学校の平常授業の復習を、毎日必ず行っている。
②テスト三週間前から、テスト勉強を真剣に行っている。
③音読、書写、反復を徹底して行い理解、暗記している。
(※スマホの扱いは、時間、内容とも保護者が管理している。持っていない子も多くいる)
結果に納得いかない子は三点のいずれか上手くいっていない。殆どの場合『①平常授業の復習』である。そこを見直し、実行に移す事で納得いく結果が出る。
上位十位内を継続的に取得している子たちが行っている共通することがある。数学・英語・国語、塾の『発展テキスト』である。教科書、ワーク、ノート、プリント等は完璧に仕上げた後の話である。最後に発展テキストの試験範囲に挑戦している。(附中の子は実練テキストを徹底的に行っている)
2025/12/21

『中三「総括」』
中三は今回も素晴らしい結果が出た。二学期末テスト、国立中学校『総合1位』の子が一人、公立中学校『総合1位』の子が二人出た。上位十位内に入った子も多くいる。
上位三名の子に共通していることがある。
『小四』の時、全員入塾した。
みんな、表情が明るい。勉強以外に好きなことをやっている。丁寧に学習している。宿題と復習は必ず行っている。確固たる学習習慣が身に付いている。
普段を大切に学習している。それらを小学生時代に身に付けている。中学生になり特別なことをしているわけではない。
「効率的な学習が出来ている」
テスト前に、睡眠を削って夜遅くまで勉強しているわけではない。塾で二三時間集中して学習する。それから家に帰り、気になる事を学習したら次の日の準備をして寝る。夜の十二時までに就寝、集中して学習したら、風呂に入って早く寝ている。
やるべき時にやるべき事を驚くくらいに集中して学習しているのである。ゾーンと言われる集中状態だ。話し掛けても気付くことはない位集中している。その時間を佐藤進学塾は大切にしている。
今の様なテストが終わった時期に本気で指導を行っている。簡単な内容はやらない。難しい内容をじっくりと時間を掛けて教える。目先の点を取る為ではなく、好奇心を喚起する為の授業指導を心掛けている。
流石に上位の子たちでも『三平方の定理「空間図形」』は習得に時間が掛かる。しかし、今やっていれば冬休みまでに習得できる。入試頻出である。今、大切なことを学習することが重要だ。
テスト前ではなく、『テストが終わった「今」』が大切なのである。
2025/12/20

『中学生「総括」』
中学生の平常授業は全教科、該当学年ののカリキュラムを全て終えた。来週から冬期講習となり、診断テスト対策を始める。
定期テストの推移を伝えた。50%の子が上位安定、30%の子が上昇基調、20%の子が横ばいであった。
「なぜ、この様な差がつくのか」
生徒たちに訊いてみた。
「復習の差だと思います」
「その通りだね」
「先生の話をよく聞いているかどうかではないですか」
「それも、あるね」
「勉強と部活のバランスだと思います」
「確かに、そうだね」
みんな、よくわかっている。大切なことが分かってきている。学力だけではなくメンタルが関係することも理解出来てきている。でも、もう一つ、差がつく大切なことが出ていない。
「もうひとつあるんだけど」
と、訊いてみた。
「『音読』です」
と私が言う。
「あっ、そうだ」
と言う顔になる。
原則的学習の『音読・書写・反復』いずれも大切だが、中でも『音読』は特に大切である。小三の時からその大切さは常に伝えている。塾の授業中も音読を重視している。すべての教科で皆に音読してもらう。中でも理科、社会は授業中の60%近くの時間は私も含めてみんなで音読をしている。
元々、上手な子もいるが、練習を重ねる間に驚くくらいに上手になった子もたくさんいる。大体、一二年一生懸命に練習すれば上手になる。それを素直にやるかやらないかである。音読が上手な子は成績が上位安定している。音読が上手になった子は、成績が上昇基調にある。この関係は絶対である。
十年ほど前、音読の大切さが教育現場で取り上げられることが多かった。特に、私立小中学校でこの大切さが大いに語られていた。今、日本ではタブレット学習ばかりが最先端で良い事の様に取り上げられる。
しかし、先進諸国では先行実施、その弊害が取り上げられ、IT機器を取り入れると成績の伸びが鈍化する事から紙媒体で学習を行い、音読や計算、書写を大切にする学習へ再び戻して一年が経過した。学習方法自体、世界レベルで見ていかなければ、子どもの能力を最大限に伸ばし育てることは出来ない。
生徒たちに訊く。
「出来ている子は何が違うのかな」
「学校でダントツ一番の子は手の指にタコが出来ていました」
「塾で一番出来る子に訊くと、『教科書の勉強を一番大切にしている』と言っていました」
「一番の子は『ワークを10回以上反復して覚えた』と言っていました」
子たちは一番大切な事に気付き始めたようだ!
2025/12/19

『「全国模試」終了』
「テストは終わってからが始まり」
何時も、私が言う言葉だ。
「どの問題を間違ったのか」
結果を出す子は、自分の答が気になる。
試験後、すぐに自己採点を行う。そして、間違った問題を見つけ出す。解答解説書をよく読んで、間違った問題を解き直す。
「なぜ、間違えたのか」
その原因がとても気になる。
結果が出るのは約一か月後だ。
それまでに間違った問題は復習する。出題元を教科書、塾テキストから探し出して根元を理解する。問題を解き直して間違った原因を考える。参考書を活用して理解を深めて、知識を広げていく。
一か月後に結果が返却されたら、もう一度復習する。その時には、スラスラと解くことが出来るはずだ。既に丁寧に復習しているから、点数は気にならない。
「二度と間違わない事が大切だ」
2025/12/18

『以心伝心』
以心伝心とは、文字や言葉を使わなくても互いの心が通じ合うことを言う。もとは禅宗の言葉で、文字や言葉では表すことの出来ない仏の神髄を師が弟子に伝えることである。
さて、小学高学年、中学生の生徒たちが姿勢を正して全国模試を受けている。その姿を見て心底「素晴らしい」と思った。
今までに、何度も注意した。姿勢の大切さを繰り返し伝えた。そして、今、美しい姿勢で模試を受けている。
入塾した子たちには最初に姿勢の大切さを伝える。テキストを真っすぐに置く。おなかと背中にこぶし一つ分をあける。左ひじはつかず、背筋をスッと伸ばす。
姿勢が美しく成れば、必ず、良い結果が出る。勉強の神様は、その子の心を見ている。姿勢が美しい子は、心が美しい。
生徒たちに文字や言葉で大切なことを伝える。手を替え、品を替え、一生懸命に伝え続ける。以心伝心、上級学年になると、多くを語らずとも此方の意図することが殆ど伝わる様に成る。
たまに、姿勢がくずれることはある。その時は、「姿勢に気をつけてね」と声を掛ける。それを、素直に受け入れて、「はい、気をつけます」と直せばいいだけだ。小四は、まだまだである。しかし、その中に二人、きちんと守っている子がいる。テストも時間いっぱい、集中して解いていた。結果が楽しみだ。
2025/12/17

『夢つうしん』
一月号の書類を生徒へ手渡している。先週金曜日、中一、中二の生徒さんから配布し始めて、今週水曜日、小四の生徒さんに配布し終える。親子一緒に内容をご確認願いたい。
1.夢つうしん
2.生徒宛の手紙
3.中三診断テスト成績優秀者一覧
4.診断テスト対策日程(※中1・中2)
5.学年末テスト対策日程(※中1・中2)
6.入試対策日程表(※中3)
以上である。
今週金曜日で塾の二学期平常授業は終了する。その後は、冬期講習会の日程に合わせて授業を実施する。学年により日程は異なる為、プリントをよく確認してから通塾を願う。
2025/12/16

『全国模試週間』
「全国模試で大切なことは」
1⃣問題用紙が配られたら、問題全体を一、二分位掛けてゆっくりと見渡していく。同時に難しそうな問題は印を付ける。
2⃣問題をよく読んでリズム良く解いていく。見た事ない問題、 難しい問題は無理して解くことはせず、後回しにする。
3⃣問題を解き終わったら、気掛かりな問題を丁寧に見直す。時間があれば全体を見直すが、ない時は二、三問に絞り込む。
長く通っている生徒たちはそれらを守る事が出来る様に成っている。何よりも素晴らしいことは、テスト前にテキストや参考書を出して復習していることである。
精鋭の生徒たちが集中して取り組む。制限時間いっぱい使って丁寧に問題へ取り組む。二、三問、気掛かりな問題に絞り込んで見直しをしていく。
上位安定している子は90~100点を狙い、上昇基調に在る子は80~90点を狙うとよい。問題の難易度にも拠るが採用している全国模試は80点で偏差値60、90点で偏差値65、100点で偏差値70位になる。
中三は入試のプレテストとして取り組む。テスト中は、最初から最後まで最大限に集中する。時計を見るのは二、三回程度である。佐藤進学塾の素晴らしい伝統を受け継いでいる。これからも、益々、頑張ってほしい。一生懸命に取り組む子たちを本気で応援する。
※2026年度 生徒募集状況
新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。
新小3・新小4・新中3は『残席「各2名」』です。
新中1は定員に達していますので、入塾希望の方は予約待ちに登録してください。
「算数・数学が得意な子、読書が好きな子、家庭学習を行う子をお待ちしています」
2025/12/15
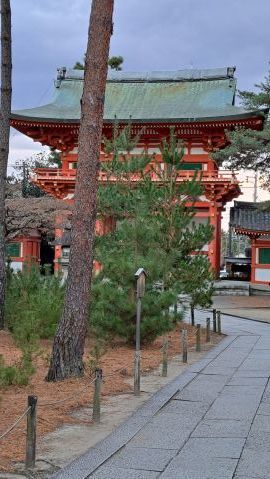
『偏差値70』
全国模試で偏差値70を突破する子が佐藤進学塾には多くいる。科目別ではなく、三科目、五科目合計の総合偏差値である。
中二後半から偏差値70を超える様に成った子がいる。小学生の時は、あまり勉強が出来る子ではなかった。
入塾面談の時に質問をした。
「得意教科は何かな」
「…」
「将来の夢は何かな」
「…」
「読書は好きかな」
「…」
何か答えようとするが、言葉が出てこないようだった。当然、入塾時は総合偏差値50にとどかなかった。しかし、この子は素直で真っ直ぐな心の子であった。私が言うことを、いつも耳を澄まして聴いていた。私が言う通りに復習をする努力を続けた。その間、保護者様も陰に陽にご協力頂いた。
結果が出なくても、その努力をやめることはなかった。三年後あたりから良い結果が出始めた。伸び悩んでいた偏差値が、一気に65を超えた。自信がついたのか、それ以降はその実力を維持した。
その時、その子に訊いた。
「数英国は安定してきたね。最近、社会も確実に点を取っている。 なぜ、こんなに社会が出来るようになったのかな」
「…」
矢張り、言葉が出てこなかった。
少し待つと、ぽつりぽつりと話し始めた。
「中一の時に地理と歴史に強い興味を持ったんです。小学校の時に佐藤進学塾で習ったことを、中学校になり今度は学校で再び習う、その時、本当に面白いなと思ったからなんです」
佐藤進学塾には努力型の秀才が多い。天賦の才能を持つ天才は諦めて凡人になることがある。ところが、努力型の秀才は諦めることをしない。諦めることなく努力を続けることで必ず勝者となる。
2025/12/14

『寒暖差』
近年、体調がすぐれない子が多くなった。それに加えてなかなか治らなかったり、ぶり返したりする子が多くなった。夏が、暑過ぎて秋はなく、一気に冷え込んだせいだろうか。
さて、寒暖差疲労と言う言葉がある。気温の変化に体がついていかない状態のことをいう。
ヒトの平熱は、36℃~37℃位に保たれている。体を守る為に、人は体温を一定にコントロールするホメオスタシスの仕組みが備わっているからだ。
多少の温度変化であれば、ホメオスタシスが機能する為、問題はない。しかし、寒暖差が大きくなると、体温を一定に保つ為、自律神経の働きが活発になる。
結果、エネルギーを過剰消費して、体に疲労が蓄積する。その疲労は肉体的な不調もあれば、精神的な不調もある。その両方の時もあるから、非常に厄介である。
不調を軽減する方法が書籍には示されている。
1.温度差をなくす
2.バランスのとれた食事を心がける
3.良質な睡眠をとる
4.適度な運動をする
5.お風呂にゆっくり浸かる
私たちが、協力できることもある。
1,3,4,5,の四点である。
「1」教室内の温度をエアコンで細やかに調整出来る。
「3」授業終了時刻を午後9時15分に設定しているから安心である。
「4」塾の勉強と部活動やスポーツクラブの両立をすすめている。
「5」大部分の子が午後9時半頃までに帰宅出来るから余裕がある。
「2」は保護者様が一生懸命に考えられている。
気温の変化は体にとって大きなストレスとなる。激しい寒暖差が続くと、自律神経のバランスが崩れる。そして、疲労がたまり、様々な体調不良を引き起こす。日頃から出来る限りの対策を行い、寒暖差疲労をため込まないようにしよう。佐藤進学塾では健康管理を第一に考えている。
※2026年度 生徒募集状況
新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。
新小3・新小4・新中3は『残席「各2名」』です。
新中1は予約待ちです。
「素直で前向きなお子様をお待ちしています」
2025/12/13

『「全国模試」意義』
上位校を目指す都心部の子は、全国模試を重視する。偏差値で自分自身の実力を知り、志望校を考える。志望校を決めてからその学校の合格偏差値を目指す子も多い。
全国模試自体、多くの種類がある。難易度にも差があり、模試受験者層の学力も異なる。同じ偏差値「60」でも、同等に扱うことは出来ない。ものさしの目盛りが異なるからである。
高校になると、三社の模試を受験する。そして、冷静に全国区で受験校を判断する。さて、高松高校を受験する時は、殆どの中学生が診断テストの成績と通知表評価のみを基準に決める。
しかし、それだけでは合否が一致しない子がいる。それを一致させる為に、全国模試偏差値推移を加える。佐藤進学塾採用の模試では偏差値68で推移している子は100%合格する。
「本番は練習、練習は本番」
私が良く言う言葉である。
練習の全国模試は本番のつもりで受けるべきである。しかし、所詮、練習なので上手くいかない時は復習すれば良い。何回、失敗しても、復習して改善し続ければいいのである。その為に全国模試は実施する。高校入試は、一回勝負である。こちらは力を抜いて、練習の感覚で受けなければならない。
2025/12/12
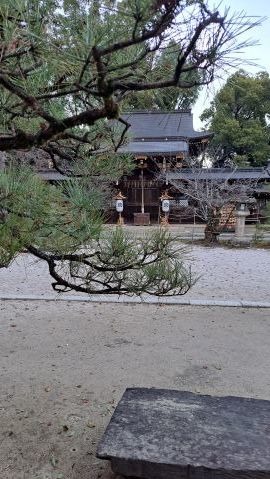
『「全国模試」週間』
来週より全国模試を実施する。最初に問題用紙が配布される。その時、すぐに問題を解き始めてはいけない。
まず、問題すべてにゆっくりと目を通す。どの様な問題が出ているかを確認する。その為に「一、二分」時間を使う。
見直しを前提に解いてはいけない。ゆっくり丁寧にリズム良く解き進める。難しい問題は、印をしてあとで解く様にする。二、三分考えて、わからない問題もあとに回す。
殆どの問題は確実に解くことが出来る。だから、あわてる必要はない。二、三問、難しく感じる問題がある。それらはあとに回せばいいのである。ここで粘ると、時間配分がくずれる。
解けなかった問題はあとで復習すれば良い。それが、全国模試の大切なところである。所詮、模試は入試の練習である。
分からない問題がある事に意味がある。難しい問題に出会うから楽しい。丁寧に復習していれば、90点は取得出来る。佐藤進学塾採用の全国模試は良質な問題が殆どだから安心して取り組めばいい。
「最後に、大切なことを伝える」
模試を受ける時は緊張しているので、解くスピードが速くなる。
「では、どうすればよいか」
自分の普段の『音読』の速さと『黙読』の速さを完全に合わせる。
一人ひとり、問題を解く最適なスピードは能力に拠り異なる。他の人の問題を解くスピードを気にしてはいけない。猛スピードで解いている人は多くのミスをしている。
模試受検中、実際に声を出すことは出来ない。しかし、賢い子は頭の中で必ず声を出している。実際に音声は出ていないのだが、しっかりと声を出しながら丁寧に文章を読んでいる。インナースピーチと言う。
「そうすれば、実力を発揮出来る」
2025/12/11

『入塾申し込み』
今年も入塾の問い合わせが多い。
コロナ禍、一時期はピタッと止まっていたのが嘘の様である。十一月頃から問い合わせが増えている。すでに、殆どの学年で新年度の定員が9割以上確定している。残席は一、二名だ。
佐藤進学塾は看板がない、広告もない、テレビ・ラジオ・SNSのCMもない、安易な広報活動はしない。唯一、ホームページにて塾の内容についてブログを中心に毎日発信している。
それでも、問い合わせは多い。
この時期、問合せフォームの質問に対するメール返信で多くの時間を使う。平日は平常授業を行っている為、入塾三者面談は土曜、日曜に行う様になる。小さな塾ゆえ時間は限られる。
新小3、新小5、新小6、新中2は、早くも残席「1名」となった。各学年、定員に達した場合は予約待ちになる。申し訳ないが、新中1は予約待ちである。ご検討中の方は、早めにご連絡願えるとありがたい。新年度生がはやめに確定すると、授業指導に専念できるので私たちも心底うれしい。
入塾希望の方は『問合せフォーム』の送信をお願いする。12月中旬からは冬期講習準備の為、返事は少しばかり遅くなることを了承願いたい。この調子だと、来年早々には定員に達して募集は締め切りと成る。
※2026年度 生徒募集状況
新小3・新小5・新小6・新中2は、『残席「各1名」』、新小4・新中3は『残席、「各2名」』です。新中1は『予約待ち』です。定員に達した時はその時点で予約待ちとなります。
「素直で前向きなお子様をお待ちしています」
2025/12/10

『全国模試』
中三の子は受験校を決定する。
①中学三年間の「内申点」
②「診断テスト」の得点
③「全国模試」の偏差値
三点の数値を見て決める。
① 200点/220点中
② 220点/250点中
③ 68ポイント
三点の数値が揃うと、高松高校合格可能性は80%を超える。
学校では①②の数値で話し合う。
塾では③の数値をくわえて話す。
偏差値を重視しない子もいる。
学校では話題に出ないからだ。
合格者追跡調査表を見ると、模試偏差値と合否の相関は高い。
全国模試を大切に考えてほしい。
一月テストを、来週に実施する。
模試予定表の通りに実施する。
学校のテスト同様大切にしよう。
高校の実テや全国模試へ繋がる。
2025/12/9

『ていねいさ』
字を丁寧に書く子は、勉強が出来る。字の上手、下手はあまり関係ない。下手でも、字が丁寧な子は出来る様に成る。
テスト勉強も終盤になると字を丁寧に書く子と、そうでない子に分かれる。丁寧に書いていない子は焦っている。焦っているから、鉛筆の音もカチャカチャと大きくなる。
「冷静さが大切だ」
丁寧に書いている子は、自律神経が整っている。交感神経と副交感神経のバランスが良い。呼吸が深く、しっかりできている。心に余裕があるから結果が出る。
脳科学者が「気持ちを落ち着けるには、『呼吸を整える』ことが最も有効である」と書籍に書いていた。
解答を丁寧に書いている子は高得点だ。「△」かなという答えに「〇」がついている時がある。学校の先生も丁寧な字が心地良く、思わず「〇」をつけたのだろうと思われる。結構良くあることだ。
2025/12/8

『傾聴』
傾聴の「聴」の漢字が意味することは、言葉に「耳」を傾け、表情に「目」で注意を払い、感情に「心」を配り、大切な話に共感することだ。
目、耳、心を使って話に耳を傾けると、相手もこちらを理解してくれる様に成る。出来る子と言うのは傾聴する事が出来る。その親も傾聴する能力が高い。
友人間で傾聴を大切にすると、その関係性は良好な状態が長く続く。師弟間で傾聴を大切にすると、生徒は先生の話を良く聴く様に、先生もその子の話を大切に聴く様になる。
親子間で傾聴を大切にすると、親子関係が良くなる。何より、子が親の話す事を良く聞く様に成る。
「うちの子は親の話を聞かないんです」と言うのは、実は親が子の言う話をよく聞いていないことが原因である。
テストが終わった今、傾聴することを大切にすると良い。
私自身も気をつけたい。
2025/12/7

『全国模試』
全国模試1月号を12月中旬に実施する。それに向けた問題集の冊子を配布する。まずは、ゆっくり丁寧に解いてほしい。
後は、以下を行うと良い。
1.塾テキストの復習
2.教科書、参考書の学習
3.前回模試「8月号」の復習
「90点」以上取得を前提に学習しよう。そうすれば、偏差値は「65」を超える。高松高校の合格可能性が高くなる。
テスト前一週間は、全力で試験勉強を行うこと。小六は附属中入試と、中学一二年生は三学期学年末テストの範囲と重なっている。中三は第五回診断テスト範囲とも重なっている。
集中して、試験勉強は行うと良い。
だらだらと長時間やる必要はなく、やるべきことを行ったならば、早めに就寝しよう。一生懸命に学習した内容は睡眠中に脳内で整理されて、不要なことは排除され大切な事は記憶として定着していく。
2025/12/6

『中一数学』
「球の表面積と体積」
公式を覚えるとよい。
覚え方は授業中に伝えた。
表面積…4πr²
体積 …4/3πr³
3.14を計算に使わない。
拠って、計算は楽である。
文字式の計算が大切になる。
三回反復すればコツは掴める。
r²=r×r
r³=r×r×r
の形で約分して計算するといい。
2025/12/5

『「塾庭」樹木の剪定』
庭師さんが、塾の樹木を綺麗に整えてくれた。塾の庭師さんはとても誠実な方である。朝から夕方まで、心を込めて剪定して下さった。
朝七時半過ぎに到着して準備を整えて、朝八時から樹木の剪定へ取り掛かる。十時に休憩、お茶を飲みながら話をする。
「枯れている木がありますね」
「今年は暑かったからですか」
「たぶん、そうでしょう」
「最近は暑すぎるのですね」
「どこの庭も木が弱っています」
「木が可哀そうですね」
しばらく、話は続く。その後、正午まで剪定作業を続けられる。午後は一時から剪定を再び始められる。午後三時に休憩、美しく整えられた庭を見ながら話をする。
「綺麗になりましたね」
「最近、庭木は少なくなりました」
「木があると心が落ち着きます」
「私も本当にそう思います」
「私も剪定に力が入ります」
「とても、ありがたいです」
「皆、気持ち良く勉強出来ます」
「では片付けをして終わります」
塾庭は、美しく凛としている。テスト対策期間中、昼も塾で勉強する。庭の緑を眺めながら勉強すると、集中力は高まり勉強が捗る。何より、目に優しい。庭の木々も生徒たちを応援してくれている。
2025/12/4

『入塾面談』
12月~3月、毎週土、日曜日に新年度入塾面談を行っている。お子様には適性検査(30分)を受けて頂く。その間、保護者様には佐藤進学塾の理念・方針を詳しくお伝えする。
保護者様からは質問を受け付け、丁寧に答える。適性検査終了後、『漢字・文法・語彙・読解』について、現時点での実力を判定して今後の課題についてお話しする。
その後、保護者様、お子様、塾長の三者でしっかり話し合う。適性検査を合わせて『80分』の時間を掛ける。保護者様の疑問点について、丁寧にお答えさせて頂き、安心して頂く。
進学塾の授業は一年間受けて初めて良さが分かる。長い時間を掛けて三者にて心を開いて話し合うので、深いところまで話を進める事が出来る。
保護者様がホームページ、特にブログをよく読まれている場合は話が早い。お子様が、礼儀正しく元気に挨拶が出来る素直で前向きな子であれば、入塾の手続きはスムーズに進む。お子様が、丁寧にスリッパを揃え、お礼の言葉を伝えて挨拶して帰って行く子もいる。うれしい事にそんな子が殆どだ。
素直で前向きな子には最適な進学塾である。ヤル気ある子の為に静謐な学習環境を守り抜く。高松高校を本気で目指すお子様に来て頂きたい。人の気持ちを思いやることの出来るお子様を待っている。
※2026年度生募集開始
新小3『新規募集』、新小5・新小6・新中2『「各1名」募集』、新小4、新中3『「各2名」募集』となっています。新中1は『予約待ち』となっています。素直で集中力のあるお子様をお待ちしています。まずは、「お問合せフォーム」を入力後、送信願います。定員に達し次第、募集は締め切らせて頂きます。
2025/12/3

『静謐な学習環境』
佐藤進学塾は静謐な学習環境を維持している。松縄、熊野神社東側の閑静な住宅街の中に立地、開校以来、少人数定員制指導を貫く。高松高校を第一志望校として頑張る子を応援する。
佐藤進学塾は凛とした空気が漂っている。先生と生徒、皆で話し合う時間は重要と考えて、様々な学校の子が情報を共有する場としている。小さな教室だが、活気は溢れている。
一人ひとりに合った、効率の良い学習方法を教える。それを習得するには時間が掛かることは事実である。しかし、皆、諦めることなくその学習方法を習得する。
塾では二、三時間、集中して学習する体制を整える。家でも二、三時間、復習する内容を具体的に伝える。それ以上は強要しない。興味あることに時間を使うことも大切だ。
人間、集中力が維持出来るのは「五十分」である。それを二、三セット行う。人間の脳の習性に合わせて、学習時間を設定している。あとの時間は、自由に使えばよい。本当にやる気ある子の集団だから成り立つ。二、三時間の学習で、最高の結果を出す。自分の力と私の指導を信じて努力する子を応援する。
※2026年度生募集開始
新小3『新規募集』、新小5・新小6・新中2『残席「各1名」』、新小4、新中3『残席「各2名」』、大変、申し訳ありませんが、新中1は『予約待ち』となっています。素直で集中力のあるお子様をお待ちしています。まずは、「お問合せフォーム」を入力後、送信願います。
2025/12/2

『テスト対策「完成」』
附属小六年生の第三回学力テスト対策、公立中・附属中学生の二学期期末テスト対策が完成した。
「本当に良く頑張った」
中学生はテスト対策中に色々な話をする。大切なことに気付いてほしいからだ。琴線に触れるまで様々な話をする。それ以外は静かに見守る。
「本が読みたい」
「部活を思いきりしたい」
「栗林公園のライトアップを見に行きたい」
テストが終わってからやりたいことは色々とある様だ。好きなことを好きなだけやればいい。ご理解、ご協力頂いた保護者様に心より感謝申し上げたい。
2025/12/1

『「小五」算数』
小五の算数は、『割合』の指導を終えた。数学に繋がる大切な単元である。また、国語の読解力が必要になる。
「もとにする量、くらべる量、割合」
問題文を読んで、もとにする量とくらべる量を見つける。「は」、「の」、「に」、「を」に気をつけて読んでいく。その後、関係図に書き表す。
素早く、正確に!
小五の基本的な割合の問題は線分図より関係図がよく分かる。左側にもとにする量、右側にくらべる量を書く。その間に矢印を書いて割合を書き込む。
あとは公式を使い計算する。
中学数学ではすべてxを使って、方程式で解くことが出来る。しかし、小学生の間は関係図を書いて理解することが大切だ。割合の応用問題に入ると、線分図を書いて考える方法を指導する。線分図は、一本、二本、三本と増えていく。書く時と解く時は、線分図の順番を逆に考える。
具体的な解法は授業で伝えた。
中学の数学では方程式が使えるのは事実だ。しかし、発展問題は問題文が非常に長い。そこから、もとにする量とくらべる量を瞬時に見つけ出す必要がある。その力は小学算数で身に付けておく必要がある。時々、適当にかけたり、わったりする子がいる。この様な子は直ぐに行き詰まる。
矢張り、関係図を書いてから式を立てることが大切だ。関係図を書く時間は慣れると、ほんの十数秒だ。その時間を大切にすると、正確に答えを出す事が出来る。ノートに書かれた解法の過程を見ると、その子の算数力、数学力が今後伸びるかどうか直ぐに分かる。
計算の速さ、正答率を気にする親御さんは多い。実際、計算力が高い子は算数が出来る。ところが、抜群に数学が出来る子は、計算力以上に問題文を図や絵に表す能力が非常に高い。計算力よりも、そういった創造する能力を大切に考えた方が良いと私は考えて指導している。
2025/11/30

『紅葉』
淡路島の夢舞台へ行ってきた。
以前は採石場であったところである。建築家安藤忠雄氏、グランドデザインに拠る施設群が伸びやかに広がる。
高度経済成長期、経済活動の為に山を削った。人間が破壊した自然を本来の姿に戻し、様々な動物や植物と人間が共生出来る空間を創造して出来上がった淡路夢舞台だ。
どの角度から見ても、どこを切り取って見ても美しい。山の緑、海、空、コンクリートが見事に融合している。世界の安藤氏が考えた素晴らしい紅葉を楽しんできた。
近年、人気の新しい施設やカフェ、レストランのオープンが続いているのが淡路島西海岸エリア。週末になると非常に多くの観光客であふれかえる程、人気の観光スポットとなっているそうだ。
それに比べて、淡路夢舞台がある東海岸はとても静かである。
2025/11/29

『計算ミス』
佐藤進学塾ではノートに計算の過程を丁寧に書く習慣を付けるように指導する。筆算はマスに合わせて数字を書いて、線分はものさしを使って書くように伝える。
それを素直に守る子は、間違いなく計算ミスは減る。計算ミスが多い子は数字が雑な子、計算を丁寧に書かない子、無理して暗算をする子である。速いばかりで正答率は低い。
「暗算でさっさとやりなさい」
といつも言う親御さんがいた。
その子は、無理して暗算で答を求めた。結果、計算ミスが多い子に成った。速く解き終わっても見直しをしない。残念だが、親がきつい事を言うと取り返しのつかない事になる。
「ゆっくり、計算すればいいよ」
私が言っても、聞かなかった。
その後、親御さんから、
「うちの子、計算ミスが多いんですけど、どうしたらいいですか」
という相談があった。
「ゆっくり計算するよう、言葉掛けしてください」
と理由を添えて伝えた。
「それでは速く出来るようになりません」
と聞く耳を持たなかった。
その後は、…、である。
「先生が仰られた通りにしよう」
と言って下さる親御さんもいた。
その子は、ノートに大きく筆算を書いてすべての問題を解いて来た。毎週、ノート一冊を使って、濃い字で心をこめてびっしりとノートに書いて来た。
「すごいね、時間が掛かったね」
と、私が言うと、
「そんなに時間はかかりません」
と、生徒は答えた。
「本当に良くがんばったね」
と、私が褒めると、
「筆算はとても楽しいです」
と、その子は答えてくれた。
その子は計算ミスが殆どない子に育った。小六の後半からは算数の偏差値が常に65を超えた。中学生では数学の偏差値が常に70を超える様に成った。
「先生、数学はおもしろいです」
と言って、私が推薦する『「発展テキスト」数学』にいつも取り組んでいた。もちろん、今、高松高校でも理系へ進んで数学を愉しんでいる。筆算を丁寧にを書いて計算する子は算数、数学が出来る子に成る。勉強に限らず、何事であってもゆっくり丁寧に行うということは本当に大切なのである。
2025/11/28

『卒業生の話』
医師を目指して高松高校で頑張っている子の話である。その子は中学二年生からグッと成績が伸びた。中学校では上位10位内となり、全国模試偏差値五科70を超えた。
その子が最後に言った。
「部屋を片付けたら、昔の模試が出てきました」
「いつ頃の模試かな」
「小四の時の模試です」
「入塾して、間もない頃だね」
「はい、そうです」
「結果はどうだった」
「国語の偏差値が『46』だったんです」
「えーっ、そんなに低かった」
「母とそれを見て、思わず大笑いしました」
「それは笑うしかないな」
「あれから、一生懸命頑張って本当に良かったです」
「本当に良く頑張ったね」
「お母さんも『良く頑張ったね』と言ってくれました」
「それは本当に良かったね」
小四で入塾してから卒業するまで、音読・書写・反復を行う『原則的学習』を忠実に守った。復習を必ず行い、ノートを提出した。私がそのノートにアドバイスを書き込むと、その通りに学習方法を改善してから再び提出してくれた。とても、素直な子であった。
それを繰り返すうちに、効率良い学習が出来るようになった。その陰に保護者様のご協力が在ったことを感じた。塾の授業中は集中力を高めてゾーンの状態に入り授業を受けていた。
普段は二、三時間、テストや入試前は四、五時間集中して学習を行い、午後十一時に日々就寝していた。睡眠をしっかりとっているので、いつも頭は冴えていた。それで、しっかり結果を出した。今も、結果を出していると言う。陰ながら応援している。
2025/11/27
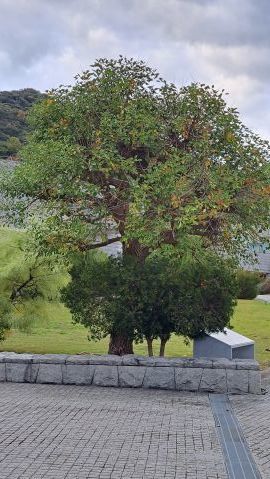
『「テスト対策」最終日』
本日、対策最終日だ。生徒も、ここまで本当に良く頑張った。あと一日、頑張って実力を発揮すると良い。
気を付けるべきことがある。
「あと一日で終わり」
と思ってはいけない。
「もうすぐ、終わり」
と考えると、脳が緩んでしまい脳のパフォーマンスが最大限に発揮出来ないそうだ。
スポーツドクターはオリンピックを目指す水泳選手にゴールの先を考えるように伝えるという。
100mがゴールならば、さらに先の120mをゴールと考える。「ゴールを突き破る感じで泳げ」と言うそうである。また、「次の大会を意識せよ」とも言うそうだ。
佐藤進学塾の生徒たちは本当に良く頑張った。テストは一旦、明日で終わる。しかし、「日曜日に終わる」位の意識でいくと良い。12月中旬の全国模試や2月中旬の診断テストを意識してテストに臨むと良い。
最後に、生徒へ訊いた。
「テストが終わったら何したい」
「とにかく、ゆっくりしたいです」
今週は、ゆっくりするといい。
2025/11/26

『「小四」算数』
『大きな面積』を指導する。
1.複雑な面積の求め方について、三通り習得する。
2.面積の単位の関係を理解、換算方法を習得する。
複雑な図形を書き写して、全体をイメージすることが重要だ。全体からつけたした部分を計算して、順にひいていく。ノートに筆算を行い、丁寧に計算して答を導き出していく。
その後、単位を換算する。
1a(アール)=10m×10m
=100㎡
1ha(ヘクタール)=100m×100m
=10000㎡
1㎢(平方km)=1000m×1000m
=1000000㎡
これらの単位の関係は確実に覚える。覚えるまでは、換算表を見ながら確認して換算すればよい。
①2500㎡=25a
②5000ha=0.5ha
③10ha=1000a
単位の換算が直ぐ出来る様にする。
小数点を右へ移して、10倍、100倍、…、とする。小数点を左へ移して、1/10、1/100、…、とする。私が授業中に伝えた具体的な方法を使うと、速く正確になる。これら、単位の換算は出来る子でも間違う。時々、まったく間違うことなく出来る様に成る子がいる。
かつて、その子に聞いてみた。
「なんで、こんなに速く正確に出来るようになったの」
「お母さんと、毎朝、五分間いっしょに練習しています」
「どれくらい、続けているの」
「二か月くらい、続けました」
「良く頑張ったね」
「お母さんは、私がよく間違う所をプリントにまとめてくれました」
「お母さん、すごいね」
「はい、それを毎日練習すると間違う所はほとんどなくなりました」
その子は中学生になり、自分でノートにまとめることがうまくなった。小学生の時、お母さんがまとめてくれたプリントが基になっている様だ。私が「こうすると良くなるよ」というと、それも実行して更に力を伸ばした。その後、この子が抜群に出来るようになったことは言うまでもない。
2025/11/25
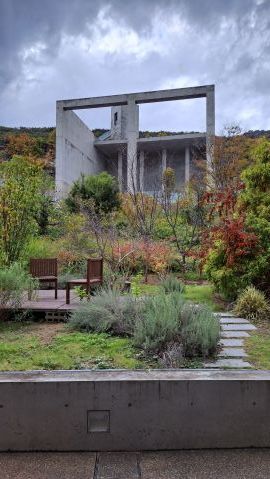
『テスト直前面談』
佐藤進学塾では一人ひとりの子と話す機会を多く設けている。中学部の生徒たちとテスト勉強の最終確認を行った。
テスト範囲の仕上がりを聞く。敢えて、アドバイスはしない。ひたすら聞いて、時々、その言葉を繰り返す。
生徒
「中理は仕上がりました」
塾長
「中理は仕上がったんだね」
生徒
「あっ、白プリの仕上げがまだ不十分です」
生徒
「ワークシートは理解しました」
塾長
「ワークシートは理解したんだね」
生徒
「あっ、まだ完全に覚えきれていません」
お子様の言葉をそのまま返す。
すると、自分が言ったことの中の矛盾に気付く。
「数演はすべて解くことが出来るのか」などと塾長や親がきつく聞いたなら、「数演はすべて解ける」と不安を抱えつつ、子どもは言い返す。お子様の思考回路は一瞬ストップするのだ。これでは、いけない。お子様が気付くことが大切だ。人にあれこれ言われてやったことは身に付かない。
次に、重点的に学習することを訊く。
「副教科を完全に仕上げます」
「それは、いいことだね」
「ワークを更に解き直します」
「とても、いいことだね」
「教科書を隅々まで理解します」
「がんばって理解してね」
すべてを肯定する。
不思議だが、すべて肯定していると、こちらが気に掛けていることに生徒はふと気が付く。そして、自分自身が言ったこと以上の勉強を行うようになる。そして、結果を出す。平常授業の時は、丁寧に教える。普段は私達が徹底的に指導して、引っ張っていく。
テスト前は子どもたちを信じて、必要以上のことは言わない。本当の意味でのお子様の自主性に任せる。テスト直前に教え込んではいけない。テスト前にむやみやたらに質問を受けてはいけない。自分で考える事をしなくなるからだ。進学塾の指導者とお子様との距離感はとても大切である。
2025/11/24

『卒業生の言葉』
テスト対策はより良い形へ変革している。以前は『たし算』の発想だったが、今は『ひき算』の発想である。必要なことに対して最大限の時間を掛けて行い、無駄なことは一切省く。
「シンプルの極み」と言える!
さらに、来年度は無駄を省く。
その構想が既に浮かんでいる。
昨年、中三の子たちに訊いた。
「三年間、佐藤進学塾のテスト対策を受けてどうだった」
生徒たちは各々答えてくれた。
「テスト前、塾では黙読により深く考えて理解する学習、家では音読により流れを掴み内容を覚える学習とうまく分けて学習することが出来、とても良い結果が出ました」
「佐藤進学塾は高松高校を目指していてみんなやる気があるので、高い集中力を維持して学習している。だから、みんなと一緒に自分も最高の集中力で学習して実力を発揮することが出来た」
「佐藤進学塾は受け身の子には向いていません。 正しい学習方法を佐藤先生から教えていただき、それをもとに自分自身で計画を立て、能動的に学習する人に向いています。それが、テスト前の対策では顕著に現れることが分かりました」
「テスト前に、先生はあれこれと勉強のことをうるさく言いません。私たちの言うことを冷静に聞いてくださいます。そのあと、的確なアドバイスを頂けることはほんとうにありがたかったです」
「わたしは、中一の時、テスト前は夜の十時には寝ていました。塾はやるべきことをやったら早く終わるので、次の日の準備をして、安心して寝ることが出来ました。さすがに今は違いますが、それでも、夜の十一時には寝ています。テスト対策が九時十五分に終わって頂けることはとても良かったです」
前向きに学習する子、正しい生活習慣が身に付いている子、塾長、副塾長の教えを素直に守り頑張る子に向いている進学塾である事が改めて良く分かる。長時間拘束をしない、多くの宿題は出さない、考え抜いたカリキュラムの下、限られた時間で効率良い指導を行い最高の結果を出すことを約束する。
2025/11/23

『三位一体』
三位一体は、さんみいったいと読む。三つのものが一つになること、また三者が心を合わせることと言う意味である。
三位をさんみと読むのは日本の古くからの習慣で、連声という発音しやすくする為の音の変化だ。平安時代に貴族の位を従三位、じゅさんみと読んだ。 現代では、三位はさんいと読む。
さて、卒業生の子で「良く頑張ったな。凄い結果を出したな」と言う子の保護者と塾長、副塾長の関係性には共通点がある。感謝の気持ちがこめられていて、それが犇々と伝わって来る。
「保護者様とお子様との関係性も、良好なものが築かれているのだろうな」ということがよく分かる。
先日、保護者様から手紙を頂いた。普段の指導に対するお礼の言葉が多く書かれていた。テスト結果に対するお礼ではなく、結果に至る過程に対するお礼である。
指導は更に効率良いものになっていく。お子様も、集中力が高まり益々頑張っていることが見て取れる。その子に限らず、頑張っている子たちというのは、皆、共通している。
『塾長⇔感謝⇔お子様⇔感謝⇔保護者様』と言う関係性が築かれていることに気付かされる。私が人として大切にしている笑顔、感謝、掃除のうちの一つである。
2025/11/22

『兄弟姉妹』
「先生、妹をお願いします」
「ありがとう。面談の日を決めて連絡するね」
「先生、弟をお願いします。まだ、入れますか」
「ありがとう。あとひとり、大丈夫だよ」
「先生、私も妹をお願いします」
「ありがとう。姉妹三人で通うことになるね」
同じ学年で三人の子が兄弟姉妹通塾の申込書を出してくれた。他にも、eメールで連絡をくださっている方がいる。
ありがたいことである。
兄弟姉妹で通って戴くと私の教育方針が共通して認識され、私の考え方が家族みんなで共有されるので、指導がとても上手くいく。音読・書写・反復を行う原則的学習、学習生産性の高い効率の良い学習指導、人を思い遣る優しい気持ち、睡眠時間の重要性、結果より過程を大切にする考え方等々が皆に浸透する。
12月上旬からは外部生徒募集を開始するが、各学年、「1、2名」の募集となる。定員に達すると、募集は締め切らせて戴き、生徒たちへの学習指導へ徹する。小さな進学塾なので、生徒一人ひとりを最大限大切にしていく。新年度募集をお待ちの保護者様におかれましては、ご理解、ご了承をお願いしたいと思う。
2025/11/21

『素直な心』
「姿勢を直してね」
「はい」
素直に直す子がいる。
「必ず、返事をしてね」
「はい」
素直に返事する子がいる。
「字は心をこめて書こうね」
「はい」
素直に書く子がいる。
一方、穏やかに伝えても姿勢を直さない子、返事をしない子、字を雑に書く子もいる。勉強以前の話である。
『素直な心』は大切である。
さて、八年前の話だ。小四で入塾した生徒がいた。「姿勢を正そうね」と言うと、一瞬「?」という顔をしたが、その日から姿勢を正そうと私が言う事を守った。椅子を下げて、お腹と背中にこぶしを一つ分あけて、背筋を伸ばして、左ひじはつかない様にして姿勢を正した。
勉強も頑張る子で素直に復習を行っていた。ただ一つ、気掛かりなことがあった。理科、社会が覚えきれないのである。中学校の中間テストで、他の子は全科目90点以上取ったのだが、その子だけ理科、社会は80点以下だった。勉強方法を話し合って改善を試みたものの二学期も変わらなかった。
期末テストの時、同じ失敗を繰り返し、結果が出た日にその子は塾を休んだ。それまで一度も休んだことはなかった。しかし、次の日、目を真っ赤にはらしてやってきた。気持ちの強い子であった。
中二になって、やっと全科目90点を超えるようになった。本人も、とても嬉しそうであった。ところが、今度は中三診断テストの理科、社会が30点を(6割)取れない。再び、勉強方法を話し合った。この時もなかなか上手くいかなかったが、最後の診断テストでは40点を超えた。
「理科、社会は覚えたら出来る」と言う指導者が多くいるが、実際には上手くいかない子もいる。そういう子供たちの気持ちに寄り添う必要がある。受験は迷っていたが挑戦、見事合格、高松高校へ進学した。苦しかった分、本当に嬉しそうだった。
『素直な心』
神様も応援してくれた様だ。
2025/11/20

『睡眠』
期末テストが一週間後となった。今まで頑張ってきたことに自信を持つと良い。みんな、本当に良く頑張っている。
「午後9時15分」
対策授業は終了する。
集中して効率の良い学習を行った。夜遅くまで、塾に生徒を拘束しない。私自身も早く寝て、体調管理を万全にする。
「健康管理が大切、早く寝よう」
と伝えて生徒たちを一人ひとり見送る。
「ありがとうございました」
生徒たちは挨拶をして、静かに帰って行く。
早く寝て、体を休めると良い。寝ている間に脳内で知識は整理される。
且つて、一人の中学生が言った。
「私は、夜の十時には寝ます。もう少し、遅くまで勉強しなければいけませんか」
私はこう答えた。
「その習慣を変える必要はないよ。早く寝て、ゆっくり体を休めるといいよ」
この子は中学の時、上位十位内をキープしていた。
無理をして夜遅くまで勉強しても、知識は定着しない。時間は限られているのでやるべきことをやって成果を出すことが大切である。学習は時間ではなく、学習生産性の高さが大切なのである。
睡眠をたっぷり取って、英気を養うことで実力を存分に発揮しよう。佐藤進学塾ではテスト前、学習面は当然だが、心と体のサポートを最大限大切に考えて効率的な指導を行う。決して、無理はしない。
2025/11/19

『小三算数』
『かけ算の筆算』の単元について
二桁×二桁、三桁×二桁の指導を行う。
かける数が一桁であれば簡単だ。九九が、しっかりしていればミスも少ない。かける数が二桁になると、少し難しくなる。
①かける数の一の位をかけられる数へ順番にかける。
②かける数の十の位をかけられる数へ順番にかける。
③①の答えと②の答えをたす。
左手にものさしを持ち、スライドさせながら線をひく。右手に鉛筆を持ち、手から離すことは決してしない。
九九は声に出しながら、答えを書いていく。目、口、耳、手を連動させて計算を行う。筆算は、ノート一枚に左右二つ、上下三つ、合計六つの筆算を書く。これらを生徒に伝え練習した。
「姿勢を正してやることが大切だよ」
「なんで」と訊く子がいる。
姿勢が美しい子は、正答率が高い。これは、事実である。美しい姿勢はリラックスした状態をもたらす。頭も心もリラックスしているから正答率が高い。頭よりも心がリラックスしているような気がする。
2025/11/18

『俯瞰』
俯瞰とは高い場所から全体を見下ろす事や、物事を広い視野で見渡す事を指す。物理的に上から下を眺めるだけでなく、物事を一歩引いて全体の状況や背景を把握する意味でも使われる。
俯瞰という言葉は、目に見える範囲を広げるだけでなく、物事の詳細にとらわれず、全体像を理解する為の姿勢を表す。問題解決の際、俯瞰的に捉える事は大切だ。これに拠り細かい部分に注目するのではなく、全体の流れや本質を掴む事が出来る。
早い学校では、テスト範囲表が配布されている。試験範囲表が配布されるまでに、教科書の書き写しと学校ワークの問題演習を一通りは終わらせておく必要がある。
テスト範囲を『俯瞰』しておくのだ。
教科書と学校ワークの学習が中途半端なままテスト勉強に入ると学習に大きな偏りが出る。教科間による学習時間の偏りが出る場合もある。問題演習を作業のように行い、深く考えていない場合もある。暗記に時間を掛けて、思考に時間が不足している場合もある。
これでは納得いく結果が出ない。
教科書と学校ワークを一通り終わらせると、テスト範囲全体が俯瞰できる。やるべき学習内容が具体的に見えて来る。拠って、落ち着いて学習することが出来る。教科間の学習時間をバランス良く配分して行う事が出来る。深く考えて、丁寧に調べて、完全理解して学習内容を完全定着させることが出来るのだ。
教科書、学校ワーク、『二回目』の学習からは、深い部分が見えて来る。「あっ、そういうことか」と根底から理解出来る場面が多くなってくる。もっと知りたくなるから辞書、参考書まで調べる。益々、理解は深まっていく。
教科書、学校ワーク、『三回目』の学習からは内容の本質が見えてくる。「あっ、わかった。なるほど」と学習内容の面白さがじんわり感じられる様に成る。教科書、学校ワーク、『四回目』の学習からは出題者の意図が見えてくる。「よしっ、解けた」と少し感動する場面も多くなってくる。
俯瞰して学習すると、テストというゴールも見えて来る。そうなると、安心して勉強を仕上げていくことが出来る。間に合わないかもしれない等の不安も消えてなくなる。
素晴らしい結果が出る!
まずは、テスト範囲を冷静に俯瞰することが大切である。その辺りについては生徒一人ひとりにじっくりと話していく。
2025/11/17

『イチローさんの名言』
「結果が出ない時、どういう自分でいられるか。
『決して諦めない姿勢』が何かを生み出すきっかけをつくる」
イチローさんの名言だ。
以前、イチローさんがテレビに出演していた時、野球を真剣にやっている高校生から質問を受けていた。
高校生
「イチローさんはピンチの時、どういう心の状態ですか」
イチローさん
「『ピンチはチャンス』とよく言うよね。
でも、ピンチの時、そんなことを考える余裕はないね。
ピンチの時はピンチ、それを正面から受けとめるだけです」
「でもね、『あの時のピンチがチャンスに変わったんだな』と、あとから思うことはよくあるよ。だから、ピンチを切り抜けたことは良かったなと思います」と言う感じのことを言っておられた。
あと、50歳になってから「138㎞/h」の球速になったという。それまで「135㎞/h」の球速がマックスだったという。心のどこかで、「無理だ」と壁をつくっていた気がすると言っていた。
「だから、みんなも自分の中に絶対に壁をつくらないでほしい。50歳になったおれが出来るんだから、皆は必ず出来るよ」と最後に言っておられた。流石は世界のイチロー、本当にいいことを言う。
2025/11/16

『「音読」と成績の相関関係』
音読が上手い子は、必ず勉強が出来るようになる。音読が下手な子で勉強が出来るようになった子は見たことがない。
しかし、音読を一生懸命練習するうちに音読が上達して勉強が出来るようになった子はいる。だから、諦めずに音読をするように、私たちは生徒たちへ繰り返し伝える。
佐藤進学塾では音読を大切にしている。全教科で私たちが音読の見本を示し、生徒たちに全ての本文、問題文を音読させる。
音読が上手い子は、益々上達する。大学卒業後、アナウンサーとなり社会で活躍している子も三人いる。
「音読と成績の相関関係は高い」
最初から音読が上手な子も多くいる。幼少期に両親からたくさんの本の読み聞かせをしてもらった子だ。読み聞かせを大切に考える家庭の家族は皆、読書好きである。拠って、お子様も勉強出来るようになる。
生徒からよくこのような質問が出る。
生徒「テストの時は声が出せません。どうすればいいですか」
塾長「実際に音読はしないけど、黙読で頭の中で声を出すんだよ」
みんな、不思議そうな顔をしている。賢い子と言うのはテストの時に声を出しているのである。それは、音読を意味する声ではなく、頭の中で聞こえる声である。聡明な子は常に行っている。
子どもの能力の発達にとって、内的発話はとても重要な事である。内的発話(inner speech)とは、自分自身への問い掛けや指示出し、思考の整理や調整などに用いられ音声を伴わない発話だと言われている。
内的発話が上手に出来る子が勉強が飛躍的に出来る事が実証されつつある上、第二言語の習得能力に大いに関係していることが分かりつつある。これらの事については、また別の機会に伝えたいと思う。
2025/11/15

『小六「学力テスト対策」』
小六は学力テスト対策を行う。
第三回学力テストは範囲が広い。
対策プリントを復習しよう。
1.間違った問題を解き直す
①問題文を書き写す
②考え方を詳しく書く
③答えを正確に書く
2.教科書から間違いの原因を探す
①大切なことを書き写す
②間違った原因を詳しく書く
3.学校ワークで似た問題を探す
①類似問題を解く
②正しい解き方を覚える
繰り返すことで良い結果は出る。
公立小の子もこれを行えば、中学校へ進学した時、テスト勉強が上手くいく。
2025/11/14

『「12月号」書類』
12月号の書類を生徒に配布する。
1.生徒宛の手紙
2.夢つうしん
3.塾長の独り言
4.『2026年度』進級のお知らせ
5.『2026年度』進級通塾申込書
中三生
1.一月・二月受験対策
2.受験勉強について
小六生
◎『「新中一数・英」究極の予習講座』について
小六受験生
◎受験勉強について
等々の書類が入っている。
到着次第、ご確認願いたい。
2025/11/13

『同期発火』
期末テスト対策、第四日目である。生徒全員が一丸と成って、試験範囲の演習へ真剣に取り組んでいる。同期発火が起こっている。脳科学の世界では、『同期発火』という言葉がある。
「ある人が何かをしようと思い前向きに行動へ移す時、 それに連動して他の人が無意識に同調した動きをする」
一人が本気で勉強を始めると、他の子も本気で勉強し始める。佐藤進学塾に天才はいないが、生徒達の心のつながりは強い。
互いに良い部分を認め、尊敬している。第一志望校である高松高校合格という共通の目標を持っている。その結果、成績上位者が数多く出る。チームワークに優れた進学塾なのである。
仮に、生徒10名が、一人「1」の学習をすると、そのクラスの学習量は合計で「10」となる。生徒10名が一人「1.5」の学習を行うと、クラスの学習量は合計「15」となる。
では、
一人当たりの差「0.5」は何か。
クラスの仲間を互いに気遣い、教え合うことに拠って「1」しか発揮しない学習が「1.5」を同期発火のために発揮して強固なチーム力が出来上がるのだ。だから、佐藤進学塾では平常授業もテスト対策も全員が同じカリキュラムで仲間を思い遣る学習体制を貫いている。
塾長の方針であり、理念である。みんな、仲良く頑張りましょうなどと言っているのではない。勉強は、一人でやっていてもやがて行き詰まる。先生と二人だと必ず依存してしまう。仲間たちと一緒にやるから面白いのである。結果として、一人ひとりが自分の限界も突破出来る。
2025/11/12

『小6「算数」』
『場合の数』の単元にはいる。
最後の単元である。まずは、樹形図の書き方を教える。丁寧に書いていくことが大切だ。もれや重なりがない様書いていく。積事象についても教えて、計算で答を出す方法も指導する。
一月中旬の土曜日には、附属高松中学校の入試が実施される。その翌週の月曜日には合格発表がある。翌日、火曜日からは、『中学数学・英語予習講座』を開講する。
ここからは中学部で使用するレベルの高いテキストを使って、教科書を超えた内容について丁寧に指導していく。中学校一年生の数学と英語を丁寧に指導していく。
中学生の中間テスト、期末テスト、学年末テスト、診断テストで『総合一位』を狙う!
お詫び
現在、小学六年生(新中学一年生)は定員いっぱいの上、予約待ちの方がとても多く控えておられます。その為に入塾及び予約待ちの受付は停止しています。申し訳ありませんが、ご理解ご了承願います。
2025/11/11

『犬の日』
2025年11月11日である。
「ワンワン、ワンワン」
犬の日だ。
「塾の犬はどこにいますか」
生徒に訊かれることがある。
「天国に旅立ったよ」
と答えると皆、驚く。
「20歳まで生きたよ」
と言うと、さらに驚く。
かつて、元気に生徒を迎え入れていた。帰りはワンワンパトロールに出掛け生徒を見守っていた。前向きな頑張る子が入塾面談に来ると、なぜか、吠えることなくすやすやと眠っていた。
五年前、静かに眠る様に天国へ旅立った。その時は、たくさんのお花と手紙を頂いた。その時、一人の子が書いた手紙が心に残っている。第一志望校受験に迷った末に初志貫徹した。結果は、見事合格だった。
一周忌に姉妹の生徒が可愛いお花を持って来てくれた。
「先生、コロちゃんにお供えしてください」
妹さんは、第一志望校受験に不安があった。しかし、見事、第一志望校の高松高校へ合格した。お姉さんもその年、第一志望校の国立大学医学部医学科へ合格した。不思議な繋がりだが、姉妹がお花を購入した花屋さんの子も塾生で第一志望校へ合格した。後日、姉妹とお母様へそれを伝えると驚いておられた。
佐藤進学塾の看板犬『コロ』は、今も天国で優しい素直な子を応援してくれている。
2025/11/10

『中学部・期末テスト対策』
期末テスト対策を実施する。
改めて、大切なことを生徒達へ向けて話す。大切なことは繰り返し、何回でも話す。耳にタコが出来て、そのタコにタコが出来るまで話す。
1.教科書の音読・書写
2.学校ワーク類の反復練習
3.学校のノート・プリントの理解
教科書をどれだけ深く理解するか。ワーク類を完璧に覚える迄反復するか。ノート・プリントを、完全に理解出来るか。
これらに拠り結果は出る。結果が出ない時はいずれかが弱い。ただ、それだけの話である。
「結果がうまく出ていないな」
と感じた時はどこが弱いのか。
保護者様も少し見てあげるとよい。私たちも常に見ているが、親が見てあげると子は心強い。
「これだけ、頑張った」
程度では頑張ったとは言えない。
「まだ、やるべきことがある」
この言葉が出て、完成に近付く。
生徒たちに詳しく話した後は、一人ひとりから質問を受ける。それに対して丁寧に答えていく。
「難しい問題は出来るんですが、計算間違いがどうしても出ます。どうしたらいいですか」
「気にしなくていいよ。人間、ミスは必ずするもので間違ったらあとで直せばいいだけだよ」
「暗記したことをテストの時に書き間違えてしまいます。どうしたらいいですか」
「普段、必ず、問題と答えを音読しながら書こう。テストの時、絶対に書き間違えないよ」
集中してやるべきことをやったならば、早く寝よう。テスト前でも佐藤進学塾は午後九時過ぎに終わる。遠い子でも、午後十時前には家に着く。出来る限り、十一時半までには就寝することを心掛けよう。健康管理が第一だ。あと、テスト期間中、スマホは親に預けてテスト範囲に集中して全力で学習しよう。
2025/11/9

『龍野市』
今年も、兵庫県たつの市を訪ねた。
兵庫県西南部、西播磨地域に位置する兵庫県たつの市はある。東経134度32分、北緯34度51分、南北に長い地形である。北は山地が広がり、南は瀬戸内海と自然環境に恵まれた地域だ。
たつの市は、播磨の小京都と呼ばれる閑静な城下町で、龍野城はじめ様々な歴史的建築物や、綾部山梅林など自然がたくさん残る街である。また、手延素麺揖保乃糸が全国的にも有名だ。
龍野城は鶏籠山の山城と山麓の平山城とのニ期に分かれている。山城は約五百年前、赤松村秀により築かれた。現在の山麓の平山城は、寛文12年に信州飯田から脇坂安政公が移って築城されたといわれている。龍野の象徴として、本丸御殿、白亜の城壁、多聞櫓、埋門、隅櫓などを復元している。
全国的に有名なヒガシマル醬油本社はたつの市にある。播磨平野の豊かな小麦に質の良い大豆、赤穂の塩はいずれも醤油づくりに欠かせない。また、清らかな揖保川の水と穏やかな気候に恵まれて、醤油が出来上がる。鉄分の少ない揖保川の水はうすくち醤油作りに適し、脇坂藩の保護のもと発達した。
尚、表題は市町村合併前の漢字が街に合うと個人的に判断して龍野市とした。龍野城下の街並みはとても美しく、古き良き時代のものが大切に保存されている。訪れる人も少なく静かに時を過ごす事が出来た。
2025/11/8
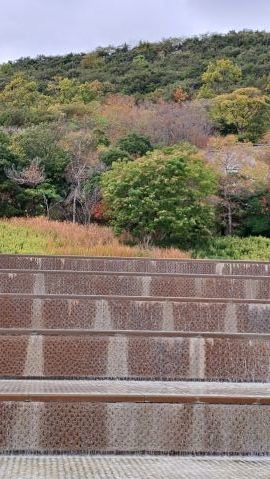
『復習ノート』
復習ノートは、佐藤進学塾の伝統を受け継いでいる。学校でのテストが上位の子が復習ノートを提出する。それを下の学年の子に見せる。ノートの良い点について詳しく説明する。
目を輝かせてノートを見ている子がいる。
他人事のように、ちらりと見る子もいる。
私の話を身を乗り出して聴いている子がいる。
あまり、興味なさそうに聞いている子もいる。
この違いはどこから来るのか。
「心」
即ちメンタルの部分に拠る。
さて、前者が復習ノートを提出した。
「すごい」
思わず声が出た。
テスト対策の復習について、先日、詳しく伝えた。その時、中学生の優秀な子のノートを見せて上げた。それを見事に真似ている。自分流にアレンジして復習している。更に良く成る様コメントを書きこんだ。
復習ノートを見ると結果が出るかどうか、すぐわかる。私が言ったことを忠実に守っている。出来る子のノートを一生懸命に真似ている。そして、丁寧に心を込めて字を書いている。
私の思いと、
先輩塾生の思いと、
生徒の思いが重なっている。
三者が『心』を通い合わせている。
高松高校や愛光校高校で活躍する子は且つて、小中学校時分の復習ノートが凄かった。その子たちの伝統をまた一人、受け継いでその軌跡を辿っていく。素晴らしいことである。
2025/11/7

『小四「算数」』
四則の間の関係を習う。
たし算とひき算の関係、
かけ算とわり算の関係は
小三で学習した内容である。
分からない時は線分図を書く。
すぐに理解することが出来る。
逆算を使い計算する。
例題
18×(108ー□÷16)=1800
(108ー□÷16)=1800÷18
(108ー□÷16)=100
□÷16 =108ー100
□÷16 =8
□ =8×16
□=128
下線部は、
先に計算をする部分である。
その部分を残しておいて、
逆算を行う。
式が長くなっても、逆算の方法は同じである。スムーズに計算出来る様に反復練習を行うこと。中学部の成績上位者はこの様な計算が瞬時に出来る。方程式の解き方もマスターしているからである。
2025/11/6

『中二数学「図形の証明」』
三角形、四角形の証明の指導を終えた。大変難しい平行四辺形の証明の指導も終えた。今日は等積変形を教える。この内容は小五の時にも塾で指導している。それを覚えている子もいる。
底辺が共通で高さが等しい三角形を選ぶ。必要に応じて補助線を引く。むやみやたらに引いてはいけない。正確に引くことが出来るまで復習が必要である。
四角形を三角形に等積変形する時は、補助線を引いて三角形、二つに分ける。その補助線に平行な線を頂点を通る様に引く。交点を利用して最後にもう一本補助線を引けば完成だ。
五角形を三角形に等積変形する時は、五角形に補助線を引き、四角形と三角形に分ける。三角形を等積変形して、全体を四角形に等積変形する。あとは上と同じことを行えば完成する。
『左脳型』の子
理屈を理解して考えると良い。
『右脳型』の子
作図を練習して理解すると良い。
殆どの人は話をしたり、物事を筋道立てて考えたりする時に左脳が働き、音楽を聴いたり、直感的に何かを決めたりする時に右脳が働く。人間、右脳を働かせるのが得意な人と、左脳を働かせるのが得意な人がいる。脳の働かせ方には個人差がある。手間は掛かるが、各々に合わせた考え方を指導する。
2025/11/5

『為替「円高・円安」』
為替市場では、「1ドル150円」を突破した。少し前までは、「1ドル140円」台後半であった。円安が進んでいる。
円とドルの関係で言えば、「円高ドル安」、「円安ドル高」は、セットとして考える。
円の価値が上がるとドルの価値が下がり、ドルの価値が上がると円の価値が下がる。シーソーの様な関係である。
変動相場制ゆえに起こる。かつて「1ドル=360円」と固定されていた。1973年、固定相場制から変動相場制へと変わった。
「1ドル100円」を基に考える。
「1ドル100円→90円」
円高ドル安である。
「1ドル100円→110円」
円安ドル高である。
1ドルが100円から90円になると、「円が安くなっているのに、なぜ、円高?」と生徒たちは混乱する。
ドルの視点に立つと、1ドルが100円から1ドル90円になるので、ドルが安くなっているのである。即ち、「円が高くなっている」ということになる。今回、1ドル140円台後半から150円台前半まで上がった。「円安」つまり、円の価値が下がっているのである。
海外旅行をする事を考えてみる。
「¥10,000円」をドルに換金、
「1ドル125円」の時「80ドル」
「1ドル100円」の時「100ドル」
となる。
125円>100円だが、
80ドル<100ドルである。
1ドル125円→1ドル100円
になった場合、
80ドル→100ドル
と円の価値が高くなった。
つまり、「円高」である。
1ドル100円→1ドル125円
になった場合、
100ドル→80ドル
と円の価値が低くなった。
つまり、「円安」である。
「最後にもう一度、確認しよう」
1ドル125円→1ドル100円は円安ではない。以前は、1ドル125円の価値があったのに現在100円の価値になった。つまり、ドルの価値は低くなり(ドル安)、円の価値は高くなった(円高)ということだ。
常日頃よりニュース見て、「1ドル148円が1ドル150円になった時、円安と報道している。なぜだろう」という疑問を常日頃より持っておいてほしい。
2025/11/4

『算数』
「計算を速くするには、どうすればいいですか」
よくある質問である。
計算が速い子が「算数が良く出来る」という一般常識がある。実際には、計算は正確な子が「算数が良く出来る」のである。無理をして、速く計算する必要など全くないのだ。
しかし、計算を速くする方法はある。
一つ目は、「反復練習」である。
二つ目は、「そろばん」を極める事である。
三つ目は、「決まりと工夫」を習得することである。
この時、速く解くことを意識してはいけない。
ゆっくり、丁寧に計算することが大切である。
① 58+65+35
=58+100
=158
➁ 125×7×8
=125×8×7
=1000×7
=7000
③ 25×28
=25×4×7
=100×7
=700
④ 75×12
=3×25×4×3
=9×100
=900
⑤ 99×35
=(100-1)×35
=3500-35
=3465
上記、計算の感覚をマスターすると良い。
あとは、反復練習して習得すると良い。
一問、3秒程度で即答出来る様に成る。
以前、指導した『かけ算の暗算』も利用しよう。
①12×12=(12+2)×10+2×2=140+4=144
➁15×15=(15+5)×10+5×5=200+25=225
③17×18=(17+8)×10+7×8=250+56=306
④25×28=(25+8)×20+5×8=660+40=700
⑤52×58=(52+8)×50+2×8=3000+16=3016
計算のきまりと工夫を習得すると、計算のスピードは格段に速くなる。しかも、正答率は100%に限りなく近づく。成績上位者はこれら計算手法を間違いなく習得している。
2025/11/3

『反復練習』
「『小数』の単元」
単位の換算を習得するには、少しばかり時間が掛かる。
1㎏=1000g
0.1㎏=100g
2.5㎏=2500g
1L=1000㎤
0.1L=100㎤
3.8L=3800㎤
単位の変換問題を演習する。
授業時間内で反復練習を行う。
三回、問題の音読をして答える。
一回目は時間が掛かる。
二回目も時間が掛かる。
三回目は素早く出来る。
「分かった」
「わかりました」
「三回目はすぐに出来たね」
「はい、できました」
「どんな気持ち」
「うれしいです」
「反復は三回するといいよ」
「そうなんだ」
三回以上反復すると、理解が完全定着する。更に四回以上反復すると、正確かつ最高の速度で解くことが出来るようになる。脳の仕組みを考えると分かる。エビングハウスの忘却曲線からも分かる。早い段階で三回以上反復練習して内容を理解定着させる習慣を付けたものが成績上位者と成るのである。
2025/11/2

『原則的学習』
附属小六は学力テスト、中学生は期末テスト、「一カ月前」となった。まず、『書き写し』を始めよう。教科書のテスト範囲となるところを音読しながら、ゆっくり書き写していく。
黙って書き写すと作業になり、深い理解を得られない。大きい声を出して、自分の耳で確認、丁寧に書き写して、さらに目で確認する。五感をフルに使い、脳を刺激することが重要だ。
字は、必ず、ゆっくり丁寧に書く。丁寧に書く時、自律神経は安定している。ゆっくりと、呼吸しているからだ。交感神経と副交感神経のバランスが最高の状態に保たれている。
「早くしなさい」
と言ってはいけない。
「ゆっくり、やろうね」
と声を掛けると良い。
普段はゆっくり丁寧に勉強していても、テストの時は緊張しているので問題を解くスピードは速くなる。人間の深層心理に、嫌な事から早く逃げようとする部分があるからだ。拠って、普段は驚く位にゆっくり丁寧に勉強する必要がある。それで、試験の時にはちょうど良い速さとなる。
実は勉強する時、早く読んで、早く書くのは勉強から逃げようとしているのだ。逆に、ゆっくり読んで、ゆっくり書いて丁寧に勉強している子は、勉強に正面から立ち向かっているのである。
最初から、勉強が楽しくて仕方ないと言う子はいない。ゆっくり丁寧に勉強している間に、少しずつではあるが面白くなる。丁寧に考えているから、本質的な面白さに気付くのだ。
さあ、テストまで一カ月となった。
『教科書の書写』からゆっくり始めよう。テストがない小三から小五の子も今までの総復習としてやってみよう。一昨年まで、期末テストに合わせて全員一緒にやっていた。昨年から、附属小学校の期末テストは中止となり実施されなくなった。小六学力テスト第三回だけが行われる。
2025/11/1

『イソップ物語』
北風と太陽が言い争いをした。
「どちらが、強いか」
勝負をすることにした。
「旅人の上着をぬがせたら勝ち」
北風は力一杯、冷たい風を吹く。旅人は上着を押さえ、ぬがせることはできない。太陽が、さんさんと光を照らす。旅人はあまりの暑さに上着を脱いでしまう。
太陽の勝ちである。
北風の厳しい態度と太陽の寛容な態度が対照的だ。太陽の寛容な態度であることが人に求められている。『北風と太陽』の物語には、「北風が勝つ」パターンのストーリーがある。
「旅人の帽子を脱がせたら勝ち」
という勝負もしていた。
北風が旅人に向かって強い風を吹いたところ、帽子を飛ばすことに成功した。太陽はそれに失敗してしまう。北風の勝ちである。実は、北風と太陽の勝負は引き分けだった。
2025/10/31

『「2026」小学部新カリキュラム完成』
今の子どもたちに対して、時代が求めるものが変わっている。
単なる知識から、それをどの様に使って「具体的に表現する」か、「論理的に記述・論述する」ことが出来ているか。
この様な事が評価の対象に成っている。
知識が多いだけではAIに取って変わられる。知識を如何に活用していくか。想像力を超えた豊かな創造力が必要になる。
豊かな創造力を付けるには、小学校の中学年までに基礎基本をしっかりと築いて、高学年で能力を最大限伸ばしておくことが大切だ。中学生になるとやる事が多く、全てに手が回らない。
小学生時点で旧態依然の入試問演習主体では、世の中が新しく求めている力は身に付かない。都市圏では、中学入試、高校入試が、全国区では大学入試で求められる事が大きく変わっている。
佐藤進学塾では、英語を小五より中三までの一貫教育としている。小学生で「文法力と表現力の基本」を身に付ける。中学生で「高度な英文法、長文読解力」を伸ばす。定期・診断テスト、入試はすべて満点を狙う。小学生時点から教科書を超えた内容を指導、中学生の時点では高いレベルの英語力を身に付ける。
算数・数学は「未知の問題解決能力」を身に付ける為に、生徒一人ひとりとの対話形式にて、授業指導を行う。小六、年内に算数を完成させて、年明けからは中学数学の指導を行い、正負の数、文字式、方程式を使った計算、文章題を習得する。頭の柔らかい間に、関数と図形のセンスを磨き上げておく。
中学校では、方程式の利用、関数、図形について、高度な問題演習を行い、論理的且つシンプルな解法を身に付ける。更に未知の問題に対しても、それらを解決する能力を伸ばしていく。テストに出題される、されない、という目先のことに拘ることなく、「論理的な思考能力」を身に付ける為の指導を行う。
自分の能力を徹底的に伸ばしたい生徒諸君!
将来、『国立大学』へ進学して、「医学部、歯学部、薬学部、理学部、工学部、農学部」等で活躍したい子の数学力を徹底的に磨き上げていく。同時に英語をはじめ、全科目をバランス良く指導する。
お子様の明るい将来を考えると、これからがとても楽しみである。
2025/10/30
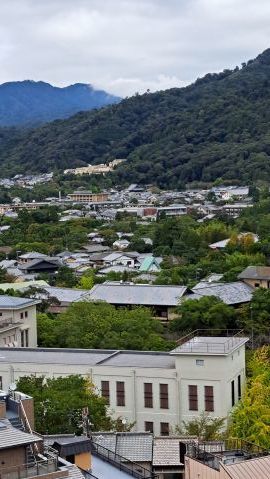
『前向きな子』
物事に対して前向きな子は、勉強が飛躍的に出来る様に成る。佐藤進学塾の前向きな子には、三つの共通点がある。
まず、一つ目は塾に誰よりも早く来て勉強していること。
小学部は午後4時40分~45分位に来ることを義務付けている。そして、生徒が全員揃う4時50分には授業を始める。
前向きな子は午後4時半過ぎに来ている。そして、前回の復習をしたり、今回の予習をしたりしている。テキストとノートをあけて、ノートにひたすら大切な事を書いている。
そして、二つ目は私たち指導者に元気よく挨拶をすること。
私たちが「こんにちは」と声を掛ける。同時に「こんにちは」と笑顔で元気良く挨拶をする。互いに気持ち良い始まりとなる。
最後に、三つ目は気持ち良く返事をすること。
私たちは一人ひとりの生徒にいろいろと声を掛ける。姿勢のこと、メンタルのこと、そして、様々な学習方法のことについてなどである。その時、気持ち良く「はい」とその都度、返事をする。
前向きな子と言うのは、こういった当たり前の事が当たり前に出来る。勉強以前に最も大切なことであると言える。こういう前向きな気持ちの良い子と言うのは保護者様もそういったことを勉強以前に、大切に考えておられる。保護者様には感謝の気持ちでいっぱいである。
2025/10/29

『仏の顔も三度まで』
温厚な人であっても、無礼を繰り返せば怒るの意味である。「仏の顔も三度撫ずれば腹立つ」という言葉が省略されて、「仏の顔も三度まで」と使われる様に成った。
言い回しを見ると、三回目までは許されると解釈する人も多いが、正しくは三回目で怒られる様子を表している。
元の文章は「仏の顔も三度撫ずれば腹立つ」とあり、三回目で腹を立てている様子が分かる。その後、「まで」が加えられ、「仏の顔も三度まで」と使われるようになった。
温厚な人も無礼を繰り返せば怒るという意味の諺なのである。
「どこから『三』という数字が出てきたか」
仏様自身のエピソードが元になっている。仏様は釈迦国の王子として誕生した。ある時、隣国のコーサラ国から「王妃にふさわしい身分の高い女性を嫁がせてほしい」という要求が出される。
しかし、その要求を良く思わなかった釈迦国は、身分の低い女性を、高い身分と偽って嫁がせる。その後、釈迦国から王妃として嫁いできた女性が、本当は身分の低い者だったと知ったコーサラ国は釈迦国を滅ぼそうと出兵するが、仏様から説得されて引き返す。
「出兵しては、引き返す」を三回行い、四回目の出兵では、「悪いのは、自国だ」と仏様は説得を行わなかった。結果、釈迦国は滅びることになり、仏様が三回説得を行った事から三という数字が使われるようになったという。正しい意味とは少し異なるエピソードである。
2025/10/28

『受験勉強』
受験で勝利する子は、受験前に命懸けで頑張るわけではない。
「えっ」
と、思うだろうが事実だ。
「では、勝利する子とは」
普段、丁寧に学習している子である。受験前には、涼しい顔で仕上げをしている。歯を食いしばって頑張ってはいない。
テスト前ではない。普段が大切なのだ。中三になり受験が始まるのではない。夏休みになって受験が本格化するのでもない。
受験に成功する子は、中三になっても、今まで通りに学習しているのだ。夏休みはもちろん頑張るが、決して無理はしない。
多くの塾では受験前、異常に力を入れる。指導者は発破を掛けるが、生徒は空回りばかりする。子どもは緊張し過ぎて、本来持っている力を発揮できない。とても残念なことである。
翻って、佐藤進学塾の中三生はゆったり勉強している。ピリピリした雰囲気など微塵もない。寧ろ、温かく穏やかな優しい空気が漂っている。そして、みんな、笑顔である。しかし、学習空間は静謐で凛とした空気感がある。皆、普段から一生懸命に頑張っているからだ。
小三、小四は、学習リズムをつくっている。小五、小六は、高度な内容を学習している。中一、中二は日々、入試を見据えて学習している。中三は中間、期末、診断、入試全てを意識して学習している。
佐藤進学塾では、受験勉強は小学生の時点から意識して行なっている。中三はその集大成と考えている。佐藤進学塾では効率の良い学習を行う。音読、書写、反復を中心に行う『原則的学習』を伝えて、素直に学習する子を誠心誠意指導していく。
「テスト前だから、勉強せよ」
と言わない。
「テスト前だから、早く寝よう」
と言う。
それで、最高の結果が出ているのだから、今現在、最高の指導が出来ていると言える。ただ、これに満足することはない。新年度から『新カリキュラム』を二年間の移行期間を経て完成形にして指導を行う。
理系人材、グローバル人材のニーズの高まりを受けて、小学部はカリキュラムを一新した。国語は勿論、英語教育を充実させている。数学教育を小学生時点から始めている。中学部では以前以上に余裕を持って学習指導を行う。佐藤進学塾の子たちの学習能力、学習生産性は益々高まっていくことは間違いない。
2025/10/27

『復習ノート』
生徒たちから復習ノートが提出されている。提出は義務付けていない。形だけやっても意味がないからだ。本当に出来るようになりたい、先生に見て頂きたいと言う子が提出すればいい。
「テスト直しが終わったら、提出してね」
とライトな感じで伝えている。
受け身の感覚でやるのでは、殆ど意味がない。自ら、能動的に行うことが大切と考えている。取り敢えず、提出しているだけでも偉い。毎回、必ず、提出する子もいる。
提出された復習ノートは丁寧に見ていく。そして、最後に私からのコメントを書き込む。二、三行の時があれば、びっしり、二、三ページの時もある。
今回も、「すごい」と思わず声が出たノートがある。
1⃣ 「間違い直し」を驚く位丁寧に行い、完全に理解している。
2⃣ 出題元を徹底的に探し出して、「出題意図」を掴んでいる。
3⃣ 「類似問題」を様々なテキストから見付け出して、演習している。
4⃣ 「辞書、参考書」を調べ尽くして大切なことを書き出している。
5⃣ 自分が「間違った原因」について考えて、詳しく記述している。
素晴らしい結果を出している子たちのノートだ。結果を出しているから、次に備えてここまでやる。その気持ちがノートからパワーとなり伝わって来る。思う様に結果が出ていない子もいる。復習を続けるうちに、必ず、素晴らしい結果が出る。
ノートという平面に鉛筆一本で勝負している。カラーペン、蛍光ペンを使い誤魔化すことはしない。強い気持ちが空間にまで広がり、やる気が私の心にひしひしと伝わってくる。それを、私も真摯に受け止めてしっかり見ていく。
中学生は期末テストまであと一カ月である。附属小学生も第三回学力テストまであと一カ月である。生徒一人ひとりがやるべきことを考えて、やるべきことをやっていってほしい。
2025/10/26

『笑門来福』
「お母さん、結果が良かったよ」
と子が親に言う。
ニッコリ笑って、親は子に
「良かったね」と言う。
「お母さん、結果が、…」
と言う時もある。
ニッコリ笑って、
「また頑張ろう」と言えばいい。
「結果が、…」
のお子様で、抜群に出来る様に成った子がたくさんいる。
「出来る子だったんでしょ」
と、冷たく言い放つ人がいる。
とんでもない!
「どれだけ努力したことか」
と言いたいが、絶対言わない。
そんなことは、私と生徒さんとその保護者様だけが知っていればいい。生徒も私たちも、驚く位に努力していることを保護者様はよく知っている。実は、保護者様も凄じい努力をしている事実がある。
その努力を、
「努力とは思っていない」
という共通点が保護者様にある。
当たり前の事をしている感覚だ!
小さな規模の進学塾ゆえ、最初から飛び抜けて出来る天才の様な子は来ない。しかし、塾の理念、方針に賛同して、「絶対に出来る様に成りたい、高松高校へ行きたい」という思いを持った子は来てくれる。
入塾後の二年間、全国模試偏差値が65を超えなかった子がいる。その間、私が伝える勉強方法をひたすら守り抜いた。少しずつ改善して、勉強方法は確実に良くなった。小六で結果が出る様になった。中学生になり、その努力が実った。いきなり、中一で上位十位内に入った。後に、総合一位を取る様に成った。
「私が、こうやるといいよ」と言うと、その子はすぐにそれを実行に移した。それは復習ノートを見れば直ぐにわかった。強く意識して改善している跡が見られるのである。今は、高松高校で頑張っている。
その様な子が、佐藤進学塾には多く在籍する。保護者様は、塾長である私を信頼して下さっている。だから、驚く位に素晴らしい結果が出る。
『親の心、子の心、私の心』
が繋がった時、結果は出る。
心のトライアングルである。
さて、私が尊敬する弁護士の中坊公平氏は小中学校の時、母親からこう言われたと書籍に書いてあった。
「お母さん、テスト良かったよ」。
母は笑顔で「お前はやれば出来るんだよ」と言ったという。
「お母さん、テストあまり出来ひんかった」。
母は笑顔で「人間は普通くらいがいいんだよ」と言ったという。
「お母さん、テスト悪かった」。
母親は笑顔で、「そういう時もあるんだよ、気にしなくていいんだよ」と言ったという。
私が出会った伸びる子の親御さんも皆、同じ感覚を持っておられる。様々な事例を紹介するこのブログを読み、今までの考え方を変えて成功した親御さんもたくさんおられる。とても嬉しいことである。
2025/10/25

『小六算数「比例」』
小六、比例の単元に入った。
算数の中でも重要な内容である。
比例の式:y=a×x
aは比例定数(決まった数)
a=y÷xで求められる。
xが2倍、3倍、…となると、
yも2倍、3倍、…となる。
「y=5×x」が成り立つとき、
x=6のとき、y=30となる。
y=50のとき、x=10となる。
「おもりの重さが10gのとき、ばねの長さが25㎝、重さが15gのとき、長さが35㎝となるばねがある」
おもりの重さ5gに対して、
ばねののびは10㎝である。
おもりの重さ1gに対して、
ばねののびは2㎝となる。
ばねののびは、
おもりの重さに比例している。
おもりの重さ(xg)、
ばねののび(y㎝)とすると、
式は、y=2×xと表される。
おもりをつるさない時の
ばねの長さは、5㎝となる。
ばねののびはおもりの重さに比例している。ばねの長さがおもりの重さに比例しているのではない。このあたりは十分注意して考える必要がある。理解出来ている子は中学数学の1次関数もすぐに分かる。
2025/10/24

『図形の証明』
中二は、『平行四辺形』に入った。図形の証明の中でも難しい単元だ。しかも、診断テスト頻出事項である。
平行四辺形の定義
「2組の対辺が平行な四角形」
平行四辺形の性質
①2組の対辺は等しい
➁2組の対角は等しい
③対角線はそれぞれの中点で交わる
平行四辺形であるための条件
定義と三点の性質に加えて、
④1組の対辺が平行で等しい
これらを理解する必要がある。証明を何度も繰り返し練習して、証明の流れを感覚的に掴んでしまおう。図形の証明で、最も頑張ってほしいところである。もう既に、頑張っている子が多くいる。
2025/10/23

『第三回診断テスト』
診断テストの結果が出揃った。
一人ひとりと話しをする。まず、生徒の意見を聞く。そして、私の考えを伝える。必要に応じてアドバイスも行う。
今回は、国語が難しかった。
この時期、言い訳をする子はいない。自分の問題点を、的確に言葉で表す。その後、学習方法の改善点を自ら見つけ出す。
難しい国語だが、50点近く取っている子もいる。国語に自信がある子だ。丁寧に塾テキストや学校ワークを復習している。
さて、中三に成り数学が大きく伸びた子がいる。診断テストは48~50点で安定している。
「安定してきた要因は、自分で分かるかな」
と訊いてみる。
「私は、中二まで、テキストの解き直しは1、2回しかしていませんでした。中二の今ごろ、先生に言われた通りに、解き直しを3、4回頑張ってするようにしたんです。数学の解法のコツがつかめるようになり、少し楽しくなってきました。それからはテキストの発展問題にも挑戦する様になりました。そうすると、テストの時に解法が直ぐに思い浮かび、佐藤先生が塾で指導していただいた通り、正確に解く事が出来るようになったんです」と嬉しそうにこたえてくれた。
時々、生徒たちに言う。
算数、数学は他の科目の二倍の学習時間を取る必要がある。仮に英語が一時間ならば、数学は二時間復習しなければ良い結果は出ない。ところが、高松の子は英語ばかりに時間を掛けて学習しようとする。
それ自体は、悪いことではない。しかし、その二倍、数学は学習しなければ本質的な理解は得られない。幸いなことに、そういう時間が中三にはいくらでもある。
「やるか、やらないか」。
あとは、それだけである。
受験生に限った話ではない。
2025/10/22

『成績上位者表彰』
中間テスト、成績が出揃った。
附属中、公立中学校の五教科上位10位内の生徒が8名である。『総合「1位」』を取得した子も複数、在籍する。
上位20以内に6割の生徒が、上位35位内に8割の生徒が入った。本当に良く頑張ったと言える。
さて、生徒一人ひとりに副賞のノートを渡していく。そして、今回、良かった点についてスピーチしてもらう。反省点ではなく、良かった点を伝えてもらう。
「得意な数学を徹底的に勉強して、100点取れました」
「良かったね」
「社会の反復練習を五回したら98点で、一問しか間違えませんでした」
「すごいね」
「朝、20分早く起きて暗記の学習をすると、合計490点を超えました」
「素晴らしいね」
日本人はわるい点ばかりを次々上げて、それをすべて変えなければいけないという真面目な気質がある。また、それが良いことだと多くの人が勘違いしている。
しかし、それは違う。
自分が努力した点、良い点、即ち長所を確認すればよいのである。そして、点数に結びついた部分について、自信を持つと良いのだ。良い点をとことん伸ばしていくことで良くない点は不思議と消えていく。
2025/10/21

『笑門来福』
笑顔が素敵な子はとても気持ちいい。家族みんなが笑顔なのだろうと思われる。まわりの皆を明るくしてくれる。
入塾面談で笑わない子がいる。
「少し笑った方がいいですよ」
と笑顔で言うと、
「今日は緊張しているんです」
と怒った顔で親から言われる。
入塾面談が笑顔で進む時もある。
「一緒に頑張ってみましょう」
と笑顔で言うと、
「ぜひ、宜しくお願いします」
と笑顔でこたえてくれる。
御縁を感じる。
とても、気持ちいいい。
手続きも終始和やかに進む。
当初、笑顔が出ない子は多い。本当の意味で緊張しているからである。色々、話しているうちに、素敵な笑顔が出る様に成る。「笑うことはいいことだよ」と言うと、「えーっ」と言い、そうなんだと言う表情に変わる。そのうち、塾では終始笑顔になる。
笑顔になると、リラックスできる。
リラックス出来ると、勉強も出来る様に成る。笑顔で勉強に取り組むと、楽しくなる。そのうち、自分が納得出来る結果も少しずつ出始める。そうなると、益々、笑顔に成る。二年、三年と通塾するうちに素敵な笑顔に成る。その頃には、成績もずいぶんと安定している。
周りの子も、みんな笑顔に成る。笑顔に囲まれた子は幸せに過ごすことが出来る。私自身、笑顔を大切にしている。笑顔溢れる塾で、笑顔溢れる子たちに笑顔で指導することは楽しい。
2025/10/20

『寒暖差』
寒暖差が激しい。
もう、十月下旬である。
先日まで、皆、半袖だった。
日中は半袖でもまだ暑い。
夜になると、流石に半袖は寒い。
シャツの上にジャケットを羽織る。
セーターを着ている子もいる。
半袖、ハーフパンツの子もいる。
この時期、不思議な光景だ。
四季が二季に変わっている感がある。
咳をしている子も見かける。
週末から急に冷え込む様である。
体調管理に十分気をつけてほしい。
2025/10/19

『「11月号」書類』
10/20(月)~22(水)、
11月号のお知らせを配布する。
1.夢つうしん
2.生徒宛の手紙
3.テスト対策完了のお知らせ
4.冬期講習会のお知らせ
(①小5~中2対象・②中3対象)
※小3・小4は実施していません。
5.期末テスト対策のお知らせ(※中学生)
冬期講習会は学年に拠り、日程及び時間が異なる。
学校が冬休み中の『休講の日』も、学年に拠り異なる。
生徒さん、保護者様のご確認をお願いしたい。
2025/10/18

『この時期、よくある相談』
生徒「結果が良くないんです」
塾長「確かにあまり良くないね」
「すごく頑張ったんです」
「よくがんばったね」
「どうしたらいいですか」
「ゆっくり、話をしよう」
「結果があまり良くない」
と言う子には3タイプある。
まず、1タイプ目。
自分の能力に対して、目標得点や目標順位が高すぎる子である。スモールステップ、目標設定は少しずつ上げていくことが大切になる。
次に、2タイプ目。
結果が良い友人と比べて、自分が出来ていないことを卑下する子である。戦う相手は友人ではなく、自分自身であることに気付く必要がある。
最後に、3タイプ目。
自分の努力を過大評価して、客観的に見て取ることができない結果を求めている子である。現実を見つめて、冷静に自分の実力を見つめることが重要だ。
結果が出ている子は、見えないところで努力している。「頑張った」という次元を超えて、初めて結果は出る。これらを相談へ来た子に丁寧に話していく。それを聞いて、奮起する子がいる。とても残念だが、気づかない子もいる。前者となるか、後者となるか、それは、その子の『心』次第であると言える。
「ピンチはチャンスである」
この後、奮起した子で結果を出す子は多い。
かつて、『高松高校合格』を手にしたKさんもその一人だ。中三の一年間、成績が上がることなくもがき苦しんだ。合格を手にした時、いの一番に駆けつけて来てくれた。
そして、こう言った。
「先生、諦めずに頑張って本当に良かった。先生からのたくさんのアドバイスがすべて役に立ちました。先生、四年間真剣に指導いただいて本当にありがとうございました」
かつて、『高松一高合格』を手にしたHさんもその一人だ。相談の時、少し厳しく言うと涙を流しながら「私は頑張っています」と抗議してきた。合格を手にした時、最高の笑顔で駆けつけて来てくれた。
そして、こう言った。
「先生、あの時はとても辛かったけど、佐藤進学塾をやめずに最後まで塾のみんなと頑張って良かった。先生、私に大切なことをはっきり言ってくれてありがとうございました」
結果を手にした子は、人の言葉に素直に耳を傾けている。自分の地道な努力を、決して人に見せることも自慢することもない。その陰で、家族がご協力して頂いていることも事実である。このあたりのことについて、私自身、『心』から感謝している。
2025/10/17

『野鳥』
佐藤進学塾、正面の庭に野鳥が飛んでくる。この時期、朝から様々な野鳥がやって来る。授業の予習や準備などをしていると、美しい鳴き声が聞こえて来る。
「どんな、鳥かな」
と思い、そっと見にいく。
教室の窓からシンボルツリーの桜を静かに見上げる。その瞬間に、鳥たちは一斉に羽ばたいていく。静かに見に行くのだが、気づかれてしまう。
姿を見ることは諦める。
美しい鳴き声だけを愉しむことにする。
2025/10/16

『復習ノートの提出』
中学生が二学期中間テストの復習ノートを提出している。私が何も言わなくても、提出している時点で素晴らしい。
「間違った問題は完全に理解したい」という思いから、復習を行う。それを提出して塾長、副塾長に見てもらう。
1.「正しい解法」で丁寧に解き直す
2.「出題元」を探し出して書き出す
3.「類似問題」を選び出して解き直す
これが、テスト直しの基本的な流れである。
1.解き直しについては、みんな良く出来ている。2.出題元~、3.類似問題~は、生徒によって、大きな差が出る。
最高の結果が出ている子には共通する点がある。出題元を徹底的に探し出している。自分が間違った原因を考え抜いて、教科書、辞書、参考書などを隅々まで調べ尽くしている。問題の核心に触れることが出来ているのである。真の理解を得ようとする気持ちが驚く位に強い。
類似問題もあらゆる所から探し出している。学校ワーク、塾テキスト、参考書、…。少しでも、関連する問題は徹底して演習している。結果、実力を極限まで高める事が出来ている。一つの問題に対して本質的な理解を追及、理解不十分な個所を完全理解しようと努力している。その努力を努力とも思っていない。
「次回、同様の問題が出た時は必ず解く」と言う思いが強い。だから、結果が出る!
2025/10/15

『結果の見方』
二学期中間テスト結果が出揃った。生徒たち一人ひとりに声を掛ける。「『一位』を狙います」と宣言した子がいた。結果は、見事、480点を超えた。残念だが、総合一位ではなかった。
「よくがんばったね」
「先生、すいません」
「三科、100点は凄いよ」
「でも、英語が…」
「文法は完璧だよ」
「ありがとうございます」
「また、チャレンジしよう」
「はい、頑張ります」
素晴らしい結果が出ている子に「本当に良く頑張ったね」と、ストレートに伝える。教科別に結果が出ている子に「得意教科に自信を持ってね」と、良い部分を伸ばす様伝える。一人ひとりの子が得意な部分がある。良いところは徹底的に褒める。
仮に、数学が98点、国語が78点とする。
ある親御さんは、
「数学、頑張ったね」と褒める。
ある親御さんは
「国語が駄目ね」と責める。
前者のお子様は、次回、数学は勿論、国語も頑張ろうと思う。後者のお子様は、国語が気になり、数学もうまくいかなくなる。気持ち、即ち、メンタルの部分は大きい。
また、ある親御さんは「数学はいいけど、国語はだめね」と言う。これでは子供の脳は混乱する。一体、「良いのだろうか、悪いのだろうか」と。どうしたらいいのか、わからなくなる。
親が点数を見て、一喜一憂すると、お子様の大きく伸びる芽を摘むことになる。一人ひとり、伸びる時期は異なる。中学で伸びる子がいれば、高校で伸びる子もいる。社会に出てから能力を伸ばして、その後、活躍し続ける子もいる。
勿論、問題点をそのままにしてはいけない。少しずつ、やり直して、改善していく必要がある。しかし、やるだけのことをやったならば、点数など気にならなくなる。そこまでいって初めて、驚く位に良い結果が出る。それは、その境地に達した親子にしか分からない。そういった親子を、私はたくさん見ている。
2025/10/14

『質問』
「質問をしなさい」
と言う親や教育者は多い。
質問をすることが大変良いことだと考えている。分からないことはすべてわかることが大切だと思いこんでいる。質問をすることが前向きな学習の姿勢だと勘違いしている。
「質問の99%」
それは疑問でしかない。
ていねいに調べると分かる、深く考えると分かる、しっかりと聞いていれば分かるのである。質問の99%は時間の無駄だ。
実際、成績上位者からは質問が出ない。
「頭がいいからだろう」
と言う人がいるがそれは違う。
調べる、考える力が高い。
聞く力、聴く力、訊く力も高い。
一般的な家庭での話だ。
「お母さん、この問題分からない」
「先生に聞いてきなさい」
子はその場でわかりたいのだ。
お母さんに助けを求めている。
親は、それを突き放している。
出来る子の家庭ではこうだ。
「お母さん、この問題分からない」
「一緒に調べてみようか」
「やっぱりよく分からない」
「お父さんにも聞いてみようか」
「わかった」
「よかったね」
お子様は納得する。
家族の協力に安心する。
調べて、考える子に成長する。
実は、出来る子も年二、三回質問する。
考えて考えてそれでも分からない時に、考えた過程をノートに記して質問にやって来る。その時は、一旦ノートを預かって私もじっくりと考えてから丁寧に答える。
テストが終わってから、復習をしてどうしても納得がいかない問題がある時、矢張り質問にやって来る。深く考え抜いているので、私が伝えることがストレートに伝わる。
「疑問、質問、ドラえもん」
真の質問は大歓迎である。
2025/10/13

『理科・社会』
小学五、六年生、中学生の理科・社会、塾の平常授業が終盤を迎えている。年内に、教科書の学習内容は塾テキストで指導を終える。その後は別の講座を実施する。
十月より、小五、小六は算数の発展演習講座を行う。中学生は診断テスト対策講座を行う。当然、学校よりも進度がはやい。
「テストまでに忘れる」
という生徒がいる。
「忘れるからいいんだよ」
と私はこたえる。
進学塾の授業後に一回目の復習を行う。学校の授業後に二回目の復習を行う。中間テスト、期末テストの前に三回目の復習を行う。そして、診断テストの前に四回目の復習を行う。
これで、100%覚えることが出来る。最後に、入試直前五回目の復習を行う。これですべてが完成する。合格者はこれを守っている。エビングハウスの忘却曲線を考えると理に適っていることが分かる。
11月は『期末テスト対策』を行う。来年1月は『診断テスト対策』を行う。そして、2月は『学年末テスト対策』を行う。3月は『予習講座』を行う。平常授業カリキュラムは考え抜いて実施している。それに合わせて復習する子は、最高の結果を出す。結局、テスト前ではなく「普段」が最も大切なのである。
2025/10/12

『三度目の「革新」』
「お子様の学力を飛躍的に向上させる為の新たなる挑戦」
一度目は小学部に発展演習講座、算数・国語を導入したこと。二度目は中学部に発展演習講座、数学・英語を導入したこと。
今回、三度目は小学部高学年の授業科目を算数・国語・理科・社会に数学・英語を導入、六科目を週二回にて指導体制を整えたことである。学習生産性を高めて質の高い指導を行う。
時代のニーズを正しく読む。
佐藤進学塾、卒業生の進学先は多岐にわたる。
東大、京大、阪大、神大、九大、広大、岡大、香大、…。国立大学進学が八割、その中の医学部医学科へ進学する子がおよそ三割を占める。既に医師となり活躍している子も多い。
一昨年より、『高松高校上位合格を目指す意識の高い子』に合わせて、学習カリキュラムを刷新して授業を実施している。新年度はそれを完成形にして授業体制を整える。
小三、小四は週一回で算数・国語の二科、小五は週二回で算数・国語・英語・理科・社会の五科、小六は週二回で算数・数学・国語・英語・理科・社会の六科を指導する。限りある時間の中で、完璧に授業準備をした上で最大限、効率的な授業指導を行う。指導レベルの高い専任教員が最高水準の授業を展開する。
効率良い指導を行う。
効率良い学習を行う。
効率良く結果を出す。
日々、二三時間の学習で最高の結果を出す為に、学習生産性を最大限に高めていく。
来年度の詳しい資料は今月末、生徒に渡す。内容、カリキュラム等を詳しく書いている。大枠は、昨年度お知らせしたものと同じであるが、若干の変更点があるので気を付けて見て頂きたい。その後、一般の方に向けてホームページ上でお知らせする。
一部を抜粋してご紹介する。
小学6年生になると、ライバルに先行出来るよう先取り学習に取り組む子が出てきます。特に「算数」は「数学」になり、難しく感じられる為、先取り学習に力が入る傾向にあります。しかし、数学は積み重ねの教科で算数を理解しないまま学習を進めても躓いてしまいます。佐藤進学塾では、週一回、従来型の『小6算数』を4月から12月まで行い完成させます。その後、先取り学習の『中学数学』を丁寧に指導していくことによって、最大限に数学力を伸ばす事が出来るよう一人ひとりに向き合い指導します。
現在、二学期生の残席は『ゼロ』、すべての学年クラスにおいて予約待ちである。12月から新年度募集に入る予定であるが、各学年一、二名の募集となる予定だ。大変申し訳ないが、ご了承願いたく思う。
2025/10/11

『理科・社会』
小学五、六年生、中学生の理科・社会、塾の平常授業が終盤を迎えている。年内に、教科書の学習内容は塾テキストで指導を終える。その後は別の講座を実施する。
十月より、小五、小六は算数の発展演習講座を行う。中学生は診断テスト対策講座を行う。当然、学校よりも進度がはやい。
「テストまでに忘れてしまう」
という生徒がいる。
「忘れるからいいんだよ」
と私はこたえる。
進学塾の授業後に一回目の復習を行う。学校の授業後に二回目の復習を行う。中間テスト、期末テストの前に三回目の復習を行う。そして、診断テストの前に四回目の復習を行う。
これで、100%覚えることが出来る。最後に、入試直前五回目の復習を行う。これですべてが完成する。合格者はこれを守っている。エビングハウスの忘却曲線を考えると理に適っていることが分かる。
11月は『期末テスト対策』を行う。来年1月は『診断テスト対策』を行う。そして、2月は『学年末テスト対策』を行う。3月は『予習講座』を行う。平常授業カリキュラムは考え抜いて実施している。それに合わせて復習する子は、最高の結果を出す。結局、テスト前ではなく「普段」が最も大切なのである。
2025/10/10

『不安心理』
「不安は動作を急がせる」
目の前のことから、早く逃げようとして動作は速くなる。
大切な動作の省略が起きるのだ。
自信がない子は、テストを速く解く。テストから早く逃げたいからだ。意識下では、ゆっくり解こうと思っている。しかし、無意識下ではテストから逃げようとしているから速くなる。
自信がない子は、『意識<無意識(潜在意識)』の状態となる。「家でゆっくり考えたら、出来た」という言い訳はよく聞く。
では、どうすれば、
実際のテストでゆっくり考えて解くことが出来るのか。
普段から、ゆっくりと動作することを意識すればよい。文章をゆっくり丁寧に読む。字をゆっくり丁寧に書く。鉛筆をゆっくり手に取り、ゆっくり机に置く。テキストを丁寧に開き、静かに閉じる。
周りの人から見て優雅に見える動作を行うのである。エレガンスと言う言葉が適しているかもしれない。エレガンスな人は一つ一つの動作を大切にしている。
常に「ゆっくり」を意識すると、『意識=無意識(潜在意識)』の状態にすることが出来る。それが常態化して、ゆっくり行動出来る様に成った時、『意識>無意識(潜在意識)』の状態に変わっていく。その時、学力は飛躍的に上がる。傍から見ると、優雅でエレガントに見える。意識と無意識は、氷山の見えている部分と海水中に隠れている部分の関係に似ている。
メンタルを鍛えることは大変だ。
しかし、正しい努力を行えば、メンタルも鍛え上げることが出来る。
2025/10/9

『優雅な姿』
遠目からだと、ゆったり見えるモノは多い。遠目であるほど、その姿はとても優雅に見える。
「湖面をスイスイと泳ぐ水鳥」
傍目には、とても優雅である。しかし、水中では、両足を動かして、必死に水をかき分けて、進んでいる。水鳥たちが懸命に足を動かしていても、苦しそうな顔などすることはない。
さて、中学生のテストが返されている。五科目、すべて返ってきた子も多い。ほとんどの子が順位も出ている。
最高の笑顔の子がいる。
「先生、『一位』でした」
「本当に良かったね」
明るい笑顔の子もいる。
「先生、『三位』でした」
「良く頑張ったね」
表情が暗い子もいる。
「あまり、よくなかったです」
「次に向けて、また頑張ろう」
最高の結果が出た子は笑顔である。470点、480点、490点を超えている。本当に、良く頑張ったと思う。軌道に乗っているのでこのまま頑張ると良い。正しい努力を続けて、ここまで来た子たちである。最初から何もせず、結果が出た子など一人もいない。
涼しい顔をしていても、驚く位に努力している。
見えないところで本当に良く頑張っている。「ものすごく、頑張ったのに」などと言うことを、口にすることはない。傍から見ると、その姿はとても優雅に見える。
頑張ったのに結果が出なかった子もいる。
本当に辛いと思うが、諦めずに頑張り続けよう。諦めることなく取り組む子には、全力で指導を続ける。努力が結果に結びつかないのは、気付いていない要因がある。テストを徹底的に見直そう。間違った問題の原因について、教科書、辞書を活用して探っていくことが大切だ。
1⃣勘違い、読み間違い
2⃣.理解が浅い為の間違い
3⃣本質的に理解出来ていない間違い
たぶん、1⃣と2⃣が、殆どである。もし、3⃣ならば徹底的に復習する。テストの時に、解けない問題は必ずある。1⃣と2⃣の間違いは、軽視しがちである。
「家でもう一度やれば、出来た」
と言って、そのままにしてはいけない。
音読をして、耳で確認するトレーニングを行う。テスト時、音読と黙読のスピードを一致させる。黙読のスピードが速いためにミスが生じるのだ。結果が出ている子は、音読が上手であり、黙読のスピードがとてもゆっくりである。
水鳥は優雅だが、水中で足をばたばた動かしている。優秀な子は、傍目には優雅に見えるが、見えないところで努力を積み重ねている。その大切さに気付いて、努力を継続する子は益々優雅に成っていく。
2025/10/8

『附属小テスト対策』
一昨年まで、附属小期末テスト対策を実施していた。附属小の子が、全員参加して取り組んでいた。昨年からは実施の必要がなくなった。附属小期末テストが廃止されたからだ。
小六学力テスト年三回は実施される。
勿論、学力テスト対策は引き続き行っている。附属小の子たちは優秀な公立小の子たちと全力で頑張っている。
かつて、附属小三から小五の子たちは期末試験に向けて、気を引き締めて勉強していた。昨年からは、…。気が緩んでいる。驚くことにテストがなくなった分、楽しい行事が増えている。
一昨年は試験対策を行っていた。
附小生は高学年が集中する。
それを見て、中学年も集中する。
伝統であり、学習の好循環であった。
公立小の優秀な子もそれを見て「負けるものか」と頑張っていた。附属小期末テストが廃止されたことはとても良いことだ。しかし、小さな目標を失った。大きな目標は小さな目標の積み重ねの下に成り立つ。
さて、附小六は第二回学力テストが実施された。結果を出すには、家での復習が必要だ。塾で理解、家で定着という流れが大切だ。12月初旬実施、最後の第三回学力テストに向けてしっかり認識してほしい。
1.間違った問題を解き直す
2.教科書から出題元を探してノートにまとめる
3.学校ワーク類から類似問題を見つけて解き直す
これらを深く考えて丁寧に行う。余裕のある子は辞書、参考書を活用する。最後にもう一度、時間を計り解いてみる。これで、すべて解くことが出来たならば完成だ。そうでなければ、1.2.3.を繰り返す。
これが、家庭での復習である。
2025/10/7

『中一・中二「数学」』
中一は『平面図形』である。
作図方法について指導する。
1.垂直二等分線
2.角の二等分線
3.垂線
コンパスを使い、素早く書く。
難しい問題も組み合わせである。
おうぎ形の弧の長さと面積の公式を復習する。
「円周」と「円の面積」の公式がもとになっている。
円周=2πr
円の面積=πr²
これに中心角の割合をかけると「おうぎ形」になる。
45/360=1/8と約分する。
135/360=3/8と約分する。
これらは覚えておくとよい。
こうすれば、暗算で処理できる。
計算ミスもない。
最後に、「π」を確認する。
πは、よく書き忘れるからだ。
面積にはもう一つの公式がある。
この公式には中心角が必要ない。
徹底的に計算演習してほしい。
中二は『二等辺三角形の証明』である。
矢張り、仮定をもとに結論を導き出す。
まず、二等辺三角形の定義と定理を確認する。それから、概形を書いて合同条件を判断する。全ての問題について、正しい解法を丁寧に解説した。それを真似て、自分で解くことが出来るように復習する。
最初は自分で解法が瞬時に閃くことはない。正しい解法を学び、その解法の通りに解くことが出来るようにする。解法を一通り学び、習得して自分自身で解いていくと良い。その時には、スラスラ解くことが出来る様になっている。図形センスがなくても、磨き上げていくことが出来る。
2025/10/6

『同期発火』
人間の脳で起きる『同期発火』という現象がある。同期発火は、自分の脳内で考えをまとめる時、相手の発する情報に反応している時にも起きている。
コミュニケーションを考える上で重要な現象である。
脳の神経細胞群は情報を受け取った時、「興味を持つ、感心する、前向きな心を持つ」ほど強い『同期発火』を起こす。これに拠り脳のパフォーマンスが高まり、凄い力が発揮出来る。
自分の気持ちや考えは、他の人にどのようにして伝わるのか。
脳と脳の間をつないで情報をやり取りする回路が存在しているわけではないのに、不思議である。たとえば、泣いている人を見るだけで悲しい気持ちになることがある。
それは、相手の発する情報、表情、身振り、手振りなどを脳が受け取り、相手と同じように脳神経細胞を同期発火させるからである。佐藤進学塾クラスの皆が、試験や入試に向けて同期発火すると凄まじい力を発揮する。一人ひとりの実力を「10」とすると、同期発火が起こった時、「12」~「15」に跳ね上がる。
「では、『同期発火』を起こすにはどうすれば良いか」
一人ひとりが、友人を尊敬する。一人ひとりの良い所を互いに認め合う。クラスの皆が、情報を積極的に共有するなどである。「皆、仲よくしよう」などと、言っているのではない。同期発火が起こると、その集団に凄いフォースが発生する。皆が一心同体となって、頑張り始めるので安心して勉強出来る。
2025/10/5

『美しい姿勢』
中学生の中間テストが全員終了した。既に、結果が出ている子もいる。テストが明けて、皆、明るい表情で塾へやって来る。
テストが終わって、いつも通り授業へ真剣に取り組んでいる。中学生は高い集中力を維持して学習出来るようになった。
テスト前ではなく、普段が大切なのだ。
皆、姿勢が美しくなっている。中でも格別、美しい子がいる。その子たちは素晴らしい結果を出している。
「姿勢と集中力」の相関関係は高い。
「集中力と結果」の相関関係も高い。
姿勢と結果が、単に比例するのではない。しかし、姿勢が良い子は素晴らしい結果が間違いなく出るということだ。
小学生にも、そのあたりの大切さを何度も伝えている。一、二回、伝えただけで直そうとする子がいる。一年、二年、言い続けなければいけない子もいる。それでも、言い続ける。
「この差は、何か」
心の素直さである。
素直な子はすぐに直す。
そして、直ぐ結果を出す。
「姿勢が綺麗になったな」
と思ったら、ほぼ、同時に学力が上がる。
「格段と姿勢が美しくなったな」
と思ったら、一位、二位、三位などという優秀な成績を取って来る。
「良く頑張ったね」と言うと、「ありがとうございます」と、姿勢を正し、気持ち良くこたえてくれる。その時の姿勢は大変美しく、声は元気で溌剌としている。その後も、美しい姿勢は続く。試験結果は高い状態で安定する。良い結果を出したければ、姿勢を美しくすれば良い。それだけである。
1.テキストを真っ直ぐ置く
2.背筋をまっすぐに伸ばす
3.肘はつかず、お腹と背中にこぶし一つ分の空間をつくる
1→2→3を順に意識する。
たった、これだけのことだ。
これだけで成績はグンと上がる。
もちろん、最高の指導者の下で生徒が正しい努力をした時の話であることは言うまでもない。
2025/10/4

『タイムパフォーマンス』
費やした時間とそれによって得られた効果や満足度の対比、すなわち時間対効果で『タイパ』とも言われる。
短い時間で高い効果を得られたならば、タイムパフォーマンスが高いという。長い時間を掛けたにも関わらず効果が低いときは、タイムパフォーマンスが低いという。
短時間で良い結果が出た時はタイパの良い学習と言える。
Z世代の間では、タイムパフォーマンスの高さが重視される。限られた時間内にどれだけの効果を得られるかが強く意識されるようになっている。
近年、ビジネスの現場でも無駄な時間を掛けることなく効率良く仕事を行い結果を出すことが重視されている。今、改めて「タイムパフォーマンスの高い学習」が注目を集めている。
今回も、佐藤進学塾ではタイムパフォーマンスを重視して、中学生の二学期中間テスト対策を実施した。三週間に亘る長い期間であったが、一日、二、三時間、集中して学習を行い最大限の効果が表れるように工夫して行った。(流石に中三生は試験直前の土日、五時間頑張ってもらった)
実際には、平常授業での指導内容の密度が高いからテスト対策期間には短時間で十分に仕上がる。テスト前、午後九時過ぎに授業は終了、「早く帰って、早く寝なさい」と生徒たちに伝えた。テスト前に慌てて仕上げるのではなく、普段の日々の学習の積み重ねが大切であると考えている。
さて、今回も、佐藤進学塾、中学生の子たちは本当に良く頑張った。一人ひとり、最高の結果が出る事は間違いない。今週からは、予習授業を再開している。目先のテストのことではなく、一人ひとりの将来を考えて授業指導を行っている。
2025/10/3
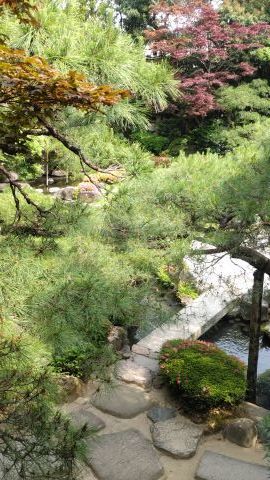
『リズム』
「ゆっくりリズム良く解いて」
生徒たちによく掛ける言葉だ。
「はやく解きなさい」
と、言うことは絶対ない。
特にテスト前はゆっくりリズム良く解いていくことが大切だ。決して、速く解いてはいけない。ミスが増えるからである。
中学部の子たちはその大切さに気付いている。結果を出す子は驚く位にゆっくり解く。50分のテストは45分で解いて、5分間だけを見直しの時間に使う。自律神経が安定している。
さて、テスト対策で「ゆっくり、解いてください」と伝えた。三十分位で解いて鉛筆を机に置いている子がいる。
「…」
早く切り上げて解説を行う。
矢張り、間違いが多い。
「『ゆっくり解いて』と言ったよね」
生徒に言うと、不満そうな顔をしている。
速く解くことが良いことと勘違いしている。
ゆっくり解くことの大切さを改めて伝えた。
テストの大切さを伝えるには本当に時間が掛かる。それでも、私は粘り強く伝えていく。大切なことは、「大切である」と。佐藤進学塾の生徒には時間が掛かっても、私の言う事を素直に理解して学力を飛躍的に伸ばす生徒が多くいる。そういう素直で前向きな可能性のある子を佐藤進学塾は大切に育てていく。
2025/10/2

『示唆』
示唆とは、それとなく教えることを表した言葉だ。
示唆は英語では「suggestion」である。「suggestion」には、示唆や提案の他に思いつきや様子などの意味も含まれている。
「発言の中で、それとなく真実を伝える」
「遠回しに、大切な何かを教え示す」
といった事を述べる場面において用いる。
テスト前、私は後者を使う。
『September』を『Seftember』と書いている子がいる。
私が「発音してごらん」と言うと、本人はハッとして、正しいスペル『p』に気付く。
『貯蓄』を『貯畜』と書いている子がいる。
「畜の漢字をよく見てごらん」と言うと、本人はハッとして、『くさかんむり』に気付く。
『日本書紀、古事記、風土記』の『き』の漢字を間違えている子がいる。
「教科書を調べて確認しよう」と言うと、本人はハッとして、『記』と『紀』の違いに気付く。
中一のテスト対策での出来事だ。中一はまだ三回目のテストゆえ、こういう事はよくある。中二、中三はテスト対策を繰り返しているのでこういう事は殆どない。決して、私が正しい答えを言うことはしない。必ず、本人に気付かせるように示唆する。
それにしても、『貯畜』は面白い。「牛、豚、鶏をたくわえること」と言う意味になる。
「モーモー、ブーブー、コケコッコー」と、とても賑やかである。
2025/10/1

『完全暗記』
結果を出す子は、解法と解答を暗記する。いくら考えても理屈が分からない時もある。そういう時は取り敢えず覚える。
暫く経って、次のセクションを学んでいる時にふと気づく。「あの時の理屈は、こういうことだったのか」と。
それでいいのである。
少しばかり、冷たい事を言うが、テスト前は『適度に諦める』ことの習慣化は大切だ。賢い子というのは意外と諦めが早い。
普段の問題演習では『10分』考えてわからなかったら諦めて、答えを見て覚えるというルーティーンに入る。それから、気持ちを切り替えて次の問題に取り掛かる。
特に、テスト前は『3分』考えて分からない時、すぐに解法と解答を見て考える。3分、5分、10分という時間を決めておき、時間を過ぎたら諦める。時間内は、かなりの集中力で問題に向き合うことができる。
先日も言った。
「集中力は最大15分」である。
諦める直前の短い時間だが、その集中力は凄まじい。15分を超えてだらだら考えても、無駄という事だ。諦めると言う言葉は否定的に捉えられがちだが、その『諦める』と言う言葉自体を肯定的に捉える。
「もう少しで解けそう」
テスト当日、そのような曖昧なことは考えず、明確な基準を持ち諦めることが出来る。一般的な常識とはかけ離れているが、結果を出す賢い子と言うのはそういうものである。メンタルが強靭だ!
しかし、テストが終わってからは違う。間違った問題は何時間、何日掛かっても調べて考える。そして、疑問点を丁寧且つ詳しくノートに纏め上げて質問にやってくる。
「この部分が納得できません」
自分が復習したノートを開いて、私に伝える。心の底から納得するまで、私の傍を離れない。私が説明を終えたところで、「なるほど」という表情を浮かべ、お礼の言葉を述べて私のもとを去っていく。
「ありがとうございました」
私も説明に『10分』以上掛けない様に心掛けている。生徒の集中力がマックスの時、説明も佳境に入る。そういった事をルール化して実際に私自身も実行している。だから、佐藤進学塾の生徒の学力は飛躍的に伸びていく。そういう素直で前向きな生徒たちの為に佐藤進学塾は存在する。
2025/9/30

『リスクヘッジ』
金融取引において使われていた言葉だ。昨今、ビジネス全般において使われている。リスクヘッジとは、「危険を予測、それを避ける為の対策を練る」 ということである。
これは学習にも応用できる。
様々な試験に必ずリスクはあり、全てのテストにおいてリスクヘッジを行う必要があることを頭においておくとよい。
では、具体的にリスクヘッジを考えてみる。
◎リスク
1.見た事ない難しい問題が出る
2.問題数が予想以上に大変多い
3.緊張して普段の平常心を失う
◎リスクヘッジ
1.事前に難しい問題を徹底的に練習しておく。解けない時は、それを除いて、目標の98点を取り切る。
2.普段より、出来る問題から解く習慣を付けておく。多い時は時間配分を考えて、95点以上取得する。
3.日頃から深呼吸の練習をしておく。緊張した時は深呼吸後、平常心を取り戻し、90点以上必ず取る。
自分に合わせたリスクヘッジを考えておくといい。しかし、テストについて過大に心配する必要はない。やる事をやったならば、あとは運を天に任せよう。努力した子は努力した分だけ、運が強くなっている。
2025/9/29

『飛躍的な成長』
学習における成長とは「受動的な学習」の域を超えて「能動的な学習」の域にはいる事である。成長には「学力の成長」と「精神力の成長」の二つがある。
車の両輪の様なものでいずれも重要だ。
学力が成長すると、勉強はある程度出来るようになる。練習を重ねた類似問題は確実に出来るようになるからだ。ところが、ある期間経つと限界に達する。難しい問題が解けない壁にぶつかる。学力的な成長だけでは次元の高い勉強はできない。
もう一方の精神的な成長が不可欠なのである。
「先生は魔法を掛けた様に難しい問題を一瞬で解きます。どうしたら、あの様に美しく解けるのですか」と訊かれる。
「算数、数学が大好きなんだよ。 難しい問題についてあらゆる角度から考えて、様々な解法を考えることが楽しいんだよ」と答える。
問題を無機的に解くのではなく、有機的に解法を創造するイメージだ。ある日、突然、それに気付くことはない。毎日、地道に学習を続けているうちにふと気づく。
「もしかして、これかな」
難しい問題を三日掛かって解けた時、気づくこともある。将来の夢が明確になり、本気で取り組んだ時、気づくこともある。友人が頑張っている姿を見て、気づく時もある。きっかけは人それぞれである。
さて、精神的な成長で問題になるのは学習の意味である。その意味を見出したときに、その子は作業的な学習から、創造的な学習に変わる。自ら学習に向かう能動的な学習を楽しむ様になる。生徒たちが、進歩している姿が時々、見られる。勉強自体が楽しくなってきて本気で取り組む姿を見ると本当にうれしい。
「良かったね」
「頑張ったね」
「すごいね」
一人ひとりに声を掛ける。
「ありがとうございます」
生徒たちは嬉しそうに笑顔でこたえてくれる。
授業を一日も休む事なく真剣に聴いて、ブログを読み続けてその意味を見つけた子も多くいる。だから、毎日、真剣に一日も休むことなくブログを書き続けている。塾長の私自身が学力面、精神面で成長し続けることが、生徒たちの『飛躍的な成長』を支え、応援することに成ると信じて努力を続けている。
その努力は楽しい!
2025/9/28

『レスポンス』
英語の「response」に由来する「レスポンス」は返答、応答、反応などの意味がある。
勉強ができる子はレスポンスが速い。指導者や大切な友人の信頼を得たり学習をスムーズに進めたりできるメリットがある。
日頃から、学習内容に優先順位をつける、様々なプリント類やノートを整理整頓するなど、レスポンスを早くするコツを身に付けると良い。
さて、先日、「『6B』のえんぴつを使ってごらん」 と中学生に伝えた話をした。その子のノートを見ると、ノートの字が濃くなっている。薄かった字が濃くなっている。手元を見ると、硬筆用の鉛筆6Bがしっかり握られている。レスポンスが速い。
「あっ、鉛筆、変えたね」
「はい」
「濃くなった分、消しゴムが真っ黒になるから、予備を用意するか、大きいものを準備するといいよ」
「はい」
それから一週間後、それも守っていた。今は高松高校二年生として頑張っている。レスポンスが早い子は直ぐに勉強出来るようになる。何より、指導者としてはとても気持ちの良いことである。
2025/9/27

『中間テスト対策』
中学生の二学期中間テスト対策が完成した。佐藤進学塾の生徒みんな、本当に良く頑張った。
「テスト対策の午前中」
1.教室の美装
2.塾庭の手入れ
3.自転車置き場の清掃
4.対策プリント類の準備
5.アプローチ、塾主庭の打ち水
をルーティーンとして行った。
最後に神棚へ水、塩、米、酒、榊を供える。蝋燭に火を灯し、二礼二拍手一礼してお参りする。
伊勢神宮のお神札を中心に、氏神様の熊野神社、石清尾八幡宮のお神札、崇敬神社の今宮神社のお神札を祀っている。京都紫野、今宮さんには日供をお願いしている。夏越の大祓えの時、ご祈祷をお願いする。松縄の氏神様、熊野神社さんは毎月お参りしている。高松の氏神様石清尾さんは毎年末、お祓いに行く。
午後より神聖な気持ちで生徒たちを迎え入れる。教室には京都西本願寺前、薫玉堂の御香を焚いている。創業四百二十年、日本最古の御香調進所の伝統が教室に薫る。心が引き締まる思いがする。
「こんにちは」
生徒たちが次々とやって来る。
「こんにちは」
一人ひとりの顔を見て挨拶する。
表情を見れば、子たちの心の状態が分かる。
少しでも気掛かりな時は、そっと言葉を掛ける。子たちは友人と一言、二言、言葉を交わす。その後は、集中して対策へ取り組む。佐藤進学塾の生徒たちは両親、先生、友人、万物から応援を受けている。そして、神様の御加護も受けている。
連休中も含めて、佐藤進学塾のテスト対策にご理解、ご協力頂きました保護者様には心より感謝したい。
2025/9/26

『レスポンス』
英語の「response」に由来する「レスポンス」は返答、応答、反応などの意味がある。
勉強ができる子はレスポンスが早い。指導者や大切な友人の信頼を得たり学習をスムーズに進めたりできるメリットがある。
日頃から、学習内容に優先順位をつける、様々なプリント類やノートを整理整頓するなど、レスポンスを早くするコツを身に付けると良い。
さて、先日、「『6B』のえんぴつを使ってごらん」 と中学生に伝えた話をした。その子のノートを見ると、ノートの字が濃くなっている。薄かった字が濃くなっている。手元を見ると、硬筆用の鉛筆6Bがしっかり握られている。レスポンスが早い。
「あっ、鉛筆、変えたね」
「はい」
「濃くなった分、消しゴムが真っ黒になるから、予備を用意するか、大きいものを準備するといいよ」
「はい」
それから一週間後、それも守っていた。今は高松高校二年生として頑張っている。レスポンスが早い子は直ぐに勉強出来るようになる。何より、指導者としてはとても気持ちの良いことである。
2025/9/25

『お礼の言葉』
「熱心にテスト対策を行って頂きましてどうもありがとうございます。教科書をしっかり勉強させたいと思います。」
保護者様から言葉を戴いた。
あと少しでテスト対策は完成する。しかし「あと少しで終わり」と思ってはいけない。「もうすぐ終わり」と思うと脳が緩む。脳科学の医師が様々な検証を行い実証している。
同じ学力の大学生を二つのグループに分ける。
前者には「もうすぐ終わりです」、後者には「まだ、しばらく続きます」と告知してテストを行ったところ、「もうすぐ終わりです」と言ったグループの正答率は大きく下がったと言う。
佐藤進学塾では期末テストも意識して対策を行っている。中三は診断テスト第三回も強く意識している。そうすることに拠り、脳に緊張感を持たせる。もちろん、試験が終わったら少しゆっくり過ごすと良い。
さて、テスト対策のお礼の言葉を戴くとこちらも力が入る。この手紙を頂く少し前に中学部の生徒から、「だいぶ仕上がったのですが、テスト直前は何をしたらいいですか」という質問があった。
私は「直前は教科書を活用して隅々まで学習する事が大切です。ワークで繰り返し間違う問題について、教科書を再度調べて音読、大切な事をまとめて深く理解することを行ってほしいと思います」と伝えた。
その様なことを生徒が家へ帰ってから家族と話して、それを皆で共有していることをうれしく思った。
2025/9/24

『筆圧』
筆圧が強い子は自信がある。
筆圧が弱い子は自信がない。
筆圧は心の状態を表している。
一概には、言えない部分もある。筆圧が強い子で、緊張している子もいる。筆圧が弱い子で、手指の力が少し弱い子もいる。しかし、自信の有無が関係していることは間違いない。
「先生、数学の点が伸びません」
一人の中学生が相談に来た。
その子は勉強を頑張っている。ところが、ノートも答案も筆圧が弱い。字が薄いのである。目を凝らしても、よく見えない。
筆圧を強くする方法はある。
1.鉛筆を正しく持つ
2.学習時の正しい姿勢
3.上質な文房具の使用
1,2の矯正には時間が掛かる。
しかし、3ならば簡単に出来る。
その子には「6B」を使う様に伝えた。鉛筆自体、上質な製品を買う様に伝えた。視認性が高まるので、計算ミスが大幅に減る。自分の解法の見間違いがなくなるのである。ミスが減ると、自信もついてくる。実際、この子も6Bに変えてからはミスが減り、中三では数学も確実に90点台が取れるようになった。
「字が薄い子はミスが多い」
さて、どうするか。
「鉛筆を変えると良い」
上質な硬筆用の『6B』に変える。芯が柔らかいので、自然と濃く書くことが出来る。筆圧が弱いことを鉛筆でカバーできる。
愛光高校へ合格して、今年大阪大学へ合格した子は最後まで「6B」を使っていた。
ほんの少しの工夫と気持ちで正答率は上げられるのである。こんな簡単なことはない。ただ、字を消すのに少し時間が掛かる。消しゴムは良質で大きめの白いものを二つ用意しておく必要がある。
2025/9/23

『テスト対策期間』
「小6学力テスト対策」
1.問題演習(40分)
2.問題解説(15分)
3.間違い直し(10分)
試験を想定したオーソドックスな進学塾での指導形態である。小学六年生には、テスト勉強の『型』を身に付けてもらう。
「中学生のテスト対策」
毎回、塾長がテスト勉強について話を行う。一つの話題について話し、一人ひとり、生徒の意見を聞く。そして、一人ひとりにアドバイスを行う。筋道立てて穏やかに伝える。
高松高校へ進学した114名の学習方法を伝える。114名の成功事例には114通りの学習方法がある。見つける迄には紆余曲折があり、努力を重ねて辿り着いたそのヒントを塾生に伝える。
話し合った後は各自、対策問題中心に学習へ入る。小学部から通塾の子は原則的学習が身に付いている。驚異的な集中力で学習する。中学部から入塾の子はその集中力を見倣い学習する。賢い子の勉強法を真似ると、それだけで結果は出る。
時々、難しい問題について友人同士で話している。互いに教え合うことで、更に学力を高めている。その後は家に帰り学習する。家は塾と比べると集中力は下がるが大丈夫だ。家はリラックスして学習出来る。佐藤進学塾は高い緊張感が伴う。その切り替えとバランスが大切である。
2025/9/22

『第二回診断テスト』
中学三年生、第二回診断テスト、みんな本当に良く頑張った。結果をもとに、一人ひとりと時間を掛けて話を行う。良い点は褒め称え、問題点は改善する手法を生徒と一緒に考えていく。
生徒との会話である。
「『240点』を超えたね。頑張ったね。特に数学の図形の問題は良く出来たね」
生徒はこう答えた。
「先生が予習事項として相似な図形を指導して下さったとき、三平方の定理も少し予習してみたんです。そうすると、解説とは違うやり方で瞬時に解くことが出来たんです」
別の生徒との会話である。
「今回、『230点』を超えたね。中でも、社会が『50点』というのは本当に良く頑張ったね」
生徒はこう答えた。
「佐藤進学塾、塾目標の238点を目指して夏休みの間、テスト範囲について隅々まで勉強しました。中でも、社会は塾で演習した問題すべてについて教科書に戻り確認しました。特に、記述問題は正しく答えを書く事が出来る様、教科書を繰り返し何回も読み返して書き写しました」
この子たちは小四の時に入塾した。宿題は一回も忘れたことがない。テキストの解答欄に空欄があったことは一度もない。間違った問題は自分が納得するまで復習してきた。本当に良く努力を重ねてきた。
佐藤進学塾の子たちはこうやって少しずつ実力を高めていく。夢のような一発逆転などを狙う子は一人としていない。生徒たちは地に足をつけて、学校でも佐藤進学塾でも家庭でも、勉強を丁寧に進めていく。十人十色、生徒一人ひとりに合った学習方法を私は一人ひとりへ丁寧に伝えていく。
佐藤進学塾は、「ただ魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」進学塾である。
2025/9/21

『テスト対策期間』
「小学六年生テスト対策」
1.問題演習(40分)
2.問題解説(15分)
3.間違い直し(10分)
一日、二科目を実施する。
一週、四科目を実施する。
試験を想定したオーソドックスな進学塾での指導形態である。小学六年生には定期テスト勉強の『型』を身に付けてもらう。附属小の子はもちろん、公立小の子も一緒に実施する。
中学生の対策は毎回、塾長がテストについて話を行う。一つの話題について話し、一人ひとり、生徒の意見を聞く。そして、一人ひとりにアドバイスを行う。筋道立てて穏やかに伝える。
高松高校へ進学した114名の先輩方の学習方法を伝える。114名の成功事例に114通りの学習方法がある。それを見つけるまでに皆、皆紆余曲折があった。努力を重ねて、辿り着いたそのヒントを塾生に伝える。
話し合った後各自、対策問題の学習へ入る。小学部から通塾の子は原則的学習が身に付いていて、驚異的な集中力で学習する。中学部から通塾の子はその学習を見倣い学習する。相乗効果で集中力は凄まじい。
時々、難しい問題について友人同士で話している。互いに教え合うことで、更に学力を高めている。その後は家に帰り、環境を切り替えて学習する。家は塾と比べると集中力は下がる。しかし、大丈夫だ。家はリラックスして学習出来る。佐藤進学塾は高い緊張感が伴う。その切り替えとバランスが大切である。
塾を活用するのは良いが、依存してはいけない。勉強が出来る子と言うのは、学校でも進学塾でも家でも勉強出来るのである。「家では勉強する気がしない」などと言う子は佐藤進学塾には一人もいない。
佐藤進学塾は九時過ぎに授業を終わる。「気になるところを勉強したら、早く寝ること!」と声を掛けて生徒たちを見送る。就寝中、良質な睡眠の中で大切なことが脳で整理されて確実に定着するのである。
2025/9/20

『気象警報発令時の対応』
「気象警報が発令された時、塾は『休校』とする」
1.小学生 「午後4時半」
2.中学生 「午後6時半」
時点で警報発令時、原則として休校とする。
ホームページ上で休校の旨を連絡する。
(授業中の為、連絡出来ない時もある)
台風接近時、天候急変時は、警報の発令を確認願う。
上記時間以降、警報発令時は自宅待機をお願いする。
警報が発令されていなくても雷雨、豪雨など危険な場合は自宅待機をお願いする。身を守る事を考えて行動してほしい。
佐藤進学塾では生徒さん、及びご家族の安心安全を第一に考えて運営している。
「少しでも、危ないな」
と感じた時は、自宅待機!
午後4時半から9時半までは、授業を行っている。授業前後は生徒一人ひとりの送りと迎えを行っている。その時間帯は、電話による対応は出来ない事、メールの確認もあとから行う事をご理解願いたい。
2025/9/19

『試験対策「第二週」』
中学部は、二学期・中間テスト対策二週目となる。第一週目で教科書の音読と書写、学校ワーク類の演習が一通り終わった。絵に例えると、下書きが終わったところである。
二週目はワーク類の反復に入る。間違った問題は教科書、辞書を調べる。そして、大切なことをノートに纏める。理解を深めつつ、徹底的に反復練習する。
問題を読んだ瞬間に、頭で考えることなく、自分自身の手が、解答、解法を勝手に書く位になるまで練習する。
「反射だ!」
それが本当のテスト勉強だ。
「手だけが学校に行って、テストを受けて帰って来ても100点を取る事が出来るようにしなければならない」
生徒たちは「少し気持ちわるい」と言う。
結果が出る子は、上記を当たり前に行っている。たまに、教科書を読むだけですべての内容を覚えてしまう子もいる。ギフテッドと呼ばれる人たちである。間違っても、その子の真似をしてはいけない。
95%の優秀な子は、声を出して、手で書いて、調べて、…を繰り返すことに拠り、学習事項を定着させている。それが出来る静謐な学習環境が佐藤進学塾にはある。
2025/9/18

『小三算数「円と球」』
「円と球」の単元について
中心、半径、直径の意味について理解していく。
◎直径=半径×2
◎半径=直径÷2
これが直ぐ分かる様にする。
「縦16㎝、横24㎝、高さ12㎝の箱がある。半径2㎝の球はいくついれることができるか」
半径2㎝より、直径は4㎝だ。
縦 16÷4=4
横 24÷4=6
高さ 12÷4=3
よって、4×6×3=72
答えは72個である。
深く理解したあとは、瞬時に出来る様にしておくこと。
『球』に関するクイズである。
1.夏の夜空を彩る。
2.海、川などで見られる。
3.とても涼やかで美しい。
もう、分かっただろうか。
4.大きい音がする。
5.「かぎや、たまや」
中学一年生の理科、
『音と光』の説明にも使う。
もう、分かった事だろう!
2025/9/17

『小六・中学生「テスト対策」』
一昨年は小中学生全学年、テスト対策を行っていた。昨年から附属小は期末テストがなくなった。拠って小三・小四・小五は平常授業を行っている。丁寧かつ詳しく指導する事が出来る。
とても良いことである。
小六、中学生の試験前は、試験演習と解説を行う。小六生は、時間を計り一斉に行う。中学生は、各自が考えて各々行う。
小学部は、塾長である私が主導する。中学部は、各自が考えて能動的に行う。勿論、一人ひとりにアドバイスは行う。
この期間、宿題は出さない。
全時間をテスト勉強に充てる。
全員が最高の結果を出す為だ。
少し矛盾するが、結果を出す子は結果に拘らない。目の前の勉強を大切にする。『原則的学習』を素直に行い最高の結果を出す。最高の結果が出る子は、既に私の目に映っている。普段の勉強の様子で分かる。理解がみんなより遅くても、我武者羅に勉強して素晴らしい結果を出す子もいる。
2025/9/16

『プレゼント』
夏休みに勉強を頑張った生徒たちにプレゼントを渡している。もちろん、全員の生徒たち一人ひとりにである。
今回は、神戸のドイツ菓子『ケーニヒスクローネ』だ!
神戸に出張で出向いた時、神戸大丸で購入してきた。さすがにすごい量なので、三箱に分けて宅急便で送って戴いた。
生徒たちは「ありがとうございます」とにこやかに受け取る。みんな、お洒落なお菓子に興味津々だ。六角形の箱にかわいいクマさんがプリントされている。持手は王冠の形をしている。
ケーニヒス クローネはドイツ語で「勝利の王冠」を意味する。メインキャラクターのクマさん(ポチ)も頭に王冠を乗せているが、けっして威張ったりはしていない。
昨日、渡した子たちが言ってくれた、
「先生、おいしかった!」
「箱がかわいかったです」
「また、次もお願いします」
保護者様からのメッセージも届く。
「がんばった子どものために、素敵なお菓子をいただきましてどうもありがとうございます」
ティータイムに家族で楽しい話をしながら、おいしいお菓子を愉しんでほしい。
2025/9/15

『小三算数「重さ」』
小三『重さ』の単元について
単位の換算を出来るようにする。
1㎏=1000g
1t=1000㎏
3㎏50g=3050g
2085g=2㎏85g
①3㎏850g+2㎏580g
=5㎏1430g
=6㎏ 430g
➁5㎏ 580g-2㎏850g
=4㎏1580g-2㎏850g
=2㎏ 730g
筆算の方法を教えた。
一緒に筆算をしていった。
正確に計算できるようにしよう。
今の子たちは、はかりの目盛りを瞬時によみとる事が出来ない。「大、中、小の目盛りに各々、注目して考えよう」。しかし、説明してもなかなか伝わらない。日頃、デジタル秤を使っていてアナログ秤目盛りをよむ感覚がないからだ。算数ではデジタル秤だけでなくアナログ秤の目盛りもよむ必要がある。
小三、小四の子たちにはそういう事を考える時間的余裕がある。また、それを心から楽しむ事が出来る。本当に勉強が出来る様に成りたい子、或いは出来るようにさせてあげたい親は、このあたりから進学塾での勉強を始めるべきと私は考えている。
小六以降はやる事があまりにもたくさんありすぎる。中学生になると、既に大きな学力差がついている。その差を埋めるのは至難の業だ。「頑張ったら逆転できますよ」など耳障りのいいことを言う人も多い。現実は資本主義が行き着くところまで行きつき、逆転が非常に起こりにくい世の中になっている。
2025/9/14

『気象警報発令時の対応』
「気象警報が発令された時、塾は『休校』とする」
1.小学生 「午後4時半」
2.中学生 「午後6時半」
時点で警報発令時、原則として休校とする。
ホームページ上で休校の旨をお伝えする。
(授業中の為、お伝え出来ない場合もある)
台風接近時、天候急変時は、警報の発令を確認願う。上記時間以降に気象警報が発令した場合も、自宅待機をお願いする。
警報が発令されていなくても雷雨、豪雨など危険な場合は自宅待機をお願いする。身を守る事を考えて行動してほしい。
佐藤進学塾では生徒さん、ご家族様の安心安全を第一に考えて運営している。「少しでも、危ないな」と感じた時は、自宅待機をお願いする。
午後4時半から9時半までは、授業を行っている。授業前後は生徒一人ひとりの送りと迎えを行っている。その時間帯は電話による対応は出来ない事、メールの確認もあとから行う事をご理解願いたい。
「危ないな」と思った時は、家で待機していればよい。
2025/9/13

『全国模試「後編」』
毎年、生徒たちに訊く。
「家の人、褒めてくれた」
「『よく頑張ったね』と褒めてくれました」
「家の人、褒めてくれた」
「『もっと頑張りなさい』と言われました」
褒めてくださる方がいる。
褒めてくださらない方もいる。
伸びる子は前者である。頑張ったことは褒めてあげると良い。私たちも頑張った事に対しては必ず褒める。しかし、その後の対応が大切であることは言うまでもない。
小学生は家の人と一緒にテストを見直す。中学生であっても結果が出ていない子は同じくである。そのあと、教科書、辞書、テキストを調べて丁寧に復習する子は伸びる。ただ、作業の様に形だけ復習をしている子は残念だが伸びない。心をこめて丁寧にやることが大切である。
「なぜ、間違ったのだろう」
「次は、出来るようにしよう」
「必ず、良い結果を出そう」
という気持ちが強い子は結果が出る。
メンタルは親の言葉に拠り創られる。
「良く頑張ったね」
「ここは良く出来たね」
「前より良くなっているよ」
と言う言葉に拠って!
2025/9/12

『全国模試「前編」』
全国模試結果を返却している。総合偏差値「70」を超えた子が七人出た。総合偏差値「65」を超えた子は半数いる。本当に、良く頑張ったものである。
「みんな良く頑張ったね」
「ありがとうございます」
笑顔でこたえてくれる。
その後、一人ひとりに向けて時間を取ってアドバイスを行う。その時、気になることは質問してもらう。それに対して丁寧に答えていき本人が納得するまで話をする。
総合偏差値60を超えている生徒が佐藤進学塾の大多数である。総合偏差値70を超えた七人の子が各学年の核となり、皆、一生懸命に頑張っている。
佐藤進学塾の伝統である。
今回、小六総合偏差値70を超える子が二人いる。もう一人、前回、70を超えた子もいる。三人はいつも復習ノートを提出している。元々頭が良くて、何もせずに凄い結果を出しているのではない。丁寧に復習をしているから結果が出ている。先日、その一人に図形の正しいノートの書き方を教えたところだ。
丁寧に復習する子が結果を出す。その復習の正しい方法は塾の授業内で常に伝えている。それを、愚直に行うことで偏差値は60を超える.復習ノートには私が色々とアドバイスを書き込んでいる。それを実行することで偏差値は65を超える。それから、自分自身で工夫改善を重ねていく子は偏差値70を超える。
2025/9/11

『集中力について』
人間が集中して勉強するとき、集中力の深さや持続時間には、リズムがあることがわかっている。
「15・45・90の法則」
人の体内には、15分、45分、90分というリズムが備わっていることを意味する。深い集中が持続出来るのは、たったの15分である。
「たったの!」
ただし、密度の高い集中時間なので、計算練習を行う、漢字や英単語を覚えるなど、短時間でも集中力がすさまじいので高い効果がある。
「15分」
を侮ってはいけない。
数学の難しい問題「一問」を考えることにも適している。国語や英語の難易度の高い「長文」を読み込んで読解することにも適している。理想は15分ごとに、自分自身の気持ちをリラックス出来る 様にすれば、「15分×3=45分」集中力が最高のリズムになる。
さて、佐藤進学塾のテスト対策時間は「二、三時間」である。(中三だけは内申点対策として五時間行う)朝から晩まで拘束することはしない。令和となった今、昭和のスパルタ主義は通用しない。
「結果が出ないのは、学習時間が足りないからだ。歯を食いしばって必死になって頑張ってやれ」などという言葉はシーラカンス的発想である。脳科学的な見地、見解からの解釈が必要だ。
「15分×3セット=45分」
「45分×2セット=90分」
「90分×2セット=180分」
180分、すなわち「三時間」、集中力が最大限発揮出来る様に考えている。昭和の根性論をおしつけない。実際、佐藤進学塾の生徒は高い集中力で三時間学習する習慣を身に付けている。結果も出している。
『「15分×3セット」×4セット』
「15分×12セット」の様々な学習を各自が工夫して行っているのである。その工夫についてのヒントは、私が、生徒一人ひとりに伝えている。拠って、長時間無理をして学習しなくても最高の結果が出る。睡眠時間も、たっぷりとる事が出来る。生徒たちにとって最も大切な健康管理も万全であるといえる。
2025/9/10

『小五算数「図形の面積」』
小五、図形の面積について
1⃣平行四辺形の面積
「底辺×高さ」
2⃣三角形の面積
「底辺×高さ÷2」
3⃣台形の面積
「(上底+下底)×高さ÷2」
台形の面積の公式の成り立ちについては、授業中に詳しく説明する。上底、下底と高さは、「垂直」の関係にある。
上底3㎝、下底5㎝、高さ4㎝であれば、面積は16㎠である。
「上底3㎝、下底5㎝、面積が20㎠の台形の高さは」
式 (3+5)×□÷2=20
□=20×2÷8
□=5
答え 5㎝
瞬時に答えられる様にする。
図形が得意に成りたい子は、図形を繰り返し書くと良い。図形のイメージをうかべてそれをノートに瞬時に書き表す。計算が速く正確になりたい子は筆算をていねいに書くと良い。ものさしを使って線をひく。マスに合わせて数字を書く。これだけで正答率は大きく上がる。
特に図形の問題は解答よりも解法の過程が大切なのである。過程を大切にする子は大きく伸びる。
2025/9/9

『本当に大切なこと』
テキストを真っすぐ置く。
ノートも、真っすぐ置く。
机に揃えて真っすぐ置く。
お腹と背中に、こぶし一つ分をあける。背筋を伸ばして椅子に座る。両ひじは机につかない。そして、両手は机の上に出す。
「姿勢を正す」
体の姿勢と心の姿勢である。
姿勢がくずれている子は、心の状態がみだれているのである。心がざわついてすこしばかり自己中心だ。姿勢が美しい子は、心も美しく整っている。心穏やかで人の気持ちが分かる。
先生の目を見て授業を聴く。
一言一句もらすことなく聞く。
一生懸命に深い所まで考える。
佐藤進学塾は、『本当に大切なこと』を守る素直な子を大切にする。
2025/9/8

『テスト勉強』
「テストに向けてやるべきこと」
1.教科書の音読と書き写し
2.学校のワーク類の反復練習
3.塾テスト対策プリントの復習
以上、三点である。
完璧に行えば、90点を超える。
上記三点すべてについて、「音読」、「書写」、「反復」を行う。調べて、考えて、最後は覚える。私は、これを『原則的学習』と呼んでいる。原則は一般に適用する、守らなくてはいけない決まり、学習の規則やルールともいえる。
教科書は隅々まで理解する。
ワークは解法解答を覚える。
対策プリントは完全習得する。
声を、しっかり出す。
手を、ひたすら動かす。
教科書を調べて深く理解する。
反復練習して完全に暗記する。
「前回のテスト、家で解き直したら全部解けました」
と、本当は実力があるかのような事を平然と言う子がいる。
家でやると、落ち着いて出来る。
理解不十分でも解く事が出来る。
ところが、テストは学校で行う。
家と違って、かなり、緊張する。
そうなると、完全理解していないと解けない。完璧に暗記していないと、正しく答える事は出来ない。「あとでやったら、出来た」は、理解不十分なのである。目をつぶっていても解く事が出来る様にする。考えなくても、即答出来る様にする。そこまでやって初めて、納得出来る結果が出る。
「目をつぶったら、問題が見えません」
と言った子がいる。
その通りである。しかし、目をつぶっても、心で読むことが出来るくらいにするのが本当の勉強であると言える。あと一つ、付け加えておく。
「テスト前三週間、スマホは親に預けること!」
トップを取る生徒にとって、これは当たり前の事である。
2025/9/7

『テスト対策』
中学生は「二学期中間テスト対策」を実施する。小学六年生は「第二回学力テスト対策」を実施する。
これから三週間、平常授業はすべてテスト対策授業にあてる。学校の教科書、学校のワーク類を持って来るとよい。一生懸命に取り組めば、成績上位者となることは間違いない。
前回、良い結果が出た子は軌道に乗っているので、勉強方法を少しだけ、工夫改善していくと良い。前回、納得のいく結果が出なかった子は音読をしっかり行い、書く量を増やし、教科書を徹底的に調べると良い。
要領の良い学習方法を最初から求めてはいけない。私が伝える『原則的学習』を丁寧に行うことで、いずれ効率良い学習方法へと辿り着く。それまでは、愚直にやるのみだ。実際、素直にやった子は素晴らしい結果を出している。
佐藤進学塾、在塾生の中には上位一桁の子が半数以上いる。高松高校、愛光高校へ合格、そして、進学して頑張っている「114名」の佐藤進学塾、先輩塾生がいる。それらが、上記を証明している。
2025/9/6

『小三算数「長さ」』
小三算数
『距離と道のり』について
家から塾へ来る
道のりを説明してもらう。
「右へ曲がって、まっすぐ、…」
それでは、
「塾へ到着しないな」
と思いながら静かに聞く。
自転車や徒歩、自動車で
移動する道筋が道のりである。
鳥になったとする。
飛んで一直線に来るのが距離だ。
「タケコプターをつけて来てもいいよ」
と言うと、
ニコニコしながら聞いている。
筆算も素早く出来る様にしよう。
2km 800m+3km500m
=5km1300m
(1000mを1㎞へ繰り上げる)
=6km 300m
筆算は丁寧に指導した。
生徒はゆっくり計算した。
繰り上がり、繰り下がりが
難しいが、出来る様になった。
2025/9/5

『慈雨』
小学生の授業前に大雨が降った。
一人ひとりの傘を受け取り、丁寧に畳んで傘立てに収納する。生徒たちは安心して教室へ向かう。少し早めに授業を終えて、生徒一人ひとりを安全に送り出す。
中学生は慣れたもので私たちの指示に従い入室、授業終了後は雨も小康状態と成り安心して帰宅する。
慈雨は万物を潤し育てる雨のこと、俳句では夏の季語である。旱天の慈雨と表現することがある。旱は、日照りを意味する。日照り続きだったところへ降る恵みの雨だ。派生して困難から救われること、待ち望んでいたものが叶えられることもいう。
佐藤進学塾、教室正面、主庭の芝生とたくさんの木々がとても元気になった。芝生や木の葉がきらきらと輝いている。今年は六月からの猛暑をよくぞ耐えきったものである。
水害に見舞われている方々は猛暑も相まって大変であると思われる。心より、お見舞い申し上げる。
2025/9/4

『診断テスト』
香川県下一斉に中三・診断テスト第二回が実施される。入試に向けて行われる大切なテストである。
佐藤進学塾でも、第二回診断テストに向けて早いうちから対策を行ってきた。対策と言っても、小手先の技術を上げて目先の点数を取る為に行うものではない。
例えば数学においては、図形、関数を重点的に学習する。図形は『相似の証明』、関数は『二次関数』を徹底して指導する。
「あれ、その単元は第二回診断テストの範囲ではない」
と思う方もいるだろう。
その通りなのである。
テスト範囲には関係なく真に大切な内容を夏休みに学習するのである。夏休みにテスト範囲だけを必死で勉強して点数を上げたところで、それは付け焼刃の力である。はっきり言って、入試には間に合わないし、高校入学後に伸びる力を養成することは出来ない。
「先生、その単元はテスト範囲ではありません」。かつてはこの様な事を言う子もいた。今ではその様なことを言う子はいない。私が「真に大切である」ということを素直に受け止めて学習する集団になった。先を見通して勉強することが受験では大切である。
2025/9/3

『小四算数「概算」』
小四、概算の単元である。
四捨五入は以前、教えている。
0,1,2,3,4…切り捨て
5,6,7,8,9…切り上げ
「千の位まで」
百の位を四捨五入する。
「一万の位まで」
千の位を四捨五入する。
その後、暗算で計算する。
もたもた筆算してはいけない。
暗算の仕方を具体的に教える。
生徒たちは声に出して確認する。
それから、ノートで計算する。
文章題は条件を確認する。
少なく見積もる場合→切り捨て
多く見積もる場合→切り上げ
それから、答えを出す。
これも、詳しく指導する。
ホワイトボード一面に書く。
それをもとにして、
生徒たちは素早く答えを出す。
今日は少し調子がよくない。
学校が始まったからであろう。
テキストとノートが歪んでいる。
「まっすぐに直して」
「姿勢を正して」
「わかったら、返事して」
と、ピシッと言う。
大切なことは伝える。
生徒の将来を考え妥協しない。
素直に受け止める子が伸びる。
2025/9/2

『小五「算数」』
小五は図形の面積を指導した。
1⃣平行四辺形の面積
公式「底辺×高さ」
底辺と高さは「垂直」の関係にある。
底辺5㎝、高さ4㎝であれば、20㎠である。
「別の辺が8㎝であれば、高さは2.5㎝となる」
8×□=20
□=20÷8
□=2.5
2⃣三角形の面積
公式「底辺×高さ÷2」
底辺と高さは「垂直」の関係にある。
底辺5㎝、高さ4㎝であれば、10㎠である。
「底辺が8㎝、面積が20㎠の三角形の高さは」
式 8×□÷2=20
□=20×2÷8
□=5
答え 5㎝
この位は、
瞬時に答えられる様にする。
「図形が得意になりたい」
ならば、
概形を繰り返し書くと良い。
「計算が速く正確になりたい」
ならば、
筆算をていねいに書くと良い。
解法の過程が大切である。
過程を大切にする子は伸びる。
2025/9/1

『サンドイッチ学習法』
一般的にサンドイッチの様な形式で学習を実施する方法の事を言う。一つ目の学習と二つ目の学習の間に休憩、特に、睡眠を挟むことで学習内容の定着を図る。
「休憩と睡眠」をしっかりとることは本当に大切である。
佐藤進学塾では小学生は午後九時、中学生は午後十一時までに就寝する様に伝えている。「たとえ受験生であっても、夜中の十二時、一時まで勉強する必要などない」と考えている。
さて、集中力を最大限に持続させる為には、佐藤進学塾方式のサンドイッチ学習法が有効だ。得意教科と得意教科の間にあまり得意ではない教科を挟み込む。
例えば、数学と理科が得意教科とする。まず、数学から勉強を始める。60分学習したところで、英語に切り替える。50分学習したところで、理科に切り替えて40分学習する。
これだけで、「二時間半」集中して学習出来る。
決して、得意ではない教科から学習を始めてはいけない。だらだらと長時間勉強するのもよくない。頭を切り替える為の休憩、体と脳を休ませて学習事項を整理定着させる睡眠をしっかり取ることが大切だ。
「苦手科目を克服せよ」
と言う言葉を聞く必要はない。
「得意教科を楽しもう」
と言う言葉を信じると良い。
得意教科は益々出来る様になる。
得意ではない教科も伸びていく。
2025/8/31

『興味関心』
生徒一人ひとりには、各々、興味関心の強いことがある。習い事や部活のことが多い。大変、素晴らしいことである。
生徒一人ひとりと話をしていて、思わぬ方へ興味があることに気付かされることが時々ある。
かつて、地理へ非常に関心が高い子がいた。中学一年生であるにも関わらず、アメリカの五大湖を瞬時に答えた。
「スペリオル、ミシガン、ヒューロン、エリー、オンタリオ」
その子を含めて、生徒にクイズを出した。
第一問
「『帷子ノ辻』何と読むか」
正解
「かたびらのつじ」
帷子ノ辻の地名の由来について生徒たちへ話す。平安時代、嵯峨天皇の皇后、檀林皇后は嵯峨野に檀林寺を創建した。 亡くなった時、棺に絹や麻糸で織った帷子(着物)がかけられていた。葬式の際、この辺りを通った時、四辻で帷子が風に舞ってはらりと落ちたことから帷子ノ辻と呼ばれるようになった。
第二問
「『車折神社』何と読むか」
正解
「くるまざきじんじゃ」
此方も由来を生徒たちへ話す。平安時代の儒者、清原頼業を祀る。後嵯峨天皇が嵐山へ遊行した時、石の前を通ると牛車が倒れ車の轅(ながえ)が折れた。頼業を祀った祠の場所とわかり、車折大明神の神号をおくった。芸能神社としても知られ、撮影所が集まっていた場所柄、玉垣に映画俳優や歌手の名が多い。
京都での大手塾勤務時代を思い出す。
「先生、車折にV6がいてんで」
女子生徒たちが興奮して話す。
「何や、車のエンジンみたいな名前は」
「お父さんと同じこと言わはる」
その後、生徒たちはⅤ6について教えてくれた。
私は興味が無いので、取り敢えずうなずいていた。
今の生徒たちに訊いてみた。
「みんな、『V6』知ってる」
「…」
知らないのは当然である。
「『Ⅴ6』かっこいい」
と当時、大騒ぎしていた女の子たちがすでに目の前の子たちの親世代である。
2025/8/30

『夏期講習を終えて』
中三生、夏期講習会を終えた。
一人ひとりに感想を訊いてみた。
「理科、社会の得点力が上がり自信が付きました」
「英語の長文読解のコツがつかめてうれしいです」
「証明問題を論理的に解く事が出来る様になりました」
「説明文の解き方が分かる様に成り安心しました」
「二次関数を解くのが面白いと感じる様になりました」
生徒たちも、私たちも、夏休みに出来る限りのことを行った。自信を持って、第二回診断テスト受けると良い。間違った問題は、もう一度解き直して復習すればいいだけである。
一昨年、
生徒が面白いことを言った。
「夏休み、毎日、がんばって復習しました。今までの勉強がとてもあまかったことに気付きました。時間を掛けて弱い単元を克服したと思ったら、また、気掛かりな内容が出て来る。そして、それをがんばって克服すると、さらに、気になる問題や単元が出て来る。もぐらたたきのような毎日でした。」
この子も、今は高松高校の二年生となり充実した高校生活を送っている。涼しい顔をしていることでも、みんな、とても大変な思いをしている。それを乗り越えていった子たちが栄冠を手にしている!
2025/8/29

『自分の口から伝える』
生徒を迎えに塾の庭で待つ。
「こんにちは」
みんな、元気にやって来る。
元気なくやって来る子がいる。
「宿題が間に合いませんでした」
「分かった。次まで、待つよ」
情けない気持ちだったのだろう。
怒られる心配をしてたのだろう。
自分の口から伝える子が減った。
親が電話でその旨を伝える。
親が塾に来て、事情を伝える。
子が成長する機会を奪っている。
私もひとりの人間である。
頭ごなしに叱ることはしない。
事情を聞いて大切な事を伝える。
宿題が出来ていないことは褒められる事ではない。しかし、自分自身の口から勇気をもって伝えたことは素晴らしいことであると言える。佐藤進学塾ではこういう小さなことを大切に考えて指導を行っている。
2025/8/28

『情報リテラシー』
情報リテラシーとは、必要な時に情報を探し出すとともに、情報を適切に活用できる能力のことである。情報リテラシー教育とは、その能力を育成するための取り組みを指す。
情報環境が整い、多くの情報を簡単に入手出来る様になった現在、子どもたちの情報リテラシー向上の取り組みは必須の教育課題である。
Web上では、検索した情報に関連した情報が送られてくる為、情報が偏る。その為、的確に情報を探し出して分析して、発信力を高める為に情報リテラシー教育は求められてきた。
開校当初、佐藤進学塾では情報リテラシー教育としてパソコンを活用して学習する時間を設けていた。しかし、生徒の集中力は続かず直ぐ飽きることから、この授業は取りやめた。
少し、話は変わる。
「あれ、この子、おかしいな」
スマホに振り回されている。
「あれ、この子、出来たのに」
スマホ中心の生活になっている。
「スマホを持つな」とは言えない時代である。
しかし、スマホに支配されると成績は下がる。
且つて、紹介した書籍である。
『オンライン脳』川島隆太著
「東北大学の緊急実験からわかった大問題」
オンライン脳とは、スマホなどのデジタル機器をオンラインで長時間使う事に拠り、脳にダメージが蓄積され、脳本来のパフォーマンスを発揮出来なくなる状態の事を指す。
便利になったことと、脳が感じている事は全く関連性がない。オンラインでは楽な分、脳の一部しかはたらかない。情報伝達は可能だが、感情は共感していない。
更に心配なのは『子どもたち』への影響である。
オンライン教育が子供たちに良い影響を与えたことを示すデータは全くない。寧ろその逆でOECDの学習到達度調査調査によると、学校にコンピュータが配置される程、数学の成績は下がるデータがある。国語の読解力でもオンライン使用が多いほど成績が下がっている。
ほんの一部の引用でも、これだけのことが書かれている。じっくり読んで頂けると、実験実証に基づいた事実である事が分かる。最近では小児科医、精神科医が同様の事を書籍に具体的且つ詳細に書いている。
聡明な保護者様は既にお気づきのことだと思う。
2025/8/27

『美しい姿勢』
正しい姿勢で学習すると胸が開き、空気を取りこみやすくなり呼吸が深くなる。深い呼吸は脳に酸素を十分に送り込んで、脳の働きを活性化する効果がある。
長時間勉強を続けていても疲れを感じにくく、集中力がアップするというメリットがある。テキストの字と目の距離が適度に保たれ目の負担が減り、目も疲れにくい。
医学的に証明されている。
拠って、生徒たちに言う。
「姿勢を正して勉強しよう」
「テキストを真っすぐ置こう」
繰り返し、何回も伝える。
聡明な子は姿勢が良い。
成績上位の子は姿勢が美しい。
最初から美しい子もいる。
美しい形に直した子もいる。
後者が殆どであると言える。
1.テキストを真っすぐ置く。
2.背筋をまっすぐに伸ばす。
3.お腹と背中にこぶし一つ分をあける。
1.2.3.(いち、に、さん)
たった、これだけのことである。
しかし、出来る子と出来ない子がいる。正確に言うと、直そうとする子と直そうとしない子である。要は、気持ちの違いである。だから、姿勢が良い子は出来る。姿勢の美しさは心の美しさに比例している。
抜群に出来る子は姿勢が美しい。
2025/8/26

『ものさし』
佐藤進学塾では学習する時に必ずものさしを使って計算する。分数計算はものさしを使うだけで、正答率は格段に上がる。
小四、正答率70%とする。
小六、90%位まで上がる。
中二、ほぼ100%に近付く。
ものさしを使うと計算がとても丁寧になる。数字がとても見やすくなる。何より、計算のリズムが良くなる。
右手に鉛筆、左手にものさしを持ち計算することにより、計算自体の美しいリズムが生まれるのだ。両手が大脳、脊髄、即ち中枢神経と連動して計算していく。
自然と姿勢も良くなる。
2025/8/25

『中一「数学」』
この夏、徹底的に一次方程式の利用へ取り組んだ。平常授業では、基本概念の習得と応用問題演習に取り組んだ。
夏期講習では、難易度の高い発展問題に挑戦した。かなりの数の問題を演習した。そして、全問題について丁寧に解説した。
生徒に感想を訊いてみた。
「発展問題は問題文が長く何度読んでも意味が分からなかったけど、先生がホワイトボードに書く線分図や関係図を書き写して考えて、家でもう一度解き直すと解くことが出来るようになりうれしいです。
正負の数の計算が出来るようになり、文字式の利用が理解できて、それらが積み重なって方程式の利用となっていることがわかりました。これからも、数学を一生懸命頑張って得意教科にしたいと思います」
2025/8/24

『マスクの着用』
佐藤進学塾では今も、マスク着用をお願いしている。手指消毒も行っている。机、椅子等備品の消毒も授業間に行っている。トイレの掃除、換気も一日三回実施している。
「それはなぜか」
この夏も、コロナ、百日咳が流行っていたからだ。更に学校の新学期が始まる。再流行することも考えられる。
佐藤進学塾では、あらゆるリスクを限りなくゼロに近付ける。皆の協力のお陰で、塾でクラスターは発生していない。過去の中三生は全員、健康な状態で受験を終えた。
すべて、私たちの方針をご理解、ご協力して頂ける保護者様の気持ちとご尽力に拠るものだ。ありがたいかぎりである。しばらく、まだ、この体制を続ける。
お子様の安全、安心を第一に考えて進学塾の運営を行う。
2025/8/23

『自分の壁を超える』
2026年、夏期講習会が終わった。どの学年も『発展テキスト』を活用した。かなり、難しい問題に多く挑戦した。
みんな、脳から汗が出る位、一生懸命に考えていた。正しい答にたどりついて、嬉しそうにしている子がいる一方、なかなか答が出ず、とても悔しそうにしている子もいた。
答えが出なくても、復習して出来るようにして来る子がいる。塾へ来ると、すぐにテキストを開いている。そして、ひたすら手を動かして勉強している。
兎に角、手を動かしている。
字を書く量と成績の相関関係は高い。字を書いた分だけ、成績が比例して上がるのではない。莫大な量の字を書いて、理解がピークに達した瞬間、成績は飛躍的に上がる。
学力には、個人差がある。規定の時間内に答えが出る子も出ない子もいる。しかし、復習すれば時間内に出来るようになる。理解後、三、四回の反復練習で正答率も劇的に上がる。
さて、今週より、平常授業に戻り、二学期予習事項を指導している。すぐに、答えが見つかる様に成った子がいる。難しい問題を諦める事無く考え抜く子がいる。時間内に全ての学習事項を習得する子がいる。六人の小学生が毎回復習ノートを提出した。宿題を完璧に仕上げた上、復習まで完璧に仕上げた。
素晴らしいかぎりである。
夏期講習会において全力で取り組んで、一生懸命に復習して出来るようになった子である。やるべきことを集中してやった子である。この夏、大きく成長した子がたくさんいる。指導者である私達には、すぐにわかる。本人も、間違いなく気付いていることだろう。
2025/8/22

『小6理科「てこの原理」』
アルキメデスの名言
「我に支点を与えよ。さらば地球も動かさん」
てこの原理に関する言葉だ。
丈夫で長い棒と支点があれば、地球でも動かすことができる。
「せんぬき、知ってる」
「…」
「空き缶つぶし機は知ってる」
「知ってます」
「ハサミは分かるね」
「はい、分かります」
ハサミの支点、作用点、力点についてていねいに詳しく教える。せんぬき、空き缶つぶし機についても、説明した。生徒たちは一生懸命に聞いている。
私の子供時代、ファンタオレンジを飲む時は栓抜きを使い、栓を抜いていた。昔、ファンタの自販機には栓抜きがついていた。お金を入れる。ゴールデンアップルの釦を押す。勢いよく、瓶が出てくる。
「ガシャン」
瓶は分厚いので割れる事はない。
それを一旦、外へ取り出す。
そして、栓抜きにかけてあける。
『アナログ』の時代だ。
先日、最新の自販機を使った。お金を入れると、静かにスタバの様な容器が出てくる。自動で扉が開き、容器を取り出すと自動で扉が閉まる。みんな、スマホで決済していた。
『デジタル』の時代である。
デジタルは連続する量を記号によって非連続に表現する。記号には生命が宿っていないので、デジタルは機械的で無機的と言える。一方、アナログは連続する量を物理的に連続して表現する。連続、即ち切れ目がないことは、そこに生命が宿ることを表すので、アナログは生命を持つ有機的なものと言える。
子供たちが最初にしっかりと学ぶべきことはアナログであると言える。
2025/8/21

『言葉掛け』
夏は生徒に発破を掛ける。
「隅々まで完璧に復習せよ」
「参考書を徹底的に調べよ」
「即答出来る様に仕上げよ」
「一日、最低十時間は勉強せよ」
以前は厳しい事を言っていた。夏休みの過ごし方次第で学力が飛躍的に伸びるからだ。しかし、最近は少し違う。
「睡眠時間を確保すること」
「学習中に休憩を挟むこと」
「決して無理はしないこと」
「午前、午後と三時間ずつ勉強しよう」
言葉掛けの内容が変わった。
コロナは一段落したが、体調を崩す子が増えた。免疫力が落ちているようだ。夏の暑さも関係している。猛暑日が何日も続いて、気温が40℃近い日がある。この情勢を鑑みて、出来る事を言葉掛けする。
ただ、これだけは言っておく。
「スマホに時間を取られると成績は落ちる。スマホの扱いには十分過ぎるほど気をつけること」
「私たちが伝えた復習は必ず行う様にして、塾テキストはスラスラ解けるようにしておくこと」
2025/8/20

『夏期講習「受験生」』
中三生の夏期講習が完成した。前半は第二回診断テスト対策、後半は第三回診断テスト対策を行った。九月に実施される第二回診断テストの試験範囲だけを想定してはいけない。
第二回は中二までの学習範囲が大半だからである。入試は中三の学習範囲が中心を占める。拠って、第三回以降の試験範囲を想定して丁寧に勉強する必要がある。
小さな子が自転車に初めて乗る時、目の前ばかり見ている。「うまく乗れた」と思っても、そのあと直ぐにひっくり返る。
勉強も、目の前だけ見ていると同じことが起きる。少し、先を見ると良い。少し先をイメージして勉強すると上手くいく。
さて、目指すは五教科238点である。ここまでいけば、実力は十分であるといえる。卒塾生も、毎年、二、三人が取得した。多い年では、五、六人が取得した。塾生のおよそ半数である。
その子たちの表情は明るかった。
高校入試では、中三、二学期の内容が大半を占める。これから半年間は本当の勝負であると言える。佐藤進学塾の数学は二次関数の利用、二次関数まとめBを終えて、相似な図形の単元の三回目に入っている。他の教科も、学校の二学期後半の学習内容に取り組んでいる。
先日、数学が得意で一番良く出来る子が言った。
「今までは塾で習った後に家で実練を解くと直ぐに解くことが出来ました。ところが、相似な図形の分野は今までの様にすいすいと解くことが出来ません。佐藤先生が仰る通りこれから習う内容が本当に大切であり高校数学へと繋がることを感じました。今まで以上に真剣に授業へ取り組みたいと思います」
22025/8/19

『暑中見舞い』
暑中見舞いの葉書が届く。
最近はめっきり数が減った。
葉書の抽選もなくなったようだ。
「夏期講習の内容を理解出来るまでしっかり復習します」
「発展問題は本当に難しかったけど、楽しかったです」
「家で解き直すと解くことが出来て、うれしかったです」
直筆の手紙には、その子の心がこもっている。心意気が犇々と伝わって来る。一人ひとりの気持ちを考えて、心をこめて返事を書く。切手を貼り、郵便局のポストへ投函する。
こちらの気持ちも必ず、伝わることだろうと思う。
2025/8/18

『書類「九月号」』
九月号の書類を一人ひとりに手渡していく。
1.夢つうしん
2.夏期講習会を終えて(塾長の独り言)
3.祭日授業実施のお知らせ
※中学生「二学期中間テスト対策」のお知らせ
内容をしっかり確認頂きたい。
気候が急変する事が最近多い。
「『気象警報発令時』、佐藤進学塾は休校とする」。
天候急変時等、危険が感じられる時は無理せず、自宅待機すること。一人ひとりが身を守る行動を取ってほしい。
2025/8/17

『小六「算数」』
『円の面積』を指導した。
円周…直径×3.14
面積…半径×半径×3.14
問題解法の一例である。
①直径10㎝の円
②直径6㎝の円
③直径4㎝の円
①+②-③にて解く。
式…5×5×3.14+3×3×3.14-2×2×3.14
=25×3.14+9×3.14+4×3.14
=(25+9-4)×3.14
=30×3.14
=94.2
計算を工夫して、暗算で計算すること。まともに計算すると、筆算を五回することになる。これは、正直めんどくさい。計算が速い子は、工夫して計算している。単に、暗算を無理して行っているのではない。
拠って、正答率も高い。
2025/8/16

『五山の送り火』
京都市内を囲む山の中腹に大文字「大」、左大文字「大」、「妙・法」、船形、鳥居形が午後八時から順番に点火される。総称して、五山の送り火と呼ぶ。
八月、京都では各家庭で精霊迎えの行事が行われる。十六日、五山の送り火は、精霊を冥土に帰す意味をもつ。
さて、今年も無事に夏期講習会を終える事が出来た。塾生皆、集中して学習していた。ご理解、ご協力頂いた保護者様には、心よりお礼申し上げる。
振り返って、今年の夏は暑過ぎた。年々、暑くなっているが、今年は六月あたりから35℃を超える猛暑日が続いた。
生徒たちの健康面と保護者様の送迎の大変さを考慮して、来年度からは更により良い形へ夏期講習会の日程を大きく変える。学習生産性をさらに上げるべく考え抜いたシンプルなカリキュラムとする。
2025/8/15

『信頼関係』
佐藤進学塾では生徒さん、保護者様との信頼関係を最も大切にしている。その為に以下のことを考えている。
まず、「約束を守る誠実さ」である。
誠実な人は必ず約束を守るので、信頼関係を築く事が出来る。何か失敗をした時にも、約束に基づいて誠実に対応を行うので信頼関係はさらに深まっていくと考えている。
次に、「言動と行動の一致」である。
言動ばかりが先行して行動が一致しない人は信用出来ないので信頼を得られない。逆に、言動と行動が常に一致している人は信頼されて、良好な関係性を築く事が出来る。
そして、「人と共感する心」である。
相手の立場や気持ちを考えてサポートすると、相手に心底安心してもらうことができる。そうすることで、相手の側もその気持ちに応えようと懸命に頑張るので、信頼関係がさらに深まっていく。
信頼関係は、教える側と教わる側における学習の質に大きく影響する。双方が信頼関係を大切にしていると、学習の質が高く安定してくることは間違いない。社会に出てからもそれは同じであると考えている。
2025/8/14

『中学生の理科』
中学生、二学期、理科の学習内容は難しい。
特に中一は難しくなる。難しい単元は『光、レンズ、音、力』である。理屈を考えてから覚える必要がある。物理分野ゆえ、単に暗記とはいかない。深く考えてから理解する必要がある。
中二は『電流』だ。次々と新しい公式が出て来る。直列回路、並列回路について、それぞれ考える。電流、電圧、電力、磁界について、各々理解したあと、それらを組み合わせて考える。
中三は『仕事、エネルギー、天体』である。仕事は、様々な計算が出来るようにする。エネルギーは位置エネルギーが運動エネルギーに移り変わる。力学的エネルギーの保存が成り立つ。
天体では、空間で起こる現象を紙面という平面で考える必要がある。これが、なかなか時間が掛かり大変だ。
「ユーチューブはすごい。すぐ、分かった」
と言った子が以前いた。
その子のテストは悲惨だった。
生徒「先生、分かっていたのに全然出来ませんでした」
塾長「本質的なことが理解出来ていなかったからだよ」
生徒「やっぱりそうですか」
塾長「理解するには手間暇が掛かるんだよ」
最近の教育に関する動画は良く出来ている。「『なるほど』と思い、分かったつもりになる」。ところが、本質や理論、概念は分かっていない。拠って、テストで良い結果が出ることはない。塾や学校で習ったことは毎日三十分でもいいから復習しよう。塾、学校、家庭と復習を繰り返す事で本質の理解は深まる。
結果を出す子は、それを当たり前にやっている。長時間、やっているのではない。時間を決めて、必ず、やっている。従って、テスト前に効率良く仕上げる事が出来る。テスト前にむやみやたら、長時間の勉強をして睡眠不足になるようなこともない。
2025/8/13

『御盆』
先祖の御霊を偲び、
供養をする日として、
御盆は大切な行事である。
先祖の精霊を迎え、
供養する期間をお盆と呼ぶ。
お盆の期間は、一般的に
八月十三日から十六日迄を指す。
お盆は、
先祖や亡くなった人たちが
苦しむ事無く成仏する様に、
子孫が報恩の供養をする時だ。
2025/8/12

『感謝の言葉』
「こんにちは、がんばってね」
私が生徒へ声を掛ける。
「こんにちは、お願いします」
生徒が私に声を返す。
「ありがとうございました」
授業が終わると、私が生徒に声を掛ける。
「ありがとうございました」
同時に生徒たちも、私へ一斉に声を掛ける。
大きな声で言うと、とても気持ちが良い。今日も、元気に塾へ来てくれてありがとう。今日も、一生懸命に授業を聞いてくれてありがとう。今日も、最後まで集中してくれてありがとう。
私の気持ちを正直に伝える。
「お子様と私達を信頼してくださってありがとう」
保護者様への感謝の想いも含んでいる。
「ありがとうございました」
笑顔で生徒たちが言う。
心の底からうれしく感じる。
2025/8/11

『成功者』
京セラの創業者稲盛和夫氏、私が尊敬する人物の一人である。稲盛氏の本は殆ど読んでいる。繰り返し何十回も読んでいる。更に読み込み、大切な事を、頭と心の両面から再確認する。
「勉強でも仕事でも、少し努力をして上手くいかないと、そこで諦める人がいます。それでは、何も得られません。粘って、粘ってもうこれ以上は頑張れないというところまでやってみるのです。上手くいかない人ほどいい加減なところで妥協して、『もう少し頑張っていればよかったな』と、くよくよします。成功する人と成功しない人の差は、実はここにあるのです」
矢張り、
本質的なことが書かれている。
2025/8/10

『早明浦ダム』
早明浦ダムの貯水率は、
本日、「79.4%」である。
今年も猛暑日が続くが、水不足の心配はない様子だ。
早明浦ダムは吉野川上流に位置する。吉野川は徳島県に、早明浦ダムは高知県に所在する。吉野川中流の徳島県池田から香川県へ分水される2億5千万㎥/年の水の事を香川用水と呼ぶ。
『農業用水、工業用水、生活用水』として、香川県に導水されている。
香川県は干害に悩まされてきた。香川用水のおかげで、今は、ほぼ解消することが出来ている。
2025/8/9

『マイボトル』
皆、水筒を持って来て、適宜、水分補給を行っている。熱中症予防の為にもいいことである。
最近、ペットボトルを持ってくる子がいる。それを飲む姿は、予備校生を連想させる。すこし、だらしない感じがする。
良く出来る子、心が安定している子は、間違いなくマイボトルを持参している。今どきのマイボトルはおしゃれだ。
最近、驚いたことがある、マイボトルの中に、ペットボトルがすっぽり入っている。保冷力は高いらしい。これは、ありだ。
高校入試の時、お弁当と水筒を持参する。
「各自、水筒を持参してもよい」
と入試の注意事項に記載がある。
ペットボトル可との記載はない。
2025/8/8

『夏休みの塾授業』
夏休みの期間、七月下旬より、小五~中三は夏期講習会を実施している。
小5・6「60分・2レッスン」
中1・2「70分・2レッスン」
中3受験「80分・3レッスン」
各学年、二週間実施する。
中三受験生は三週間実施する。
時間も期間も、短期集中で行う。
密度の高い学習で効果を上げる。
どんなに賢い子であっても、集中出来る時間は、二、三時間に限られる。学年に応じて、生徒さんが最大限に力を発揮出来る様指導した。ご理解、ご協力頂いた保護者様には心より感謝したい。
2025/8/7

『小六「算数」』
『辺の比と面積の比』について
図形と関数は時間を掛けて丁寧に指導している。算数、数学で最重要単元であるからだ。図形と関数ほど面白い単元はないからだ。論理的思考能力を磨き上げるには最高だ。
「高さの等しい三角形は、底辺の比と面積の比が等しい」
この感覚を問題演習中に身に付ける。底辺が9cm、15cmであれば、高さの等しい三角形の面積比は3:5である。比例式を使えば、面積をすぐに求められる。
次の条件が分かったとする。
△OAB:△OBC=3:1
△OBC:△OCA=2:3
連比の考え方を使うと、
△OAB:△OBC:△OCA
=6:2:3とすぐわかる。
図形の問題は、小学生の頭が柔らかい間にやると良い。直感的に解くことが出来る様になる。中学生は、理屈で考える様になる。筋道立てて論理的に解く様に変わる。直感と理屈の両方を合わせると、あらゆる問題が瞬時に解ける様になる。一度解けた知恵の輪が瞬時に解ける感覚と似ている。
図形はおもしろい。
2025/8/6

『敬語』
敬語とは、相手に敬意を表す言葉である。目上の人と話している時、相手を敬い、大切に考えていることを伝える為に使う。尊敬語、謙譲語、丁寧語に分けられ、詳しくは授業で伝える。
「丁寧な言葉を使おうね」
と言う機会が増えている。
入塾直後の子は敬語を使わない。知らない場合は、仕方のないことだ。こちらが、一つひとつ教えていく。
賢い子は丁寧な言葉で話す様に変わる。目上の人に対しては、友達に話すような軽々しい言い方はしないようになる。
「よろしくお願いします」
「もう一度、教えて下さい」
「ありがとうございました」
入塾当初から丁寧な言葉遣いの子もいる。勉強は飛躍的に出来る様に成る。私たちに指導されて、意識して直していく子もいる。勉強は徐々に出来る様に成る。
最近、高松の子が讃岐弁を話さなくなった。「食べまい、こっち来まい、やめまい、…」。かつては小さな子も讃岐の言葉で丁寧な言葉を使っていた。小学校高学年以降は尊敬語、謙譲語、丁寧語を使いわける事は当たり前だ。身近な友人であっても丁寧に話すことは大切だ。人として大切な事のうちの一つである。
2025/8/5

『色彩と心理について』
「赤」注意力を喚起、人の感情的興奮をもたらす。
「橙」楽天的な印象を与え、陽気に見える。
「黄」明るさや希望を与え、集中力がアップする。
「緑」情緒を安定させて、安心感の増加をもたらす。
「青」爽快感を与え、精神的に落ち着かせる。
「紫」高貴さ優雅さを表す。
「黒」力の象徴、相手を威圧する。
「白」純潔さや純真さを表す。
佐藤進学塾の壁は真っ白である。机の天板もすべて、真っ白である。椅子はブルーとグリーンのファブリックである。ロールスクリーンも合わせて統一している。
美しい絵を八点飾っている。目から入って来る色彩と言うのは大切である。三点は、フランスで活躍する絵本作家、谷口智則さんの作品だ。三輪晁勢さん、金丸悠児さん、キロメロさんなどを展示している。
「先生、成績が上がりません」
以前、中三の生徒が相談にやって来た。勉強方法と心の在り方について話をした。その子は、それを素直に聞いて実行した。しかし、成績はなかなか上がらなかった。その子は、再び相談に来た。真っ黒の服を着ていた。その頃、その子は黒い服ばかり着ていた。
その事には触れず、心理面について様々な話をした。その子は、素直にその話を聞いた。その後、成績が上がる兆しが見られた。
生徒「先生、成績が上がり始めました」
塾長「とても、服装が明るくなったね」
その時、真っ白いシャツを着ていた。この時、はじめてその子へ服装について伝えた。本人はハッとした表情に変わった。心が明るいから、明るい服を着るのではない。明るい服を着るから、心が明るくなるのである。心が明るくなると、同時に成績は上がり始める。半年後、その子は見事に高松高校へ合格した。
2025/8/4

『文房具』
最近、様々な文房具が売られている。昔は良質なモノしか売られていなかった。選択肢も限られ、選ぶ余地はほぼなかった。
幼少の頃、小学校の前に小さな文房具屋さんがあった。みんなそこで、必要な文房具を買っていた。
「消しゴム、ください」
「どっちにする」
「こっちにします」
「はい、50円ね」
学校へ行くと、皆、同じ様な文具を使っていた。今は消しゴム一つでも多くの選択肢がある。以前、巨大な消しゴムを持ってきた子がいた。両手でごしごし消していた。
「もう少し、小さい消しゴムにしてね」
「塾の規則に大きい消しゴムと書いていました」
唖然としたことを思い出す。
佐藤進学塾では、マスノートを推奨している。このノートも、各社様々なものがある。表紙がブルーのものが主流だ。可愛い動物などがプリントされたものもある。
たまに、黒い表紙のノートを使う子がいる。「なぜ、黒を選ぶのだろう」。最初に見た時は、ぞっとした。小さな子が黒を選ぶのはあり得ない。以前、小学生が黒のノートを提出した。こちらの考えを伝えた。
塾長「黒い表紙のノートは心理的に良くないよ。次から明るい色のノートを買ってね」
生徒「マスは同じだし、別にいいじゃないですか」
このようなことを言う子で勉強が出来る様に成る子はいない。進学塾での勉強も長続きすることはない。先生が言うことは聞いた方がいい。勉強が出来るようになる為に小さなことでも伝えているのである。
人の言うことを素直に聞く子が出来るようになる。実行して納得いかないものは別に行わなくてもいい。色彩一つとっても、「重要なことがある」という事実を感じることが大切だ。服装も文房具も、すべて、明るい子は勉強が良く出来る。これは間違いのない事実である。
「先生、お願いします」
「はい、見ておくね」
二人の小学生が復習ノートを提出した。夏休みの間、毎日ノート一冊ずつ、一生懸命に復習をして出している。二人とも明るい色調のノートで、一人は表紙にかわいい動物の絵が描かれている。心底、ホッとする。矢張り、この子たちも日々良く出来るようになっている。これからが楽しみである。
2025/8/3

『受験生』
中三は午後一時から夏期講習を行っている。一人ひとり、挨拶して教室へ迎え入れる。
「こんにちは」
「今日も、頑張ってね」
教室内は涼しい。
友人と言葉を交わす。
ウォームアップに入る。
診断テスト第二回、「230点」突破を塾目標として、夏期講習で既習事項の総復習を行っている。
210点が目標の子もいる。
220点が目標の子もいる。
一人一人に合わせて声を掛ける。
全員、やるべきことがある。
1.教科書を理解後、暗記する。
2.学校ワークを完璧に覚える。
3.塾テキストで応用力を伸ばす。
受験生ゆえ、本気である。
極めて、正答率の高い子がいる。
その子達に共通することがある。
解法の過程を丁寧に書いている。
私の目を見て説明を聞いている。
復習を行い、理解を深めている。
もう一つ、気が付いた。
中二の夏期講習も全力で取り組んでいた。更に遡って考えてみる。入塾した日から、集中して取り組み、復習を一生懸命に行っていた。その地道な積み重ねが、高い正答率の礎と成っている。
小三から中二も頑張っている。
『「今現在」の頑張り』が大切で、後々、生きて来る。今現在、全力で取り組む子が、中三に成り安定した結果を出す。将来、中三で結果を出す子が今の時点で、既に、私の目の中で光り輝いて見える。
2025/8/2

『小五「算数」』
『平均』を指導した。
平均の概念について教える。
その後、問題演習を行う。
「五回のテストの平均点が62点である。次のテストで、何点を取れば、平均点が65点になるか」
五回のテストの合計点
「62×5=310点」
六回のテストの合計点
「65×6=390点」
よって、
次のテストで80点取ればよい。
こういう問題が瞬時に解けるようにしよう。平均は割り算をよく使う。わり算の筆算は時間が掛かる。
「むずかしい」
小学生の生徒はよく言う。
難しいのではない。
少し、面倒なのである。
子の言葉を鵜吞みにしてはいけない。ノートへ丁寧に筆算する。繰り返し練習した分、正答率は上がっていく。そして、中学校の方程式に繋がる。一次、二次、連立、…、すべての方程式に!
中学生の夏期講習は発展テキストにて取り組んでいる。
『方程式の利用』
この単元に入ると差が出る。
素早く答を出した子に訊く。
「もう、解けたの」
「はい、解けました」
「それにしても、速いね」
「小学校の時に、よく似た問題を何度も復習したので覚えてます」
「すごいね」
「方程式の公式にあてはめると、それを簡単に解くことができます」
出来る子と言うのは、小学生の時にやるべきことをやっている。
算数、数学は積み重ねである。
2025/8/1

『運動の効果』
中三の生徒が部活を引退した。今年も暑い中、良く頑張った。総体直前は三時間以上練習する日もあったという。中一、中二も真っ黒の子がいる。暑いのに、本当に良く頑張っている。
熱中症には気を付けてほしい。「体調がおかしいな」と感じた時は無理をせずに休む様にしよう。体の動きが自分の意に反して「スローだな」と感じたら直ぐ休むべきである。
私が中学生の時も部活はハードだった。
夏休みは、昼食を挟んで六時間の練習だった。特に、中一の時はきつかった。一日中、球拾いしかさせてもらえなかった。
「座るな、喋るな、水飲むな」
当たり前の決まりであった。中二の怖い先輩が見張っていた。規則を破ると鉄拳が飛んできた。罰として、何十週も走らされた。兎跳びもやらされた。
今は昔、
昭和の時代の話だ。
今ほど暑くはなかった。
最後の15分だけ、中一の部員同士で練習することが許された。それが、唯一の楽しみであった。あとの、5時間45分は只管球拾いだった。夏休みが終わると、30人以上在籍した部員がたった10人に減っていた。
さて、
体を動かすとやる気が出る。
体を動かしている人の方が仕事のパフォーマンスが高いそうだ。子どもにおいても、運動で体を動かしている子は勉強が良く出来る。芸術的な活動をして体を動かしている子も良く出来る。カロリンスカ大学の実験で証明されている。勉強前にたった五分間だけでも体を動かすと、勉強の効率は上がるそうだ。
ウォーキングやストレッチを少し行うだけでもいい。体をほんの少し動かすだけでいいそうだ。塾へ自転車、徒歩で来る子はそれ自体が運動になっている。車で送迎の子も、明るい時は少し離れた所で降りてからしっかり歩いてくるといい。
しかし、あまりにも激しい運動や練習時間が長時間に及ぶ場合は、逆に学習効率が大幅に下がるという。その辺りについては十分に気をつけてほしい。コロナが落ち着いて、再び、昭和の根性論を良しとする脳まで筋肉になってしまった指導者が増えてきているような気がする。
2025/7/31
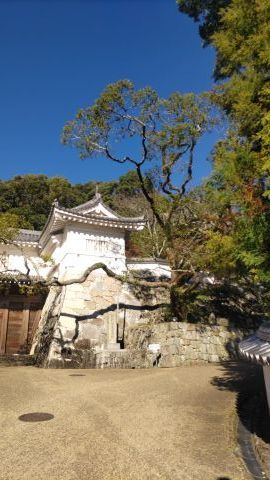
『小6算数「比の利用」』
「比の利用」について
1.比例式を立てる
2.線分図を書いて、式を立てる
いずれかで解くことが出来る。
比例式は、
外項の積=内項の積も使う。
中学生で習う公式である。
難しいのは連比である。
共通部分の最小公倍数を考える。
A:B=2:3、
B:C=5:6ならば、
3と5の最小公倍数15を考える。
A:B=10:15、
B:C=15:18となる。
答えは、
A:B:C=10:15:18である。
コツを掴めばすぐに出来る。
A:C=10:18=5:9である。
B:C=15:18=5:6である。
まずはしっかり復習しよう。
応用問題の指導は、楽しい。
それを楽しむ子を
育てることが、私は楽しい。
一つお詫びがある。
現在、小六は多くの子が予約待ちに登録している。入塾をご希望されても、なかなか入塾出来ないこと、入塾の時期がいつになるか分からないこと、心よりお詫び申し上げる。
2025/7/30

『夏期講習会』
夏期講習を無事に進めることが出来ている。暑さの為に体調をくずしている子もいるが、皆、全力で取り組んでいる。
みんな、楽しそうに授業を受けている。問題を解く時は、真剣な表情に変わる。解けたときは笑顔になる。
小三、小四の子は平常授業を実施している。二学期予習を引き続き、通年テキストを使い行っている。
算数は良質な問題に数多く当たり、瞬時に答えられる様にしていく。問題を読んで、「パッ」と答えられると気持ちいいい。
国語は記述問題を鍛え上げる。模範解答通りに、正確に記述出来る様に練習していく。正しい記述方法を覚えると楽しい。
テキストの復習方法については詳しく説明している。
家で丁寧に仕上げてから復習してほしい。余裕がある子は参考書を使い、知識の幅を広げていくと良い。受験研究社の問題集へ挑戦するのも良い。時間があるから様々なことが自由に出来る。
2025/7/29

『肯定的な言葉』
佐藤進学塾では否定的な言葉を使わない。二十数年前の設立当初は意識して使わない様にしていた。今現在では潜在意識下に否定的な言葉自体が存在していない。
「出来ない、無理、苦手」
等の言葉を発しない。
口から発する言葉は大切である。その言葉を、自分自身の脳が真実として受け止めるからだ。
入塾直後、
「○○が苦手」と言う子は多い。
やれば出来るのに、勉強との距離を置いている。と言うより、面倒なことを避ける為の言い訳をしている。
私は、常に『肯定的な言葉』を生徒に投げ掛ける。
「出来る、絶対にできるよ」
「ゆっくりで、大丈夫だよ」
「間違っても、直せばいいよ」
小さな進歩が見られた時、すぐに褒める言葉を掛ける。
「良く頑張ったね!」
少し大変そうな時、大丈夫である旨を伝える。
「だいじょうぶだよ!」
生徒も、次第に変わって来る。
少しずつだが、確実に変わる。
「分かるまで考えます」
「出来るまで頑張ります」
「すみずみまで覚えます」
こういう言葉を自然と発する様に変わる。少数だが、否定的な言葉のままの子もいる。いつまで経っても、否定的な言葉を親が掛けているからだ。子も変わることが出来ない。家で過ごす時間は長い。
『子は親の鏡である』
親が肯定的な言葉を使う。
子も肯定的な言葉を発する。
夏期講習の感想を訊いた。
「難しい問題が解けた時「やったー、出来た!」と感動しました」
「見たことのない発展問題に挑戦するのはものすごく楽しいです」
肯定的な言葉が出て来る。
中学生の数学と英語の発展テキストは、最上位レベルの問題集である。果敢に取り組む事に意義がある。「出来たら、すごい」「出来なければ、復習する」。ただ、それだけ、私は出来ていないことを責めない。別に今出来なくてもいい。難しい問題が出来た時は「やったー、出来た!」と、素直に声に出せばいい。
2025/7/28

『御日供』
神棚に榊を供える。
水、米、塩、酒を供える。
それから、蝋燭へ火を灯す。
「二礼、二拍手、一礼」
神様を尊び、感謝の意を伝える。
「生徒皆が、健康で安全に夏期講習を受講できますように」
夏期講習の無事を祈願する。
かつて、いつも一番に夏期講習へやって来る子がいた。そして、神棚に頭を下げていた。小声で何かをぶつぶつと、必死に言っていた。塾を卒業する日まで続けていた。
中一の時、評価36であった。
中二の時、評価37であった。
中三の時、評価45となった。
中一、中二の時は勉強をなめていた。授業中も寝ていて、私の怒りを誘うことが多かった。しかし、中二終盤「気持ちを入れ替えて勉強するので先生お願いします」と言ってきた。無理だろうと思っていたが、本気でやりだした。本が好きで読解力は高かった為、結果は直ぐに出始めた。
神様の御加護もあったのだろう。
今は東京の国立大で小さな頃からの夢であった魚の研究に没頭している。
神棚は三社造りの宮型である。
中央には、
総氏神とされる伊勢神宮
右には、
氏神様の熊野神社、石清尾八幡宮
左には、
崇敬神社の京都紫野今宮神社の御札をお納めしている。
今宮神社さんには御日供をお願いしている。神職さんに朝夕、お参りして戴いている。本殿に入ると、御日供の木札が掲げられている。佐藤進学塾と墨で書かれている。参道にはあぶり餅で有名な『かざりや』『一和』がある。鬼平犯科帳でもよく出て来る老舗の茶店だ。映画『国宝』のシーンにも使われている。
神様に感謝して、
心静かに夏期講習を進めていく。
2025/7/27

『通知表評価』
九教科の評価合計
「42㌽」
高松高校を安心して受験できる。
内申点は、
三年間で「220㌽」となる。
「200㌽で高高受験が可能」
と言っても生徒はピンとこない。
では、どうやって考えるか。
評価合計を「40」とする。
五教科「5,4,4,5,5」
副教科「4,5,4,4」
中一は「40」とする。
中二も「40」とする。
中三は五科二倍、副教科四倍だ。
五教科46、副教科68となる。
合計「114㌽」となる。
三年間の合計
「194㌽」
200㌽に「6㌽」たりない。
では、どうすれば良いか。
五科と副科に「5」を増やす。
五教科「5,4,5,5,5」
副教科「4,5,5,4」にする。
五教科24×2「48」
副教科18×4「72」
合計「200㌽」となる。
具体的に数値を計算する。
やるべきことが見えて来る。
かつて、生徒が言った。
「やるべきことをやったつもりだったが、通知表の評価は自分が考えるものとは大きく違った。自分には甘さがあった。この夏休み、講習会を本気で受講するとともに、佐藤先生から言われたやるべきことについては全力で取り組んでみたいと思う。そして、今の自分を少しでも変えて、二学期には今の状態よりも確実に良い結果を出すことを目指していきたい」
この子は今「44㌽」だ!
佐藤進学塾ではこういう子たちを本気で応援していく。問題の本質が自分にあることに気付くことなく、人のせいにしている子は何も変わらない。問題の本質を自分なりに見極めて、問題点を改善していこうとする子は、必ず、良い方へと変わる。
心が素直な子は変わる!
2025/7/26

『御縁』
「文章中に『チリン、チリン、…』とある時は、お遍路さんの鈴の音、すなわち四国八十八箇所のことですね」
「へー」
「遍路とは、弘法大師が修行した八十八の霊場をたどる巡礼のことです。遍路する人のことをお遍路さんと呼びます。…」
初めて聞く話に、生徒、皆、興味津々である。
「『コンコンチキチンコンチキチン、…』とある時は京都祇園祭の祇園囃子、山鉾巡行を思い浮かべるといいですね。…」
「へー」
「祇園祭は平安時代の疫病退散を祈る祭礼を起源としています。疫病神をおびき寄せるために山鉾巡行でお囃子を奏でて誘い出し、…」
「へー」
「では、中心素材について考えます」
生徒、皆が真剣に聞いている。
皆が目を輝かせて聴いている。
私の小学生時代、広島市の進学塾へ通っていた時の国語の授業の話だ。
1.中心素材を考える
2.起承転結を考える
3.主人公の心情をとらえる。
と言う流れで説明して頂いた。
幼少期、
大阪、福岡、広島に住んでいた。
その時、
四国、京都とは無縁であった。
進学塾の先生から聞く話はとても新鮮で、驚きの連続であった。その後、京都へ長く住むことになった。八坂神社の祭礼、祇園祭のことを詳しく知った。当時の職場が四条烏丸にあり、山鉾巡行も実際にこの目で見た。「コンコンチキチン、コンチキチン」という音も耳に残っている。
そして、今、四国高松に住んでいる。時々、お遍路さんに出会うことがある。「チリン、チリン」と言う優しい鈴の音を耳にする。四国八十八箇所、善通寺はじめ、幾つかのお寺にはお詣りしている。
御縁を感じている。
そして、今、教わる側から教える側になった。しかし、教える側に成っても教わることの方が、まだまだ多い気がする。いくつになっても、学ぶ事はたくさんある。
2025/7/25

『小5算数』
『分数、小数の計算』について
分数の計算は通分、約分を行う。
最後に約分を忘れてはいけない。
さて、小数は分数に直す。
次に、最小公倍数で通分する。
そして、最大公約数で約分する。
小数は出来る限り、
暗算で分数に直す。
「0.6=10分の6=5分の3」
覚えておくといいものがある。
0.5=2分の1
0.25=4分の1
0.125=8分の1
0.375=8分の3
0.625=8分の5
0.875=8分の7
これらを覚えておくと計算が速い。
22025/7/24

『三年前のブログ』
期末テストの復習ノートが提出されている。生徒一人ひとりのノートを丁寧に見て、応援メッセージを書き込んでいく。良い結果を出している子には共通点がある。
「字が濃く、大きく、心を込めて書いている」
一人のノートから悲痛な叫びが聞こえてきた。
「一生懸命やっているんだけど、良い結果が出ない。皆の恩に報いる為にも、高高へ絶対行きたい。先生、ぼくは一体どうしたらいいんですか」。
その子は良く努力している。
中二の時、良い結果が出ていた。
原因について、ノートを見て考えていく。深いところまで、よく勉強出来ている。難しい問題に対しても、深い理解が得られている。問題文を書き写した『モンペ「資」』という語句が引っ掛かった。類推すると、本人は『モンペ「姿」』と書いたつもりだ。この様なミスが目立つ。
一生懸命になりすぎて、空回りしている。結果、多くの勘違いを誘発している。難しい問題は深く考えている。しかし、簡単な所は軽く考えている。簡単な所、即ち、基礎基本は重要だ。此処を、無意識のうちに軽視していたのである。本人には、そんな気持ちは全くないが…。
「では、どうしたらいいか」
「音読しながら勉強すればよい」
学習が作業化する子は「黙読」して勉強している。本質的な学習を行う子は「音読」して勉強している。『音読→思考→書写→理解→反復→定着』これが、正しい学習の流れだ。
結果を出したかったら、
「声を出して勉強せよ」
結果を出したかったら、
「体を動かして勉強せよ」
佐藤進学塾では当初から
『音読』を重視している。
(後半略)悲痛な叫びを発した生徒は無事、高松高校へ合格した。これは、奇跡でも何でもない。中三の一年間も努力を続けたからだ。最後まで諦めることはなかった。私を最後まで信じてくれた。私の言う通り原則的学習を継続した。その努力が結果に結びついた。今も部活と両立して勉強を頑張っている。
2025/7/23

『小4算数』
『わり算と割合』について
二桁でわる時、
仮の商がたてにくい。
親子で一緒にやると良い。
「7かな、8かな」
「8でわってみよう」
「あれっ…」
「7だ」
と言う感じで、時間が掛かる。
しかし、
二回、三回と練習を
繰り返すと即答出来る様になる。
丁寧に復習すれば、
スムーズに計算出来る様になる。
「わる→かける→ひく」
のリズムの繰り返しである。
右手に鉛筆、
左手にものさしを持つ。
数字はマスに合わせて書く。
学年が上がると、
手際良く計算出来る様になる。
割合については、
関係図と線分図の
書き方を丁寧に教えた。
夏休みは、新学期の
学習内容を更に予習していく。
2025/7/22

『小5算数』
『公倍数・公約数の利用』
「縦90m、横162mの長方形の土地がある~(略)。」
(1)くいの間隔 (2)くいの数 を求めよ。
「90と162の最大公約数」を求める。
もちろん、素因数分解を使う。
くいの間隔は18mだ。
(90+162)×2=504m
長方形の周りの長さ=(縦+横)×2
長方形は、間隔とくいの数が同じである。
504÷18=28(間隔の数)
くいの数は28本となる。
一直線ならば、28+1=29本となる。
『間の数』の考え方を使うと分かる。
この程度の問題は、
考える事なく解けるようにしておこう。
2025/7/21

『通知表の評価』
「『オール5』頑張ったね」
「ありがとうございます」
中学生の通知表評価が出始めた。
『オール5』に近い評価を頂いている生徒が大変多い。中間、期末テスト、授業態度、提出物良好である子は「5」である。
「『5』を取る為に何をするか」
まず、授業態度である。先生の話をしっかり聴く事だ。テストを作るのも、評価するのも自分の学校の先生なのだから。
次に、教科書、ワーク、プリント、塾テキストを原則的学習に基づいて学習して理解すること。理解後、完全に暗記すれば、高い得点を必ず取得出来る。
頭で考えなくても、手が、勝手に答えを書く位にしなければならない。提出物は心を込めて丁寧に行う。忙しい先生が見るのは、一人あたり、「ほんの一瞬だ」。その一瞬に全てをかけなければならない。
高評価の子は、私の話を良く聴いている。
私の話を良く聴く子は、学校の先生の話も聴いている。
Aさん「佐藤先生、見たことのないすごく難しい問題が出ました」
Bさん「学校の先生は『その問題を出す』と言ったよ。佐藤先生も『大切だからやってね』と言ったよ」
Aさん「…」
こんな具合である。いつも言うことだが、聡明な子は、耳だけでなく『心』で聴いている。私は生徒たちにいつも言っている。「学校の先生、両親、友人の話はよく聴くように」と。
『聴』には、耳、目、心、十という漢字が含まれる。「相手の『目』を見て、自分の『耳』でもらすことなく聞いて、その内容を『心』の中で『十回』考える事」と私は解釈している。二、三回、考えた位では良い結果は出ない。しかし、十回考えたならば良い結果は必ず出る。
「しまった」
と思った子は夏に頑張ればよい!
2025/7/20

『三年前のブログ』
期末テストの復習ノートが提出されている。生徒一人ひとりのノートを丁寧に見て、応援メッセージを書き込んでいく。良い結果を出している子には共通点がある。
「字が濃く、大きく、心を込めて書いている」
一人のノートから悲痛な叫びが聞こえてきた。
「一生懸命やっているんだけど、良い結果が出ない。皆の恩に報いる為にも、高高へ絶対行きたい。先生、ぼくは一体どうしたらいいんですか」。
確かに、その受験生は良く努力している。中二の頃には最高の結果が出ていた。
原因について、復習ノートを見て考えていく。深いところまで、とてもよく勉強出来ている。難しい問題に対しても、深い理解が得られている。問題文を書写した『モンペ「資」』という語句が引っ掛かった。類推すると、本人は『モンペ「姿」』と書いたつもりだ。この様なミスが、結構目立つ。
一生懸命になりすぎて、空回りしている。結果、多くの勘違いを誘発している。難しい問題は深く考えている。しかし、簡単な所は軽く考えている。簡単な所、即ち、基礎基本は重要だ。此処を、無意識のうちに軽視していたのである。本人には、そんな気持ちは全くないが…。
「では、どうしたらいいか」
「音読しながら勉強すればよい」
学習が作業化する子は「黙読」して勉強している。本質的な学習を行う子は「音読」して勉強している。『音読→思考→書写→理解→反復→定着』これが、正しい学習の流れだ。
結果を出したかったら、
「声を出して勉強せよ」
結果を出したかったら、
「体を動かして勉強せよ」
佐藤進学塾では当初から
『音読』を重要視している。
授業時、生徒全員に音読させる。
全ての授業において、毎回!
音読が下手な子は勉強が出来るようになる事はない。家で学習する時に音読をしていないからだ。音読をすることなく勉強しても作業となるだけである。出来る様に成りたければ、大きい声で音読しながら勉強すればよい。だまされたと思ってやると良い。必ず、結果が出る。
(後半略)悲痛な叫びを発した生徒は無事、高松高校へ合格した。これは、奇跡でも何でもない。中三の一年間も努力を続けたからだ。最後まで諦めることはなかった。私を最後まで信じてくれた。私の言う通り原則的学習を継続した。その努力が結果に結びついた。今も野球部と両立して勉強を頑張っている。
2025/7/19

『終わってからが始まり』
全国模試が全学年終わった。結果は八月下旬に送られてくる。およそ、一か月後である。 模試受験者数が多い為である。
それまでに、やっておくべきことがある。
結果を出す子は、模試に本気で取り組む。そして、間違い直しも本気で取り組む。間違った問題が気になるからだ。わからないことが悔しいからだ。
まずは、間違った問題を解き直す。すぐに解くことが出来たならば問題ない。もし、分からない時は要注意だ。
1.塾テキスト、辞書、参考書を調べて出題元を探し出す。
2.正しい解法・解答を考えて、ていねいに解き直しをする。
3.間違った原因を理解後、二、三回反復練習して定着させる。
結果が返って来た時、もう一度解き直してみる。その時、即答出来たならば、理解、習得出来ているといえる。即答出来ない時はさらに復習を繰り返す。出来る子は、必ずやっている。だから結果が出続ける。
2025/7/18

『高校入試と全国模試』
香川県の公立高校入試は、内申点と五科入試、面接で決まる。内申220㌽、入試250点満点だ。その数値を単に合計するのではない。相関表に記入して合否を決める。
高松高校について、
「合計400点あれば合格する」
と言う人が、且つて多くいた。
今はその様な事は当てにならない。入学定員は280名に減り、時代は大きく変わった。
入試得点は診断テストの推移を見ていくことで、予測できる。模試偏差値との相関関係も高い。偏差値65から70あたりで安定している子は合格点を確実に取る。
さて、全国模試で高い偏差値を取る子には共通点がある。
1.テスト中、鉛筆を置かない。
(問題を解く気持ちが強い)
2.テスト中、時計を見ない。
(完全に集中している)
3.解答用紙に丁寧に字を書く。
(メンタルが安定している)
4.姿勢を正して、問題を解く。
(良い意味リラックスしている)
5.問題用紙に解法の過程を書く。
(答より解法を大切にしている)
これらを実行する子は、間違いなく最高の結果が出る。結果を出す子は私たちの授業を真剣に聞き、宿題や復習を丁寧に納得いくまで行っている。私たちの授業を聞いている子は学校の先生の話も良く聞いているし、学校の宿題や復習も必ず行っている。逆も、また然りである。
時計ばかり見て、雑な字を書き、姿勢がくずれて、答えだけを書いて、サッサと鉛筆を置いている様では良い結果など出るはずはない。とても残念なことだが、こういう子もいる。私がいつも言うことであるが、テストに集中して、ゆっくり、リズム良く、丁寧に解くことが最も大切だ。
2025/7/17

『小4算数「概数」』
概数は慣れることが大切だ。
まず、四捨五入を理解する。
「0,1,2,3,4」
は切り捨て、
「5,6,7,8,9」
は切り上げだ。
「4」以下は切り捨て、
「5」以上は切り上げ、
拠って、四捨五入である。
「『千の位まで』の概数に表す」
12350ならば、
千の位は「2」
百の位の「3」を切り捨て、
約12000となる。
12585ならば、
千の位は「2」
百の位の「5」を切り上げ、
約13000となる。
この感覚がつかめるまで繰り返し練習するとよい。
「『百の位』を四捨五入して、1000となる数は□以上□未満か」
500以上1500未満である。
「『千の位』を四捨五入して、25000となる数は□以上□未満か」
24500以上25500未満である。
感覚的に分かる様になるまで復習しておくこと。
2025/7/16

『小3算数「かけ算」』
『かけ算』について
15×2×5
=15×10
=150
25×7×4
=25×4×7
=100×7
=700
かけ算では計算する順序を変えても答は同じになる。
25×12
=25×4×3
=100×3
=300
「25×4=100」
の形を見つけ出す。
135×6
=600+180+30
=810
①100×6=600
➁ 30×6=180
③ 5×6= 30
暗算の感覚を身に付けよう。
2025/7/15

『ピンチはチャンス』
「ピンチ」とは差し迫った事態、危機的状況など追い詰められた苦しい状態のことをいう。「チャンス」とは物事を行う上で絶好の機会のことをいう。
つまり、「『ピンチはチャンス』とは、危機的状況を絶好の機会と捉え、それを乗り越えることで自分を大きく成長させることが出来る」と言うことができる。
英語で表記するとこうなる。
「tough times bring opportunity」
pinch,chanceの単語がない。
そのため、
意外に思えるかもしれない。
『tough times=厳しい時期』
『opportunity=好機』
と訳す事が出来る。
「ピンチはチャンス」を
理解していればイメージできる。
さて、中学生は期末テストの表彰及び反省会を行った。一人ひとりを褒め称えて、副賞を進呈した。良い結果が出た子は明るい。更に得意科目を伸ばしていけばいい。夏休みはチャンスである。発展テキストに挑戦するのも面白い。
全力で取り組んだのに上手くいかなかった子もいる。私達はその辺りを冷静に見つめている。一人ひとりに合わせて、細やかにサポートしていく。
「勉強時間」の不足。
「集中力」の低さ。
「覚えること」が不十分。
いずれかの理由があてはまる。期末テストはそんなに難しい問題は出ない。出たとしても後で復習すれば良い。9割が教科書、ワーク類から出題される。
「隅々まで理解して覚える」
最後は完全に覚えないと高得点は狙えない。理解を重ねるうちに覚えてしまうことが大切なのである。
「ピンチはチャンス」である。夏休みを大切に過ごすことで、自分を大きく成長させることが出来る。時々、神様がスランプという大きな試練を与える子もいる。受け入れて、素直に努力すればいいだけだ。それを行う子を私達も最大限に応援していく!暑い夏休み、限られた時間の中で集中して学習しよう!
2025/7/14

『小4算数「四角形」』
「垂直・平行と四角形」について
作図は、三角定規、分度器、コンパスを使う。すばやく、作図出来る様、しっかり練習しておこう。
「角」について
1.対頂角
2.同位角
3.錯角
中学生で習う内容だが、習得すると計算が速い。
「四角形」について
①台形
一組の向かい合う辺が平行な四角形
➁平行四辺形
二組の向かい合う辺がそれぞれ平行な四角形
③ひし形
4つの辺の長さがすべて等しい四角形
④長方形
4つの角の大きさがすべて等しい四角形
⑤正方形
4つの辺、4つの角がすべて等しい四角形
「対角線の性質」について
(1)2本の対角線の長さが等しい四角形
長方形、正方形
(2)2本の対角線がそれぞれの真ん中で交わる四角形
平行四辺形、ひし形、長方形、正方形
(3)2本の対角線が垂直に交わる四角形
ひし形、正方形
図形のイメージを頭にうかべて即答できるようにしよう。頭の柔らかい小学生の間に図形のセンスを磨き上げておこう!
2025/7/13

『気温と湿度』
気温が高い。
おまけに湿度も高い。
湿度が高い時、
熱中症になりやすい。
気温32.5℃、湿度41%
「WBGT26.9℃」
暑さ指数ランク「警戒」
気温32.5℃、湿度56%
「WBGT29.9℃」
暑さ指数ランク「厳重警戒」
暑さ指数「WBGT」
Wet Bulb Globe Temperature
熱中症予防を目的として
アメリカで提案された指標だ。
単位は気温と同じ(℃)
で示されるが、
その値は気温とは異なる。
暑さ指数(WBGT)は人体と
外気との熱のやりとりに
着目した指標だ。
①湿度 ②日射・輻射③気温を
取り入れた指標である。
湿度には要注意だ。
「熱中症かな」
と思った時は体を休めてほしい。
2025/7/12

『生徒募集について』
佐藤進学塾では夏期講習の募集は行わない。今現在、通塾している子たちの為に、必要な時間、特別な機会として提供する。普段通り静謐な学習環境の中、講習を受講することが出来る。
少数精鋭指導の為、募集定員には限りがある。高松高校を第一志望校として、本気で一生懸命に頑張りたいお子様に限って、二学期生は受け付ける。
現在、「全学年、全クラス、『予約待ち』」である。九月から、受付可能なクラスより順番に受け付けを開始する予定である。
「学年『総合一位』を取りたい」
「絶対、『高松高校』へ行きたい」
「『数学』を完璧にしたい」
学習意欲の高い子に限り、『問合せフォーム』送信を願う。
小学生は、「二時間」集中して学習出来ること。中学生は、「家庭学習」の習慣があること。何れも、指導者の言う事を素直に聞いて実行に移すこと。この三点は、入塾以前の最低条件である事を伝えておく。
毎週土曜日に入塾面談は実施している。時間は『80分』、納得いくまで話し合って、「佐藤進学塾であれば本当に頑張ることが出来る」と思った時点で入塾を決めてもらう。保護者様、お子様、塾長の三者で詳細について話し、考えて戴く。最低一年は受けないと本質は分からない為、体験学習は実施しない。
「素直で前向きな子を待つ!」
2025/7/11

『テスト間違い直し』
復習ノートが提出されている。結果が良い子はテスト後の復習を重んじる。拠って、更に完成度が高くなる。もちろん、納得がいかない結果が悔しくて、一生懸命復習している子もいる。
「ケアレスミスがあり、敢えて深い所まで復習しました」
「もっと隅々まで勉強すべきだったなと反省しています」
「普段の塾の復習を今まで以上に大切にしていきます」
「頑張ったね」と声を掛ける。すると、この様な言葉が返ってくる。私が言った勉強を素直にすべて行っている。時間も内容も方法もすべて守っている。メンタル面が強く成長している。
1⃣「周りの人に『感謝』すること」
2⃣「『肯定』的な言葉を使うこと」
3⃣「『笑顔』で人と接すること」
4⃣「結果ではなく、『過程』に目を向けること」
5⃣「『ゆっくり』リズム良く、問題を解くこと」
これらを守る子は、メンタルが強い。さて、復習ノートを丁寧に見ていく。字が大きく、心を込めて書いている。生徒の心が伝わって来る。間違った問題を丁寧に直して、出題元を教科書から探し出している。間違った原因を突き止めて、それを詳しくまとめている。
「学習内容を完全に理解する」
「絶対に間違わないようにする」
「自分自身の学力をさらに高める」
という気持ちが伝わってくる。結果を出す子は、数値を冷静に見つめている。諦めずにやり抜けば結果は出る。結果が出ている子は努力を重ねている。ただ、それを大変なものとはあまり思っていない。
2025/7/10

『小3算数「かけ算」』
小三は「かけ算」に入った。
かける数は、1桁である。
繰り上がりに気をつける。
574×7について考える。
1⃣一の位にかける。
7×4=28
一の位は8
「2」繰り上がる。
2⃣十の位にかける
7×7=49
49+2=51
十の位は1
「5」繰り上がる。
3⃣百の位にかける
7×5=35
35+5=40
百の位は0
「4」繰り上がる。
千の位は4となる。
答は「4018」となる。
筆算の方法を詳しく伝えている。
繰り返し練習すれば身に付く。
九九を確実にすること。
繰り上がりを習得すること。
三回以上反復すれば、
正確に暗算出来る様に成る。
2025/7/9

『全国模試「8月テスト」』
来週は全国模試を実施する。
「8月テスト」実施週間である。
1⃣問題が配られたら全体に目を通す。あわててすぐに解き始めてはいけない。テスト全体を確認後、ゆっくり解いていく。
2⃣難しい問題は印をつけて後に回す。時間配分を考えて、リズム良く解いていく。余裕があれば、気になる問題を解き直す。
3⃣最後まで鉛筆を置いてはいけない。最後の最後まで、粘り強く取り組む。ラスト一分で、突然、答えが閃くこともある。
わからない問題があっても気にしなくていい。その問題は、後でゆっくりと復習すれば良い。模試で全科目満点を取ることは不可能なのである。自分の実力を最大限に発揮しよう!
2025/7/8

『小5算数「分数の計算」』
「分数の加法・減法」について
1.まず、通分する
2.次に、分子をたす・ひく
3.最後に、約分する
通分は最小公倍数を使う。
10と15→30
12と18→36
約分は最大公約数を使う。
12と15→3
15と25→5
21と36→「?」
素因数分解を利用する。
3×7×12×=252
最大公約数は3
最小公倍数は252
絶対に約分を忘れないこと。
10分の5=2分の1
15分の12=5分の4
35分の15=7分の3
この程度は覚えておこう
繰り返し練習することで分数の計算は速く正確になる。通分、約分が出来れば、分数の加法・減法はすぐ出来る。帯分数の計算も繰り返し練習しておこう!
2025/7/7

『七夕伝説』
昔あるところに、神様の娘の織姫と、若者の彦星がいました。織姫は機織りの仕事をしていて働き者で彦星は牛の世話をしているしっかり者でした。
やがて、ふたりは結婚しました。すると、今まで働き者だった二人は急に遊び暮らすようになってしまいました。怒った神様は、ふたりの間に天の川をつくって引き離してしまいました。
二人は泣き続け、それを見た神様はまじめに働いたら、一年に一度だけ、ふたりを会わせると約束しました。それからは心を入れ替えて一生懸命働くようになったそうです。
それから、年に一度だけ天の川を渡って会うことが許されるようになり、その日が七夕となりました。
(これは一説で、諸説あります)
2025/7/6

『真夏日』
最高気温が
25℃を超えると夏日、
30℃を超えると真夏日、
35℃を超えると猛暑日という。
40度を超えると酷暑日という。
2022年、日本気象協会発表で新たに『酷暑日』が追加された。
今週は暑かった。
猛暑日もあった。
生徒たちも真っ黒である。
これから総体の季節だ。
気をつけて練習してほしい。
さて、塾はエアコンで快適に過ごすことが出来る。生徒たちがやって来る前に、教室は快適な温度設定にしている。大体、毎日、授業が始まる三時間前にはスイッチを入れている。
熱中症には気をつけてほしい。
「様子がおかしいな」と感じた時は、体を休めるべきだ。無理をせず、直ぐにアイシングをしてほしい。私たちも、塾における生徒さんの様子を細やかに気を付けて見ていく。
2025/7/5

『出席率』
佐藤進学塾は出席率が高い。
今日は大山学習を終えた中学生の子たちが、日焼けして真っ赤な顔をして次々と塾にやってきた。
「四時に帰って、シャワーをして塾に来ました。先生の大切な授業を『ちょっと疲れているから』と言って休むわけにはいきません。いつも通り、がんばります」と一人の子が言った。
もう一人も、笑顔で頷いている。
「大山登山の途中で水筒、ペットボトルの水をすべて飲み干してしまいました。今も、何だかのどがカラカラで、体が干からびているような感じがします。でも、塾の授業は頑張ります」と、さらにもう一人の子が言った。
公立中の子たちも暑い中、部活を終えてフーフー言いながらやってきている。小学校の塾授業が終わる前からやって来て、何やらみんなで楽しそうに話をしている。運動部の子が多いのにとても早く来ている。
「毎日、暑い日が続いているので、みんな熱中症気味で、学校のお友達は休んだり、途中で家へ帰る子がとても増えています。私も、部活を終えて頭が少し痛くなりましたが、今はなおっています。今日も塾の予習を頑張りたいと思います」
他の子たちも頷いている。
授業を終えて、副塾長が言った。
「今日は本当に皆、集中して良く頑張りました。家へ帰ったらすぐに寝て、体をゆっくり休めて下さい」
2025/7/4

『宿題』
小学部は「宿題」がある。
家庭学習習慣をしっかりと付けさせる為である。時間には限りがあるので、適正な量を出す。解答・解説書も渡すので分からない時は活用できる。
佐藤進学塾は宿題をやって終わりではない。
間違った問題は解き直しをする。間違った原因を参考書などで調べる。再び解き直して、完全に習得する。佐藤進学塾はその名の通り進学塾であるから、それをやってあたりまえである。
ここまでやって、完成する。
これが出来ていない子は成績が上がることはないし、安定することもない。結果を出す子は、上記を必ずやっている。宿題が出来ていないなど、言語道断である。厳しい事を言うようだが、これらが出来ない子は佐藤進学塾へ通う資格はない。
やっている子は全国模試で結果が必ず出る。
中学部は「宿題」がない。
そのかわり、塾授業の復習を完璧に行うことを義務付けている。能動的に学習を行うのである。中学では宿題による受動的な学習では、一時的に成績が上がることがあっても上がり続けることはない。
塾授業は復習をしていることを前提に進めていくので、復習をしている子は理解がさらに進んでいくが、復習をしていない子は回を追うごとに理解が出来なくなっていく。復習をしていない子に、手取り足取り教える気はない。一生懸命に復習をしている子に対して、最高の学習指導を行う。
勿論、努力しているにも関わらず、十分に理解出来ない場合は分かるまで、出来るまで徹底的に教える。努力をする子には手厚い指導を行うが、努力を怠る子には手厚い指導は行わない。
これが、本当の平等であると考える。努力しない子に時間を掛けていては、努力をする子にとって迷惑でしかない。努力している子に対して、私の時間、能力を最大限に惜しみなく発揮する。
さて、やるべきことをやった子は、期末テストも最高の結果を出している。来週、実施する全国模試でも間違いなく偏差値65を超えていく。どんな素晴らしい結果が出るか、今から楽しみで仕方がない。
夏休みを控えて、上記の通り、大切なことをはっきり伝えておく。佐藤進学塾は、親にも子にも迎合することなく将来有望な生徒たちの為に本気の指導を行う。心して取り組んでほしい。
2025/7/3

『隣の芝生は青く見える』
自分よりも他人が良く見える心理を指す。他人が、自分よりも良く思えてしまう反面、自分の持つ良さに気が付かず、悪い面ばかりが気になるという心理である。
The grass is always greener on the other side of the fence.
日本語訳:フェンスの向こうの芝生はいつも青々としている。
さて、佐藤進学塾の芝生が青々としてきた。生徒たちも元気で良く頑張る。本当に頑張る子は、入塾後、三年、五年、七年と頑張り抜く。
一年位では、頑張ったとは言えない。
成功した時、驕ることなく努力を続ける。失敗した時、反省して正しい努力を行う。良い時ばかりが続くわけではない。そのサポートを私たちが行う。
さて、芝生が青々しているのには理由がある。
一つ目は、芝を張る時に床土を施しているからだ。土を取り除いて、排水性の良い土壌に改良している。二つ目は毎日、水をあげているからだ。気温が高いと多くの水が必要になる。三つ目は毎週、芝刈をしているからだ。通気性が良くなり、芝が健康になる。施肥、雑草抜き、目土、穴あけも適宜行う。
これらは、学習にも通じる。
一つ目は、
進学塾での正しい指導である。
二つ目は、
日々の家庭学習の継続である。
三つ目は、
学習内容の日々の改善である。
生徒たちと、テスト結果について一人ひとりと話をした。良い結果と思う子は今の努力を続けると良い。納得いかない結果と思う子は問題点を見つけて改善していく必要がある。
結果を人と比べて考えるのは良くない。良い成績を維持するには相応の努力がいる。芝生の成長、美しさに限らず、何事においても大切なことは共通している。それを理解して行動する子が成功する。
2025/7/2

『全国模試』
七月中旬に全国模試を行う。
佐藤進学塾では、偏差値65以上を成績優秀者として表彰する。この全国模試は偏差値65で高松高校合格可能性50%を超える。偏差値68で、高松高校の合格可能性80%を超える。
但し、高校受験は内申点も関係する。診断テストの得点推移も大切だ。
都会では偏差値で受験校を決める。全国模試偏差値の信頼度は高い。ただ、一つのものさしであり絶対ではない。全国模試の種類も数多くある。母体数も受験者の学力も異なる。
さて、全国模試の質問である。
「何を勉強すればいいですか」
「塾のテキストを復習しよう」
「何時間、勉強するべきですか」
「一日三時間、いつも通りだよ」
「どんな問題が出るのですか」
「塾テキストと同じ形式だよ」
一つ、確実に言えることがある。普段、塾の授業を一生懸命聴いて、丁寧に復習していれば、大丈夫だ。全国模試は出題範囲が広い。直前に全て勉強することは不可能だ。
では、どうするか。
間違った問題を解き直す。理解不十分な単元を勉強し直す。解法や重要語句は完璧に覚える。辞書、参考書を活用する。実行している子は結果を出す。
1.平常時、塾授業の取り組み
2.平常時、家庭での丁寧な復習
3.テスト前、塾・家庭での復習
上記、三点がポイント、いずれも当たり前の事である。当たり前の事が習慣化している子は結果が出る。
2025/7/2

『素晴らしい伝統 続々編』
一昨日の話の続きである。
三人は中二から頑張り始めた。
塾長
「受験勉強は中三からでは遅い」
三人
「その理由を教えて下さい」
「賢い子は中三から頑張る」
「それは、そうですね」
「中二からならば差がつく」
「なるほど。そうなのか」
しばらく、話は続いた。
三人は真剣に取り組み始めた。
月日は過ぎ、入試日を迎えた。
「入試、がんばれよ」
「はい、頑張ります」
三人は成長していた。入試当日は、「力を出し切った」と言った。心配をよそに悪ガキ三人組は、三人とも高松高校へ合格した。三人は同じ中学校に通っていた。その中学校の高高受験者の内申点、ワースト3であった。学校の先生からは「三人とも、絶対に無理」と言われていた。
内申点が低かったのに、よくぞ合格したものである。しかし、これは奇跡ではない。三人は診断テスト210点を超えるまで頑張った。また、当時は内申190点位でも逆転が可能であった。
掃除は心を磨き上げる。
2025/7/1

『考える時間』
勉強について、ゆっくり考える時間が必要だ。
毎日の勉強に関する様々なルーティーンは大切である。ところが、なぜかそのリズムが合わなくなることもある。
一生懸命やっていても、勉強は時に作業化してしまう。それを断ち切る時間は大切だ。最高のリズムで出来ている時もある。その時でさえ、少し調整していく必要はある。
今までの自分の勉強について様々な角度から考える。テストが終わった後はテスト結果を基に考える。問題点を見つけ出し、改善する為に考える時間は大切だ。
「結果自体、良いも悪いもない」
『そう思う「心」』があるだけだ。
自分の結果を客観的に見て、冷静に考える時間が大切だ。一生懸命に勉強していても、 スランプに陥ることがある。それを抜け出すには、相当の時間が掛かる。
「神様が与えた試練」
としか考えられない時もある。
スランプを抜け出すべく徹底的に努力した子は後に大きく伸びる。小さく屈むと大きくジャンプできる。生徒も保護者様も、その時間を待つ心の余裕が大切だ。時間が長引くこともある。
どの位、時間が掛かるかは分からない。時間の使い方、時間に対する考え方というのは難しい。しかし、時間を大切に考えて、行動する子の学力は間違いなく高い。
今、この瞬間もテストを振り返り、自分の問題点を改善しようと努力している子が殆どだ。残念ながら、「こんなに頑張ったのに結果が出なかった」と不満を口に時間を無為に過ごす子もいる。佐藤進学塾では客観的に結果を見て、一人ひとりにやるべきことを伝えていく。
2025/6/30

『夏越の祓』
今年も、半年の歳月が過ぎ去った。今日は、夏越の祓である。氏神様の神社にて、茅の輪をくぐった人もいることであろう。
私も京都紫野、今宮神社さんでくぐってきた。左へ一回、右へ一回、左へもう一回まわって通り抜ける。御祈祷も受けた。
「水無月の夏越の祓する人は千歳の命延ぶと言うなり」
と唱えながら茅の輪をくぐる。
六月の晦日は夏越の祓の神事が行われる。罪穢れを祓い清め、無病息災を祈願する。茅の輪をくぐり、人形を水へ流したり火で燃やしたりする。京都の人々は、この日を大切にする。
「先生、車折神社(くるまざき)に茅の輪が出てたよ」
「水無月、家族みんなで食べたよ。おいしかったよ」
「人形(ひとがた)に自分の名前を書いて納めて来たよ」
且つて、京都の子たちは何かあるごとにいろいろと話し掛けて来た。文化の違いを感じさせられることが多かった。夏越の祓は今年一年間前半の罪穢れを祓い、無事に過ごすことが出来たことに感謝する。そして、今年の後半も元気に過ごすことが出来るように祈る大切な神事である。
縁あって、京都紫野の今宮神社さんに日供をお願いしている。御本殿の前に『佐藤進学塾』と墨で書いた木札が参道の『かざりや』、『一和』と共に掲げられている。朝夕に、神職さんよりご祈祷頂いている。
2025/6/29

『素晴らしい伝統 続編』
昨日の話の続きである。
この伝統は十年前より続く。
当時、悪ガキ三人組がいた。最初の頃、塾長である私の言う事を全く聞かなかった。私は、随分と厳しい指導を行った。
平成の時代の話である。
本気で指導をしていると、気持ちが少し伝わり始めた。時間は掛かったが、私の気持ちは生徒に伝わった。大方、三年ほど、掛かった。保護者様も、私を信頼して辛抱して下さった。
ある日、三人が近寄って来た。
そして、こう言った。
「先生、手伝います」
「それは、助かるわ」
その日から、清掃の手伝いは始まった。三人が手分けして清掃する。机の下に潜り込んで、消しかすまで拾っていた。三カ月もするとプロ並みになった。机と椅子はピカピカで真っ直ぐに並べられている。驚くべきは、その時間である。最初は、十分位掛かっていた。その頃、三分位で出来る様に成った。
「新幹線の清掃員レベルやな」
「ありがとうございます」
三人組はニコリと笑って答えた。
当初、笑う事など無かった。
歳月を経て心が穏やかになった。
(明日へ続く)
2025/6/28

『素晴らしい伝統』
「先生、手伝います」
中学生が声を掛けてくれる。
小学部、中学部の
授業の間に清掃を行う。
1.机の天板の美装
2.机のアルコール消毒
3.お手洗い、洗面所の清掃
塾長が室外で自転車整理、
副塾長が室内の清掃を行う。
有志の子たちは、
早く来て手伝ってくれる。
ありがたいかぎりである。
(明日へ続く)
2025/6/27

『全国模試』
「偏差値が『5』上がりました」
「それは良かったね」
「志望校へ合格出来そうです」
「本当にがんばったね」
「油断せずに復習します」
「まだ上がる余地があるよ」
かつて、京都の総合塾にて中学受験をする小学生との会話だ。高松の子は全国模試に興味がない。親もあまり重視しない。
「偏差値が…」言っても、あまり興味を示さない。その子たちも、高松高校へ進むと変わる。「偏差値が『3』上がりました」高高の実テ、様々な全国模試で大学進学を考えるからだ。
さて、佐藤進学塾では七月初旬に全国模試を実施する。模試の勉強は、約一カ月間行う必要がある。範囲が広いからだ。考えることは大切である。興味を持つことも大切である。しかし、それだけでは点を取ることは出来ない。理解後、解法と解答を完全に習得してはじめて得点できる。
復習して、覚え直しをする必要がある。しかし、覚えにくい内容もある。その場合、テキストや教科書に戻る。大切な事を書き写して理解を深める。それから、再び覚える。トレーニングは小学生の間に行うと有効だ。覚えるためのコツとタイミングがあるからだ。それを小学生の時に肌感覚として習得する。
中学生で暗記事項が増えても対応出来る。小学生の間は頭が柔らかい。覚えることも楽しく感じる。小学生時点での正しい学習方法の習得は本当に大事である。もし、失敗しても、修正する時間が十分にある。遅くとも、小六の四月までには入塾してほしい。小五までに入塾すると学習方法を確立する事が出来る。
2025/6/26

『復習の重要性』
「テストは終わってからが始まり」
テストが良かった子は、直ぐに復習へ取り掛かる。一生懸命に頑張った分、間違った問題が気になるからだ。間違った原因を徹底的に調べて、納得いくまで考える。
「ケアレスミスなのか、本質的な理解が出来ていないのか」
教科書、辞書、参考書などを調べる。そして、問題点を見つけ出す。それを詳しくノートに纏める。二度と間違う事の無い様、反復練習する。類似問題を見つけてそれも解き直す。
ケアレスミスであっても、問題の本質を考え抜く。本質的な理解が得られるまで深く考え、参考書を調べ尽くす。一つの問題をあらゆる角度から考えていく。
「勉強方法に問題点はないか」
勉強方法の改善点も見つけ出す。集中して学習できているか。時間を有効活用できているか。問題演習量は十分であるか。声がしっかり出ていたか。常に、手を動かして勉強することができていたか。反復練習は必要な回数できていたか。何より、強い気持ちを持って試験に臨むことが出来たのか。
それらを紙に書き出してから考えて、学習方法をより良い形へ改善していく。その時、私が推奨する原則的学習の型である『音読・書写・反復』を変える事は絶対にない。
2025/6/25

『素直さ』
中二で入塾してきた子の話だ。
「佐藤進学塾の卒業生で、京都大学医学部医学科の○○さん、香川大学医学部医学科の□□さんのように、私も勉強を頑張りたいので入塾をお願いします」
勉強は全力で頑張っていたが、どうしても附属中で一位を取ることが出来ずに悔しい思いをしていたと言う。
「私も、将来は医学部へ進みたいんです。その前にやるべきことをやって、附中で一位を取りたいんです。○○さんも□□さんも佐藤進学塾出身で附中では一位だったと聞いています」
どこから聞きつけたのか、二人のことを驚くくらい良く知っている。その気持ちは本物と受け取った私は言った。
「これから、私の推奨する『原則的学習』を中心に、私の言う通りに勉強をしてみて下さい」
「はい、分かりました」と元気に返事をしてくれた。
後日、授業中の会話である。
「まずは、テスト範囲のすべての教科書を書き写しなさい」
「はい、分かりました」
「教科書は音読しながら書き写しなさい」
「はい、やってみます」
「学校の問題集は最低三回は反復しなさい」
「必ず、やります」
「2Bの鉛筆を使いなさい」
「次までに準備します」
「カラーペンは使わないようにしなさい」
「…」
この時、怪訝そうな顔をしていた。
「蛍光ペンを教科書に引いてはいけません」
「なぜですか」
「教科書の内容は全て隅々まで大切だからです」
「そうですね」
私の指示することに対して、少し不満そうな時もあったが、かつてブクブクに膨れていた筆箱を見ると、カラーペンは無くして、鉛筆と赤ペンだけにすっきり整理されていた。ノートを見ると、教科書の内容をびっしりと書き写して、ワーク類の反復をしっかり行っていた。
「先生、附中で五教科も九教科も両方『一位』を取ることが出来ました」
「良かったね」
その後、定期テスト、診断テストは常に五教科・九教科、総合三位以内で、何回も総合一位を取得した。医学部医学科へ向けて、鋭意、勉強中である。同期の公立中学校出身の塾生二人も医学部医学科へ向けて頑張っている。来年も、また、医者の卵がたくさんうまれそうである。
2025/6/24

『思い遣り』
佐藤進学塾で勉強する時、長い髪の生徒はヘアゴムやヘアピンで髪をくくっている。中学生はショートヘアの子が多い。
昨年の出来事だ。ある子が、髪をふりみだして勉強している。表情がこちらから見てわかりにくい。本人が、一番勉強しにくそうだ。「次から髪をくくって来てね」と伝えた。
「私、ヘアゴムを余分に持っているので使って下さい」と塾のお友達が申し出てくれた。その子は「『ありがとう』と言ってヘアゴムを受け取り、サッと髪をくくった」
何だか、ほっこりする瞬間であった。みんな、髪をピシッとくくって勉強する姿がとても凛々しく見えた。
それから、一年が経った。
ヘアゴムをもらった子は、今はショートにして勉強を頑張っている。他の子たちとも、仲良くしている。先日、新規入塾して不安そうにしている子に声を掛けて上げていた。思いやりの気持ちが連鎖している。
2025/6/23

『理科・社会』
理科・社会は生活に密接している。心豊かな生活をおくっている子は理科・社会が出来る。単に豊かな生活とは少し異なる。「『心』豊かな」生活である。
佐藤進学塾では理科、社会を大切にしている。とても、おもしろいからだ。理科、社会を愉しんで勉強している子は、時間を掛けなくても良い結果が出る。
さて、香川県公立高校入試は、内申220㌽、入試250点を相関表に記入する。それをもとに合否を判定する。
香川県の入試は五教科、各50点、英語と理科、社会は簡単だ。数学と国語はかなり難しい。だから、こういうことが起こる。
①数46,英48、国46,理48、社48
➁数45、英45、国42、理40、社40
③数35、英44、国35、理48、社48
①②③、いずれも
入試得点210点以上で合格である。
但し、内申点は200㌽あるとする。
①の子は高校でもトップになる。
国立大学医学部を目指す子が多い。
➁の子も高校で良く伸びる。
数英国が良く出来ているからだ。
理科社会は選択科目を勉強する。
③の子も合格できる。
最近、これを狙う子が多い。
佐藤進学塾では、①②の合格を目指す。高松高校進学後のことを考えているからだ。合格して入試は終わりではない。高松高校へ入学してから、夢に向かって心新たに勉強する。合格する点数だけを取らすための授業はしない。真に大切なことを指導して、高校の高度な学習へ繋げる。
佐藤進学塾のHPトップでも語っている。
『第一志望校合格、その先のお子様の将来を考えて責任を持って指導を行う』
このスローガンを大切にこれからも指導を続けていく。
2025/6/22

『「二桁×二桁」の暗算』
18×17
=(18+7)×10 + 8×7
=25×10+56
=250+56
=306
慣れると、暗算できる。
筆算よりも格段に速い。
18×12=200+16
=216
といった感じである。
18×12=180+36
=216
これでも、勿論出来る。
25×28=33×20+40
=700
これは計算の工夫でも出来る。
25×28=25×4×7
=700
いろいろな考え方をすると、単なる計算であっても結構面白い。小学生には、面積図を使って説明する。中学生には、展開と因数分解を使って証明する。
以前、小学生の生徒に
「18×18=」と訊いた。
「260+64で『324』です」
と二人が同時に答えた。
たった『三秒』で!
頭が柔らかい間は、直ぐに習得できる。勉強も運動もそして、音楽はじめ芸術も同じだ。小三、小四から進学塾のハイレベルな勉強を始めると大きなアドバンテージとなる。
2025/6/21

『ユーチューブ』
以前の話だ。
中学生との会話である。
「青ペンを使うと暗記力が上がるというのは本当ですか」
「えー。どこから、その情報を得たの」
「ユーチューブです」
「賢い子は鉛筆と赤ペンしか使わないよ」
「えー、そうなんですか」
「本当に賢い子は、赤ペンもほとんど使わないよ」
「赤ペンも使わないのですか」
「塾の模試偏差値65以上取得の子は鉛筆で勉強しているよ」
そういえば、東京大学へ合格した卒業生の子も、中学校も高校も学習は鉛筆だけで勝負していた。青ペンはもちろん、カラーペンなど持っているのを見たことがない。
他の、中学生との会話である。
「罫線のない紙に書いて勉強すると成績が上がるのは本当ですか」
「えー。どこで、聞いたの」
「ユーチューブです」
「本当に賢い子は中三までマスノートを使うよ。学校では大学ノートだけど」
「えっ、そうなんですか」
「京都大、自治医科大、岡山大、香川大、熊本大、島根大、高知大、…、の『医学部医学科』へ進んだ塾の生徒たちはみんな中三までマスノートを使ったよ。高校、大学でもマスノートの子も多くいるよ」
ユーチューブの内容は玉石混交である。石の情報の方が圧倒的に多く配信されている。見る側は無料だが配信する側は収入を得ているのだから…。玉の情報は、正当な対価を払う人だけが得られる。それを得るルートはユーチューブからではない。
生徒たちに最高の学習方法を伝える為に、私は書籍から知識を得る為に時間を使う。常に、書籍を五冊、同時並行して読んでいる。それらには費用と時間を惜しみなく使う。そして、必ず、正当な対価を払う。無料で情報を得るなどという考えはない。
平成時代の出来事を思い出す。
「先生、『天体』の内容が全てわかりました」
「どうやって、復習したの」
「ユーチューブの動画を見ると理解出来ました」
「あっ、そっ」
後日、テストの結果が出た。私が伝えた通り、素直にノートに書いて教科書を調べて復習した子たちは皆、90点以上を取得した。ユーチューブを見て勉強した子は54点で顔面蒼白だったことを思い出す。
聡明な子はスマホに依存していない。TikTok、ユーチューブなどあまり興味を示さない。時間があれば、好きな本を読んでいる。だから、賢いのである。高松高校進学後も、華々しい結果を伝えに来てくれる。話をしていると、大量の情報から真の情報だけを選択して、日々、有意義に過ごしていることが分かる。
2025/6/20

『最高の完成度』
中学生、テスト対策が完成した。
今回は九教科を完璧に仕上げた。
生徒全員、本当に良く頑張った!
中一は一生懸命に勉強した。
中二は自分の限界に挑戦した。
中三は出来る限りの事を行った。
佐藤進学塾、生徒皆が最高の完成度だ。最高の状態でテストに挑むことが出来た。テスト後は、少しゆっくり過ごすとよい。
部活を楽しむのも良い。
趣味を楽しむのも良い。
友人と楽しく遊ぶのも良い。
オン、オフの切り替えは大事だ。勉強ばかりではつまらない。勉強を頑張る子は、様々なことを楽しむ。テスト対策の期間中、寒暖差が大きく体調面が気になった。それを、ものともせず、生徒たちは頑張り抜いた。一生懸命頑張った生徒たち、ご協力頂いた保護者様には心より感謝申し上げたい。
2025/6/19

『テストで重要なこと』
「実力を発揮するにはどうすればよいか」
1.テストが配られたらテスト問題全体に目を通す。
※問題の量と難易度を確認する。
2.難しいと感じた問題は印をつけて後にまわす。
※時間がない時は解かなくてもよい。
3.深呼吸をして、ゆっくり、リズム良く解く。
※見直しは気になる問題だけ行えばよい。
パニックになった時、一度、テストから目を離す。それから、ゆっくりと深呼吸をする。交感神経は下がり、副交感神経は上がる。自律神経は安定する。
平常心を取りもどす事が出来る。長くても、三十秒位である。一人ひとり、自分のペースを大切にテストへ取り組むと良い。
2025/6/18

『小4「算数」』
小4、『図形』を指導した。
前半は垂直と平行である。
三角定規を使って確認する。
角度については、中学校レベルまで教える。対頂角、同位角、錯角である。小四位の年齢の子ははまだ頭が柔らかい。スッとしみこむ様に理解する。
後半は台形と平行四辺形である。
1.台形(定義)
一組の向かい合う辺が平行
2.平行四辺形(定義)
二組の向かい合う辺が平行
平行四辺形(性質)
二組の向かい合う辺は等しい
二組の向かい合う角は等しい
対角線がそれぞれの中点で交わる
これらを小四の子たちが分かるはんいで教える。図を書いて、ゆっくり教える。この時点で理解しておくと、中二、図形の証明はスラスラ出来る。小四の算数には大切な要素が多く含まれている。
2025/6/17

『大切な時間』
佐藤進学塾の生徒たちは時間を守る。授業開始「15分前」には全員が教室に集合する。とても、気持ち良いことである。
時々、入塾説明の時、親子から訊かれる。
「部活で、遅れてもいいですか」
「時間は、必ず、守って戴きます」
大切なことは妥協しない。
在籍する生徒たちは当たり前のことと感じている。厳しいなどとは、微塵も感じていない。寧ろ、心地良い位に感じている。生徒一人ひとりが時間を大切に考えているからだ。
小学生は「16時40分頃」集合だ。授業開始までには「20分間」復習が出来る。その間、私たちが宿題や質問の対応を行う。
毎回「20分」の復習も、中学部の子であれば、一週間で「1時間」となる。一カ月で「4時間」となる。一年間では「48時間」、なんと「2日間」となる。三年間ではおよそ「一週間」分となるのである。
小さな積み重ねが大きな差と成る。
中学部の生徒は部活をしていて、片道三十分以上掛かる子も多い。それでも、皆、時間を守る。中学生は「19時」集合指定である。早く入室している子は成績が安定している。時間感覚を示す『空間認知能力』が高いので勉強が良く出来るのだ。
学校も家も塾から遠い子がいた。
その子はいつも一番に来ていた。
「いつも、早く来ているね」
「静かに勉強出来て、気持ちいいんです」
「家が遠いのに、大丈夫」
「心掛け次第で時間は何とでもなります」
この子は、小四から中三まで通い高松高校へ合格して進学した。後に第一志望の国立大学へ進学した。時々、近況報告に来て、元気な姿を見せてくれる。毎回、20分、六年間で「十二日間」も多く勉強した事になる。一日、三時間勉強するとして「96セット」である。まさに『塵も積もれば山となる』 である。
2025/6/16

『集中からゾーンへ』
ゾーンというのは、集中力が極限までに高まった状態のことをいう。神経を研ぎ澄ませて集中するゾーンへ入ることに拠り、ハイレベルなパフォーマンスを発揮出来る。
集中力を極限まで高める為に、気が散る要因はすべて排除しておくのが効果的だ。あらかじめ、周囲を整理整頓しておけば、目の前の学習に集中することが可能と成る。
以下の三点、
ゾーンに入る条件である。
1.成功するイメージをもつ
自分が成功する様子を強く思い浮かべる。自分の目標を紙などに書いて大きい声で唱える。ポジティブなイメージを思い浮かべて、脳をわくわくさせて、集中力を高めていくとよい。
2.ルーティーンを意識する
ゾーンへ入る為に、ルーティーンを意識するのは大切だ。野球選手がバッティング前にバットを動かすのはルーティーンの一種だ。学習前に好きな音楽を聴いてから机に向かうなどルーティーンを作るとよい。
3.深呼吸をおこなう
深い呼吸をすることに拠ってセロトニンが分泌される。そうすると、ゾーン状態に入りやすくなる。まずは、鼻からゆっくりと空気を吸い込む。その二倍以上の時間を掛けて、口からゆっくりと息をはき出す。呼吸が整うと、集中力が高まりやすくなる。自律神経が関係しているからである。
2025/6/15

『「七月号」の書類』
七月号の書類を月曜日より配布する。
1.夢つうしん
2.保護者の皆様へ
3.全国模試日程のお知らせ
※一学期中間テスト成績優秀者
一人ひとりに宛てた手紙
毎日発信する「塾長ブログ」、毎月配布する「各種プリント」、お子様と一緒に読んで頂きたい。読んで、実行している子は、実力が飛躍的に伸びている。
2025/6/14

『機密文書』
随分前の話だ。
笑うに笑えない話だ。
「今日、マジックで名前を消しました」
「は、何のこと」
「学校の先生が『個人情報を保護する為にプリントの名前を全部消しなさい。それから資料を捨てます』と言われたんです」
「え、大丈夫なの」
さて、学習塾を経営していると個人情報を多く取り扱うことになる。名前、住所、電話番号、成績、…。佐藤進学塾ではこういった文書の扱いには十分過ぎるほどに気を付けている。
機密文書処理は近隣に所在する総合リサイクル企業にお願いしている。シュレッダー搭載車が巡回、塾へ立ち寄って頂く。
目の前で書類が裁断されていく。その後、工場で融解処理する。裁断は五分程度、二トントラックの荷台部分で行われる。融解後、処理証明書が届く。処理後、書類は再生紙となる。その費用は五箱で1,100円である。個人情報を保護出来る上、リサイクル出来るのだからありがたい。
役目を終えた紙類はリデュース、リサイクル、リユースする事が可能である。現代社会において、必要不可欠な廃棄物の適性処理の二大要素を含んでいる。
まず一つ目は、地球環境保全の為の二酸化炭素削減である。融解処理は二酸化炭素排出削減、地球温暖化の抑止に貢献する。そして二つ目は、個人情報保護法への有効性である。機密文書も焼却埋立する時代から細断、融解する事に拠り確実に抹消する時代へ変化した。
「SDG's」と言う言葉の下で様々な要求が企業に求められる現代、企業活動と地球環境の関係について取り組むべき課題は、廃棄物である書類の適性処理もその一つであると考えられる。
2025/6/13
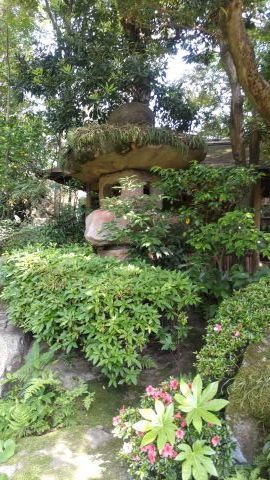
『算数「小四・わり算」』
小四はわり算の単元を指導した。
60÷30=(6÷3=2)=2
170÷50=(17÷5=3あまり2)=3あまり20
「10」の2つ分だから、あまりは20である。あまりを間違わないように気を付けよう。わる数が2桁の時、かりの商を立てるのに少し時間が掛かる。
かりの商が大きい時は「1」下げる。
かりの商が小さい時は「1」上げる。
しかし、三回位反復すると、すぐに商が立つようになる。慣れると、感覚が研ぎ澄まされる。「コツがつかめた」と感じる。スラスラ解けるので、計算が楽しくなる。
一、二回目の反復は時間が掛かる。しかし、三回目の反復は直ぐ出来る。だから、「頑張ったものが勝ち」である。出来る子というのは粘り強い。三回目の反復まで頑張り、コツを掴む。だから、凄く出来るようになる。四人の子が涼しい顔をして楽しそうにスラスラ解いている。復習している子たちである。
2025/6/12

『佐藤進学塾の課題』
佐藤進学塾には課題がある。
まず、宿題である。問題演習を行い、学習内容を定着させる。次に、復習である。間違いを直し、教科書を調べて深い理解を得る。そして、参考書の活用だ。関連する単元を学習して知識の幅を広げていく。
これで『課題』は完成である。
丁寧に行う子は、全国模試の偏差値が総合で『65』を超える。中学校のテストで『上位一桁』を取得する。
まず、宿題を完璧に仕上げよう。復習は必ず、丁寧に行おう。トップを目指す子は参考書を徹底して活用しよう。
但し、中学生に宿題は出さない。復習中心に勉強してもらう。宿題は受動的な学習になり、復習だと能動的になるからである。
宿題が出ないから「ラッキー」などと思ったら大間違いである。復習していることを前提に授業を進めていくので、復習をしていないと授業内容が分からなくなる。理解度が低い為に質問すらできない。
一学期中間テスト、多くの生徒が上位を取得した。『総合「1位」』の子もいる。その子たちは、矢張り、すべて行っている。勉強を楽しんで行っている。『成績上位者一覧』は今月中旬、封筒へ入れて手渡す。
2025/6/11

『50点満点』
昨年、附属中の一年生は中間テストが理科一科目、50点満点であった。期末テストの範囲が広くなることを考えて、五科目のテスト勉強をしつつ、理科のテスト勉強には力を入れた。
一人が50点満点を取得した。
「先生、50点満点でした」
うれしそうに伝えてくれた。
私が言う通りに勉強した。まず、教科書を音読しながら、隅々まで書き写した。次に、学校ワークを三、四回反復練習した。その都度、教科書を調べた。そして、理解後覚えてしまうまで勉強を粘り強く続けた。とても、素直な子である。
一週間前に、公立中のテストが終わった。公立中の友人がその子に声を掛けた。
「最後まで気を抜くなよ」
公立中の子は最後に気を抜いて、惜しいミスが出た。それを「友人に伝えたかった」と言う。声を掛けられた子は素直に受け止めた。「ありがとう。気を抜かず最後まで頑張るよ」とにこやかにこたえていた。
附属中の子は、私にこう言った。「『最後まで気を抜くなよ』と友達に言われてから、学校のワークを念には念を入れて、五回、六回、七回と反復練習しました。それが、良かったんだと思います」。
さらに、こう続けた。「友達に『気を抜くなよ』と言われて、気を抜きかけていた自分にハッと気がつきました。大切な事を教えてくれた友達には心から感謝しています」。二人とも、素直な子である。
2025/6/10

『原則的学習』
1.教科書を音読して書き写す。
2.学校のワーク類を反復練習する。
3.学校のノート・ワークシートを覚える。
小中学生、テスト前の原則的学習である。丁寧に行う子は必ず結果が出る。日々、三時間の家庭学習を行う必要があり、継続すると結果が出る。テスト前、それ以上行うのは当然である。
小学5・6年生は、算国二時間、英理社一時間で合計三時間だ。中学生は、数英二時間、国理社一時間で合計三時間である。
原則的学習をテスト三週間前から丁寧に行うと良い結果が必ず出る。詳しいことについて、中学生にはテスト前に生徒たちとディスカッション形式で賑やかに話を進めていく。
テストに向けての正しい学習方法を、一人ひとりに向けて具体的に伝えていく。私が一方的に話をするのではなく、生徒の意見や気持ちを聞きとりながら、ゆっくりと丁寧に話を進めていく。
一日二十四時間、時間は限られている。だらだら長時間勉強しても無駄である。学習は効率的に行うことが大切だ。塾方針として長時間拘束はしない。最大限、効率の良い学習を行い、納得出来る結果を出す。
1.教科書を重視して学習すると上手くいくタイプの子がいる。佐藤進学塾では『左脳型』と呼んでいる。理論や概念を深く理解してテストをじっくりと解き進める子だ。左脳型の子は教科書をじっくり深く学習すると良い。学校ワーク類の反復は少なめの「二、三回」で定着する。
2.学校のワークを重視して学習すると上手くいくタイプの子がいる。佐藤進学塾では『右脳型』と呼んでいる。反復練習して解法のコツを掴みテストをリズム良く解いていく子だ。右脳型の子は演習を徹底して行うと良い。学校ワーク類の反復は多いめの「四、五回」で定着する。
小学生の間は、いずれのタイプかわからない。脳に可塑性があり、柔軟であるからだ。教科書、ワークをバランスよく行う必要がある。
「教科書の書き写しができない」
と言ってくる子がいる。
「必ず、やらなければならない」
と私は答える。
小学生の間はワークの演習だけで点を取る子もいる。しかし中学生になると、教科書の深い理解が必要になる。中一の間は簡単だが、中二後半から難しくなる。中三になり、急に点数が伸びなくなる子がいる。
こうなると、演習ばかりやっても点が取れない。教科書を軽視すると、あとで伸びなくなる。分からない時、間違った時は、必ず、教科書を調べることが大事だ。勿論、辞書、参考書を活用しても良い。
生徒「先生、中三になってから成績が伸びません。どうしたらいいでしょうか」
塾長「先生に復習ノートを見せてくれるかな」
生徒「はい、分かりました。このノートです」
塾長「復習ノートの内容は完璧だ。とても丁寧に学習出来ている」
この後も、成績は伸び悩んだ。十二月頃、勉強方法について再度話し合った。すると、教科書を軽視していることが分かった。「教科書を深い所まで理解してみよう」。それから「『演習⇔教科書』の型」で勉強した。何とか入試に間に合った。無事に高松高校へ合格できた。成績が伸び悩んだ時は原点に戻り、原則的学習を丁寧に繰り返し行うと良い。手間も暇も掛かるが、丁寧に行うと良い結果が出る。
2025/6/9

『副教科について』
一学期期末テスト対策を実施している。今回は、副教科を含め九教科である。テストに向けて気を付ける点を具体的に話す。
そのあと、一人ひとりから質問を受け付ける。副教科についての質問がたくさん出た。
「副教科の勉強はいつ頃から始めたらいいですか」
「今週の土曜日には始めよう。二週間は最低必要です」
「テストの問題はどこから出題されるのですか」
「殆どの問題は教科書と学校のワークからです」
「どこをしっかりと覚えたらいいですか」
「教科書の太字を中心に覚えるといいです」
「細かいところはやらなくていいのですか」
「五教科ほど、教科書の隅の方からは出ません。学校のプリントはしっかり勉強しておきましょう」
「記述問題はたくさん出されるのですか」
「記述、記号選択とバランス良く出題されています」
「五教科と副教科、どちらが大切ですか」
「敢えて言うなら副教科です。中三で内申点が、四倍されるからです」
テストまであと二週間、集中して学習を行う。
その為に、静謐な学習環境を守り維持する。
生徒さんと保護者様には、安心してご通塾戴く。
2025/6/8

『「メンタル」が強い子』
学力十分で、復習も完璧に行い、テストで力を発揮出来る子がいる。一方、学力十分で、復習も頑張っているのにテストで力を発揮出来ない子もいる。
この違いは『メンタル』である。
前者は、自分自身が頑張ったこと、自分が出来ることに意識を強く向けている。後者は、頑張りがたりていない部分、自分が出来ていない部分に驚くくらいに強く意識が向いている。
出来る子でも、仕上げは完璧ではない。学習が不十分なところは必ずある。しかし、意識をそちらへ向けることはない。
だから、テスト本番で実力を発揮することが出来る。自分自身の意識を、自分の出来る部分へ向ける様にしている。テストでも自分が出来る問題に自然と目が行くのである。
「よく頑張ったね」
と私が声を掛ける。
「ありがとうございます」
と気持ち良くこたえる。
前向き且つ明るい受け答えが出来る子はメンタルが強い。私の言うことを素直に受け止め、学習における問題点は改善して実行に移していく。やるべきことをやっていれば、出来ていない部分もそのうち出来る様になる。不思議なようであるが、これは事実である。
テスト対策の期間中、佐藤進学塾の生徒全員が真剣に頑張っている。一人ひとりの学習しているノートを見ると、間違っていたりポイントがずれていたりする。しかし、テスト前、私はそれに敢えて触れない。私がそこに触れると、意識がそちらへ向く。「出来ていない」と本人は焦り始める。
だから、出来ていることを、静かに伝える。「この単元、よく理解出来ているよ」。そうすると、不思議なことに出来ていないところにも気づく。自分自身で気が付くと、冷静に対処できる。
テスト前は『静かに生徒を見守ること』が大切である。
かつて、テスト前に生徒へ細かいことを厳しく言っていた。それで、良いことは一つもなかった。生徒たちも、迷惑であったことだろうと反省している。今では、穏やかに話しかける。テスト前は、生徒本人が一番「頑張らなければならない」ということを分かっているからだ。
くれぐれも、親が言っていはいけないことがある。「大丈夫なの、もっと頑張らないと、失敗するわよ」三点も、お子様を否定している。大丈夫ではない、頑張りが足りない、失敗する。
これでは、いけない!
だから、親もこう言うといい。「頑張ってるね、大丈夫、きっとうまくいくよ」実際に出来る子の親は、この様な言葉掛けを必ずしている。私も肯定的な言葉を掛ける。お子様の心は落ち着いて大変安定する。メンタルは、指導者と家族と友人の発する『言葉』にすべてが掛かっている。これが真実なのである。
2025/6/7

『小五算数「公約数」』
小五、公約数を指導した。教科書ではわり算で考える。塾テキストでは、かけ算の形で考えて答えを出す。この方が圧倒的に速い。その上、正確に答えを導き出す事が出来る。
「18の約数」を考える。
18=1×18
2×9
3×6
拠って、答えは
{1,2,3,6,9,18}
である。
約数が2つだけのものを、素数という。1とその数自身以外に約数をもたない数のことである。1から100までの素数については即答出来る様、トレーニングしておこう。
2,3,5,7,11,13,17,19,23,…。
約数が3つの数もある。
4,9,25,…。
例えば、
25=1×25
5×5
{1,5,25}と約数は3つ。
これも覚えておくと良い。
最大公約数、最小公倍数については、素因数分解による解き方を教えている。中学校で習う手法である。練習を重ねることでマスターできる。速く、正確に答えを出すことが出来る様に成るので、便利である。
さて、小五の子たちは深く考える事に長けている。静かにじっくり考えるタイプの子が多い。素晴らしいことである。皆、授業に集中しきる事が出来ている。
2025/6/6

『小四算数「わり算」』
小四、わり算の単元を指導した。わる数は「2けた」である。仮の商を立てるのが難しい。
最初は生徒たちと皆で一緒に考える。塾長の私が、引っ張っていく。それから、各自、演習にはいる。
「仮の商」が直ぐに立つ子がいる。復習をしっかりしているから、わり算の感性が磨かれている。問題を解く速度が速い上、問題の正答率も高い。すこし、誇らしげである。
一人ひとり、見ていく。
少し遅い子には「仮の商」の立て方を教える。少し速い子には答の検算の方法を教える。
お友達の出来具合いばかり気にする子がいる。
「集中しなさい」
ぴしゃりと言う。
友だちと比べる必要などない。
自分を信じて解き進めると良い。
「早く解きなさい」と言わない。
「ゆっくり解きなさい」と言う。
「みんな、良く頑張ったね」
と言うと、皆にこにこしていた。
「ありがとうございます」
と元気にこたえる子もいた。
「仮の商」を直ぐ立てるには、ひたすら反復練習をするしかない。何回も何回も、繰り返し反復復習することで「仮の商」が瞬時にたてられる様に成る。その時が来るまで頑張ろう!すでに、小五、小六塾生の子たちの中には、復習を重ねて瞬時に仮の商が立つ子が多くいる。とても誇らしげである。
2025/6/5

『ぴったり仮面「成長編」』
「午後4時40分、『ぴったり仮面』や」
且つて、二人の小学生が自転車で一緒に仲良く塾へ来ていた。到着すると、二人が同時に言葉を発した。
私が「『ぴったり』は分かるけど、なんで『仮面』なんや」と訊くと、二人は、顔を見合わせてニコニコと笑うだけだった。未だに仮面というのはどう意味か分からず仕舞いである。
二人だけのルーティーンである。
二人は、小三から佐藤進学塾へ通っている。最初は、二人とも車の送迎であった。その頃二人は、特に、仲良くはなかった。
二人に共通することがあった。優しい心の持ち主であること。小四あたりから、二人は自転車で来始めた。
塾の帰りは、二人で仲良く帰る様になった。子どもというのは、小さなきっかけで仲良くなる。
自転車には不思議な力がある。
中学生となり成長した二人は今も一緒に来ている。しかし、今は「午後7時00分、『ぴったり仮面』や」と言う事はない。時間のことを自分で考えて、危険から身を守る術を自分で考えて、雨、風などの自然を自分の肌で感じているからだ。行き帰りの安全に十分、気をつけて、静かに帰ってほしいと思う。
2025/6/4

『「小五理科」の授業』
以前の話である。
「先生が教えて下さったことがこの本にすべて書いています」と言って、小学部の生徒が一冊の本を私に差し出してくれた。見ると『植物』のことを詳しく説明した図鑑であった。
佐藤進学塾は理数系の指導を重視している。理科の授業でも、説明が詳しくなりすぎる時がある。受粉についてとても詳しく説明したことがあった。
中学生、高校生レベルまで話の内容は踏み込んでしまう。その話を興味深く聴いている子が結構いる。こういう子たちは将来がとても楽しみだ。
さて、小学生が持って来た本を見ると、図書館(高松市)の印がある。家の人と一緒に訪ねて興味を持ち、借りたのであろう。本の内容を話す時、その子の目は、キラキラと輝いていた。
かつて、卒業生の保護者様から聞いた話だ。
学校の先生から、「お宅のお子様が、小学校に登校していません」と電話があったと言う。お母様は、心当たりのある所を探した。しばらくして、歩道に座り込むわが子を見つけた。お子様は、道端に咲く花を見つめていた。
「どうしたの」と母が言うと、
「お母さん、この花、きれい!」
と興奮気味に言ったと言う。
お母様は、
「本当、綺麗ね」と言うと、
お子様は、
「私が見つけたんだよ」
と誇らしげに言ったと言う。
「お母さん、この花何て言うの」
と続けて言うので、
「今度、図書館で調べようね」
と優しく答えたという。
お母様は、
「そろそろ学校へ行こうね」
と言うと、
お子様は
「あっ、学校行く途中だった」
と急いで学校へ向かったと言う。
お母様は、塾長である私に「うちの子、夢中になると時間感覚が飛んでしまうんです」と話してくれた。このお子様は、後に、東京大学へ進学している。成功するお子様は保護者様が優しく見守っている。
2025/6/3

『最重要学年「中2」』
佐藤進学塾では、中二を最重要学年と位置付けている。中二という時期は中途半端だ。「受験など、まだ先のこと」と考えている。部活動ばかりに力を入れる子も多い。
中三であわてて勉強しても間に合わない。既に、中一・中二の内申点は確定している。「中三からでも、間に合いますよ」などということは決して口にしない。
中二の段階では高松高校受験の厳しさを肌感覚としてわかっていない。そんな中、中二でひと足先に受験勉強へ取り掛かった子が勝利して、高高進学後に成績上位で推移する。
『小四』までに「家庭学習習慣」を身に付ける。
一日、二時間、家庭学習を集中して行うこと。
『小六』までに「正しい学習方法」を身に付ける。
音読、書写、反復を中心に学習を行うこと。
『中一』のテストで良い「結果」を出しておく。
全科目において、90点以上確実に取ること。
定期テストの三回目までに必ず、良い「結果」を出す。内申点も関係する。ここで、自信をつけておく。一回目、二回目は上手くいかないこともある。最初は問題が簡単で、一、二点差で順位が大きく上下するからだ。その時、順位は気にする必要はなく、公立は90点、附属は80点を基準に考えると良い。
その時、問題点を見つけ出す。
「凡ミスだった」
など言ってはいけない。
「凡ミス」、実は、本質が理解出来ていない。「おかしいな」と思った時は、親も一緒に考えた方がよい。最初のうちは、親が見るとすぐに問題点の本質がわかる。その時点で改善すると、すべて上手くいく場合が多い。中二あたりになると問題点の本質が見えにくくなる。学習内容が高度になるからだ。
例えば、「数学92点、英語81点」とする。
この時、数学に力を入れて100点を取りに行く。まず、得意科目を強化する。そして、自信を持つ。それから、英語の改善だ。このあたりは、私が一人ひとりに細かく的確な指示を出す。
さて、中一で学習が軌道にのると安心だ。中二になると、テスト前の授業を強化する。週三の試験対策にプラス特別授業で「週四」となる。更にテスト前は「土、日」も行う。但し、授業は二、三時間である。
集中力を極限まで高めて、各自「ゾーン」に入り学習を行う。塾でも、家庭でも、最大限に集中して学習を行う。夜は早めに就寝して、次の日の授業に備える。睡眠、そして、健康管理が最も重要である。軌道にのるまでは親のサポートも必要だ。軌道にのった後は、健康管理のみを行えばいい。
2025/6/2

『社会「地理・歴史・公民」』
「社会が苦手です。どうしたらいいですか」生徒からよく聞く言葉である。「教科書をよく読んで理解して覚えたらよい」とこたえる大人が多い。
しかし、興味関心のない子にとって教科書の内容は呪文かお経にしか感じられない。よく読んでいる間に眠くなる。授業中もボーッと聞いている。拠って、社会が出来る様にならない。
「では、社会が出来る子は一体、何をどの様にしているのか」
1.新聞を読む、書く
2.ニュースを見る、聞く
3.様々な本を読む
4.授業をよく聴く
5.先生始め大人の話を聞く
まず、この五点が社会の勉強の素養となる。ひと昔前の子とは、よくこんな会話を交わしていた。
「なんで、そんなに社会の事を良く知っているの」
「父からいろいろと教えてもらっているからです」
「お父さんはどこから得た知識なの」
「いつも新聞、本を読んでいてニュースも見ています。新聞、本、ニュースから得た知識だと思います」
「すごいね」
「はい、わたしも見習う様にしています」
さて、新聞購読率、30歳代は30%、40歳代は40%、50歳代は50%を切って、減少の一途を辿っている。「電子版があるから必要ない」という大人もいる。しかし、子にとって紙という媒体は大切である。
塾長である私は今も日本経済新聞を購読している。自分から興味を持って読み始めたのではない。政府系金融機関勤務時、先輩から「必ず、読め」と言われた。今となっては、先輩には感謝の気持ちしかない。
佐藤進学塾の大切な生徒たちに改めて言う。「必ず、新聞(小学生新聞)を読め。そして、ニュースを見よ。好きな本で良いからたくさん読め」。何十年か後に、必ず、「良かった」と思うことは間違いない。
2025/6/1

『肯定的な言葉(続編)」
(昨日の続き)
保護者様も肯定的な言葉の大切さに気付かれる方が多い。否定的な言葉は極力控えて、意識して肯定的な言葉に変えていく。
肯定的な言葉を掛け続けられると、お子様の心は鏡の様に光り輝く様に成る。自分自身の事を肯定する様に成る。自己肯定感の高い子に変わっていく。
「国語を丁寧に勉強します」
「改善点を具体的に伝えるね」
「五回位、反復してみます」
「教科書を確認するといいよ」
生徒たちは、「やってみます」「頑張ります」「挑戦します」 と素直に答えることが多くなる。かつての出来事を思い出す。以前何回も、ブログで書いたことだ。附属期末テストの社会が58点だった。その子は、良く出来る子だった。その年、社会が難しかった。(以前、附属小は期末テストが年二回あった)
ちょうど、保護者面談の日を控えた頃だった。保護者様は私とお子様、両者の気持ちを察しておられた。「先生、この子と『正倉院展』に行ってきます。本物にたくさん触れてきたいと思います。ぜひ、この子から感想を聞いてみてください」。社会のテストについて、一切触れることはなかった。
親御さんはお子さんとテストをていねいに解き直していた。親子で一緒に考えて、ノートへ丁寧に復習していた。お母様は、お子様に「『難しい問題で大変だったね。こういう時は、いつも以上に復習をしておけばいいのよ』」と声を掛けてくれた」ということをお子様から聞いた。
後日、その子は正倉院展のことを明るく話してくれた。開口一番「奈良でおいしいものを食べました」と言った。それから、正倉院展で心に残ったことを一生懸命、私に伝えてくれた。以降の附属期末テストはすべて80点以上であった。お母様とご家族のサポートをひしひしと感じた。
2025/5/31

『肯定的な言葉(前編)』
「はやく、しなさい」
「なんで、できないの」
「何回言ったら、わかるの」
お母様が、つい、言ってしまう言葉である。すべて、お子様を否定した言葉である。残念だが、この様な言葉を掛ける限り、お子様は勉強が出来る様に成ることはない。
では、どう言えばいいのか。
「ゆっくり、しようね」
「もう一回、やればいいよ」
「何回でも、言ってあげるよ」
私は、お子様のすべてを肯定する様にしている。決して、人格を否定することはしない。もちろん、生徒一人ひとりの問題点は、すぐに伝えて改善させる。怠けている時は、その事実についてはっきり伝える。人として間違った事をした時は、その事実について冷静に叱る。子供たちに迎合することはしない。
「私は国語が苦手です」
「勉強時間がたりないからだよ」
「ぼくは暗記が苦手です」
「書いて覚えていないからだよ」
なぜ、否定的な事を子供が言うのか。それは、周りの大人たちが否定的な事ばかりを言うからである。「あなたは、国語が出来ない」と言われたら、子は国語が苦手と思いこむ。「全然、覚えられんのやね」と言われたら、子は暗記が苦手と思いこむ。
ところが、佐藤進学塾へ一、二年通うと生徒たちは否定的なことを言わなくなる。今現在の状況を冷静に判断して、改善することを考えるようになる。佐藤進学塾の中では、指導者である私達が肯定的な言葉を意識して使う様にしているからだ。子というのは、親や先生の鏡なのである。(明日へ続く)
2025/5/30

『「一学期中間テスト」結果』
一学期中間テスト結果について、二人の生徒に訊いてみた。「同じ学校、学年、教科」のテスト内容についてである。
「学校のワークから出題されていました。一問、間違ったのですが、教科書の隅から出題されていました。期末テストは教科書を隅々まで勉強する様にしたいと思います」とこたえた。
「難しい問題がたくさん出ていました。見たことのない問題が多く、あせってパニックになりました。期末の時は難しい問題をもっとがんばります」とこたえた。
公立中のテストは教科書、ワークから出題される。難しい問題は殆ど出ない。前者は問題を冷静に見て、学習方法の改善を試みている。後者は言い訳をして、次に行う事を見誤っている。
さて、今回も、『総合一位』をはじめ上位者が多く出ている。殆どの子たちが五教科450点を超えている。その子たちはケアレスミスが非常に少ない。メンタル、即ち心が強くないと実現不可能であるといえる。五科目『90点』以上、取得出来ていれば、大丈夫だ。間違った問題は復習すればよい。
1.出題元を教科書から探し出す
2.学校ワークの類似問題を解く
3.根底から理解する迄復習する
来週からは、『一学期期末テスト対策』に入る。今回は副教科も実施される。皆が、勉強しやすいように私たちも環境を整え、様々な準備をして全面的に協力する。今回も集中して、ゾーンに入り学習しよう。だらだら長時間勉強するのではなく、時間(ゴール)を決めて集中して行う密度の高い学習が大切である。
2025/5/29

『国語力』
幼少期に保護者が読み聞かせをしっかりと行っているお子様の国語力、即ち読解力、語彙力、国文法力は高い。
国語の出来る保護者様に訊く。
「お子様の高い国語力の要因は何でしょうか」
保護者様は間違いなくこう答える。
「小さい頃に多くの絵本を『読み聞かせ』していることだと思います。気がついた時には読書を愉しむ様になっていました」
国語が出来る子には、他にも共通点がある。
1.家庭の会話力
静かな家庭環境の中、家族で質の高い会話が行われている。
2.新聞、小学生新聞の購読
家族が新聞の内容について、毎日、話しをしている。
3.読書の習慣
家族みんなが読書を愉しんでいて、共通の趣味として考え方を共有している。
これに加えて、進学塾で国語の各種問題演習を行うことにより国語力はもちろん、学力全般が大きく伸びていく。読書習慣が在る子の物語文(小説)の読解力は高い。新聞購読している子の説明文(論説文)の読解力は高い。家庭での会話量が多く質の高い家庭の子は語彙力、国文法力、記述・論述力が高い。
優れた指導者が素晴らしい指導を行っても、上記三点が整っていない場合、解法の技術を学んで一時的に国語力が上がっても、本質的な国語力が継続的に上がることはない。国語は全ての科目に通じる。時間が掛かっても上記三点を整えることでお子様の表情は明るく前向きになり、国語は必ず出来る様になる。
2025/5/28

『こども防災万博』
授業後、ふたりの小学生が私に話し掛けて来た。
「何か、質問かな」
「先生、大阪万博で開催される『こども防災万博』の発表者に選ばれました」
「えっ、すごいね」
「香川県内から10名が選ばれて自分たちの意見を発表します」
「ところで、どういう取り組みなのかな」
と訊くと、生徒たちは一生懸命に防災万博の取り組みと趣旨について、説明してくれた。
実は私自身、その取り組みについては聞いたことが無かった。授業がすべて終わってからネットで調べてみた。
令和7年5月28日(水)、大阪・関西万博EXPOホールにて、「防災万博」が開催されるという。
社会課題に取り組む自治体・団体・子どもたちの活動を紹介することで、次世代を担う防災・地域創生の取組を広く発信することを目的としている。
教育、防災、創生の三本柱のもと、香川大学の金田義行特任教授、磯打千雅子特命准教授をはじめとする専門家によるレジリエントな社会構築に関するパネル討論、小中学生による未来の防災アイデアのプレゼンテーション「こども防災万博」のほか、AI・メタバースなど最新DX技術を活用した防災ソリューションの発表など、多彩なプログラムが展開される。
「こども防災万博」には県内の10名の小学生が参加し、自ら考えた防災アイデアを発表するという。
(防災万博の内容については香川大学HPより)
進学塾の学習だけではなく、様々な形態で学習し、それをまとめて発表すると言うことはとても素晴らしいことだと思う。また、後日、子ども防災万博の具体的な内容についてゆっくり聞こうと思う。
2025/5/27

『「中間テスト結果」の感想』
中間テストの結果が出た。
中学生に訊く。
「テスト、どうだった」
「五教科90点以上取る事が出来て嬉しいです」
「塾目標の480点を超える事が出来ました」
「数学と英語が100点で良かったです」
皆、具体的に伝えてくれる。
「期末テストも頑張ろう」
と声を掛ける。
「はい、がんばります」
と元気よく答えてくれる。
一学期中間テストは五科「90点」以上取ることが出来ていれば、順位はあまり気にしなくてもよい。
2025/5/26

『一学期中間・期末テスト』
佐藤進学塾では、一学期中間・期末テストを「一つのテスト」として考えている。中間テスト終了後、期末テストに向けて、引き続き学習することが重要だ。
中間テストが終わった。ひと月後に期末テストが実施される。結果がすべてではない。しかし、結果を見れば全てがわかる。「結果が良い」ということは、正しい努力が出来ている。
中間テスト後の復習について改めて確認する。
間違った問題を丁寧に直す。
1.問題を書き写す
2.教科書で出題元を探す
3.解法を出来るだけ詳しく書く
間違った原因は次の三点である。
1.明らかな勉強不足
2.読み間違いや勘違い
3.難易度の高い問題
1.勉強不足は論外だ。
日々、三時間、テスト前は六時間以上行うこと。
2.読み間違いは音読不足だ。
教科書を調べて、考えて、音読して学習する必要がある。
3.難易度の高い問題は仕方ない。
難しい問題については、復習して理解すればよい。
テスト後は平常授業を行う。進学塾カリキュラムに基づいて予習授業を実施する。その後、三週間は期末テスト対策となる。さて、「出来るようになりたい」と思って、一生懸命に勉強した子のノートは凄い。『飛び出す絵本』の様に、字が飛び出て来る時がある。
鉛筆一本で仕上げたノートである。ノートの字からは凄い気迫を感じる。本気でやれば、その気持ちは必ず指導者に伝わる。指導者は、その子に一生懸命、的確なアドバイスを行う。それが、心の奥底に響いて勉強は出来るようになる。
みんな、期末テストもしっかり頑張ると良い!
2025/5/25

『「附属小六」学力テスト対策』
中学生のテスト対策が終了した。生徒たちはホッとしていることと思う。少し、ゆっくりするといい。その後は期末テストに向けて気持ちを切り替える。
佐藤進学塾では、小六の学力テスト対策が始まっている。平常授業では、重要事項を説明後、各種問題の演習に入る。大切なことはすべて生徒に『音読』してもらう。
テスト対策では、対策問題の演習からはいる。演習後、問題の解説を行う。制限時間を守り、『黙読』で問題に取り組む。
音読の習慣があれば、黙読で取り組む時にも、自分の声が脳と心からはっきり聞こえて来る。この感覚が、大切なのである。インナースピーチ、内的発話である。
問題演習後は解説を行う。難しい問題は詳しく説明する。対策問題が8割出来る様に、家庭で復習を丁寧に行おう。あとの2割はわからなくてもいい。完璧に仕上げる必要はない。八分目まで仕上げればよいのである。あとは半年後、一年後にいずれ出来るようになる。
さて、復習方法を再確認する。
1.間違った問題を解き直す
2.教科書より出題元を探す
3.類題を見つけて解き直す
4.辞書、参考書を調べる
5.さらに、2、3回解き直す
これで、完成と言える。出来る子は、やっている。それが結果に繋がっている。大切なことを理解して「出来る様になりたい」という気持ちが強い子は出来る。勉強を「心の底から頑張りたい」と思っているからだ。本気で取り組む子たちを塾長、副塾長が全力で支える。
2025/5/24

『北風と太陽』
昔、北風と太陽は「自分のほうが強い」と主張していました。その議論に決着をつける為、「旅人のコートを脱がせたほうが強いということにしよう」と勝負をしました。
先攻の北風は、力ずくでコートを吹き飛ばそうと冷たい風を旅人に浴びせました。しかし、旅人はコートをしっかりと掴んだのでコートはびくともしませんでした。
後攻の太陽は温かい熱気を旅人に浴びせました。旅人は暑さに負けて、コートを脱ぎました。(話には続きがある)
さて、小三、小四の授業、算数は「塾長」、国語は「副塾長」が担当する。佐藤進学塾では専任教員二名がレベルの高い授業指導を全生徒に行う。塾長が理系、副塾長が文系担当である。
以前、塾長が北風、副塾長が太陽の役を担っていた。今は二人とも、太陽である。たまに、塾長の北風が吹くこともある。「ビューッ」と。小三、小四の子も、塾に慣れてきた。良い意味、リラックス出来ているが緊張感が薄れてきている。
今一度、大切なことを伝える。
1.正しい姿勢で学習すること
テキストを真っすぐ置いて、背中とお腹にこぶし一つ分あけて、両ひじはつかずに背筋を伸ばすこと。
2.塾長、副塾長の話を真剣に聞くこと
先生の目を見て、一言一句もらすことなく話を一生懸命に聞くこと。特に、副塾長の話をよく聞くこと。
3.問題演習では集中しきること
他の子のことは気にせず、自分のペースで、深く考えて問題をていねいに解いていくこと。
※授業終了時、消しゴムのかすを机の角に集めて、いすを並べてから帰ること。次に来る中学生が気持ち良く使えることを心がけること。自分のことだけではなく他の人の事を常に考えること。
この三点を守る事が出来たならば、勉強は飛躍的に出来るようになる。実際、それを守り勉強している。小学部高学年の子や中学部の多くの子は、全国模試『偏差値65』以上を取得している。中学部の子は8割が該当する。各中学校でも、総合『一位』をはじめ、『上位一桁』の子が多く在籍している。
※については、非認知能力のうちの一つである「他者と協力できる社会的能力」を高めることに役立つ。目に見える学力である認知能力だけを伸ばしても、社会で活躍できる人間になることは出来ない。様々な非認知能力の向上は大変重要である。
2025/5/23

『小4「単位の換算」』
小4は『小数計算』を指導した。小数点を揃えて筆算を行う。縦横のスペースをしっかり取る。繰り上がり、繰り下がりには十分気をつけるように言う。
これらの計算自体は小三の時に指導している。気をつけるのは小数点である。小数点を正しく打つ方法を具体的に指導する。
左手にものさし、右手に鉛筆を持ち、丁寧に筆算をしていく。途中、姿勢を正す様に、何度も指導する。
計算ミスを防ぐには、姿勢が重要なのである。
「目線を水平にする」と判断力が鋭くなる。
姿勢が悪くなり目線が傾くと、左右の目や耳からはいってくる情報に違いが生じる。脳内では情報伝達が困難になり、誤差を補正する必要が出て来る。結果、理解力や判断力が鈍くなり、間違いやミスが多くなる。医師(脳神経外科)が書籍の中に書いておられた。
さて、計算は皆、完璧に習得した。あとは、単位の換算を含む小数の計算である。単位の換算の考え方、小数点を動かす方法を丁寧に教えた。前回の復習をしっかり行っている子はすぐにコツを掴んでいる。
「L、mL、dLを含む計算」
「㎞、m、㎏、gを含む計算」
これらが出来たら完成である。
詳しくは生徒たちに伝えている。
2025/5/22

『あまりのあるわり算』
小三の子に『あまりのあるわり算』の単元を指導する。
「38÷5=」
五の段の九九を考える。
5×1=5、…、
5×7=35、5×8=40
5×7=35
38-35=3
よって、
38÷5=7あまり3である。
確かめは、5×7+3=38
割られる数と等しい。
よって、答は合っている。
この感覚を磨き上げる。その為に、オリジナルプリントを配布した。最初のうちは真面目に取り組むと、一枚、一時間以上かかる。だから、真面目に一枚、やらないでほしい。まず、「5分間」毎日、実施してほしい。一年間続けると、「5分間」で100問、解く事が出来る様になる。
計算スピードは、驚く位に速くなる。継続が大切である。一年間続けた結果、100題を58秒で解く事が出来る様になった子がいた。計算が速くなる『魔法のプリント』である。但し、一年間、継続しないとその魔法はかからない。一年後がとても楽しみである。
2025/5/21
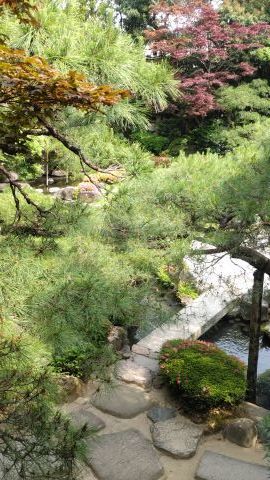
『学力テスト』
附属小学校の六年生は学力テストが年三回実施される。入試を想定した出題範囲の広いテストである。第一回学力テストは、六月初旬に実施される。試験範囲は小五の内容が中心である。
佐藤進学塾では学力テスト対策を行う。まず、制限時間を設定して対策問題を実施する。問題演習後、重要事項解説を行う。附属小学校六年生の子は、「上位十位内」を狙う。
間違った問題は解き直す。
1.問題をノートに写す
2.教科書を調べて出題元を探す
3.解法を詳しく書いて解き直す
理解出来た後に、さらに、二、三回解き直す。テスト前、もう一度解き直して完成する。公立小の子も一緒に行う。公立の子の中に頑張る子がいる。中学校進学後は総合『一位』を取る。
かつて高松高校へ合格、進学した子が小六の時に時間を掛けて復習をしていた。小三、小四の時はいつも泣きながら塾へ通っていた。お母様が必ずお子様を教室まで連れて来てくれた。母親の粘り勝ちである。
「よく頑張るようになったね」
と私が声を掛けたことがある。
「算数が出来るようになりたい」
とこたえたことを思い出す。
愛光高校へ合格、進学した子が小六の時に、毎週、復習ノート一冊を仕上げて提出した。
「なんで、こんなにがんばるの」
と訊いたことがある。
「出来ないことが悔しいんです」
と言ったことを思い出す。
二人に共通していることがある。心の持ち方、気持ちの部分だ。「絶対、出来るようになりたい」という強い思いだ。対策の時、頑張った子は中学部で結果を出している。高松高校へ合格する子は小学生の時に頑張っている。中三になる前段階で頑張っている事実がある。中三時点で大きなアドバンテージがある。
2025/5/20

『先輩方への質問』
佐藤進学塾では、塾の優秀な先輩方へ自由に質問する機会を設けている。先生ではなく、先輩に質問するのである。
「復習ノートを上達させるにはどうしたらいいですか」
「問題の意図を考えて、間違った問題を直すことです」
「意図を考える」ということに、生徒たちは深く感銘を受けていた。実は私も、時々言っているのであるが…。矢張り、身近な先輩から聞くと効果は高い。
「漢字を完璧に覚えるにはどうしたらいいですか」
「まずは、何回も書いて覚えることです。辞書を引くことも、大切です。最後に、私はパーツに分けて覚えていました」
「パーツとは何ですか」
「例えば、へんとつくりを分けて考えます」
「具体的にどういうことですか」
「『記』はごんべんとおのれと覚えます」
「ありがとうございます。すぐ、やってみます」
「どういたしまして」
私も一緒に聞いていて、「なるほど、この子はこうやって覚えていたんだ」と気付いた。
「参考書はどのくらい活用するといいですか」
「中間テストは教科書、ワーク、プリントから出題されます。参考書レベルの内容が、テストに出されることはほとんどありません」
「参考書を使って勉強しなくてもいいのですか」
「もちろん、参考書で勉強することは良いことです。気になる事はその都度、調べるといいと思います」
「よくわかりました。ありがとうございます」
「がんばって、いい成績を取ってください」
佐藤進学塾では時々、この様に優秀な先輩方にいろいろな話を聞く機会を設けている。佐藤進学塾の伝統である。塾では『塾長・副塾長⇔上級学年塾生⇔下級学年塾生』という関係性をとても大切にしている。勿論、本当に困った時は、塾長、副塾長に質問するといい。
2025/5/19

『小学生「算数」』
小学生が、テキストの問題をノートに解いていく過程を見ていると、様々な間違いに気付く。今は全学年、計算演習の単元が主体である。ノートの問題点は以下、三点に集約される。
1.計算力が不足していること
2.ケアレスミスが多いこと
3.単位換算間違いが目立つこと
各々の解決方法を示す。
1.復習時間を増やすこと
2.解く速度を落とすこと
3.反復練習を徹底すること
「あとはやるか、やらないか」
それだけである。
諦めることなく復習を続けていけば、素晴らしい結果が必ず出る。やる気ある小学生は毎週、復習ノートを提出している。ていねいに計算して、間違った原因について深く考えている。私がノートにアドバイスを書いて本人に渡すと、次の週にそのアドバイスに基づき復習を行っている。出来る様になる訳である。
2025/5/18

『最後の総仕上げ』
公立中学生の子たちが、一学期中間テスト前、最後の総仕上げを行った。生徒を迎えるにあたり心をこめて清掃を行う。教室内は勿論、庭も隅々まで綺麗に整える。
「先生、こんにちは」
「ラスト、がんばってね」
「よしっ、がんばろう」
という声も聞こえて来る。
「○○ちゃん、教えて」
と聞いている子もいる。
中二、中三はテスト対策授業に慣れている。サッと、教材を取り出して、勉強を始める。中一もそれを見習い、すぐに試験勉強を始める。
皆が集中し始めると、教室内は凛とした雰囲気が漂う。窓には樹々と花々、芝生の緑が映りこんでいる。少しつかれた時、眼と心を優しく癒してくれる。中二、中三になると、常に手が動き続けている。只管、ノートに問題を解いて、大切な事を書きこんでいる。中一の子たちも見習って集中して勉強している。
佐藤進学塾中学部は、午後9時15分に終了する。終了時刻が決まっているから試験勉強に集中する事が出来る。早い子であれば、午後10時には就寝出来る。中三の子でも、午後11時には就寝すべきだ。
睡眠はとても大切である。
「明日の準備が終わったら、早く寝て下さい」
「はい」
と全員が気持ち良く返事する。
2025/5/17

『集中力』
個人差はあるが、集中力の持続時間は一般的に「一時間」程度である。ところが、一時間最大限に集中しているのではない。
集中力には、「『20分』ごとの波」、即ち、周期がある。20分間は、高いレベルで集中出来る。その後少し落ちてから、再び、20分間集中出来る。
さて、佐藤進学塾のテスト対策直前期間は「三時間」集中して学習する。理に適っているのである。
「20分×3周期」×3セット
「長時間、だらだら勉強しても意味はない」と、私は考える。
普段の平常授業では、「20分×3周期」の「2セット」である。テスト前対策授業は、「20分×3周期」の「3セット」である。
この位が、最も効率良く学習出来る。決めた時間ゆえ、ゴールが明確に設定されているので集中出来る。また、ゴールへ向けてしっかりとギアを上げていくことができる。集中力の持続時間「1時間」を基準とする。それを「3セット」行う。家へ帰って、ひと休みする。その後、再び「3時間」復習を行う。
家では声を出して、体を動かして、積極的に勉強出来る。自転車、徒歩の子は体を動かすので特に良い。書籍『運動脳』にも、そのあたりのことについては詳しく書かれている。空間を変えることで、ガラリと気分が変わる。「学校、塾、家」、それぞれの場所で集中する。同じところでは脳が飽きるのである。
佐藤進学塾は「家、学校でも集中して勉強出来る」子たちの集団である。佐藤進学塾の集中力を「10」とする。家での集中力は「7」位になる。そのギャップがいい。高い集中力を維持することは難しい。塾では、友人と競って学習する。家では、一人集中して学習する。切り替えが大切であると私は考えている。
2025/5/16

『中間テスト対策完成』
中学生は五月初日より、中間テスト対策を開始した。連休中の祭日、一日も休むことなくテスト対策授業を実施した。附属中は中間テスト未実施だが、一緒に行った。
中二、中三の子たちは対策にも慣れているので自分で準備して能動的に学習を行っていた。素晴らしいかぎりである。中一の子たちにはテスト勉強について詳しく説明した。
最初のうちは少しばかり注意する場面もあったが、三日も経つと上級学年の子たちを見習って集中して勉強する様になった。毎回、学習状況を私が一人ひとり確認しながら行った。
土曜日には中二、中三、日曜日には中一の子たちと個人面談を行い、テスト勉強の進行状況を確認して、私が改善すべき点を具体的に指示した。その後、気掛かりなことを訊いて、問題点は安心できるまで話し合いを行って解決した。
テストが終わった、今、少しばかりゆっくり過ごすと良い。部活の練習に励むのもいいし、読書を愉しむのもいい。自分の好きなことを、好きなだけやればよい。来週火曜日からは中学生の全学年、予習授業を行う。中一は文字式、中二は一次関数、中三は二次関数である。三週間後は、期末テスト対策に入る。
さて、連休中は小学部の子たちも祭日も休むことなく授業を実施した。佐藤進学塾、殆どの生徒が一日も休むことなく授業に参加して一生懸命演習へ取り組んでいた。此方も素晴らしいかぎりである。ご理解、御協力頂きました保護者、そして、一生懸命頑張った生徒たちには心より感謝している。
2025/5/15

「音読→書写→反復」の流れを完成させて、すべて暗記する。漫然と行うと作業化する。作業化すると学習効率は下がる。
「作業化を防ぐには」
気になる事を教科書で調べる。
国語、英語は辞書を活用する。
難しいことは参考書を調べる。
「調べて、考えることを挟む」
そうすると、作業化しない。
脳をフルに使っているからだ。
参考書を活用して学習する子は深く考えている。ただ、中間テストに参考書レベルの問題は殆ど出ない。だから、テスト前はそこまでやる必要がない。しかし、出来る子はそこまでやる。物事の本質を根底から理解したいという探求心が強いからである。
真剣に取り組んでいても、何回も繰り返し間違える問題がある。その都度、調べて、考えて、理解を深めていく。そして、再び、問題演習を行う。最後には解法、解答を完璧に覚えてしまうくらい勉強することが重要だ。今週は教科書、ワークの内容を一言一句違わず覚えてしまう。
「記述はどうすればいいですか」
と言う質問があった。
高松市の中学生、中間テストでは教科書の通りに答を書く必要がある。学校ワークの解答通りに答を書く必要がある。一生懸命自分で考えても曖昧な記述の答えは×となる。出題意図とは異なるとみなされるからである。教科書、学校ワークを完全に覚えよう。暗記しなければ、満点を取ることは出来ない。
勿論、塾の平常授業では応用・発展的な内容を指導する。暗記では対応出来ないレベルだ。それは、中間テストが終わってからの楽しみにしておく。「脳から汗が出る位、一生懸命に考えよう」。
2025/5/14

『「六月号」の書類』
六月号の書類を大きい封筒に入れて、塾の生徒たち一人ひとりに手渡した。
1.夢つうしん
2.開講より二か月が過ぎて
3.夏期講習会予定(二枚綴)
4.期末テスト対策(中学部)
一人ひとりに宛てた
手紙と共に同封している。
毎日発信する「塾長ブログ」
毎月送付する「各種プリント」
お子様と一緒に読んで頂きたい。
親子でしっかり読んで
それを実行している子は
実力が飛躍的に伸びている。
2025/5/13

『「五月病」と子どもの関係』
連休明けは疲れが出やすい。「連休は体を休める時期である」と考える。実際、賢い子の家庭はそうしている。しかし、長期旅行などへ出かけた子の疲れはピークに達している。
親は「お金と時間をかけて、皆で楽しいことをしたのになぜ」と言うが、それは思い違いだ。
五月病のような症状をお子様は怠けていると、親は考えがちである。しかし、それは違う。真面目な子ほど連休を機に緊張の糸が切れやすいのである。
新年度が始まり、クラスや担任が替わる環境の変化を受けとめ前向きに取り組んでいる子供達だが、多くはストレスをため込んでいる。少し我儘になったり、勝手なことを言ったりする。
ここで、親が怒ってはいけない。
「では、どうすればよいか」
お子様とのコミュニケーションでは肯定も否定もすることなく、お子様に気持ちを思い切りはき出させることが大切になる。おうむ返しや相づちに加えて、「○○ちゃん、それはつらい気持ちになるね」などと共感するなど、子どもの気持ちをそのまま受け止めてあげるとよい。
間違っても、「□□ちゃん、そんな時はこうすればいいのよ」などと親の考えを押し付けてはいけない。
絶対に避けたいのは保護者が余裕を失いヒステリックになり、子どもに更なる負荷をかけることである。お子様は完全に心を閉ざしてしまう。ほとんどの場合、お子様は否定されずに親に話を聞いてもらうだけで気持ちが軽くなるので、保護者様には傾聴をお願いしたい。
大人の五月病は集中力の低下やうつ状態などが前面に現れるが、子どもは自分の精神状態を説明する力が弱いために発熱や腹痛など身体の症状となって出やすいのである。お子様、一人ひとりの体の弱い部分に症状が現れる。頭が痛い子、お腹が痛い子、熱が出る子、倦怠感が出る子など様々だ。
長く続いたコロナ禍の生活で、親も子も相当に疲れはたまっている。休みには、心と体をしっかり休めることを心掛けてほしい。睡眠時間をたっぷり取ること、良質な栄養をしっかり摂ることに気を遣ってほしい。賢い子というのは、普通の生活の中で親が穏やかに関わってくれることが一番うれしいのである。
2025/5/12

『修学旅行』
中三の子たちが、修学旅行へ学校別に次々と行っている。皆、「とても、楽しかった」と言ってお土産を買って来てくれる。早速、他の学年の子にお裾分けする。
「ありがとうございます。ぼくたちも、来年は沖縄に行けるのですね」とニコニコしながらお土産を受け取っている。
実は、地元の中学校の子が、一時間前に沖縄から帰ってきた。出発前、「帰宅日はしんどかったら休んでゆっくりしていいよ」と私は生徒に言ったのだが、何と、全員出席している。
「今日はあまり無理しなくていいから、二時間、頑張ることの出来る範囲で頑張ってね」と言うと、みんな「大丈夫です」とこたえてくれた。
今日は、中二の子たちも特別対策授業へ参加している。地元、中学校の子たちは、今日が修学旅行の帰宅日であることを知っているので、疲れているのに全員が対策に参加していることに驚いていた。それと同時に、中間テストとテスト対策の重要さを改めて感じていた。
2025/5/11

『芝生と皐月』
今日、日曜日は、公立中学校テスト対策だ。中一の子たちは、初めてである。上級学年を見習い、集中して頑張っている。
中二、中三は鉛筆が常に動いている。机に置くことなどない。鉛筆を動かした分だけ点が伸びる事実を体感しているからだ。
塾庭の芝生が青々としてきた。皐月の花も一斉に咲き始めた。緑と赤のグラデーションが美しい。
「芝生がきれいですね」
「教室が明るいですね」
「花が色々咲いてますね」
生徒たちが口々に言う。
静かに眺めている子もいる。
かつて勤務していた京都市の学習塾で「どのような塾が理想ですか」とアンケートを取ったことがある。「芝生があって、木がある塾」と言う意見が生徒たちから出た。当時、塾は三条通りに面したビルの中にあった。塾は右京区嵯峨、嵐山に近い風光明媚な地にあったが、塾自体は緑とは無縁であった。
高松市で進学塾を設立する時、親友の兄で一級建築士の大山健先生にお願いした。建物は安全な造りで、自然素材を多用したもの。東面はガラス張りで教室の中が明るいこと。庭は煉瓦と枕木を据えて、芝生と木を植えること。緑は、生徒たちの目に優しい。自然は、生徒たちの心に優しい。
書籍に「緑を目にしながら勉強を行うと、パフォーマンスが約『25%』上がる」という記述があった。
2025/5/10

『内申点について』
中一の生徒たちは初めてのテスト対策である。中間テスト勉強の具体的な方法、大切な内申点について話をする。
まず最初に、
『原則的学習』の話を行う。
1.教科書の音読と書き写し
2.学校ワーク類の反復練習
3.学校ノート・プリントの暗記
以上、詳しく具体的に話を行う。附属中の子は、実練とワークシートもある。今年度、中間テストはない年だが、公立の子と一緒に話をする。具体的な事は生徒たちへ丁寧に伝えている。
次に、内申点の話をする。
中1 45㌽
「5×9教科」
中2 45㌽
「5×9教科」
中3 130㌽
「10×5教科+20×副教科」
(五科は2倍、副科は4倍)
内申点合計は「220㌽」、入試得点合計は「250点」である。これら二項目の詳細を相関表へ記入後、面接の得点を加味して合格が決まる。中一の内申点が反映される。拠って、中一から受験は始まると言える。高松高校、過去三年合格者全員200ポイントを超えている。8割の子が、210ポイントをクリアしている。
中三で内申点が急に上がる子はいない。中一、中二、中三でバランス良く取っている。中一「41」、中二「42」、中三「130」の子が多い。中一、二は「4」がある。ところが、中三はオール「5」にしている。
これが合格する子の典型である。
中三は本気で頑張る。中一、中二でも、やるべきことをやっている。中三で、逆転など起こらない現実を伝える。中一、中二、内申36とする。オール4、頑張った結果だ。中三で頑張りほぼオール5、「120」を取ったとする。凄い頑張りであるが、合計は「192」だ。内申点合計200㌽は越えない。
最後は、「疑問・質問・ドラえもん」。生徒の質問に丁寧にこたえる。現時点での真実を出来る限り正確に伝える。高松高校へ合格する子は中一、最初の中間テストから原則的学習を真剣に行っている。保護者様のご理解とご協力を犇々と感じる。
具体的且つ丁寧に説明するのだが、残念な質問をする子もいる。
生徒「私は教科書の書き写しは苦手です。他のやり方はありませんか」
塾長「天才でない限り、他のやり方はありません。教科書の書き写しをしている子は、上位十位内である事実を言っているだけです。『無理にやれ』とは言いません。先生の話を聞いて、『よし、やってみよう』と思う子は、素直にやればいいだけです。要は、あなたの集中力とヤル気に掛かっています」
昨年に引き続き、今年も佐藤進学塾生の高松高校受験者全員が合格した。高松高校受験専科進学塾としてから114名、生徒の9割超が高松高校へ合格している。しかも、この子の上の子も佐藤進学塾から高松高校へ合格しているのだが…。
2025/5/9

『データとグラフ』
小四、算数が進んでいる。
データとグラフの単元に入った。
グラフの目盛りに注意する。
一目盛りが「1」とは限らない。
5目盛りで100gならば、
1目盛りは「20g」である。
5目盛りで500gならば、
1目盛りは「100g」である。
北半球と南半球の都市について、一年間の気温の変化のグラフが示された練習問題がある。北半球は夏のとき、南半球は冬になる。気温のグラフは山と谷になる。
このあたりの話をすると、皆、興味津々である。
「日本でサンタさんは、何に乗って来るかな」
「トナカイです」
「オーストラリアのサンタさんは、何に乗って来るかな」
「サーフィンに乗ってきます」
二人の子が直ぐに答える。
「さて、なぜ、季節が反対なのかな」
「北半球と南半球で太陽の光があたる角度がちがうからです」
すぐに答えられる子がいる。
様々な事に興味を持つ子は、将来がとても楽しみである。
2025/5/8

『一日「二十四時間」』
佐藤進学塾にはいくつかのルールがある。生徒みんなが気持ち良く勉強できる大切な学習環境を守る為だ。時間については、少し厳格である。時間は最も大切であるからだ。
授業開始時刻の15分~20分前に、生徒全員が教室へ集合する。そして、ウォームアップを行う。進学塾の友人たちと話をして、リラックスしてもいいと考えている。
ハイレベルな授業を二時間行い、規定時刻五分前に必ず授業を終える。私たちが時間を守る。生徒たちも時間を守る。
生徒の帰宅時、天候が急変する時もある。想定外の事が起きる時もある。それらを見越して、五~十分前に授業を終える。
それから友達と話をしたり、ゆっくり片付けをしたりしても、既定時刻に帰ることが出来る。お迎えの保護者様も帰宅を待つ保護者様も安心である。
静謐な学習空間という最高の環境を創り上げる。それには、塾生みんなが時間を守ることが大切になる。
「佐藤進学塾はヤル気が出る」
生徒たちがいつも言う言葉だ。
「佐藤進学塾は成績が上がる」
保護者様からよく聞く言葉だ。
時間は全世界共通、一日二十四時間、全人に対して平等に時間が与えられている。時間をどう使うかは個人の自由だ。しかし、使い方に拠って人に迷惑を掛けることもあれば、周りの人に喜ばれることもある。
佐藤進学塾は、「『時間』を大切にする塾」である。時間を大切に考えるお子様の為に、静謐な学習環境を守り抜く。決められた時間、集中して学習することで一人ひとりが最高の結果を出す。
この様な考え方は「少し変わっている」と言われることもある。先日、書籍を読んでいて気がついたことがある。塾長である私が、時間の使い方、学習方法、整理整頓、プロセスの改善等々、一般的な日本人の発想とは異なり、ドイツ人の発想に大変近いことである。時間使いと整理整頓はまさにドイツ人だ。
日本の名目GDPは世界四位に転落した。変わって、TOP3入りしたのはドイツである。ドイツ人の働き方として特徴的なのは日本人に比べて少ない労働日数、労働時間で成果を出している点である。その労働生産性は日本と比べて実に約1.5倍である。学習生産性にも共通することが多くあるようだ。
2025/5/7

『内申点について』
中一の生徒たちは初めてのテスト対策である。中間テスト勉強の具体的な方法、大切な内申点について話をする。
まず最初に、
『原則的学習』の話をする。
1.教科書の音読と書き写し
2.学校ワーク類の反復練習
3.学校ノート・プリントの暗記
詳しく具体的に話を行う。附属中の子は、実練とワークシートもある。今年度、中間テストはない年だが、公立の子と一緒に話をする。具体的な事は生徒たちへ丁寧に伝えている。
次に、『内申点』の話をする。
中1 45㌽
「5×9教科」
中2 45㌽
「5×9教科」
中3 130㌽
「10×5教科+20×副教科」
(五科は2倍、副科は4倍)
内申点合計は「220㌽」、入試得点合計は「250点」である。これら二項目の詳細を相関表へ記入したあと、面接の得点を加味して合格が決まる。
中一の内申点が反映される。拠って、中一から受験は始まると言える。高松高校、過去三年合格者内申点も伝える。皆、200ポイントを超えている。8割強の子が、210ポイントをクリアしている。
中三で内申点が急に上がる子はいない。中一、中二、中三でバランス良く取っている。中一「41」、中二「42」、中三「130」の子が多い。中一、中二は「4」があるが、中三はオール「5」にしている。
これが合格する子の典型である。
中三は本気で頑張っている。中一、中二でも、やるべきことをやっている。中三で、逆転など起こらない現実を伝える。逆転に見える様な現象は起こるが、それはレアケースである。
中一、中二、内申36とする。オール4、頑張った結果だ。中三、本気で頑張りほぼオール5、「120」を取ったとする。凄い頑張りである。ところが、合計は「192」だ。内申点合計200㌽は越えない。
最後は、「疑問・質問・ドラえもん」。生徒の疑問・質問にていねいにこたえていく。現時点で正しい事実を出来る限り正確に伝える。高松高校へ合格する子は、中一、最初の中間テストから原則的学習を真剣に行っている。ご家庭の方のご理解とご協力も犇々と感じる。
生徒「私は教科書の書き写しは苦手です。他のやり方はありませんか」
塾長「天才でない限り、他のやり方はありません。教科書の書き写しをしている佐藤進学塾の子たちは、成績上位者一覧の通り、必ず、上位十位内に入っている事実を言っているだけです。『無理にやれ』とは言いません。要は、あなたの集中力とヤル気に掛かっているということです」
2025/5/6

『中間テスト対策』
連休中であるが、今週は月曜日からは実践テスト演習を行う。数学、英語から順番に進める。今回は中間テストを実施しない附属中学校の子も一緒に行う。大切なことを再確認する。
1.教科書の音読と書き写し
2.学校ワークの演習と反復
3.ノート・ワークシートの暗記
これらを丁寧に行い、実践演習の内容を完璧に復習する。そうすれば、テストでは100点を取ることも可能だ。当たり前のことを当たり前にやるだけである。
中学校の中間テストは、教科書の隅々までていねいに覚えなければならない。理解することはもちろん大切であるが、最終的にはすべて覚える必要がある。
教科書を隅々まで覚える。学校ワークの解法・解答を覚える。ノート、ワークシートの内容を覚える。
あとは、実践演習で時間配分を身に付けて、問題の出題傾向を知る。間違った問題は分かるまで教科書を調べる。覚えて、理解して、完璧に覚える。注意すべき具体的なことは授業中に直接皆へ伝える。全力で頑張って最高の結果を出そう。中間テスト日までは中学校のテスト範囲のテスト勉強に専念するとよい。
2025/5/5

『学校行事予定表』
小学校、中学校の行事予定表を確認することが出来た。それをもとに、講習会、テスト対策等の日程を決める。
佐藤進学塾、2025年度の日程、詳細予定を順番に決めていく。夏期・冬期講習会、テスト対策の予定は、保護者様にプリントでいち早くお知らせする。
原則として二か月前までに、遅くとも一か月前にお伝えする。毎月、「A3大判の封筒」に各種書類をいれて二十日頃までに、生徒さんへ直接お渡しする。
保護者様に、早めのお知らせは喜ばれる。家庭の予定を立てやすいからだ。各学校、各種行事が実施される日常が戻った。学校は口頭による伝達も有り、私が全て把握する事は出来ない。
学校行事により、塾を遅れたり休んだりする場合、『メモ書き』を副塾長へご提出願う。宿泊学習などの場合、『予定表コピー』を添えて頂きたい。(口頭では間違いが起こりやすいこと、ご承知願いたい)
「分かった時点」と「近づいて来た時点」の二回、副塾長へお知らせ頂くと有難い。
小中七学年、十小学校、七中学校ゆえ予定表の各日程は複雑極まりない。よろしくお願いしたいと思う。
2025/5/4

『本当に勉強が出来る子とは』
勉強が出来る子というのはまず、「『学校』での勉強」を大切にする。基礎、基本を学ぶことが出来るからだ。学校の先生方、共に生活する友人との関係性をとても重視している。
次に、「『進学塾』での勉強」を大切にする。発展問題の解法を学び、応用力を伸ばすことが出来るからだ。塾の先生、同じ夢、目標に向けて頑張る友人を心より尊敬している。
そして、「『家庭』での勉強」を大切にする。周りを気にせず、大きい声で音読しながら自由に勉強出来るからだ。何より、心の繋がりの最も強い家族との生活を大事に考えている。
「家では勉強する気がしない」
この様なことを言う子は、勉強が出来る様にならない。本当に勉強が出来る子というのは、家で、集中して復習をしている。毎日、必ず、『二、三時間』集中して行っている。
「集中して」と言っても、黙って、座って、難しい顔をして、必死に勉強しているのではない。三時間のうち、二時間は音読して理解している。一時間は調べて理解を深めている。教科書、辞書、参考書の問題、解法、すべて音読している。同時に、ひたすら手を動かして文字を書いている。
大事な事を覚える時には、自分で『替え歌』をつくる。それを歌いながら、覚える。歌に振り付けを考え、ダンスしながら覚える。出来る子と言うのは、このような勉強をしている。「手、目、耳、口、体」、五感と全身を使って勉強する。
これらは、家でやるべきことである。これは塾では出来ない。塾でダンスされては困る。新単元を習う時は、座って集中して聴く必要がある。だから、佐藤進学塾の中学部は、週三日の通塾を義務付けている。それ以外は三日間、家で五感をフルに使って復習すべきだ。あと一日は、思いっきり遊べばいい。
スポーツ、楽器、読書、絵画、…。自分が好きなことをすればいい。出来る子は、好きなことも納得いくまでやっている。毎日、塾で「黙って長時間、勉強しろ」などと言う気は全くない。出来る子は、学校、塾、家での勉強すべてを大切にしている。塾だけに偏ることは無い。
現代社会はかつてないスピードで変化している。「働き方改革」と言う言葉が世間に根付いて来た。只管長時間働いて成果を出すという事は否定的に捉えられる様に変わった。「長時間学習して成果を出す」という時代も終わった。近いうち、「学習方法改革」と言う言葉が聞かれるようになるだろう。
佐藤進学塾では、貴重な時間を最大限大切にして最高、最良の指導を続けていく。
昨年、卒業生の国立大学医学部医学科の子が遊びに来た。
「私、何でも完璧に理解しないと気が済まないんです。でも、長時間だらだら勉強するのは嫌で、時間を決めて集中して行う佐藤進学塾の勉強方法はとても合っていて、今でも続けています」と言った。
2025/5/3

『音読の上達』
音読は、黙読で起こる読み飛ばしがなくなる為、文章を丁寧に読む事が出来る。また、自分の声を通して耳からも情報が入る為、目から情報が入るだけの黙読より情報量が圧倒的に多い。
その為、学習内容を上手に整理することが出来るようになり、文章の理解が深まる。また、文章を音読する事で語彙や表現を感覚的に理解出来る為、語彙力及び表現力が大きく向上する。
1.すらすら読む事が出来る
2.心を込めて読む事が出来る
3.理解してから読む事が出来る
上記の様に音読が上達すると、明らかな学習効果が出始める。
塾長「次は良い結果が出るよ」
生徒「えーっ、本当ですか」
音読が上達する瞬間がある。
私は決して見逃すことはない。
「巧くなった」と思う日がある。
「上達したな」と思う日が来る。
日々、1ミリずつ上達する。
努力を続ける事で、ある日、それが100日で100ミリ、1000日で1000ミリ=1メートルに達する。そこまで来ると、突き抜けた感じがする。およそ三年掛かるわけだが、素晴らしく上達するのである。
生徒「成績が上がりました」
塾長「それは、よかったね」
「先生が言った通りです」
「真剣に努力した成果だよ」
「ありがとうございます」
「無理をしないようにね」
具体的な上達の基準とは何か。
1.句読点で息継ぎをして、ゆっくりと読むことが出来る
2.漢字を正しく読み、助詞を正確に捉えることが出来る
3.心を込めて、感情を文章に合わせて読むことが出来る
まずは技術的なこと、漢字、助詞、句読点である。そして、感情的なこと「心をこめて」ということだ。読み間違いをおそれず、ゆっくり読むことが大切だ。最後に、自分の心を込める。
音読が下手な子は、読み間違いをおそれて速く読む。拠って、なかなか上達しない。間違ってもいいから丁寧に読む。句読点で息継ぎしてゆっくりと読む。「少し、上達したな」と思ったら、心を込めて読む。
保護者様も、ご協力頂きたい。一緒にお子様のペースで読んであげてほしい。音読が上手くなると、必ず勉強が抜群に出来る様になる!
教育に関する真実を、これからも出来る限り正確に伝えていく。佐藤進学塾が目指す教育に関しての真実である。毎日、『コラム』を一つ掲載、愚直に続けていく。継続することこそが、私は大切と考える。
2025/5/2

『連休中の平常授業』
佐藤進学塾では連休中も平常授業を行う。学習はリズムが大切である。塾の平常授業があると学習リズムは良い状態に整う。
佐藤進学塾の子はその辺りの事が分かっている。ほぼ、全員が出席している。普段通りに学習へ集中している。
特に、中学生は連休明けに中間テストがある。その大切さがよく分かっている。中一の子は初めてのテストだ。
テストの大切さは頭の中では分かっている。だが、心の底からは分かっていない。先日から、時間をつくりテストの大切さを伝えている。具体的に詳しく話をしている。
「難しい問題を中心にテスト勉強した方がいいのですか」
「出題は基本問題が中心、教科書中心にしっかり学習しよう」
「塾のテキストは復習しなくていいのですか」
「テスト前は、学校のワークを中心に繰り返し復習しよう」
「学校の先生が言ったことをメモしています。それもテストに出ますか」
「素晴らしいことです。学校の先生の話をよく聞くことは大切です。それはテストにも出ます」
「他の問題集などを買った方がいいのですか」
「学校のワークだけで十分です。あと、学校のノート、プリントの内容も大切です」
「睡眠時間を減らして勉強すると友だちが言っていました。そこまで、がんばった方がいいですか」
「睡眠は最も大切です。睡眠を削ってまで勉強する必要はありません。睡眠時間を確保しましょう」
中二、中三は言わなくても分かっている。既にテスト勉強を始めている感がある。素晴らしいことだ!
2025/5/1

『読書の重要性』
佐藤進学塾には、読書が大好きな子が多い。ところが、読書が大好きだからといって、国語力が高いとは限らない。国語力を高めるには十分な問題演習が必要だ。
読書は「インプット」、演習は「アウトプット」にあたる。両方が成立して初めて読解力、即ち国語力は高まる。辞書の活用による語彙力の強化も必須と言える。
それはさておき、読書が大好きな子はみんな、飛躍的に学力が伸びる。読書は「心を高く押し上げている」と私は考える。
心と学習意欲は、車の両輪の様なものだ。ヤル気がある子は、勉強が出来る様に成る。そのヤル気は心から生じるのである。
生き生きとした心の子は、人の話をとても素直に聞く。聞いた話を直ぐに実行へ移す。諦める事無くそれを継続する。
学習面においても、多くの恵みをもたらす。語彙力、読解力、思考力である。他にも想像力、知的好奇心などがある。早期教育を行っていても、結果が出ない子は多い。親が読み聞かせや読書を行っていないことが要因で、作業の様に学習を行う習慣が身についている。お子様にとって、面白みがないわけである。
ところが、読書好きな子は様子が違う。最初は理解が遅くても、後々、驚く程出来る様に成る。連休中は、大いに読書を楽しむと良い。そして、それを趣味にすると良い。豊かな人生を送ることが出来ることは間違いない。何より、読書が好きな子は笑顔が素敵で、非認知能力のコミュニケーション能力が高い。
2025/4/30

『大型連休』
佐藤進学塾では連休中も平常授業を実施する。祭日であっても、普段通りに授業を行い学習のリズムを整えていく。
中学生は五月中旬に中間テストがある。今大切なことをいつも通りにきちんとやっておけばテスト前にあわてることもない。
テスト前には試験対策授業を行う。しかし、長時間、無理して詰め込みの勉強をさせる事はしない。その様な事をしても理解は非常に浅い為、すぐに大切なことを忘れてしまう。
何より普段の積み重ねが大切である。スポーツでも、芸術でも普段から練習を積み重ねている人が真に凄いのであり、試合や発表会直前に慌てて練習する人の実力は知れている。
ところが、勉強になると、テスト前だけ勉強して結果を出そうとする人が意外にも多い。とても、残念なことである。
勿論、そういう考えの人は佐藤進学塾にはいない。普段を大切に学習していく子の集団である。思う様な結果が出なくても、普段の復習を重ねていく事で結果はいずれ出る。一度良い結果が出ると安定する。
毎年、連休中に授業を行っているが休む子は殆どいない。特に結果が安定している子は休まない。大切なことは普段にある。普段を大切にする子が大成する。そのようなお子様を応援する保護者様の集団ゆえ、私たちも安心して授業指導を行うことができる。ありがたいことである。
2025/4/29

『中三「二次方程式」』
中三、二次方程式の単元が終盤に差し掛かった。二次方程式の利用、まとめB問題を終えて探求問題に入った。探求問題は、入試レベルである。難易度は高い。今週、完成させる。
二次方程式の計算には因数分解、平方根の知識を使う。利用は文字式を立てる時に小学生の知識を多く使う。意外なことだが事実である。式を立てたあとは、中三の知識をフルに使う。
速く解く為には、高一の知識も必要であるから、それも生徒たちに指導していく。「これは高一の公式だからね」と言うと、皆、習得して解法の過程においてうまく使いこなしている。
小四、小五から継続通塾している生徒が大半だから、小学生の知識はしっかり頭に入っている。「小四と小六の知識を使うよ」と言うと、皆、すぐに思い出して条件を整理している。
中三のハイレベルな数学の問題を指導していると、積み重ねの大切さを心底感じる。小学生の知識が完全習得出来ていないと解く事は出来ない。そこを甘く見ている人がとても多い。
「夏休みに頑張れば、取り戻せる」と軽々しく言う大人が地方には多いが、それは無理だ。小学生の知識は小学生の時に得なければならない。頭が柔らかい小学生のうちに取り入れるべき知識は後から勉強しても入らない上にうまく使えない。
私自身、広島市在住時に進学塾で算数の基礎をたたきこまれた。発展問題をすべて習得する為にひたすら復習した。国語は辞書を活用して声を出して学習した。理科、社会は出来て当たり前だった。
家から坂を下り、バスで片道一時間かけて通塾するのは大変だったが、国鉄で片道二時間掛けて通っている子もいた。私がバスを降りてから、さらに三十分掛けて家に帰る友人もいた。
その友人の名を今も覚えている。沼田の半田くんだ。消しゴムに、「ハンダ・ハンダ」とカタカナで大きく名前を書いていた。それが、消しゴムだけに消えかけて、汚れて「パンク・パンダ」と見えたので、皆から「パンクパンダ」と言われていた。本人は「ハンダじゃけん」といつもおこっていた。昔話だ。
だから、今、完璧に指導できる。
進学塾の先生には感謝しかない。
凄い仲間たちと凄い指導を受けた。
難易度の高い二次方程式の問題では、小三から高一までの知識を組み合わせて解く必要がある。今後は、二次関数、図形の相似でも同じであると言える。夏休みに頑張っても取り戻す事の出来ない部分がある。
佐藤進学塾の子たちは積み重ねが出来ているので、答えを論理的に導き出すことができている。流石に、普段と違い時間が少し掛かっているが、確実に答えを導き出すことが出来ている。素晴らしい!
『余談』
当時、数十年前、パンクパンダこと、半田君の住む沼田はド田舎であった。ところが、今はモノレール・アストラムラインが通り、高級住宅地と変わり様子が一変して驚くばかりである。 ここ、松縄も二十年前、周りは田んぼだらけだった。レインボーロードが開通して、今は閑静な住宅地に変わった。
2025/4/28

『「全国模試四月号」結果』
先週後半、全国模試の四月号結果を生徒一人ひとりに具体的なアドバイスをしながら手渡した。
「よしっ」
思わず、声が出る子もいる。
「ニコッ」
と笑顔に成る子もいる。
「うーん」
悔しそうな子もいる。
およそ8割の子が、偏差値「63」を超えている。偏差値「70」を超えている子も多くいる。
佐藤進学塾では偏差値「50」台からスタートの子が多い。生徒みんなが「5~15」偏差値を上げていく。「良く努力を続けてきた」と毎年のことだが、心底思う。中三、受験生の子が集大成として、素晴らしい結果を出す。やがて、その子たちが巣立つ。
「新年度の子はどうかな」
と思ってみていると、
新学年の子たちが全力で頑張り始める。佐藤進学塾の伝統である。凄い結果を出す子が卒業すると、それに続く新たな子が出て来る。今年度も高松高校を受験した塾生全員が合格した。それに続く子たちが新たに出て来るのだ。
「優秀者一覧に載ったよ」
と伝えてあげる。
「ありがとうございます」
と嬉しそうにこたえる。
結果を出すまで、地道に頑張った事を知っている。家族の方も全面的に協力して頂いた事を知っている。私達は、感謝の気持ちしかない。
「偏差値70を超えたよ」
と副賞を進呈、褒めてあげる。
「勉強の面白さが分かりました」
と力強く言葉を返してくれる。
偏差値70を超えると自信がつく。プライドが人一倍、高くなる。凄まじく集中して結果を出す。佐藤進学塾の高度な授業を一言一句もらさず真剣に聴く。塾がない日は家庭で三時間集中して復習する。間違った問題は三回反復する。調べて考えて、書いて覚える。音読、書写、反復を徹底する。
結果を出す子は、塾でも家でも頑張る。家では声を出して学習する。ロケーションを変えることで集中力は驚く程に高まる。佐藤進学塾には「家では勉強出来ない」など言う子はいない。偏差値68に達するまではみんな凄く努力している。集中力と結果は簡単に得られるものではない。一度手にした子は放さない。
今回、成績上位者一覧に掲載されていない子も、正しい努力を続けると良い。模試成績表にヒントがたくさんある。塾長と副塾長はそれを手にするまで応援を続ける。現高二が小学生の時、成績上位者一覧には一人もいなかった。小六で五割の子が載り、中二で全員が載った。そして、全員高松高校へ進学した。
2025/4/27

『天才と秀才2』
(昨日の続き)
天才型と秀才型、
「どちらが良いか、すごいか」
などと言うのは決められない。
たまに、天才型の子で努力を厭わない子がいる。音読、書写、反復を楽しんで行う子がいるのだ。ただ、音読が非常に上手く、書写を行う時に深く考えるので、反復練習は少ない回数で済む。その様な子は驚く位に良く出来る様に成る。このタイプの子には、秀才の子が努力しても勝負にならない。
しかし、人生を長いスパンで考えてみる。中、高、大学生あたりまでは、勝負にならないかもしれない。ところが、二十年、三十年と言う長いスパンで考えると、30歳、40歳になった時、努力を重ねている秀才が成功する事例は多くある。ちょうど、社会で働き盛りと言われる年代である。
社会的に成功している人たちもよく言う。
「能力の差などというものは意外に小さい。ところが、熱意の差は驚く位に大きい」
(京セラ創業者、故稲盛氏)
「私は、人の十倍努力してきた。『すぐやる、必ずやる、出来るまでやる』」
ニデック(日本電産)創業者の永守氏もこの様に公言している。『すぐやる、必ずやる、出来るまでやる』は名言である。現在、会社経営はサポート役として関わりつつ、私費を投じて設立した京都先端科学大学で理事長として世界に挑戦できる人財や自ら起業したいと言う夢のある人財の育成に尽力している。
正しい努力を続けるといい。その努力は人の二倍、三倍行わなければならない。最初のうちは大変だが、継続することで効率良い学習が出来るようになり、素晴らしい結果が出る。やがてその努力は楽しみへと変わっていく。努力を努力とすら思わなくなる。佐藤進学塾はそういう子を最大限に応援していく。
その努力の方法は私が具体的に伝える。それを素直に聞き入れて実行に移すことが大切なのは言うまでもない。一昨日、中二の生徒たちに話をした。中二の子はかつて小学生時分、全国模試の成績上位者が一人もいなかった。それが、正しい努力を重ねていくことで、今では、8割の子が上位者に名を連ねている。
2025/4/26

『天才と秀才1』
天才は文字通り天から授かった才能、生まれつき備わっている先天的な能力のことである。
秀才の才能は、後天的に得られたもの、すなわち自らの努力によって得た能力のことである。
天才は教科書を一、二回読むだけで、テストは100点を取る。秀才は教科書を音読、書写、反復してテストは100点を取る。生まれつきの才能と努力で得た才能には大きな違いがある。
佐藤進学塾は秀才型の子が多い。
天才の子は短い学習時間でテスト結果を出す。重要語句などは教科書やテキストを一回読むだけで覚える。拠って、発展問題に取り組む時間的余裕がある。
秀才の子はテスト結果が出るまでに少し時間が掛かる。時間的余裕がない為、発展問題の演習が不十分であることも多々ある。重要語句は三、四回書くことによって初めて覚えることができる。
「では、天才型が良いのか」
「そうとは、言い切れない」
天才の子は学習内容を始めあらゆることをコピーマシンであたかもコピーする様に覚えることが出来る。従って、辛い事、嫌な事も直ぐ覚えて忘れない。必要な事も、不要な事も瞬時に覚えてしまう。秀才の子はすべての事を一旦忘れる。嫌な事など一晩で忘れてしまう。必要な事だけ覚えていくことが出来る。
天才は地道な努力を嫌う傾向がある。音読や調べものは好んで行うが、書き写しは嫌がる。その様な子は中二、高二で伸び悩む子が多い。理解出来ていても、テストの時に解答を上手く答えられなくなるのだ。「手で様々なことを繰り返し書く」ということには人として大きな意味がある。
秀才の子は努力を厭わない傾向にある。音読、書写、反復といった努力をする子は、中二、高二あたりからグングン伸びていく。中二、高二という学年は理屈で考える内容が急に増える。暗記で押し切きることができなくなる。考えて、調べて、自分の手で書いて理解する学習が必要となる。
理数系科目において、それは顕著だ。天才の子はセンスと閃きで問題を解き進む。秀才の子は自分が得た知識を組み合わせて解き進む。最近、メディアやネットでは天才ばかり称賛する傾向にある。ところが、受験に強いのは意外だが秀才である。秀才の子は確実に点を取るからだ。また、秀才型の子の方が天才型の子よりも圧倒的多数派である。そういったことを良書には詳しく書いている。(明日へ続く)
2025/4/25

『時間と時刻』
小三の算数は
『時刻と時間』を指導した。
ふだんの計算は
「10進法」である。
時間と時刻は
「60進法」を使う。
◎1時間=60分
◎1分 =60秒
60進法の計算は、
少し時間がかかる。
習得すれば、
「n進法」が理解出来る。
非常に大切な単元である。
説明に40分掛けて、
20分間演習している。
しっかりと家庭で
復習する必要がある。
二時間も練習すれば、
60進法のコツは掴める。
その後、
反復することで習得できる。
Q1「午前10時30分の5時間40分後は」
10:30+5:40=15:70=16:10
これを筆算で行えるようにする。
A1「午後4時10分」
Q2「午後2時15分の3時間50分前は」
14:15-3:50=13:75-3:50=10:25
これを筆算で行えるようにする。
A2「午前10時25分」
小三の段階で習得した子は、
小四になると、
暗算で出来るようになる。
驚く位に早く、
瞬時に答を出すことができる。
佐藤進学塾で
『小三』から学ぶ
アドバンテージは大きい。
2025/4/24

『計算問題』
どの学年も、算数、数学は計算から始まる。中二・中三は皆、計算が速い。しかも、正答率が驚く位高い。100%に近い子もたくさんいる。
ひたすら、反復練習を繰り返してきたからである。速く計算してもミスが出る。ゆっくりで良いから、反復練習を繰り返すとよい。
そうすることで、徐々に適正な速さへと近付く。半年、一年と経った頃にはかなりのスピードで計算できる。反復練習を一生懸命に繰り返し練習している生徒の話だ。
佐藤進学塾は学習意欲の高い子が多い。
しかし、「以前とは少し違うな」と感じることが最近では多くある。当たり前の事が、出来ていないのである。
例えば、九九である。昔の出来る子は、九九を間違うことはなかった。ところが、最近は良く出来るはずの子が七の段、八の段を間違う。繰り上がり、繰り下がりも同じである。「7+9」は、「17-8」は、「…」、正しい数値を即答できない。これでは余りのあるわり算に時間が掛かる上正答率も上がらない。
練習するうちに出来る様に成るから、安心ではあると言える。反復練習は必ずしてほしい。している子としていない子では大きな差がある。偏差値で言うと「15」くらい開いていく。
昔の様に、「風呂で、家族で九九をみんなで言う」などなくなっているのであろう。声を出して勉強する機会が激減していることを感じる。小中学生は「声を出している間」が勉強している時間である。お子様の声が聞こえている間が勉強している時間である。
昔は、九九が合うまで風呂を出させてくれなかった。
「…、七九=六十八」
「残念、最初からやり直し」
出来る子の家というのは、皆、そうだった。
二桁×二桁の九九も覚えると良い。
「11×11、12×12、…、19×19」
以下も暗算で出来る様にする。
99×25=(100-1)×25=
105×18=(100+5)×18=
25×24=25×4×6=
「この計算、知ってるかな」
12×18=(12+8)×100+2×8=
15×19=(15+9)×100+5×9=
「はい、知ってます」
と言った子は、優秀だ。
最近は毎年、訊いている。
現在、全学年において計算問題を指導している。しかし、計算の単元に時間を掛けるわけにはいかない。関数、文章題、図形に時間を多く掛ける為である。『計算』は家で復習して完全に定着させてほしい。
小学生の間は、保護者様もご確認頂きたい。
『漢字』も同様であることを伝えておく。国語辞典を引いた回数だけ全国模試の偏差値は上がる。これももちろん紙の辞書の話である。電子辞書ではない。出来る子は今も昔も変わらない。ただし、電子辞書も上手に活用している。紙の辞書8、電子辞書2といった比率である。具体的なことは後日話したい。
2025/4/23

『復習の方法』
小学生の算数について
1.テキストを仕上げる
式・考え方・答はノートに、答はテキストに書く。
2.答え合わせを行い、復習をする
〇×だけして、答えは書かない。
間違った問題は、解答解説書をよく読む。
①問題を書き写す
②式・筆算・考え方・線分図を書いて考える
③二、三回反復して解法を習得する
(小三・小四の子は保護者様が答え合わせを行う)
3.参考書『自由自在』
小三・小四用(小三、小四)
高学年用 (小五、小六)
◎参考書を読み、深く理解して問題演習を行う。
1、2は全員、必修とする。
3は余裕がある子は行うとよい。
参考書を活用する子は、模試偏差値65を超える。
最初は無理のない範囲で少しずつ始めると良い。
国語の復習は、副塾長が授業中に詳しく伝える。
基本的なやり方は算数と同じである。
『国語辞典』を活用することが大切になる。
細かい内容については授業中に伝えている。
2025/4/22

『姿勢を正す』
新入塾の生徒さんは、「姿勢を正して学習すること」を一番に心がけてほしい。在塾生も、初心に戻り姿勢を正してほしい。姿勢が美しい子は、勉強が抜群に出来る様になるからだ。
姿勢が良くない子でも勉強が出来る子はいる。しかし、その様な子は抜群に出来る様には成ることはない。まあまあ、できる程度である。これは、事実である。
「姿勢が良いから勉強が出来るのか。それとも、勉強が出来るから姿勢が良いのか」
どちらかは分かない。
「卵が先か、ニワトリが先か」という因果性のジレンマに似ている。二つの関連した事象において、「物事のどちらが原因か分からない」という意味で使われる。
「自分の姿勢がどうなのか」
勉強している姿を、スマホで撮影してもらうとよい。
自分の姿勢を第三者の目で客観的に見ることができる。
「美しい姿勢になるには」
以下五点に気をつけると良い。
1.テキストを机と平行に置く。
2.椅子に少し深く腰掛ける。
3.背筋をまっすぐに伸ばす。
4.おなかと机の間に、こぶし一つ分の空間を作る。
5.両手を机の上に出し、左ひじは付かない。
これで、美しい姿勢を維持することが出来る。たった、これだけのことである。素直な心があれば、直ぐに出来ることである。私も常に声掛けをする。何回でも声掛けをする。それを素直に守ればよい。流石に無駄な努力を私はしない。その期限は長くても一年である。最初の三カ月は徹底して言う。
矢張り、
「『三カ月』が勝負である」
2025/4/21

『芝刈り』
日曜日に塾庭の芝を刈った。
縦に刈り、横に刈る。
際を刈り、サッチを集める。
施肥後、水をたっぷり遣る。
眩しい位に芝生が青く輝く。
赤、白のマンサクが満開である。
白と赤のツツジが咲き始めた。
芝生にツツジの白、赤が映える。
「芝生、きれい」
と友達と話している子がいる。
「ツツジが咲いてる」
と声を掛けてくる子もいる。
「あの花、なんだろう」
と訊いている子もいる。
心があたたかくなる。
塾は勉強するところだ。
認知能力を高める場だ。
同時に非認知能力を育成する進学塾を目指す。
2025/4/20

『石の上にも三年』
辛くても、我慢強く耐えればいつかは成功するという意味だ。石の上に三年間座っていれば、石が暖まってくることから、「辛くても辛抱すれば報われる」ことのたとえで使われる。
由来は二つある。
まず一つ目は、インドのバリシバ尊者の話。八十歳で出家、三年間石の上で座禅し続けた。その間、休むことはなかった。修行の末、悟りを開くことができた。そして二つ目は、中国の達磨大師の話。達磨大師は九年間、壁を向いて誰とも会話することなく座禅を続けた。忍耐の末、悟りを開くことができた。
この二つの話が由来となり、「石の上にも三年」 と言う言葉が出来たそうだ。三年とは、長い年月や長い期間の比喩である。
さて、入塾後、まず『三か月』が重要だ。三か月間の取り組みで、勝負が決まる。塾長、副塾長の言うことを出来る限り、守る様にしよう。特に、副塾長の言う事を守ろう!
1.集中力が上がる
2.学校の成績が上がる
3.勉強自体が楽しく成る
先に入塾している生徒たちを見れば分かる。その子たちも、入塾当初は大変であった。今は、楽しそうに勉強している。良い結果が出ているからだ。多くの塾生が全国模試偏差値「65」を超えている。早い子は、半年で結果が出る。遅い子でも、三年で結果が出る。まさに、「石の上にも三年」である。
1.テキスト、ノートを机に真っすぐ置く。
2.背筋を伸ばし、肘をつかず、姿勢を正す。
3.先生の話を、一言一句もらすことなく聴く。
4.問題文を指でなぞりながら大きい声で音読を行う。
5.深く考えて、ノートへゆっくり丁寧に濃い字を書く。
まずは、この『五点』を守る。私も、副塾長も、何回も伝える。繰り返し、穏やかに伝える。耳にタコができて、そのタコの中にタコができるまで言う。在塾生とのやり取りは、いつもこの様な感じである。
「姿勢を正そうね」
「はい、気を付けます」
「ゆっくり考えようね」
「はい、ゆっくり考えます」
「字をていねいに書こうね」
「はい、ていねいに書きます」
佐藤進学塾は、大多数がこの様な子の集団である。素直な子は、抜群に出来る様に成る。特に、副塾長のことを良く聞く子は!
しかし、残念な事例もある。何遍言っても、テキストが歪む。何遍言っても、肘をつく。何遍言っても、音読をしない。これでは、99.9%勉強は抜群に出来る様にならない。勉強以前、心の問題である。まずは心を磨く必要がある。残念だが、こういった真に大切なことを軽視する人間が世の中増えている。
2025/4/19

『第二週・金曜日』
中一の数学は『正負の数の乗除』を終えた。累乗、指数の計算を習得して定着させよう。
(-5)²=+25
考え方 (-5)×(-5)
(-5²)=-25
考え方 -(5×5)
乗法・除法は負の数の数に注目するとよい。偶数個ならば「+」、奇数個ならば「-」である。あとは、小六の計算と同じである。 途中、分数計算の約分も出来る限り暗算しよう。
中二の数学は、『連立方程式の利用』 について完成させた。皆、問題文を読んで確実に方程式がたてられている。計算力も、かなり上がってきている。復習を重ねている子は、速い上に正答率が高い。みんな、楽しそうに問題を解いている。素晴らしいことである。
中三の数学は、『二次方程式の利用』の応用問題演習である。みんな、良く復習している。佐藤進学塾では生徒全員、一人ひとりに質問しながら授業を進める。そのスピードは、驚く位に速い。
「生徒が質問するのではない。
塾長が生徒に質問するのである」
真にレベルの高い進学塾と言うのは、生徒の質問は意外と少ない。その分、指導者の生徒に対する質問は多い。それに対して的確に答えさせることで、生徒の思考力を徹底して鍛え上げる。専任教員側の質問力が高いのだ。拠って、最小限の時間で生徒の学力は最大限に上がる。勿論、生徒の質問は大歓迎だ。
2025/4/18

『第二週・木曜日』
小五は『小数のかけ算』である。
計算方法は、小四と同じだ。
小数点を左へ動かすだけである。
カードの並べ替えの問題を行う。
難しいので丁寧に教える。
みんな即座に答えてくれる。
全問、正解である。
新小五、みんな、
算数のセンスがとてもいい。
数学も出来るようになる!
小六は、
『文字式の計算』を指導する。
1.文字式の計算
2.等式の表し方
3.方程式の計算
これらを一回で指導する。
小学生の間は頭が柔らかい。
今のうちに練習しておくと良い。
復習している子は、
抜群に出来るようになっている。
中学ではかなり出来るようになる。
何より、姿勢が美しい!
各中学校進学時、
総合一位予備軍が多くいる。
これからが、楽しみである。
2025/4/17

『第二週・水曜日』
小三の算数は『時刻と時間』を指導した。ふだんの計算は殆ど「10進法」である。時間と時刻は「60進法」を使う。
◎1時間=60分
◎1分 =60秒
60進法の計算は、少し時間がかかる。習得すれば、「n進法」についても理解出来る。非常に大切な単元である。説明に40分掛けて、20分間演習している。しっかりと家庭で復習する必要がある。一時間も練習すれば、60進法のコツは掴める。その後、反復することで習得できる。
Q1「午前10時30分の5時間40分後は」
10:30+5:40=15:70=16:10
これを筆算で行えるようにする。
A1「午後4時10分」
Q2「午後2時15分の3時間50分前は」
14:15-3:50=13:75-3:50=10:25
これを筆算で行えるようにする。
A2「午前10時25分」
小三の段階で習得した子は、小四になると、暗算で出来るようになる。驚く位に早く、瞬時に答を出すことができる。佐藤進学塾で『小三』から学ぶアドバンテージは大変大きい。今年の小三は集中力が高い。姿勢も良く、とても気持ち良く指導ができる。
小四は、算数の授業、二回目である。『大きな数2』を指導する。
1.字は濃く大きく書くこと
2.数字はマスに合わせること
3.筆算は必ず定規を使うこと
万、億、兆は、|で区切る。これらを繰り返し伝える。これだけで、位取りを間違う事はなくなる。繰り上がり、繰り下がりは正確に計算できるようになる。実際、小三から通っている子はその習慣が身に付いていて完璧だ。
「100億の10倍は」
「1000億です」
「100億の100倍は」
「1兆です」
「100億の1000倍は」
「10兆です」
「325億の100倍は」
「3兆2500億です」
「10億の10分の1は」
「1億です」
「10億の100分の1は」
「1000万です」
「325億の100分の1は」
「3億2500万です」
必ず、即答できるようにしよう。
授業が終わり、生徒へ帰宅するように伝える。小四の子は次々と帰途につく。ひとりの小三の子が出てこない。「何かあったのかな」と思い教室へ戻ると、小三の子が、黙々と机の上の消しゴムのかすをそうじして、美しく整えている。「ありがとう、集めるだけでいいよ」と言うと、ニコリと笑い帰って行った。
この様な心の美しい子との出会い、指導できることに対する大きな喜びを今改めて感じている。
2025/4/16

『第二週・火曜日』
小五は、
英語、理科、社会、二週目だ。
理科は『植物の発芽と成長』単元の指導を終えた。温度、水、空気、日光、肥料の5条件について深く理解しておこう。実験において器具、注意事項、考察、結果を完全理解しよう。
社会は『国土』の単元の指導を終えた。国土は山、平野、川を暗記する。おもしろい覚え方を教えたのでそれを利用しよう。日本地図(地図帳)を徹底的に活用してほしい。
小六も、
英語、理科、社会、二週目だ。
理科は、『ものの燃え方』の単元の指導を得た。ものが燃えるために必要な条件、空気の成分、ものを燃やす前後の空気について、深く理解しておこう。
社会は『憲法・政治』の単元の指導を終えた。日本国憲法、三権分立、地方自治について理解を深めておこう。毎日、新聞を読む、テレビのニュースを見る、ラジオのニュースを聞くことが大切になる。
中一の数学は、
『正負の数の加減』単元の指導を終えた。整数、小数については交換法則を使って瞬時に暗算できるようにしておこう。分数については通分、約分があるので、丁寧に式を書いて計算する習慣を付けよう。この時期、スピードよりも正確さが重要である。意外にも、計算が速い子は正答率が低い。
中二の数学は、
連立方程式のまとめだ。
1.速さの利用(線分図)
2.割合の利用(増減の表)
3.濃度の利用(イラスト)
まず、図、表、イラストを描く。次に、それをもとに文字式で表す。文字式を連立方程式にする。加減法、代入法で計算する。答えを吟味して、確認する。みんな、良く理解出来ている。復習してマスターするとよい。塾で説明した手順を理解してから覚えよう。
リラックスタイムに一人の生徒が、「面白いギャグが思いつきました」と言うので、一応、きいてみた。「大きいラクダは、お気楽だ」と張り切って言う。少し笑った。みんな、ほんの少しだけ笑っていた。
話は逸れて、そばめしの話になった。「そばめし、食べたことある人」と訊くと、誰も食べたことはない様だ。神戸発祥でその成り立ちを伝えると、一人の子が「長田区じゃないですか」と言う。他の子が、「それはどこですか」と訊くので、「阪神大震災で被災した地区で、今は復興のシンボルとして鉄人21号の巨大モニュメントがある所だよ」と言うと、「鉄人28号です」と一人の子が間髪入れずに言った。
どの学年の子も、みんな明るい。
明るい子は勉強が出来る様に成る。
佐藤進学塾の授業を楽しむと良い!
『「五月号」の各種書類について』
今週、月曜日から、『「五月号」の書類』を入れた封筒を生徒さん一人ひとりに渡しています。保護者様におかれましては、各種書類についてご確認願いたいと思います。
1.夢つうしん〈全学年〉
2.春期講習会を終えて他(3枚)〈全学年〉
3.お手紙〈全学年〉
4.五月分授業料について〈全学年〉
5.2025受験合格報告〈全学年〉
6.小学生の勉強について(2枚)〈小学生〉
7.附属中入試家庭学習について(3枚)〈附属受験・小学生〉
8.宿題について〈新入塾・小学生〉
9.中学校定期テスト対策日程〈中学生〉
10.一学期中間テスト勉強について〈中学1年生〉
2025/4/15

『第二週・月曜日』
中三数学は、
平方根の指導を終えた。
平方根の計算の利用では、
「平方完成」を使いこなそう。
a²-2ab+b²=(a+b)²-4ab
a²- ab+b²=(a+b)²-3ab
a² +b²=(a+b)²-2ab
a²+ ab+b²=(a+b)²- ab
a²+2ab+b²=(a+b)²
a²+3ab+b²=(a+b)²+ ab
a²+4ab+b²=(a+b)²+2ab
リズム、感覚、
このパターンを掴もう。
①a=3+√2,b=3-√2のとき、a²+ab+b²の値
a²+ab+b²
=(a+b)²-ab
a+b=6、ab=7、
拠って、式の値は
36-7=29となる。
慣れると、暗算出来る。
②a+b=√3、a-b=√5のとき、4abの値
4ab
=(a+b)²-(a-b)²
式の値は
3-5=-2となる。
此方も、瞬時に
式変形出来る様にしよう。
皆、計算力が上がっている。
今週は二次方程式を指導する。
2025/4/14

『予定表』
生徒たちが次々と学校の予定表を提出してくれている。それをもとに塾年間予定の細かい部分を組み立てる。平常授業、講習授業、受験対策の日程を決める。祭日授業実施日を確定する。
そして、附属小六の学力テスト対策、公立中・附属中の中間・期末・学年末、診断テスト対策の日程を決める。予定については、各々二か月前までには書面で保護者様へお知らせする。
毎月二十日までに封筒へ入れて生徒へ渡すので、確認後はファイリングをお願いする。進学塾ゆえ、何回も同じことを言ったり、繰り返しプリントを渡すことはしない。一回のみ、書面にて確実に通知する。
さて、多くの手紙が添付されている。
「いつも丁寧なご指導ありがとうございます。今年度もよろしくお願いいたします。」
「他の子たちがとても頑張っている様子で、とても良い刺激を受けています。」
「毎日のブログ、楽しみに読ませて頂いています。参考になることが多くありがたく思っています」
「家庭学習の習慣がつくように、私も協力していきますので先生からもご指導よろしくお願いします。」
「がんばって良い結果が出るよう、家の方ではわが子の健康管理に気をつけていききます。」
たくさんのお手紙に感謝の気持ちでいっぱいである。
2025/4/13

『庭の手入れ』
塾庭の芝生を刈る。
縦に、横に刈っていく。
最後に際を刈っていく。
そうすると、美しく整う。
塾の庭は、
トキワマンサクが満開だ。
赤と白が交互に咲いている。
桜は葉桜となった。
花は散ったものの
樹木の力が感じられる。
つつじが咲き始めている。
もう少し経つと、
木が真っ白になる位に咲く。
塾庭の花が賑やかである。
芝生とのコントラストが美しい。
生徒たちを穏やかに迎え入れる。
2025/4/12

『第一週・金曜日』
新年度、平常授業の第一週目を小・中学部とも、無事に終えることができた。保護者様には心より感謝申し上げる。
さて、今年の『高松高校合格体験記』は読まれたことと思う。今年の体験記は読んでいてほっこりする内容が多い。
昨年は、かなり強烈な内容のものがあった。これこそが、まさに佐藤進学塾と言った感じである。
「『六年前、沈黙が続いた入塾面談のあの日から、ぼくの高松高校合格への旅路が始まった。』
はじめの頃は、ハイレベルな授業についていくことが出来ず、下を向いて問題を解いている振りをしているだけだった。姿勢やノートの使い方など学習以前のことを細々と注意される日々。特に、話を聞いていない時に「やる気がないなら帰れ」と言われた時は本当に辛かった。成績も上がらず、逃げたいと思ったことは数えきれない程ある。それでも自分を信じて先生が仰る通りに努力を続けた。それをあとおしする様に、先生もぼくを絶対に見はなすことはなく、一生懸命に指導を続けてくださった。
努力は功を奏し、中学校では良い成績を維持することが出来た。初めて、期末テストで五教科総合一位を取れた時の喜びは今でも忘れられない。最初の頃は、嫌々行っていた塾であったが、いつしか自然に『行きたい』と思うようになっていた。」(~続く~)
佐藤進学塾は「本当に頑張りたい」と思う気持ちが強い子たちを応援する塾である。素直で前向きな子は大成する。しかし、その過程には想像を絶する位大変なものがある。生徒たちは驚く位に努力している。保護者様も驚く位、ご協力頂いている。私は、そんな親子をひたすら全力で応援する。
努力している子ほど、努力していることを言わない。ご協力頂いている保護者様ほど、その事を他言することはない。傍から見ると、大したことないように見える。しかし、現実はまったく違う。佐藤進学塾の子たちは本当に良く努力している。私はそのことを誇りに思う。
佐藤進学塾は少人数制集団授業を貫く。各クラス6名から13名の定員制、塾長、副塾長の目が一人ひとりに行き届く。入塾した子は静謐な学習環境を守る。新入塾生も在塾生も安心して高いレベルの学習を続けられる。「小四、小六、中三」は定員に達していて予約待ちだ。保護者様には重ねて感謝申し上げる。
2025/4/11

『第一週・木曜日』
新年度、四日目の授業である。
小五、二回目である。算数の単元は『小数のかけ算』である。計算方法は小四と同じだ。小数点を付けるだけである。
かける数と積の大きさの関係を正しく理解しよう。B問題を確実に習得して、実力を高めていこう。参考書にも挑戦しよう。ヤル気ある子ばかりである。これからがとても楽しみだ。
「宿題のやり方」
1.テキストを仕上げる
2.答え合わせをする
(〇×を付ける)
3.ノートに復習する
①間違った問題を写す
②間違った問題を直す
(図、考え方など詳しく書く)
③教科書、参考書を調べる
小六の子は、『対称な図形』を指導した。線対象と点対象について考え方と作図方法を指導した。詳しくは、生徒一人ひとりに伝えている。解法の過程を大切にする子は必ず、抜群に出来るように成る。既に、抜群に出来るようになっている子がたくさんいる。本当に良く頑張っている。
中二は、国語・理科・社会の授業日だ。
理科は『化学』を指導した。
1.問題を音読して解く
2.問題文と答を音読する
3.説明をしっかりと聞く
社会は『地理・歴史』を指導した。
1.説明を音読する
2.問題文を音読する
3.説明を聞いて答を書く
理科、社会は音読が大切になる。
テスト前には書き写して覚える。
音読をするとすぐに覚えられる。
復習して重要な事を暗記しよう!
中三の子は、本日も診断テスト対策を行った。(附属中が修学旅行の為)
2025/4/10

『第一週・水曜日』
新年度、三日目の授業である。
「小三」、授業初日である。
1.鉛筆の持ち方
2.正しい姿勢
3.授業の進め方
について丁寧に教える。
算数の単元は『かけ算・わり算のきまり』である。八の段、九の段の九九に少し時間が掛かる。直ぐに、言えるようにしよう。初日、一生懸命取り組んでいた。少しずつ慣れていくものと思われる。
「宿題のやり方」
1.テキストを仕上げる
2.答え合わせをする
(〇×を付ける)
3.ノートに復習する
①間違った問題を写す
②間違った問題を直す
(図、考え方など詳しく書く)
③教科書、参考書を調べる
「小四」の子たちは、今日が初めての子もいる。皆、元気にやって来る。授業が始まってからは、大切な学習内容を指導しつつ、正しい姿勢について指導する。
『大きな数』の単元を指導した。
四桁ごとに | で区切る。
万、億、兆の位取りを確認する。
指でなぞり、声を出して、
大きな数を確認していく。
そうすると、
位取りを間違う事はない。
みんな、真剣に取り組んでいた。いつも言うことだが、速く解く必要はない。ゆっくり、リズム良く解けばよい。答えに至る途中の過程を重視する。丁寧に解いて、正答率を上げることが重要だ。復習を重ねることで、適正なスピードに落ち着く。
保護者様にお願いしたい。
「早くしなさい」は禁句!
何故なら、雑になり、
深く考えない子に成るからだ。
私は常に言う。
「ゆっくり、考えよう」
深く考えて、
ていねいに解く子に育つ。
保護者様が、
「ゆっくりしようね」
と声を掛ける。
私も、
「ゆっくり解こうね」
と声を掛ける。
そうやって育った子は自律神経がとても安定する。交感神経と副交感神経のバランスが整うことで、強いメンタルが養成される。親の言葉が、お子様の心の栄養になっている。良い言葉を掛けて育てられた子は豊かな心に育つ。
「宿題のやり方」
1.テキストを仕上げる
2.答え合わせをする
(〇×を付ける)
3.ノートに復習する
①間違った問題を写す
②間違った問題を直す
(図、考え方など詳しく書く)
③教科書、参考書を調べる
「中一」は、
国語・理科・社会の授業だ。
理科は『生物』を指導した。
1.問題文を黙読して解く
2.問題文と答を音読する
3.説明をしっかりと聞く
社会は『地理』を指導した。
1.説明を音読する
2.問題文を音読する
3.説明を聞いて答を書く
理科、社会は音読が大切になる。
テスト前には書き写して覚える。
音読をするとすぐに覚えられる。
復習して重要な事を暗記しよう!
「中三」の子は、本日、
診断テスト対策を行った。
(附属中が修学旅行の為)
中三はやることが多くある。
1.塾、学校の復習
2.中間テストの勉強
3.診断テストの勉強
番号順を優先順位としよう。
2025/4/9

『第一週・火曜日』
新年度、最初の授業は私でさえ緊張する。生徒たちも、もちろん緊張している。新入塾の子は、特に緊張している。
適度な緊張感は、学習に良い影響をもたらす。気が引き締まる思いとなり、初心に戻ることが出来るからだ。また、思いを新たに授業へ臨むことが出来るからだ。
小五、小六は、初めての理科、社会の平常授業である。
1.テキストを音読する。
2.重要事項の説明を聴く。
3.問題演習を一緒に行う。
4.ドリル演習を各自行う。
5.間違い直しをノートに行う。
音読⇒書写⇒反復が重要である。みんな、集中して学習している。授業をしっかり聞いて、深いところまで理解している。素晴らしいことである。家では復習して暗記する。余裕が出てきたら、参考書を活用して学習すると良い。小五の地球儀、地図は必須である。小六は新聞を読む習慣を付けよう。
中一は、数学、英語である。予習講座で既に一通り指導している。平常授業では、レベルの高いテキストで応用問題演習を行う。家では復習して理解を深める。いつも通り、集中して授業を受けていた。宿題は出さないのでその分復習をしっかり行ってほしい。普段の復習が大切である。
中二は、三月より予習授業を行っている。数学、英語はかなり進んでいる。数学は、連立方程式の単元を続けていく。『速さ』の問題演習を行う。距離の式…①、時間の式…②、①②を連立して計算していく。「線分図→文字式→方程式」、この流れは方程式と同じだ。加減法と代入法を使い分ける。
いつも言うことだが、中二で全力で頑張った子が高松高校へ合格する。中三になって慌てて勉強しても、上位層に追いつく事は出来ない。逆転など、絶対に起こらない。稀に逆転に見える現象も起こる。それをクローズアップして凄い事の様に紹介する例も多い。日本人にはその様な逆転劇を好む人が多い様だ。
佐藤進学塾では、地に足を付けて勉強をしていく。中三では心に余裕を持ち、笑顔で楽しんで勉強する。涼しい顔をして、中三での一年間を過ごす子が成功する。それを私たちも笑顔で応援する。
2025/4/8

『第一週・月曜日』
新中三は三月より予習授業を行っている。数学、英語はかなり進んでいる。数学は平方根の単元を終えて、二次方程式の単元に入った。
すでに乗法公式は習得している。それを平方根に当てはめる。
(3√2)²=18
(5√3)²=75
これが暗算できるようにする。
3/√2=3√2/2
分母の有理化は暗算で処理する。
有理数と無理数を瞬時に区別して計算する。
二次方程式は、解の公式を教えて使い方を練習した。二次方程式から解の公式を導きだす方法も伝えた。いずれも大切である。しっかり復習しておこう。来週までに中三の計算はすべて終える。
さて、数学で良い結果を出すには復習に時間をかける必要がある。例えば、数学と英語の復習時間比は2:1である。仮に家庭での復習、日々一時間、英語を勉強、とても良い結果が出るとする。数学は、日々二時間、勉強して大変良い結果が出るのだ。数英バランス良い結果の子はこれを自然と行っている。
数学と言うのは結果を出す為には時間が掛かる教科なのである。但し、数学が三度の飯より好きな子に2:1の比は、あてはまらない。この様な例外的な子は1:2の比になる時もある。
2025/4/7

『新年度平常授業』
新規入塾する子は、とても緊張していることだろう。
継続して通塾する子は、心新たに頑張ることだろう。
佐藤進学塾平常授業、一連の流れを伝えておく。
先生「こんにちは」
生徒「こんにちは」
笑顔で気持ちよく挨拶をする。
生徒「お願いします」
先生「はい、どうぞ」
靴を並べてから教室へ入る。
静かに荷物を置いて、筆記用具を準備する。
授業が始まるまで、指示に従って学習する。
15分、ウォームアップして授業を開始する。
テキストを机に真っすぐ置いて、姿勢を正す。
テキストは左、ノートは右に並べて置く。
先生の話を、先生の目を見てしっかりと聴く。
「ここは、こうしてくださいね」
指示を受けた時は、うなずいてから
「はい、ありがとうございます」
と言う。
「ここまで、理解出来たかな」
と言われた時は、
「はい、わかりました」
と元気良く返事をする。
もし、分からない時は
「ここが、よく分かりません」
と遠慮なく聞けばいい。
授業終了時に、私たちが
「ありがとうございました」
と言う。
生徒のみんなも、
「ありがとうございました」
と元気に言う。
在塾生はいつも通りに来ると良い。新入塾の子が困っていれば、声を掛けてほしい。また、初心に戻り、一生懸命頑張ってほしい。みんな、元気に通塾してくることを待っている。前向きな優しい子ばかりだから、安心して勉強出来る。静謐な学習環境を守っているので、集中して勉強出来る。
みんな、安心してくると良い。
2025/4/6

『佐藤進学塾の庭』
「私が初めて佐藤進学塾に行った時、丁寧に手入れされた庭やピカピカの教室を見て『本当にここは塾なのかな。』とびっくりしたことを今でも覚えています。」
と、今年の合格体験記に書いてくれた子がいる。
佐藤進学塾には庭がある。教室の東側と南側にあり、教室よりも、庭の方が随分広い。敷地面積は合わせて、150㎡あるからかなり広い。塾としては贅沢な広さである。
教室の東側は全面ガラス張りで光が燦燦と差し込んで明るい。塾庭には芝生が植えてあるので緑が映えて目に優しい。
「先生、お庭が綺麗ですね」
と言われることがよくある。
そういわれると、此方も嬉しい。
シンボルツリーは桜である。今年も美しい花を咲かせている。今満開の時を過ぎて花びらが舞っている。とても風情がある。夜はライトアップしている。
「うわー、きれい」
と思わず口にする子もいる。
楽しみにしている近隣の方もいる。
芝生が休眠から覚めて元気に青々としてきて、桜の花とのコントラストが美しい。トキワマンサクも満開になり、深紅の花をつけている。昨年から真白の花も加わった。椿も満開であり、赤と白の花をいっぱいつけている。つつじ、皐月、霧島つつじも、もうすぐ咲く。
佐藤進学塾の生徒はみんな明るい。塾は樹木の花々でとても明るい。明るいので気持ち良く学習出来る。手入れして戴く穏やかで優しい庭師さんに感謝である。その心が樹々を通して生徒に伝わっている。
2025/4/5

『高松高校合格体験記2025』
高松高校合格体験記の最新版をトップページに上げた。
「この塾で、三年間、諦めずにやりきる。」
入塾面談において、父、本人、塾長の三者で一時間半、徹底的に話し合い、心底、納得してから上記を決意した子である。
「ここで最後までやり抜く。」
最初の授業でそのレベルの高さと分かりやすさと勉強の面白さに衝撃を受けた子が決心した事である。
「本当にここは塾なのかな」
小三の時、丁寧に手入れされた庭やピカピカの教室を見て、びっくりした子が素直に感じたことである。
心をこめて書いてくれた合格体験記を読んでいると、思わず涙が出そうになった。長い様で短い、六年間であった。三年間、五年間の生徒もいる。一人ひとりが想いをていねいに綴っている。
真に大切なことが後輩たちへ伝わることと思う。合格に至る過程には、想像を絶する大変なものがある。みんな、苦労している。驚く位に努力している。しかし、合格した子はそれを微塵も感じさせない。
いつも「笑顔」を大切にしていた。
いつも「言葉」を大切にしていた。
いつも「友人」を大切にしていた。
一人一人の文章をじっくり読みこんでいくときっと、大切なことが分かる。
2025/4/4

『お手伝いの大切さ』
「お手伝いしてる?」
と時々、生徒たちに訊く。
「お風呂の掃除をしています」
「夕食作りを手伝っています」
「弟の勉強を見てあげています」
様々な答えが返って来る。
勉強が出来る子は、家の手伝いをしている。
それには、以下、三つの理由があるからだ。
1.自立する力を養成できるから
2.責任感や自己肯定感が育つから
3.段取り力や行動力が身につくから
逆に言うと、これらが身に付いていないと、いくら勉強しても結果は出ないということだ。
「先のことを予測しながら行動する」
手伝いは意外と高度な思考が必要になる。
それが、手伝いをすることで自然と鍛えられる。
夕食の準備をする場面で考えてみる。
料理の出来具合いを見て、様々な準備をする。
1.テーブルの上を片付ける。
2.テーブルをふきんで拭く
3.家族の皿や箸を用意する
4.全員のご飯を茶碗によそう
5.皆の出来た料理を並べる
6.食事後の皿をきれいに洗う。
どの様に工夫すれば、効率良く出来るか。
どの様に行えば、早く正確に出来るのか。
考えながら、取り組む事に拠り、先を見通す力や思考力が身に付く。
同時に、早く正確に作業を行う為のコツや感覚を得ることが出来る。
何より、家族間のコミュニケーションを深められる。
「ありがとう」
感謝されることで、人に喜ばれることを知る。
こういう子たちは、効率良く勉強する。
手伝いをする時、段取りを考えているからだ。
段取りがいいから、要領良く勉強を進められる。
また、人の気持ちを察して行動する事が出来る。
困っている人がいると、すぐに手を差し伸べる。
相手が喜ぶことを、手伝いを通じて学んでいる。
手伝いをする子は、ある行動で見抜く事が出来る。
塾へ来た時、気持ち良く挨拶をする。
靴をていねいに並べてから教室へ入る。
鞄をそっと置いて、静かにテキストを取り出す。
一つひとつの所作が、静かで美しいのである。
すべての動作が、人のことを考えていて穏やかだ。
これらが出来ている子は、勉強が要領良く出来る。
2025/4/3

『掃除の大切さ』
佐藤進学塾は常に美しい。
隅々まで掃除が行き届いている。
塾庭も、教室もピカピカである。
東側は全面ガラス張りである。
庭の芝生が、輝いて見える。
とても気持ちよく勉強出来る。
塾備品は上質なものを配置している。
生徒は素直な心の子ばかりである。
だから、いつも集中して勉強出来る。
かつて、永平寺の高僧が言っていた。
「掃除をすることは自身の心を磨くことである。
無心になって掃除をすれば、心が美しくなる」
塾長は日々、心を磨く努力をしている。
生徒たちも、心を一生懸命磨いている。
晴らしい人間は間違いなく謙虚である。
佐藤進学塾の教室はとても明るい。
静謐と言う言葉が相応しい学習空間だ。
生徒も先生も心を磨き続けているからである。
2025/4/2

『笑顔の大切さ』
笑顔の子は、心も表情も明るい。
こちらも、明るい気持ちになる。
笑顔の子は、笑顔の友人に囲まれる。
だから、益々、みんなが笑顔に成る。
笑顔の子は保護者様も笑顔である。
だから、家族のみんながとても明るい。
家庭が明るいから、益々、笑顔に成る。
笑顔の子が発する言葉は肯定的である。
「頑張ります」
「続けます」
「挑戦します」
前向き且つ肯定的な言葉が飛び出してくる。
大変なことが有っても、
「ピンチはチャンス」と前へ進んでいく。
結果、以前よりも高いステージに上がっていく。
笑顔の子は何をやっても上手くいく。
笑顔を意識するだけで、全てのことが上手くいく。
2025/4/1

『美しい姿勢』
まず、
テキストを机にまっすぐ置く。
次に
机と自分、自分と椅子の間に、
こぶし一つずつの空間をあける。
そして、
ひじはつかず、
背筋をスッと伸ばす。
これらを意識すると、
姿勢は必ず美しくなる。
入塾時、
姿勢が美しい子はいない。
しかし、
一回伝えるだけで
美しく直す子がいる。
一ヶ月くらい掛けて、
美しく直す子もいる。
一年くらい掛かって、
美しく直る子もいる。
素直な気持ちがあれば、
姿勢は必ず美しくなる。
「あっ、この子、
姿勢が綺麗になったな」
と思った時、
不思議な位に成績が上がる。
生徒の姿勢と成績の
相関関係は非常に高い。
「この子、姿勢が100点だな」
と思う子はテストも100点取る。
これは事実である。
かつて、国立中三年の子が、
最後の二学期期末テスト
五科・九科『総合一位』だった。
終始、姿勢が綺麗であった。
頑張っていた子がもう一人いた。
同じく国立中三年の子で
五科『総合四位』だった。
姿勢はお世辞にも
きれいとは言えなかった。
一位と四位、両方素晴らしい。
しかし、僅差が姿勢に表れていた。
2025.3.31

『最初が肝心』
四月は新年度の始まりである。小中学生は新学年に進級する。佐藤進学塾も新年度平常授業が始まる。自分が置かれた環境が大きくガラリと変わる。新たなチャンスが目の前に現れる。
『最初が肝心』、最初を大切にする子は、これからの一年間を充実して過ごすことが出来る。
「先生の話をしっかり聞こう」
学校でも、塾でも、習い事でも指導者の話をもらす事なく聞くことは最も大切であると言える。
「配布書類はしっかり読もう」
時間、期間、日程をはじめ、決まりごとを守るようにしよう。書類はファイリングを行い、正確に読み込むことは重要だ。
「塾長ブログに目を通そう」
ブログでは、心構えを始め大切なことを分かりやすく伝えていく。いずれも、真意をくみとり素直に実行していくとよい。素晴らしい結果を出す子にはみんな、共通点がある。聞く、読む、目を通す間に大切なことに気付く。それを実行するうちにすべてのことが前に進み始める。
新年度授業開講に拠る授業準備に専念する為、電話による新年度生徒募集は一旦締め切ります。新年度、継続通塾される方、新たにご入塾を決定された方、ご検討された方、本当にありがとうございました。
2025.3.30

『新年度テキスト』
新年度のテキストが届いた。大きな箱が十二箱、塾の前に積み上げられる。早速、テキストの検品を行う。
まず、箱から全ての教材を取り出す。学年別、教科別に丁寧に並べる。そして、テキスト、解説書、テストをセットにする。
生徒数とテキスト数を照合する。テキストの不備を確認する。テキストは重いので、結構、腰にこたえる。テキストは結構、エッジが鋭い為に気を許すと手を怪我する。
休憩しながら、順番に作業を進めていく。段ボールは、すぐに集積所へ運び出すので、生徒の目に触れることはない。
今年も、素直で前向きな生徒たちが受講する事を心から嬉しく思う。生徒の顔を一人ひとり思い浮かべながら、新しいテキストを準備していく。
真っ新なテキストは気持ちがいい。紙とインクのにおいが心地良い。分厚いテキストの内容が、子たちの脳と心の糧となっていく。新年度の新たな指導が、今からとても楽しみである。
2025.3.29

『国立大学合格報告後期』
後期の合格発表の報告に来てくれた。
「広島大学教育学部に合格しました」
「おめでとう。良くがんばったね」
「高校で素晴らしい先生に出会ったおかげです」
「えっ、どんな先生」
「凄く厳しいんですが、私たちの勉強や将来の事を真剣に考えてくれていたんです」
「それは本当に良かったね」
実は、この子、中三の時に私とうまくコミュニケーションが取れなかった。私がいろいろ指示を出すのだが、むしろ逆のことをしていた。このままでは、先々、困るなと思っていた。
しかし、その後、良い師と出会って、この子は大きく変わったようだ。高校では大変な出来事もあったそうだ。それを乗り越える為にも、自分の限界に挑戦した様だ。この子は根性だけは昭和の子並みに強いものがあった。それが新たに出会った先生によって開花させられたのだろう。
驚くことに顔つきが全く違っていた。中学校の時は少し暗く、少し反抗的な感じの所があった。それらが全く真逆になっている。とても明るく、穏やかな顔つきに変わってしまっているのだ。前向きなところは全く変わっていないが…。
「広島でも体に気をつけて頑張ってね」と言うと、
「先生、四年間、本当にありがとうございました。先生の勉強方法は高校でもとても役に立ちました」と言って、にこやかに帰って行った。
新年度授業開講の為、電話による新年度生徒募集は一旦締め切ります。ありがとうございました。
2025.3.28

『春休み』
春休みに是非、やっておいてほしいことが以下の三点である。
1.前学年テキストの総復習
2.一年間の全テストの復習
3.春期講習学習内容の復習
安心して、新学年を迎えることが出来る。特に、受験生はしっかり行うべきだ。上位層の受験生は夏休みに本気で勉強する。ところが、春休みは、そこまでやる子は少数派である。
「ここで、大きな差をつける」
いつも言うことだが、あとで逆転することはない。99%、起こりえない。先にやるべきことをやって、問題点は改善しておくと良い。学習内容に対して、自信を持つことが出来る。
この自信が、勉強を継続する原動力となる。春休みに復習する事を最大限、大切にするとよい。遊んでも良い。旅行へ行くのも良い。部活を全力でやっても良い。それでも、時間はまだある。復習にかける時間は必ずある。だらだらやるのは駄目だ。時間は24時間、限られている。時間を決めてビシッとやろう。
「勉強は時間でなく『質』である」
質の良い学習は結果に繋がる。学習の質を高めるには、結果が出る正しい学習方法を身に付けていく必要がある。それは、塾長である私が授業指導の中で伝えていく。佐藤進学塾の卒業生が学習の質を極限まで高めて素晴らしい結果を出している。その結果が学習は質を高めることが大切である事を証明している。
※全学年、定員まであと僅かです。
(新小四、新小六、新中三は予約待ち)
新年度授業開講の為、本日で電話による新年度生徒募集は一旦締め切ります。ありがとうございました。
2025.3.27

『卒業記念』
三月始めに中一、中二、
診断テストと学年末テスト、
成績優秀者の表彰を行った。
皆、全力で頑張った。
生徒一人ひとりが、
最高の結果を出している。
生徒の努力を褒め称え、
副賞を進呈していった。
改善点も同時に伝えた。
結果は教室に掲示している。
保護者様には、
三月号にてお知らせした。
輝かしい結果を見て、
「私もがんばります」と言って、
勉強している小学生が多くいる。
とても、嬉しいことである。
小六卒業生に
お祝いのプレゼントを渡した。
「一年間頑張った事を褒め称えて」
「中学生で活躍して飛躍できるように」
「これからも心身健康であることを祈って」
皆、嬉しそうに受け取っていた。
新年度、一人ひとりが益々
頑張ってくれることは間違いない。
ハクモクレンの花が満開だ。
真っ白い花が辺りを明るくする。
生徒たちの成長を祝うかの様に!
※全学年、定員まであと僅かです。
(新小四、新小六、新中三は予約待ち)
今週、金曜日で募集は一旦締め切ります。
2025.3.26

『花束』
小学生の子が、花束をプレゼントしてくれた。昨年は私が受け取った。今年は副塾長が受け取った。
「かわいいお花をありがとう」とお礼を言うと、
「庭のお花です」と今年もこたえてくれたそうである。
昨年の会話を思い出す。
「家に花が咲いているんだね」
「今、たくさん咲いています」
「すごく、綺麗だろうね」
「はい、とても綺麗です」
「素敵なおうちだね。塾の花ももうすぐ咲くよ」
「何の花ですか」
「桜、つつじ、まんさく、サツキ、…、たくさん咲くよ」
「楽しみにしています」
花や木など、自然に興味を示す子は心優しい。佐藤進学塾では心の在り方を大切にしている。この様な心優しい子が育っていることは心底嬉しい。塾のテラスに花を飾ると、今年も教室がパッと明るくなった。シンボルツリーの桜の花も三分咲きである。ライトアップしているので、夜も華やかである。
※全学年、定員まであと僅かです。
(新小四、新小六、新中三は予約待ち)
今週、金曜日で募集は一旦締め切ります。
2025.3.25

『春期講習』
新年度、
春期講習の第二日目である。
新小六の生徒は、
『発展問題演習』に取り組む。
様々な発展問題を演習している。
新中一の生徒は、
『新中一予習』の終盤である。
数学は方程式の利用を演習している。
新中二の生徒は、
『新中二予習』である。
数学は連立方程式の利用へ入った
新中三の生徒は、
『新中三予習』である。
平方根の計算を全て完成させる。
さて、中学生は、
三学期通知表評価が出揃った。
高松高校入試の内申点となる。
学年末テストに向けて、
皆、全力で取り組んだ。
納得出来る結果が出ている。
オール5、40以上の子が殆どだ。
『4』の子は
『5』にする手立てを
具体的に生徒へ伝えた。
『5』の子は
『5』を維持する手立てを
徹底して生徒と話し合った。
話をしていると生徒の目が
一瞬、きらりと輝く時がある。
心の底から納得した瞬間である。
本当に良く頑張ったと思う。
安心して勉強を続けられる。
新年度がとても楽しみである。
※全学年、定員まであと僅かです。
(新小四、新小六、新中三は予約待ち)
今週、金曜日で募集は一旦締め切ります。
2025.3.24

『国立大学合格報告』
今年度、第一号は
香川大学医学部だった。
中学校の時からの「夢を叶えることが出来て、とても嬉しい、医学を学ぶ事が出来る環境に感謝している」と言っていた。
第二号は
千葉大学園芸学部だった。
(千葉大学園芸学部は、1949年、千葉大学発足時に設立された「国立大学」唯一の園芸学部である。園芸及びランドスケープ分野におけるアジアで最も伝統ある高等教育機関である)
「高二の時、真剣に将来を考えていると自分の適性に合う学部学科が見つかった。それからは千葉大学を第一志望として勉強に集中することが出来た」と言っていた。
第三号は
徳島大学総合科学部だった。
「厚生労働省認定の公認心理士となり、保健医療、福祉、教育等の分野において心理学に関する専門技術を持って任務にあたり、社会に貢献したい」と言っていた。
そして、今日も、国立大学の合格報告を受けた。
三人、一気にやってきた。
一気に華やかでにぎやかになる。
「こんにちは」
「どうだった」
「先生、合格しました」
「それは、良かったね」
「岡山大学歯学部へ合格しました」
「おめでとう。頑張ったね」
「○○くんはどこに合格したの」
「大阪大学工学部です」
「がんばったね」
「ありがとうございます」
「□□くんはどこへ合格したの」
「大阪大学工学部です」
「えっ、ふたり、一緒なの」
「はい、偶然ですが一緒です」
「そんなこと、あるんやなあ」
「はい」
「塾生の◇◇くんが大阪大学大学院の工学部にいるよ」
「それは心強いです」
岡大へ進学する子は、
「高三の時に医学部へ進むか、歯学部へ進むかとても悩みました。周りの人たちが『医学部、医学部』と言う中、冷静に考えました。様々な資料を調べて、自分の適性や性格を考えて歯学部を第一志望とすると決めてからは迷うことなく全力で勉強に取り組みました。岡大の面接で『大学院へ進む気持ちはありますか』と訊かれ、『ありません。六年後は歯科医となり現場で働くつもりです』と答え、失敗したかな、と思っていると『あなたは正直な人なんですね』と言われ、少しホッとしました」と言っていた。
阪大へ進学する子は、
「家庭の事情で愛媛に転居する事と成り、単身、愛光高校へ乗り込みました。内部生は既に高校の課程も終えていて、英語課程は高一、数学課程は高二でほぼ終了するというハードなカリキュラムでした。最初はついていくのに精一杯でとても苦しい思いをしました。文理選択でも迷いましたが、自分のやりたいことは工学にあると考えて理系へ進むと、更に勉強のレベルは高くなり大変でしたが、高二後半からは自分のペースで落ち着いて学習に取り組めるようになりました。愛光の二次試験対策にも助けられて、無事に第一志望校へ合格できたことをうれしく思っています」と言っていた。
もう一人の阪大へ進学する子は、
「僕の母は『勉強しなさい』と一度も言ったことはありません。それに甘えて、高一の時は勉強を本気でしていなかった気がします。しかし、いつまでもこのままではいけないと思い、部活を引退、高二からは本気で勉強に取り組みました。すると、得意の数学がグングン伸びはじめ、結果が出ると楽しくて、益々数学へ真剣に取り組むようになりました。国語の駿台模試は偏差値29と悲惨でしたが、それはそれとして、やるべきことをやりました。共通テストでは自分の実力を発揮することが出来、二次試験までの間、落ち着いて勉強へ取り組む事が出来ました」と言っていた。
三人とも両親、先生、友人、支えて頂いた人への感謝の気持ちをしきりに言っていた。それと友人の大切さを伝えてくれた。「高校にはいろいろな人がいる。少し「?」という考え方の人もいるが、人の気持ちの分かる素晴らしい人がたくさんいる。その中で自分にとって高校生活を充実させて、その後の人生を変えるほどの友人と一緒に過ごすことが出来たことは最高であった」と三人が口を揃えて言っていた。
阪大の子は両親が大阪見物、万博の開催を楽しみにしていると言う。もう一人の阪大の子は既に下の兄弟姉妹たちがみんな一緒についてきて梅田界隈で遊び楽しんで帰ったと言う。岡大の子はしばらくはマリンライナーで通学すると言う。親の負担も考えて、落ち着いてから岡山での生活を考えると言う。
最後に、
「うちの父が毎朝、先生のブログを楽しみに読んでいるんですよ」
と言われてびっくりした。
朗報はまだ続きそうな感じだ!
2025.3.23

『爽快』
今日はテニスが楽しかった。
20代の社会人、若い子たちと練習したからである。
みんな、テニス好きの元気な明るい子たちである。
容赦なくテニスボールをガンガン打ち込んでくる。
最初は少しタイミングが合わない。
合いはじめると、ラリーが延々と続く。
自分の気持ちが上がって来るのが分かる。
こちらが本気で打ち込むと、更に速い重い球が返って来る。
驚く位にボールが回転していて、着地すると凄く跳ね上がる。
ボレーストロークも結構続く。
流石にしんどくなってくるが面白いから続ける。
体が軽くなり、ラケットを振り抜くことが出来て調子が良くなる。
最後は、四人でダブルスのゲームを楽しんだ。
ジュースになり、なかなか勝敗が決まらない。
三ゲームして一勝二敗、勝っても負けてもすごく面白かった。
実はこの六カ月間、テニスが絶不調であった。
技術面についていろいろ考えて、様々な練習をした。
ガットもポリ、ナイロン多くの種類のものを試した。
それでも絶不調からは抜け出す気配すら見えなかった。
それが今日、やっと抜け出した感じである。
それも、不思議な位に一気に抜け出せた。
生徒たちが高松高校へ受験者全員合格した。
肩の荷が下りたから、気持ちが軽くなったのだろうか。
「いや、違う!」
本当にテニスが好きで、テニスを楽しむ純粋な気持ちの人たちと一緒に楽しむことが出来たからである。勉強もスポーツも芸術も、どのようなことであっても、本当に一生懸命に打ち込む人たちと一緒にやると自分の力が最大限に発揮出来る。真剣にそして楽しんでやっている人と一緒にやると同期発火が起こる。
2025.3.22

『全員合格』
佐藤進学塾塾生全員が公立高校へ合格した。
『高松高校』受験者、全員合格である。
高松西高受験者も全員合格である。
昨年に引き続き、塾生全員合格、本当にありがたい。
午後一時、全員が塾へやってきた。
なぜか、いつものメンバーよりも一名多い。
かつて、塾生であった子が一人一緒にいる。
小三から通っていた子である。
この子も、高松高校へ受かったと言う。
ひと安心である。
みんなで二時間位楽しく話をしてから帰って行った。
女子が多い学年だったので話が炸裂して教室が爆発しそうだった。
もうこの子たちと会えないと思うと本当に寂しい。
一緒にみんなで写真を撮ったので、それを一人ひとりへ送ろうと思う。
また、塾であったこの子たちの思い出は、後日ブログに書いていきたい。
今迄の事を思い出すと、今日は気持ちがいっぱいいっぱいである。
2025.3.21

『吉兆』
庭の樹々、花が満開である。
梅が桃色の花をつけている。
椿が深紅の花を咲かせている。
ハクモクレンも花が咲く間際である。
シンボルツリーの桜も蕾が大きく膨らんでいる。
平戸躑躅も多くの蕾を付けていて、白と赤の花が咲く。
椿にはメジロが訪れる。
つがいが頻繁に飛んでくる。
一昨年、庭師さんが植え替えて戴いた塾正面のトキワマンサクは赤花と白花がもうすぐ満開となる。霧島躑躅、満天星躑躅も次々と花を咲かせる。
庭が明るく、賑やかである。
鳥のさえずりが心地良い。
※全学年、定員まで僅かです。
2025.3.20

『模試最終日』
今日は、新小四、新小六、算数、国語の二科目実施日である。新小四は残念ながらまだまだであるが、新小六は、模試の大切さを理解して、本格的に勉強し始めている子も多くいる。
「きちんと見直しをしなさい」
と、言う親がよくいる。
これもあまり言ってはいけない言葉である。
「見直し出来なくてもいいのよ」
或いは、
「見直す時間があれば見直してね」
と言うと、実力を発揮出来る。
実際、塾の成績上位者は殆ど見直しをしない。正確に言うと、丁寧に解いているので、正答率が高く見直しをする必要がないのである。見直しを前提に解くと、雑になりミスが目立つのだ。
一般的に言われていることは、成績上位層の子にはあてはまらないことが多い。
「質問をしなさい」と言う親の子は、
聞けばいい、と安易に考えて、深く考えない子に成る。
「見直しをしなさい」と言う親の子は、
あとで見直しすればいい、と考えて雑に解く子に成る。
「早く解きなさい」と言う親の子は、
早く雑に解いて、まったく見直しをしない子に成る。
「わからなくても、いつか分かるようになるよ」
「見直しは出来なくてもいいから丁寧に解こうね」
「ゆっくりていねいにあわてることなく解いてね」
この様に言えばいいのである。
そうすれば、「質問をする、見直しをする、適度に早く解く様になる」子に成る。
結果、成績上位者となる。
「勉強なんて別にしなくていいのよ」。
こういえば、お子様は本気で勉強する子に成るのである。
ただ、家庭環境が最高の状態である場合に限るのは当然と言える。
2025.3.19

『模試第三日目』
今日は、新小五、新中一、算数、国語の二科目実施日である。新小五、新中一共に、模試の大切さを理解して本格的に勉強し始めている子も多くいる。
「早く解きなさい」
と、言う親がよくいる。
これは絶対に言ってはいけない言葉である。
「普段通りていねいに解きなさい」
或いは、
「いつも通り落ち着いて解きなさい」
と言うと、実力を発揮出来る。
実際、塾の成績上位者は驚くくらいにゆっくりと問題を解く。ところが、遅くなったり、急に速くなったりとリズムがくずれる事はない。ゆっくり、リズム良く解き進めていく。
「制限時間で間に合うかな」、と気にかけながら見ていると、最後五分前位に解き終えて、二、三問だけ集中して見直しを行っている。テスト後、「見直しをしたら間違いが見つかって良かったです」と言う。
「早く出来ているけど大丈夫かな」とみていると、鉛筆を置いて時計ばかり見ている。見直しをすることもなく制限時間を終える。この様な子に限って、テスト後、「あとで考えたら簡単だった」などと言う。
出来る子が必死に早く解く、と言うのは一般的な常識の間違いと言える。出来る子はゆっくりリズム良くとても涼しい顔をして解くのである。普段もそうである。早く解く子と言うのはミスが多い。困ったことに見直しも一切しない。
普段出来ていない子がテストの時に出来るはずはない。普段からゆっくり丁寧に考えて解く習慣がある子が模試で良い成績を残す。成績を上げたければ、普段の取り組みを変える事から始めなければいけない。そのあたりは、私から一人ひとりに向けて伝える。それを素直に実行した子は結果が出るということだ。
2025.3.18

『模試第二日目』
今日は新小六、新中1の英語、理科、社会、そして、新中二、新中三の国語、理科、社会の全国模試の日である。
新小六、新中1は、まだ、全国模試に慣れてない子もいる。新中二、新中三は殆どの子が慣れている。
大切なことは、次の五点である。
1.重要問題集中心に塾テキストを徹底的に復習しておくこと
2.テスト用紙が配られたら二分位でテスト全体を見渡すこと
3.テスト中は集中してゆっくりリズム良く解いていくこと
4.テスト時間中は鉛筆を置くことなく終始持っていること
5.難しい問題は無理して解かずに印をつけて後まわしにすること
以上である。
結果を出す子は、上記すべてが出来ている。
さて、上記以上に大切なことがある。テスト結果が出るのは約一か月後である。全国の塾の採点を行い、集計するのには当然その位の時間が掛かる。それまでに、生徒一人ひとりが自己採点を行い、間違った問題はやり直して、理解後、習得しておくことが何よりも大切である。
『テストは「終わってからが始まり」なのである』
結果を出す子は、それを必ずやっている。
結果を出したければ、それらをやればいいだけである。結果があまり出ていない子は、「がんばった、がんばった」と大仰に言う。結果を出す子は「もっとやらなければならないことがたくさんあった。次は、気をつけたい」と必ず言う。上記のことがすべて出来ているので言うこと自体が全く違うのである。
2025.3.17

『模試第一日目』
今日は新中二、新中三の、数学と英語の全国模試の日である。15分ほどテスト勉強をしてから、テストへ入る。その時、生徒を見ると、ひとりの右利きの子が左手で書いている。
「どうしたんや」
「先生が『大事なことは左手で書ける位にしておけ』と言ったから左手で書いているんです」
「あれは冗談や、その位『がんばれ』と言う意味や」
「え、そうなんですか」
「右手を怪我したんかと思うて心配したわ」
「すいません」
「あやまらんでええよ、テストがんばれよ」
「はい」
さて、模試が始まると、皆真剣に取り組んでいる。先の診断テスト、学年末テストで良い結果を出している子は凄まじい集中力で取り組んでいる。素晴らしいことである。
2025.3.16

『全国模試』
来週は小中学生全学年、全国模試を実施する。模試には大切な意味がある。主に、以下の三点である。
1.入試の練習が出来ること
2.理解度を確認出来ること
3.偏差値と順位が分かること
入試の練習だからこそ、本番のつもりで真剣に受けると良い。間違った問題は、徹底的に復習すると良い。偏差値65を超える為に、何をするか考えると良い。
偏差値65は高松高校合格基準である。偏差値68だと合格可能性は80%となる。
(※佐藤進学塾採用の全国模試の場合)
入試は、一回限りの勝負である。ところが、模試は年間に三回実施する。小三は「21回」、小五は「15回」受験できる。これだけの回数があれば、受験までに調整出来る。
特に、小学生は有利である。
練習の機会は多いほど良い。
先日、ブログに書いたことだ。かつて卒業生が、小三の時、偏差値50台だった。中三では、70を超えて、心に大きな余裕ができた。数学の問題を解くのが、とても楽しそうだった。目をキラキラ輝かせて、私の授業を聞いていた。こういう子たちの成長を見るのはこちらも楽しい。
2025.3.15

『佐藤進学塾「塾生」』
今年度、中三、診断テストで総合一位を取った子が二人いた。そのうちの一人は小学生で入塾した時、塾の授業についてくることが最初のうちはまったくできなかった。
他の子が、10問解く間に、2、3問しか解けなかった。いつも、悔しそうな顔をしていた。
「先生、どうしたらいいですか」
「気にしなくていいよ。 復習して解けるようにしよう」
その子は素直に復習を続けた。
私も復習ノートの添削を続けた。
それでも、他の子には追い付くことは出来ない。しかし、一生懸命、諦めずに頑張った。中一の時、結果が出なかった。それでも私が言う通りに復習を続けた。中二で良い結果が少しずつ出始めた。そして、ついに、一学期中間テストで総合上位十位内へ入ることが出来た。
「ぼく、一位を目指します」
「そうか、頑張れよ」
その日から集中力がさらに上がった。此方も細かい指示を具体的に出した。それを愚直に守った。塾には総合一位の安定した実力の子がいる。その子も気に掛けて、いろいろと声を掛けてくれた。しかし、残念だが、総合一位はなかなかとることができなかった。
「先生、ありがとうございます」
いつも大きな声で言ってくれる。
感謝の気持ちが強い子である。
佐藤進学塾には私の指示通りに正しい努力をして素晴らしい結果を出す子がいる。
一人や二人ではない。
十人も、二十人もいる。
素直で前向きな子に正しい努力の仕方を一人ひとりへ的確に伝える。それを素直に実行へ移して復習する子は素晴らしい結果を出す。それは大きな自信へと変わる。一日当たり、家庭学習の時間は二、三時間である。長時間、だらだらやる必要などない。
それで、確実に結果を出す。
出ない時は別の策を伝える。
素直な子に真剣に向き合い誠心誠意、熱く指導を行う。親にも子にも一切迎合しない。
尖った進学塾であり続ける。
※全学年、定員まで僅かです。
2025.3.14

『記憶の定着』
記憶は曖昧である。繰り返し覚えた事を間違う事はまずない。ところが、意識していない事は意外と覚えていない。
毎日、目にしている事も…。
「庭が綺麗になりましたね」
「あっ、気づいたんだね」
「はい、明るくなりました」
「そうだね、すっきりしたね」
この会話を聞いて、初めて気が付いた子もいる。
「うわっ、ほんとだ」
この会話を聞いても、まだ気付いていない子もいる。
「えっ、どこどこ」
昨年、正面六本の木を庭師さんに植え替えて頂いた。塾庭の風景はガラリと変わった。コニファースカイロケットからトキワマンサクに樹種を変えた。コニファーは近年の猛暑に少し耐えられなかった様子だ。申し訳ないが交代して頂いた。
記憶とはそんなものである。記憶を定着させる為には繰り返し覚える必要がある。脳は睡眠中、その日に起こった出来事を整理する。繰り返し行った事は覚える側へ、一回だけ行った事は忘れる側へ、それぞれ振り分けると言う。
大切な勉強も、何気ない出来事も一回しか行わないと全て忘れる。拠って、復習しないと…である。運動も、芸術も、勉強も、四、五回練習した事は重要として深い記憶と成るそうだ。
さて、塾の庭には紅花マンサクと白花マンサクが交互に並ぶ。もうすぐ、紅白のおめでたい光景と成る。花言葉は「幸福の再来」。花言葉は「閃き」でもある。佐藤進学塾にふさわしい。少しばかり、咲き始めている。満開の光景がとても楽しみだ。志望する大学合格の報告も次々と受けている。
※全学年、定員まで僅かです。
(新小三は新規募集中です)
2025.3.13

『中学「予習講座」』
新中一、数学・英語の予習が進む。
今週は『方程式』が完成した。
来週から『関数』へ入る。小学校で習った、決まった数字が『a』に変わるだけだ。それが分かれば、負の数に気を付けて計算するだけである。
100%分からなくていい。80%程度分かる様に復習する努力をしてほしい。10問中、8問正解すればよい。毎日、一時間復習すればよい。分からない時は、解答解説書を読めばよい。
生徒に訊いてみた。
「方程式、どうだった」
「とても楽しかったです」
「復習すると出来ました」
「文章題は小学校と同じです」
新中三、数英予習が進む。
『因数分解』が完成した。展開公式は習得した。それを反対に考える。因数分解はパズルの様で楽しい。新受験生ゆえ、100%分かる必要がある。120%分かる位、努力をしてほしい。
次回からは、『平方根』へと進む。平方根についての理論概念からしっかり教える。そして、計算演習を行う。その後は、平方根の利用を行い完成させる。皆よく復習しているのでスムーズに進んでいる。
高松高校へ合格する為には、強い気持ちが必要だ。此方もしっかりと準備をして完璧な授業指導を行う。素直に復習する子たちを私たちは最大限に応援していく。
2025.3.12

『勝負は「中二」』
中学部は「週三回・二時間半/回」の授業である。その中でも数学授業の密度は特に高い。佐藤進学塾は理系、特に、数学の指導に力を入れているからだ。
新中二は『式の計算の利用』の指導を終えた。この単元は大変難しいので、生徒が復習をしているか、指導者である私には、すぐわかる。
佐藤進学塾の授業は、対面式である。私が生徒に質問する。生徒がそれに答える。その繰り返しである。生徒は一日、十回位順番が回って来る。復習を行っている生徒はリズム良く出来る。私は生徒が答えられない難しい質問はしない。復習して答えることができる質問を生徒の能力に応じて臨機応変にする。
拠って、私とのやり取りがきちんとできたならば理解出来ていると言える。出来ていない場合は、復習を増やす様に伝える。
中学部は宿題を出さないので、復習については具体的且つ細やかに一人ひとりへ伝える。受動的な宿題は無駄だが、能動的な復習は大いに意味がある。要は掛けた時間ではなく、中身なのである。
さて、話は変わる。
「中二で受験の勝負が決まる」
最初が肝心であることを伝える。
成績上位者は、中三になると同時に本気で受験勉強を始める。拠って、そこから頑張っても殆ど差はつかない。頑張っても、上位層の出来る子とは更に差が開いていくばかりだ。
『42.195㎞フルマラソン』を思い浮かべるとよく分かる。
前半、差はつかない。折り返し地点辺りから徐々に差が付き始める。後半、先頭集団は大きく他者を引き離す。その後、先頭集団はそのままゴールする。先頭集団での競争はあるが、後続集団から逆転はない。
これが、受験とよく似ている。
大切なのは『今現在』なのである。
中三の秋頃、佐藤進学塾塾生は「高松高校を受験したい」と皆、必ず言う。
1.内申点200㌽
2.診断テスト210点
3.模試偏差値65㌽
この三点が最低限必要になる。
(診断テストは難易度で上下する)
佐藤進学塾でも、診断テストの合計点が30点以上伸びる子がいる。実際に、中二で183点を中三第五回で218点まで伸ばした子がいる。驚く位に努力して勉強した結果である。これは逆転でも奇跡でもない。
「212点の子が、215点になり、211点になり、220点と成る」
「228点の子が、235点になり、232点になり、238点と成る」
こういう推移の子が殆どだ。前記の子は例外的な子である。
上位の子は驚く位努力しているが、本人はそれを努力と思っていない。勉強を愉しむ余裕があるからだ。受験生として、当たり前位に考えている。そういった前向きな子たちを徹底して応援する進学塾である。
※全学年、定員まで僅かです。
2025.3.11

『吉報』
卒業生が訪ねて来てくれた。
「先生、こんにちは」
「合格したんだね」
「はい、合格しました」
「良かったね」
「香川大学の医学部へ合格しました」
「すごい。おめでとう」
現役合格である。
相当、頑張ったのであろう。
しばらく、いろいろ話をした。
二人の姉と兄も、佐藤進学塾へ通ってくれていた。一番上の姉は二人の子を持つ母となり、在宅で仕事も頑張っていると言う。もう一人の姉は神戸大学で頑張っていて大学院へ進むと言う。そして、兄は京都大学で頑張っていて此方も大学院へ進むことを考えていると言う。お母様は、一人ひとりの子をよく見ていて、適性を考えてお子様の将来を応援しておられる。
塾の話になり、「○○くんは元気だとか、□□さんはどうしてるかな、△△さんと会ったよ」とか話していると、一人の生徒から電話が掛かって来た。
「先生、千葉大へ合格しました」
「おめでとう。すごいね」
「はいありがとうございます。また塾へ行きます」
「あー、是非来てね」
丁度、噂をしていたら、電話が掛かって来たので驚いた。
卒業生はその後もしばらく話をして、最後にこの様に言ってから帰って行った。
「佐藤進学塾は先生が一人ひとりを見て本気で指導してくれて、生徒同士が一つとなって頑張るところがとても良かったです」と言って!
※全学年、定員まで僅かです。
2025.3.10
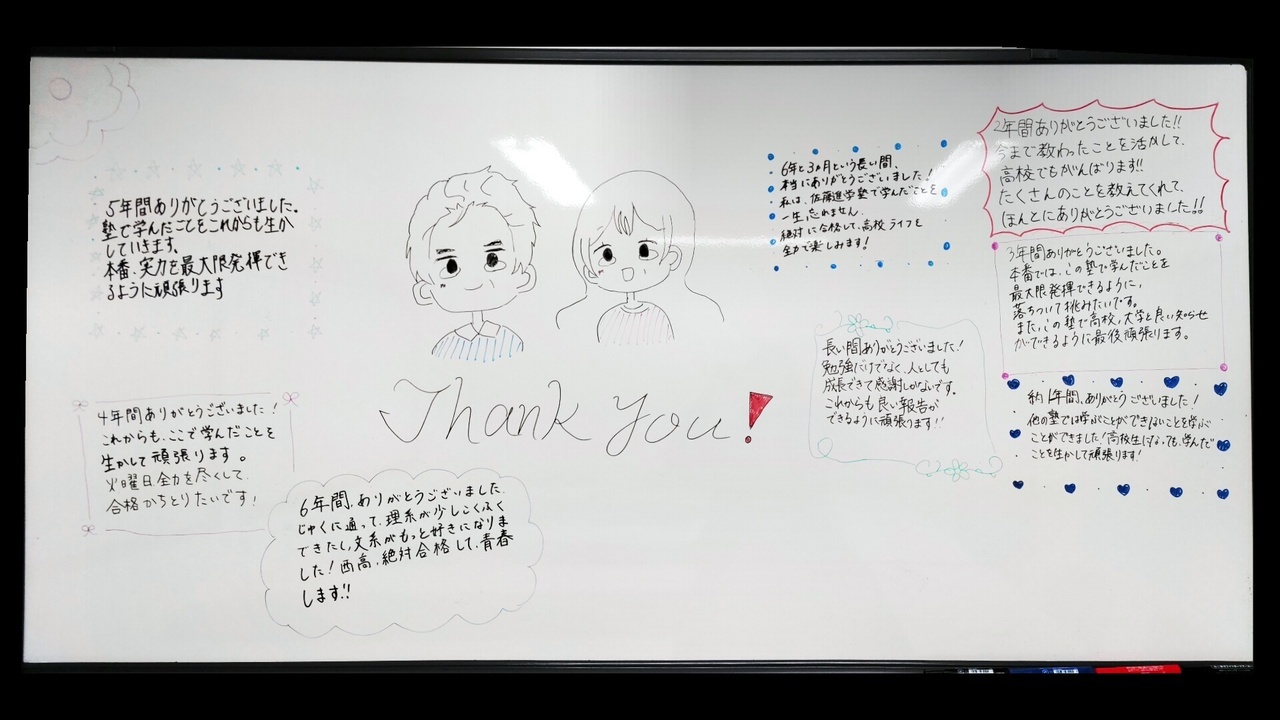
『卒業の日』
「出会いは風のようで♪別れは雨のようで♫すべてのことあるままにながれてゆくもの♬」
土曜日、日曜日に入試実践演習を実施、佐藤進学塾のすべてのカリキュラムが完成した。全員、最後まで通塾してくれた。皆、仕上がりは最高である。自信を持ち、試験に臨むと良い。
私達が考えられる出来る限りの事を行った。本当にありがとう。今は、感謝の気持ちでいっぱいである。卒業生が最後にホワイトボードへメッセージを残してくれた。塾長、副塾長の顔が、大きく書いてある。
「ありがとう」思わず、声が出た。
「先生、写真撮ろう!」
みんなが塾に戻ってきた。
「庭にする、教室にする]
「庭がいいです」
みんなで最後に写真を撮った。皆とてもにこやかであった。合格発表の日に全員の分を用意しておく。
皆が帰ってから、一人ひとりのメッセージを読ませてもらった。風のような出会いを今年も思い出す。
2025.3.9

『全国模試』
再来週の月曜日より、全国模試実施週間である。実力問題集を配布した。丁寧に仕上げてほしい。塾テキストもしっかり復習するとよい。余裕がある子は参考書を勉強しておくとよい。
目標は全科90点突破!
且つて、中学生との会話である。
「私、小四の時、偏差値が52だったんです」
「えっ、そうだった」
「その時、偏差値の意味がよく分からなかったんです」
「それは、そうだろうね」
「でも、小五になって、これではだめだと思いました」
「大切なことに気づいたね」
「それから頑張って、一年間で偏差値61にまで伸ばしたんです」
「頑張ったことを覚えてるよ」
「今では、偏差値70を超える様になって本当に良かったです」
「本当に良く頑張ったね」
この子は受験前、塾の発展テキストの問題にいつも真剣に挑戦していた。それが終わると、参考書を読み込んでいた。自分で考えて、自分のペースで勉強する。自ら能動的に学習する。これこそが真の受験勉強であると言える。
今、阪大医学部を目標に頑張っている。
2025.3.8

『感染症対策』
佐藤進学塾では、感染症対策を続けている。
1.授業時マスク着用
2.入室時の手指消毒
3.教室内の常時換気
以上、今でも行っている。
教室内で食事はもちろん軽食も禁止、お菓子は論外だ。当然の事だが、水分補給は認めている。そこまで気を配る。
生徒さん、保護者様には、様々な考えの方がおられる。中でも、そういった事にとても気を遣われている心配りの細やかな方が多い。その様な方が安心して学習できる環境を守る。
今日は香川県公立高校入試実践模試を実施した。以前は、塾で昼食を食べて入試の時間割通りに実施していた。今は、午前と午後を分けている。土曜日は午前の部、午前九時から午後一時まで三教科の入試問題を実施する。日曜日は午後の部、午後一時から午後四時まで二教科の入試問題を実施する。
入試を想定した総仕上げだ。生徒の健康面を優先して、静謐な環境下で実施する。この甲斐あって、昨年迄の四年間、皆、体調万全で受験できた。そして、輝かしい栄冠を掴んだ。佐藤進学塾では、感染症対策一つとってもここまで考えて行っている。学習面に関しては、さらに細かい部分まで考えて行っている。
※新年度募集、全学年、定員まで僅かです。
2025.3.7

『中三受験生』
塾カリキュラムが今週で完成する。佐藤進学塾の感想を、生徒一人ひとりに訊いた。
「最初はいくらやっても、良い結果は出ず、諦めそうになりました。その時、先生から『そろそろ本気でやってみろ』と少し厳しめに言われました。先生の言う通りに学習を続けていくと模試の偏差値が52から60を超えるようになり、勉強が面白いと感じられる様になりました。中学校で診断テスト、五教科総合一位を取った時はとても嬉しかったです。」
一人の子が言ってくれた。
「授業の時に行うスピーチが始めは上手く表現できませんでした。友達のスピーチを聞き、工夫して表現を重ねていくと自分の気持ちが上手く皆に伝わる様になりました。その頃、友人と話をする事がとても楽しくなりました。また、自分の考えをうまくまとめる事が出来るようになった感じがします。テストの記述問題にも上手に対処できるようになった事を覚えています。」
また、ひとりの子が言ってくれた。
「中一の時に、復習をしていなかった時、私、先生からすごく叱られたんです。その時は、叱られたことがいやなだけでしたが、家に帰って冷静に考えると、『私の事を真剣に考えて大切なことを伝えてくれたんだな』ということに気付き、それからは必ず復習をするようにしていきました。内申点も200点を超えて安心して高松高校を受けられる事が出来るのは、あの日の一言がきっかけのように感じています。」
そして、一人の子が言ってくれた。
「佐藤進学塾は学習の指導内容もレベルが高くとても良いのですが、それ以上に礼儀作法に厳しいことが最初のうちはとても驚かされました。でも、姿勢が良くなったり、みんなにお礼を言うようになったりしてから、いろんな人とうまく関わる事が出来る様になった気がします。『ありがとう』という習慣がついてからは友人関係もうまくいき、学校の先生からもとても大切にされる様になりました」
それから、一人の子が言ってくれた。
「テストが終わるたびに成績表が出ます。それを家に持って帰り母に見せると、必ず、悪い所をたくさん指摘されました。いつも、悲しい思いをしていました。塾へもっていくと佐藤先生はまず、努力した点、良くなった点を褒めてくださいました。それから、問題点を探し出し、具体的な改善方法を伝えて下さいました。その事を母に伝えると、『本当だね。良かったね』と褒めてくれました。」
ほぼ、二人の子が同じ事を言ってくれた。
他にもいろいろと話してくれた。
みんな、自分の思いを懸命に伝えてくれた。
最後の最後まで一人ひとりを全力で応援する。
※新年度募集、全学年、定員まで僅かです。
2025.3.6

『新中二』
新中学二年生、数学と英語の新学年予習授業を続ける。数学は『式の計算の利用』を終えた。等式の変形は、コツをつかめば簡単だ。説明(証明)は、型を覚えると良い。
(例題)
偶数と奇数の和は奇数になる。
このことを説明せよ。
(解答例)
m、nを整数とすると、
偶数は2m 、奇数は 2n+1 と表せる。
(ここまでは中一の知識である)
和は
2m+(2n+1)
=2m+2n+1
=2(m+n)+1
m+nは整数なので、2(m+n)+1 は奇数である。
よって、偶数と奇数の和は奇数になる。
1.ことばを文字式で表す
2.文字式の和を計算する
3.説明することを結論付ける
図形の問題は概形を書いて、公式を利用して計算する。式の計算は出来て当たり前で、式の利用の単元で大きく差がつく。完璧に仕上げてほしい。もう一回、練成問題を演習する。その後は連立方程式へ進む。
入試まで、あと二年である。
新中二の一年間が大切である。中三の一年間は差がつかない。上位受験生全員が頑張るからだ。新中二を本気で取り組む子が栄冠を掴む。最後に逆転など99%起こらない。聡明な生徒と親はわかっている。
※新年度募集、全学年、定員まで僅かです。
2025.3.5

『大きな成長』
以前頂いた手紙である。
「最近、『塾が楽しい』という様になりました。また、忘れ物をしないように自分でチエックリストを作り、部屋にはっており、良い変化が訪れたことにとても驚いています。
私たちも出来る事をやっていこうと、部屋の使い方を変えてみたり、小学生新聞を購読してみたり、図書館で本を借りてみたり、いろいろ試しているところです。
宿題がスムーズに仕上がったり、家族で新聞の内容について話したり、有意義に時間を使う事の心地良さを感じています。」
小三、小四、平常授業は週一回である。学習の核と為ることを願っている。週一回ゆえ、授業には熱がはいる。小さい子は躾も大切である。勉強だけ出来てもダメだ。其処は迎合しない。
「返事をしてね」
「お礼を言おうね」
「姿勢を正してね」
「靴は並べようね」
「先生の目を見て聞こうね」
「心をこめて字を書こうね」
「ゆっくり文章を読もうね」
等々の声を掛ける。
授業指導の内容だけでなく、他にも伝えることが山ほどある。それらを丁寧に伝えていく。その気持ちが伝わると嬉しい。最後に、「この一年『熱く』ご指導頂きありがとうございました。」と書かれていた。
※新年度募集、全学年、定員まで僅かです。
2025.3.4

『テスト後』
生徒とテスト結果を基に、私が一人ひとりと話している。それをお子様が家の人に話し、内容を共有している家庭も多い。穏やかに、親がお子様の話を聞いている。お子様は親に、丁寧に先生との話を伝えている。
『塾長⇔生徒さん⇔保護者様』の関係性を大切にしている。この関係性を築いているご家庭のお子様の成績は良い。お子様の心が安定しているからである。
さて、来週は公立高校入試である。
新中三生は、一年後に入試を迎えるということだ。ちょうど、一年後である。新中一、新中二、新中三は数英予習授業を実施している。
テストが終わった今こそ、本気で勉強すべきである。今、やっておけば、テスト前は楽に仕上がる。上位集団の子たちはテスト前本気で頑張る。だからなかなか差がつかない。しかし、普段となると話は別だ。やる子とやらない子に分かれる。ここでしっかりやっておけば、確実に結果は出るということだ。
「がんばったのに、結果が…」と不満そうな顔の子が時々いる。確かにテスト前は全力で頑張っている。ところが普段はと言うと、それほど頑張っていない。不断の努力がたりないから仕上がりが甘い。次回、中間テストは五月だ。拠って、今の時期は気が緩む。こういった時期に、出来る子は集中して勉強する。
1.『テスト』の間違い直し
2.新学年『予習授業』の復習
3.『全国模試』へ向けての学習
この時期、時間があるから丁寧に学習出来る。テスト前に慌てて、長時間勉強しても無駄である。今の様な時期に集中してやることが大切だ。出来る子は、三時間集中して学習している。意外だが、テスト前は効率良く勉強して早く寝ている。10時過ぎに寝て結果を出している子もいる。
結果を出したければ「今、やるべき」である。
佐藤進学塾は、今、本気で予習を行っている。
それは、聡明なお子様、保護者様には伝わっている。
2025.3.3

『新年度生徒募集「最終月」』
佐藤進学塾は、『高松高校受験専科』である。塾長が理数系、副塾長が文系を担当、指導レベルの高い二人の専任教員が責任を持って指導を行う。小中学部、全科目を指導する。
特に、小学部は算数と国語、中学部は数学と英語、理科に力を入れて指導を行っている。昨年度からは、小5、小6の『英語教育』、小6の『数学教育』を行い、既に軌道へ乗った。
将来、医学部中心に理系へ進学希望する生徒が多い。その為に高松高校は最適な進学先と考える。医学部進学を目指す勉強、高松高校上位合格を前提にハイレベルな指導を行っている。
実際に高松高校卒業後、医学部医学科へ多くの子が進学、医学の勉強を行っている。京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、自治医科大学、香川大学、島根大学、熊本大学、高知大学、徳島大学、愛媛大学等々へ進学している。
現場で医師として、活躍し始めた子も多い。国立大薬学部、理学部、工学部、農学部への進学者も多い。自分の目標に向かって、一人ひとりが突き進んでいる。
佐藤進学塾に興味、関心のある方は、三月中に是非ご連絡頂きたいと思う。
三月末、一旦募集を締め切る。
そして、新年度の授業へ専念する。
「将来有望な生徒たちの為に!」
※全学年、定員まで僅かです。
2025.3.2

『肯定的な言葉』
佐藤進学塾では否定語禁止である。お子様だけでなく、保護者様にもお願いしている。
否定語を発する子は、勉強が出来る様にならない。
「出来ない、分からない、無理」など言うと、それを脳が真実と受け止めるからだ。
肯定的な言葉を発する子は、とても、表情が明るい。
「出来る、分かる、頑張る」と言うと、それを脳が真実と受け止めて、本当に出来る様になり、心が明るくなるからだ。
この時期、テスト結果をもとに家庭では様々な話が行われる。どんな結果であっても、「よく、がんばったね」と、まずは声を掛けてほしい。
皆、頑張ったのは事実である。
テスト結果には、良いも悪いもない。その時点での学力が、単に数値化されただけである。テスト自体、大いに問題がある場合もある。問題を精査して、冷静に判断しなければならない。
「良くない結果だな」という教科が見つかった時はチャンスである。
問題点が見つかったわけで、改善する機会が到来したのだ。その方法を、教科書、辞書、参考書を調べて徹底的に考えるとよい。いつも、全教科100点などという子はいない。最高の結果を出す子は、そして、その保護者様はそういう考えをしている。ピンチをチャンスと捉え、徹底的に間違いを直している。
随分と昔の話になる。
ブログで何回も伝えた。
附小五年期末テストの社会で53点を取った子がいた。
(最近まで附小期末テストが実施されていた。今は附属小六学力テストが年三回行われるだけだ)
他はすべて80点以上である。数字だけを見ると「53点」というのはショックである。保護者によっては、激怒される方もおられる。この親御さんは試験を精査してから、丁寧に連絡をくださった。
「どうも、歴史が弱いようです。本屋さんに行って、歴史まんがと小説を一緒に買い求めました。 来月は奈良で開催される『正倉院展』を訪ねて、本物に触れてきたいと思います。先生、今後ともご指導の程、どうぞ宜しくお願い致します」
この親御さんのお子様は後に東京大学へ進学、今は法曹界で活躍されていると聞いている。
親御さんの肯定的な考えと言葉がお子様を成長させる。
2025.3.1

『読書』
「最近、本、読んだ」
「はい、読みました」
塾では教養溢れる様々な話題で盛り上がる。みんな、楽しそうに話す。「佐藤進学塾は楽しい」と言われる所以でもある。
本を読む子は『読解力』が高い。長い文章に常日頃より接しているからだ。本を読む子は『語彙力』が高い。莫大な量の活字に日々、接しているからだ。
また、本を読む子は、心がとても豊かである。主人公の気持ちに寄り添い、多くの事を想像するからだ。
ただ、本を読む子が学力が高いとは限らない。しかし、学力が高い子は読書家である。寝食を忘れてまで読書に没頭する子は勉強が出来るように成る。そして、学力は飛躍的に伸びる。
時々、こんな相談を受ける。
「先生、子どもが本ばかり読んで勉強しないんです。大丈夫でしょうか」
私は、こう答える。
「素晴らしいことです。好きなだけ、本を読ませてあげてください」
この様な子は勉強し始めると、凄い集中力で勉強をし始める。その時が来ることを安心して待っていればいい。本が好きな子は幼少の頃、親から本や紙芝居の読み聞かせをしてもらっている。本が好きな子は、親も読書の習慣がある。リビングでは家族がいつも本を読んでいる。
「なんで、そんなにいろんなことを知っているの」
「お父さんがたくさん本を読んでいて、それをぼくも読むからです」
「大人の本だから、難しいのとちがう」
「難しいけど、すごくおもしろいんです」
この子は高高を卒業後、九州大学で頑張っている。
本を多く読む子は、様々な文章を正確に理解する。拠って、短時間で多くの内容を理解する事が出来る。結果、集中力が高くなり、密度の高い勉強が出来る。二、三時間、ピシッと集中して勉強、結果も出す。それが分かっているから、無駄な時間を過ごすことはない。親も子に「早く、寝ましょう」と声を掛け、健康管理に最大限気をつけておられる。
「何より、読書を愉しむ人と話をすると楽しい」
2025.2.28

『進学塾』
これからの世の中、頭が良いだけではAIに負ける。
「シンギュラリティー」
即ち、術的特異点は、80年代に多くの研究者が使う様になった言葉である。人間と人工知能の臨界点を指す言葉だ。つまり、人間の脳レベルの『AI』が誕生する時点を表す。
AIが人間を超えると考えるのは早計である。AIは人間と協調する為に活用されると考えられる。AIの発展によるDXが起こることに拠り人間の在り方も本質的に変わる状況が予測される。
新年度、佐藤進学塾小学部のカリキュラムを大きく変える。
旧態型の進学塾、四科目指導から、「数・算・英・国・理・社」六科目完全指導へと変えていく。将来、国立大学の医学部、歯学部、薬学部、理学部、工学部等を目指す子の理数系センスを磨き上げる。
高松高校で伸びる子は小中学校時点で理数系科目の理論概念の根底を理解している。文系科目の読解力、語彙力、文法力を完璧に身に付けている。佐藤進学塾専任教員である塾長が理数系を、副塾長が文系を、全科目について、責任を持って指導する。
佐藤進学塾は「高松高校合格後の将来を考えて、大切なお子様の為に指導を行う格式高い静謐な進学塾」であり続ける。旧態依然の進学塾から新しい形の進学塾へ進化していく。
佐藤進学塾は設立二十年を超えた。更により良い教育を提供する。時代の変化はスピードを増す為、五年後にはスタンダード化する。丁度、お子様が高松高校進学時である。そこまで考えて、徹底指導を行う。
※新小5・小6・新中1・中2・中3、定員まで各『1名』です。
2025.2.27

『最初が肝心』
全力でスタートを切る子は勝利を掴む。あとで頑張っても追いつくことは難しい。逆転に見える様な出来事がたまに起こる。珍しいので、その様な話に人は飛びつく。
しかし、聡明な人は見向きもしない。
さて、小六は『文字式』である。全ての計算手法を指導した。「どうかな」と訊くと、「楽しい」と答えてくれた。来月からは方程式に入る。その後、図形を指導する。
中一、中二は数学、英語ともに新学年の予習に入った。リズム良く進めていく。丁寧に復習していくと良い。数学は計算すべてを三月までに予習する。
中一(新中二)は式の計算、連立方程式、中二(新中三)は展開、因数分解、平方根、二次方程式である。
もう一度、言っておく。
「最初が肝心である」
全力で頑張ろう!
※全学年、定員まで僅かです。
2025.2.26

『卒業生の思い出』
佐藤進学塾には伝説の姉妹がいる。時々、近況を知らせに塾へ来てくれる。姉は国立大学医学部医学科で勉強している。医学の勉強とダンス部の活動を両立、充実した日を過ごしている。
妹は国立大学教育学部で舞踊の研究分野について学んでいる。幼少期から続けているバレエとは体の使い方、作法等、すべてちがうが新鮮でおもしろいそうだ。
二人とも姿勢が美しい。
「いつからバレエ、やってたの」
「二人とも、三歳からです」
なるほど、美しいわけである。
姉は、附属中期末テストで且つて、総合一位を取った。いつも、上位成績だが、なかなか、一位を取ることは出来なかった。期末テストの日に台風が来た。台風により、試験は延期となった。みんな、少し間延びしてしまったことを覚えている。
「先生、何をすればいいですか」
「間違った問題を再度調べよう」
素直にやり切った。そして、附中で『総合一位』を初めて取った。それから成績は驚く位に安定した。
妹は、診断テストが伸び悩んだ。肝心な時に、200点を割り込んでしまう。テスト当日、緊張し過ぎるからであった。ノートを見ると、やるべきことはやっていた。
「高松高校を受験しよう」
「はい、全力でやります」
他の塾生の応援もあり、見事、高松高校へ合格した。お母様も泣いて、喜んでおられた。
入試演習前に、姉妹のかつての話をした。
一人の子がぽつりと言った。
「次は、私が応援する側になることができるように受験を全力で頑張ります」
※新中一、新中二、新中三は定員まで、 あと「一名」です。
2025.2.25

『小四・算数』
小四平常授業が終盤を迎えた。『わり算』の単元を復習する。小数のわり算で、わる数は「2けた」、少し時間が掛かる。
1.仮の商を立てる
2.わる数と商をかける
3.わられる数からひく
この繰り返しである。リズムが整ってきた。皆、正確に計算が出来ている。「素晴らしい」。努力の賜物である。
文章題は『割合』を使う。まず、題意を関係図に表す。
もとにする量→くらべる量
「くらべる量÷もとにする量」
何倍になるか、求められる。問題の文章を音読する。もとにする量を見つける。関係図に表し数値を書き込む。皆、集中して解いている。ノートが整ってきた。ノートが整うと正答率は上がる。ノートの状態は脳の状態を表しているからだ。ノートが整っているという事は、頭の中も整理されて整っている。
右手に鉛筆を持つ。左手にものさしを持つ。マスに合わせて数値を書く。これを守ることで、正答率は大きく上がる。計算するスピードも上がる。小四で、算数の「型」を身に付ける。正しい型を身に付けて、正しい努力を行うことで算数の実力は飛躍的に伸びる。
※定員まで、新小四は「3名」、新小五は「1名」、新小六は「1名」です。 (四月開講)
2025.2.24

『予習授業』
佐藤進学塾は『予習形態』の授業である。それを復習すれば、力は付く。必ず、結果も出る。新しい単元については私たちの授業をしっかり聞いていればそれでよい。
分からない時は例題に戻る。それでも分からない時は、解答解説書を丁寧に読む。そして、深く考えて、解き進める。最初は完璧に分からなくてもよい。その都度、見直していけばよい。
一人ひとりの理解度を確認して、私も、丁寧に説明していく。大切な公式やルールを学ぶ。それを正確に使えるようにする。ゆっくりと、解いていけばいい。
「あっ、わかった」
と言う瞬間がやって来る。
「あっ、おもしろい」
と感じられる時がやって来る。
「よしっ、結果が出た」
という日が必ずやって来る。
その時まで、家で地道に復習すると良い。復習は最初、時間と手間が掛かる。それらが、後に効率の良い勉強に繋がる。効率良い勉強をしている人は且つて、手間暇かけて学習した経験を持つ人だ。親も子も、それを大変とは思っていない。寧ろ、愉しんで乗り切った感がある。その応援を私達が全力で行う。
※新中一に続いて、新中二・新中三も今週『新学年予習講座』に入ります。 各学年残席「一名」です。
2025.2.23

『原動力』
生徒たちに、今まで頑張ってきた原動力について訊いてみた。且つて、一人の子が言った。
「佐藤先生の数学の教え方が的確で『なるほど』と思うことが多かった。 家で解き直すと、自分の力で解けるようになる。繰り返すと楽しいと思える事が大変多くなった。得意の社会はとても自信があった。それが受験勉強へ向かう原動力です」
この子は素直で前向きな子だった。小四で入塾してから、ずっと、前向きに努力を続けた。流石にその時は将来、中学校で『一位』を次々取るとは思えなかった。
中一の時から、教科書や学校ワークは出来て当たり前のことである。塾テキスト、なかでも「発展テキストの演習を大切にしよう」と伝えている。
ある子が、「受験が終わったら、たくさん楽しいことがあります。それが原動力です」と言った。思わず笑いそうになった。とても、中学生らしくていい。それでもいいのである。
さて、競争率について少し話をした。皆、冷静に数値を見ている。あと一箇月、受験勉強を楽しむ余裕があれば合格出来る。合格する細かい手法は、一人ひとりに細かく伝えた。それを楽しんでやればいい!
2025.2.22

『集中力』
土曜日の午後、佐藤進学塾で「三時間半」集中して学習する。中三入試実践演習である。午前中、家で「二時間」、午後、塾で「三時間半」、夜、家で「二、三時間」受験勉強を行う。
合計八時間、土、日に勉強する。同じ場所だと四時間を超えると学習は作業化する。しかし、三時間半までは塾で凄い集中力で学習出来る。あとは、家で調整する必要がある。
指導する側の私は、三時間半の演習準備に3時間掛けている。指導手順の詳細確認に数学1.5時間、英語1時間、演習プリントの準備に0.5時間だ。拠って、演習の密度は非常に濃い。
数学の得点が安定してきた。国語が40点を超えて来た。英語は50点に近付いて来た。理科、社会はまだ伸ばすことができる。
1.入試問題演習(50分)
2.重要事項解説(30分)
3.間違い直し(10分)
上記を2セット実施する。数学、英語、各90分である。国語、理科、社会は平日に同形式で実施している。このあとは、家で復習する必要がある。指導する側の私も本気で予習及び授業準備を行っている。
場を変え、気持ちを切り替える。長時間だらだらやる必要はない。時間を決めて、集中して行う。集中して密度の高い学習を行えば、実力は大きく伸ばすことが出来る。そして、合格を手にすることができる。
※全学年、定員まで僅かです。
二月の募集は2/28(金)まで
2025.2.21

『入塾面談』
毎週土曜日は、新年度入塾面談日である。生徒一人当たり、「80分」を確保している。
1.適性検査「30分」
(保護者との二者面談)
2.学習相談「40分」
(保護者、生徒、三者面談)
3.事務連絡「10分」
塾の指導について、丁寧に説明させて頂く。お子様の様子を、しっかり聞かせて頂く。保護者様のお考えについて確認させて頂く。土曜日、生徒さん一名の面談、心をこめて行う。
こちらの配慮をご理解戴き、大切なお子様の三者面談にご参加される方が多い。その様な保護者様とは、面談で話がスムーズに進む。我が子のことだけでなく、相手や塾の生徒の事も考えているからだ。
佐藤進学塾は、『「高松高校」受験専科』である。しかし、合格を勝ち取るテクニックだけを教える塾ではない。社会貢献が出来る人間を育てる塾である。人の気持ちが分かる心と頭を育てる塾である。その為の学力を最大限に伸ばす指導を行う塾である。
「高松高校合格後の将来を考えて、大切なお子様の為に指導を行う格式高い静謐な進学塾」であることをご理解戴けると幸いである。
※全学年、定員まで僅かです。
二月の募集は2/28(金)まで
2025.2.20

『テスト対策完成』
一月上旬から診断テスト対策を行った。
二月上旬から学年末テスト対策を行った。
そして、今週金曜日にテストが終了する。
二か月間、本当に良くがんばった。週末は少しゆっくり過ごすと良い。
来週からは新年度予習講座と成る。数学と英語の予習を行う。テキストは準備出来た。気持ちを切り替えて、新しいスタートを切ろう!
何事も、最初が肝心である。
※新中二・新中三も来週より、『新学年予習講座』に入ります。 定員まで「一名」の募集です。
2025.2.19

『ほど良い緊張感』
緊張には、良い緊張と悪い緊張がある。良い緊張は、心や体を引き締め、パフォーマンスを上げる。悪い緊張は、ミスや失敗を招く原因になる。
その違いは、どこにあるのか。ズバリ、緊張の度合いにある。適度な緊張と過度の緊張だ。
テストの感想を訊くと「凄く、緊張した」「パニックになった」「難しい問題が出た」とこたえる事が多い。言い訳、ベスト3である。結果が出ない子は必ず言う。
私も、テニスやゴルフでミスした時、「緊張して、力が入った」 と反省する。生徒たちの気持ちは、少しわかる気がする。
適度な緊張感は良い。実力を発揮出来るからだ。では、適度な緊張感を保つには?!
その一、ゆっくりと呼吸をする。その二、ゆっくりと問題を読む。その三、ゆっくりと答えを書く。この三点を守ることである。あせっている子は、すべてが速くなっている。「ゆっくり=おそい」ではない。「ゆっくり=ていねい」なのである。
結果を出す子は、ゆっくり、リズム良く問題を解いていく。呼吸が整うと自律神経が整う。交感神経と副交感神経のバランスがとても良くなる。交感神経(アクセル)と副交感神経(ブレーキ)が最高の状態で機能している。
呼吸を意識することは難しい。では、何を意識すれば良いか。ゆっくり動作を行う様意識する。体の動き、話すスピードなど全て所作をゆっくりに意識する。
佐藤進学塾では、「ゆっくり、考えよう」「ゆっくり、字を書こう」「ゆっくり、行動しよう」と生徒に声を掛けている。
来週、テストが終わった時、「落ち着いて取り組めました」「あまり緊張しませんでした」「難しい問題も解けました」と言う言葉を期待している。「『ゆっくり』を意識する」ことで、すべてが可能と成る。
2025.2.18

『実力を発揮する』
テスト前に、いつも伝えることが三点ある。
まず、一点目
「問題が配られたら、すべての問題に目を通すこと」。
問題の構成や難易度を確認してから試験に取り掛かる。必ず、時間配分がうまくいく。
次に、二点目
「見たことない問題や難しい問題には手を出さないこと」。
焦ったりパニックになったりすると、冷静さを失う。平常心で取り組むことで普段通り問題を解く事が出来る。
最後に、三点目
「問題文を指でなぞりながら読んでから問題を解くこと」。
テストの時は、問題文を読む速度が速くなる。音読する速さで丁寧に黙読すると、正答率は上がる。
この三点を守ることで、実力を確実に発揮出来る。練習の時と同じ状態で取り組むと良いのである。
『テスト本番≒テスト練習』
の状態にする。
これが、なかなか難しいが…。
結果が出る子は、守っている。運動の試合も、音楽の発表会も同じだ。「このテストは簡単だ」と思ったならば、満点を狙う。「今回は難しい」と思ったならば、9割を狙う。
解けない問題は、あとで復習すれば良い。テストが終わってから、生徒たち一人ひとりに声を掛ける。「良くがんばったね。解けなかった問題は復習しよう。分からない問題があることが分かり良かったね」点数のことにはあまり触れない。本人が、一番よく分かっているのだから。
お問い合せはこちら

| 電話受付時間 | 火・水・木 14:00~16:00 月・金 16:00~18:00 |
|---|

入塾をご希望、ご検討の保護者様は
『お問合せフォーム』をまず最初にご送信願います。
(24時間受け付けています)
入塾希望・お問合せの電話はこちら
◎火・水・木 14:00~16:00
月・金 16:00~18:00